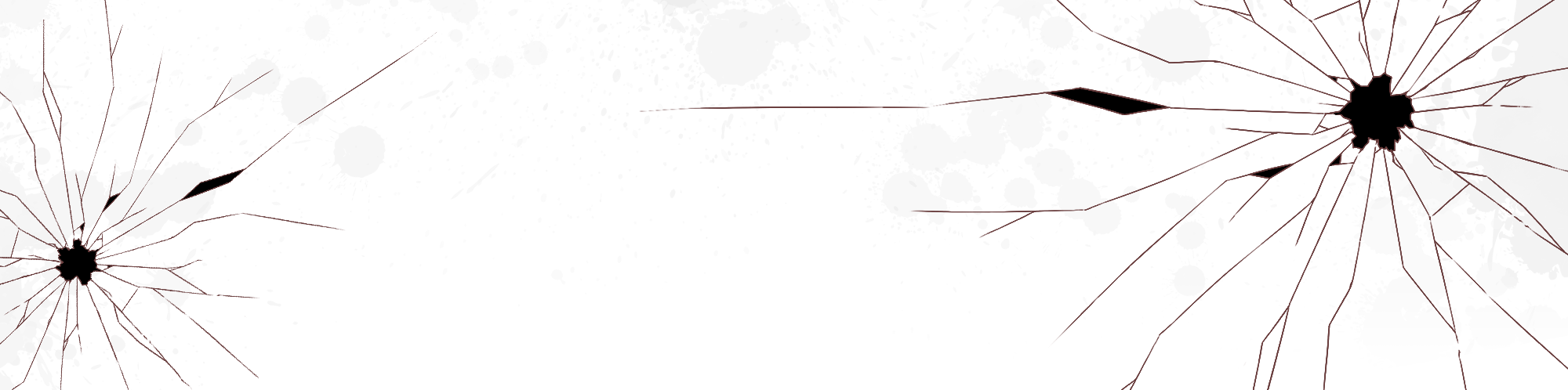第十一話 練習台
「ああ……、そうだな。やるって言ったからな。やろう。今日は何する?」
「手を握る練習したい。手を繋いで逃げる時に、怖がっていたら不便だから」
ふうっと一つ息を吐いて、ヴィクトールの険が取れたように見えた。
「解った。アラームセットして、一定時間手を握ってみよう」
隣り合わせに並んだベッドに、向かい合って座った二人は、お互いの手を握り合った。ファティマの手は冷たくしっとりしていて、細くしなやかで白かった。肌理の細かい若い肌が、すべすべして手触りがいい。
(こんな手をしていたのか……。小さいな)
一方ヴィクトールの手は大きく、乾いていて暖かかった。指も太く、がっしりしているが、肉付きが良くふっくらしていて、男らしいごつごつとした手というよりは、中性的な丸みのある手だ。
(暖かい……。優しそうな手……。意外と、嫌な感じはしないわね)
「大丈夫か、ファティマ?」
ヴィクトールはこの訓練の時間、必ずこの言葉をかけてファティマを気遣う。
「意外と平気。ちょっとドキドキするけど、何とか大丈夫」
ファティマの順応性の高さには目をみはるばかりだ。あんなに嫌がっていたのに、この一カ月ほどの間にここまで進展した。
不意にヴィクトールがファティマの指の間に指を絡めるように手を握ってきた。密着度が高くなる手に、反射的に手を放して小さな悲鳴を上げるファティマ。
「あ、ごめん。嫌だったか?」
ファティマはハッと我に返り、
「ごめん。練習だから嫌がっちゃいけないのよね」
と謝った。謝らなければならないのはヴィクトールもだと考えた。
「いや、俺が悪い。無理はするな」
手を握りなおして、ヴィクトールはファティマに提案した。
「なあ、ファティマ」
「なあに?」
「この練習の目標点を決めよう」
「目標点?」
エンリーケが脱落し、ファティマとヴィクトール二人きり。男性恐怖症を克服しようにも、ヴィクトールただ一人が配慮すればもう逃げ切れるはずなのだ。だがファティマは治療を続けてほしいという。ならば目標点が必要だ。
「どのぐらいまで恐怖症を治したい?一緒に逃げるのに不自由しないぐらいでいい?それとも、他の男とも気軽に付き合えるようになるぐらいまで治したい?」
考えたことがなかった。ファティマは、男性恐怖症を克服して、一体どうなりたいのだろう。
「ん……どうしようかな……」
「一緒に逃げるのに不自由しないぐらいだったら、もう合格だと思うんだけど」
「え……?」
それは、この治療法をもうやめるということだ。なぜだかファティマにとって、この時間が失われることがとても寂しく感じた。出来れば、もっと続けたい。まだまだ、男性への苦手意識は払拭しきれていない気がするのだが。
「そ、そうね……。それなら、いっそ、他の男性とお付き合いしても困らなくなるぐらいまで治してほしいわ」
「そうか」
「ヴィクトールを利用して悪いけど、これからも練習台になってくれる?」
(練習台……。そう、だよな。こいつは逃げきったら、いつか普通に娑婆を生きて、どっかの誰かと結婚してもいいんだ。俺みたいな悪党と一生つるむわけじゃないもんな。練習台、か……)
「いいぜ。付き合ってやるよ」
「ありがとう」
そこで、スマートフォンのアラームが鳴った。手をつなぐ時間は終わりだ。ヴィクトールはぱっとファティマから手を離した。
「今日はこれでおしまいだ。また明日もやろう」
ヴィクトールは気にしていない風を装って、「食材買いに行こうぜ」と、ファティマを買い物に連れ出したが、「練習台」という言葉がボディーブローのように効いているのを感じていた。
(俺はあくまで練習台なんだ。これから何やっても、俺の為じゃない。ファティマの人生のため、他の誰かのため。決して、俺と仲良くなりたいわけじゃない。俺はしがない悪党だ。ファティマみたいな将来有望な天才と、仲良くなって良いわけないんだ)
「手を握る練習したい。手を繋いで逃げる時に、怖がっていたら不便だから」
ふうっと一つ息を吐いて、ヴィクトールの険が取れたように見えた。
「解った。アラームセットして、一定時間手を握ってみよう」
隣り合わせに並んだベッドに、向かい合って座った二人は、お互いの手を握り合った。ファティマの手は冷たくしっとりしていて、細くしなやかで白かった。肌理の細かい若い肌が、すべすべして手触りがいい。
(こんな手をしていたのか……。小さいな)
一方ヴィクトールの手は大きく、乾いていて暖かかった。指も太く、がっしりしているが、肉付きが良くふっくらしていて、男らしいごつごつとした手というよりは、中性的な丸みのある手だ。
(暖かい……。優しそうな手……。意外と、嫌な感じはしないわね)
「大丈夫か、ファティマ?」
ヴィクトールはこの訓練の時間、必ずこの言葉をかけてファティマを気遣う。
「意外と平気。ちょっとドキドキするけど、何とか大丈夫」
ファティマの順応性の高さには目をみはるばかりだ。あんなに嫌がっていたのに、この一カ月ほどの間にここまで進展した。
不意にヴィクトールがファティマの指の間に指を絡めるように手を握ってきた。密着度が高くなる手に、反射的に手を放して小さな悲鳴を上げるファティマ。
「あ、ごめん。嫌だったか?」
ファティマはハッと我に返り、
「ごめん。練習だから嫌がっちゃいけないのよね」
と謝った。謝らなければならないのはヴィクトールもだと考えた。
「いや、俺が悪い。無理はするな」
手を握りなおして、ヴィクトールはファティマに提案した。
「なあ、ファティマ」
「なあに?」
「この練習の目標点を決めよう」
「目標点?」
エンリーケが脱落し、ファティマとヴィクトール二人きり。男性恐怖症を克服しようにも、ヴィクトールただ一人が配慮すればもう逃げ切れるはずなのだ。だがファティマは治療を続けてほしいという。ならば目標点が必要だ。
「どのぐらいまで恐怖症を治したい?一緒に逃げるのに不自由しないぐらいでいい?それとも、他の男とも気軽に付き合えるようになるぐらいまで治したい?」
考えたことがなかった。ファティマは、男性恐怖症を克服して、一体どうなりたいのだろう。
「ん……どうしようかな……」
「一緒に逃げるのに不自由しないぐらいだったら、もう合格だと思うんだけど」
「え……?」
それは、この治療法をもうやめるということだ。なぜだかファティマにとって、この時間が失われることがとても寂しく感じた。出来れば、もっと続けたい。まだまだ、男性への苦手意識は払拭しきれていない気がするのだが。
「そ、そうね……。それなら、いっそ、他の男性とお付き合いしても困らなくなるぐらいまで治してほしいわ」
「そうか」
「ヴィクトールを利用して悪いけど、これからも練習台になってくれる?」
(練習台……。そう、だよな。こいつは逃げきったら、いつか普通に娑婆を生きて、どっかの誰かと結婚してもいいんだ。俺みたいな悪党と一生つるむわけじゃないもんな。練習台、か……)
「いいぜ。付き合ってやるよ」
「ありがとう」
そこで、スマートフォンのアラームが鳴った。手をつなぐ時間は終わりだ。ヴィクトールはぱっとファティマから手を離した。
「今日はこれでおしまいだ。また明日もやろう」
ヴィクトールは気にしていない風を装って、「食材買いに行こうぜ」と、ファティマを買い物に連れ出したが、「練習台」という言葉がボディーブローのように効いているのを感じていた。
(俺はあくまで練習台なんだ。これから何やっても、俺の為じゃない。ファティマの人生のため、他の誰かのため。決して、俺と仲良くなりたいわけじゃない。俺はしがない悪党だ。ファティマみたいな将来有望な天才と、仲良くなって良いわけないんだ)