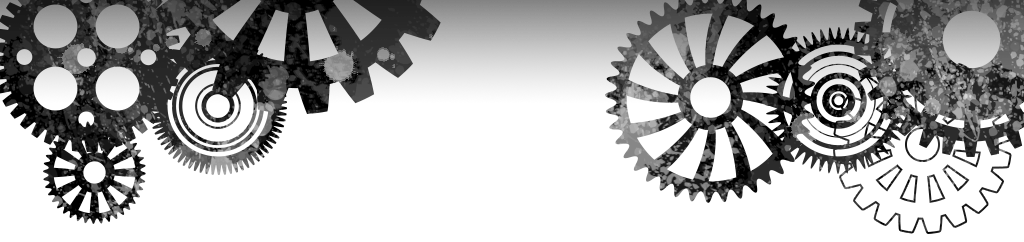孤独な鳳仙花
夢小説設定
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
1人が好きだ。
誰かと居ると自分が孤独であると余計に痛感してしまうから。
紅茶が好きだ。
その温かさや香りは荒んだ心を穏やかにしてくれるから。
執務室で首領の帰りを待っていた。仕事であれば秘書である自分も同席するのだが今回は首領の個人的な買い物の為、私は待機となった。
首領には「君もたまにはお洒落したらどうだ?プレゼントしてあげよう」と言って頂いたが丁重にお断りした。そんなことに興味もする必要だって無い。
その為持て余してしまった時間をどう過ごすかを考えた結果、私の数少ない趣味である紅茶を淹れることにした。ティーセットを並べお湯を沸かす。そうだな。今日はダージリンにしよう。丁度秋摘みの茶葉が手に入ったところだ。
茶葉を入れたティーポットにお湯を注ぎ入れたタイミングでコンコンとノックの音が聞こえた。一体誰だろうか。どうぞ、と返事をすると扉がゆっくりと開く。
「失礼します、首領。ご報告したいことが・・・」
「中原幹部、お疲れ様です」
丁寧に一礼して入室してきたのは幹部の1人である中原中也だった。彼は執務室をぐるりと見渡し、首領の姿が見当たらないことに気付くと私の傍に歩み寄ってきた。
「首領は不在か?」
「えぇ。首領は私情で外出中です。ご報告とはなんでしょう?私でお伺い出来ることでしたら伝えておきますが」
「いや、いい。急ぎの案件って訳でもねぇからな。また改めて伝えに来る」
「承知しました」
「ところでそれ、紅茶か?悪ぃが俺にも淹れて貰っていいか?」
「勿論です。丁度蒸らし終わった所ですのですぐにお淹れしますね」
帽子を取り執務室に備え付けられているソファーに中原幹部は座った。
私は来客用に用意してあるシンプルなティーカップを用意し紅茶を注ぐ。ふわりと香った紅茶の香りが心地いい。
「どうぞ」
「あぁ、ありがとうな」
「っ!」
注ぎ終えたティーカップをテーブルに置こうとした私の手と受け取ろうと手を伸ばした中原幹部の手が触れそうになり反射的に手を引いてしまった。中原幹部としては私への気遣いのつもりだったのだろうけれど私にとってそれは恐怖にしかならない。
「申し訳ありません」
「いや、俺こそ配慮が足りなかった」
軽く頭を下げ、改めてテーブルにティーカップを置く。口に運び1口飲んだ中原幹部は徐に口を開いた。
「手前は、いつまでそうしてるつもりだ?」
静かな、それでも少しの怒気を含んだ声色。緊張を覚え跳ねた心臓を悟られないように声を出した。
「なんのことでしょうか?」
「しらばっくれてんじゃねぇよ。手前の異能力のことは理解してる。だがそうやって逃げてばかり居ても何も変わらねえだろ」
「・・・」
「他人に触れたくねぇなら普通に話すだけだって良いだろうが。大勢とが無理なら俺とだっていい。もう少し視野を広げたらどうだ?」
「貴方に、何が分かるのですか、」
思わず口から溢れた言葉に中原幹部の目が少し見開く。しかしすぐにいつもの鋭い目付きに戻る。
「分からねぇな。変わろうともせずに逃げてばっかりいる奴の考えなんざ」
「貴方に私の気持ちが分からないように、私にも貴方の気持ちは分かりません」
「手前、いい加減に・・・!」
「私はっ!・・・貴方の最期も見たことがあります」
昔から知るその顔が、その手が消える瞬間を何度も見た。目を閉じれば鮮明に浮かぶ程に。
ほら、今もそんな顔をする。
「・・・気にかけてくださったことはありがとうございます。ただ、それだけです」
「俺は、手前の為に何も出来ねぇのか?」
「お気持ちだけで十分です。・・・さぁ、紅茶が冷めてしまいますよ」
伝えることはこの先きっと無いけれど・・・
本当は、立場も環境も変わった中で、変わらない貴方の温かさに私はずっと救われているんですよ、中也さん
誰かと居ると自分が孤独であると余計に痛感してしまうから。
紅茶が好きだ。
その温かさや香りは荒んだ心を穏やかにしてくれるから。
執務室で首領の帰りを待っていた。仕事であれば秘書である自分も同席するのだが今回は首領の個人的な買い物の為、私は待機となった。
首領には「君もたまにはお洒落したらどうだ?プレゼントしてあげよう」と言って頂いたが丁重にお断りした。そんなことに興味もする必要だって無い。
その為持て余してしまった時間をどう過ごすかを考えた結果、私の数少ない趣味である紅茶を淹れることにした。ティーセットを並べお湯を沸かす。そうだな。今日はダージリンにしよう。丁度秋摘みの茶葉が手に入ったところだ。
茶葉を入れたティーポットにお湯を注ぎ入れたタイミングでコンコンとノックの音が聞こえた。一体誰だろうか。どうぞ、と返事をすると扉がゆっくりと開く。
「失礼します、首領。ご報告したいことが・・・」
「中原幹部、お疲れ様です」
丁寧に一礼して入室してきたのは幹部の1人である中原中也だった。彼は執務室をぐるりと見渡し、首領の姿が見当たらないことに気付くと私の傍に歩み寄ってきた。
「首領は不在か?」
「えぇ。首領は私情で外出中です。ご報告とはなんでしょう?私でお伺い出来ることでしたら伝えておきますが」
「いや、いい。急ぎの案件って訳でもねぇからな。また改めて伝えに来る」
「承知しました」
「ところでそれ、紅茶か?悪ぃが俺にも淹れて貰っていいか?」
「勿論です。丁度蒸らし終わった所ですのですぐにお淹れしますね」
帽子を取り執務室に備え付けられているソファーに中原幹部は座った。
私は来客用に用意してあるシンプルなティーカップを用意し紅茶を注ぐ。ふわりと香った紅茶の香りが心地いい。
「どうぞ」
「あぁ、ありがとうな」
「っ!」
注ぎ終えたティーカップをテーブルに置こうとした私の手と受け取ろうと手を伸ばした中原幹部の手が触れそうになり反射的に手を引いてしまった。中原幹部としては私への気遣いのつもりだったのだろうけれど私にとってそれは恐怖にしかならない。
「申し訳ありません」
「いや、俺こそ配慮が足りなかった」
軽く頭を下げ、改めてテーブルにティーカップを置く。口に運び1口飲んだ中原幹部は徐に口を開いた。
「手前は、いつまでそうしてるつもりだ?」
静かな、それでも少しの怒気を含んだ声色。緊張を覚え跳ねた心臓を悟られないように声を出した。
「なんのことでしょうか?」
「しらばっくれてんじゃねぇよ。手前の異能力のことは理解してる。だがそうやって逃げてばかり居ても何も変わらねえだろ」
「・・・」
「他人に触れたくねぇなら普通に話すだけだって良いだろうが。大勢とが無理なら俺とだっていい。もう少し視野を広げたらどうだ?」
「貴方に、何が分かるのですか、」
思わず口から溢れた言葉に中原幹部の目が少し見開く。しかしすぐにいつもの鋭い目付きに戻る。
「分からねぇな。変わろうともせずに逃げてばっかりいる奴の考えなんざ」
「貴方に私の気持ちが分からないように、私にも貴方の気持ちは分かりません」
「手前、いい加減に・・・!」
「私はっ!・・・貴方の最期も見たことがあります」
昔から知るその顔が、その手が消える瞬間を何度も見た。目を閉じれば鮮明に浮かぶ程に。
ほら、今もそんな顔をする。
「・・・気にかけてくださったことはありがとうございます。ただ、それだけです」
「俺は、手前の為に何も出来ねぇのか?」
「お気持ちだけで十分です。・・・さぁ、紅茶が冷めてしまいますよ」
伝えることはこの先きっと無いけれど・・・
本当は、立場も環境も変わった中で、変わらない貴方の温かさに私はずっと救われているんですよ、中也さん