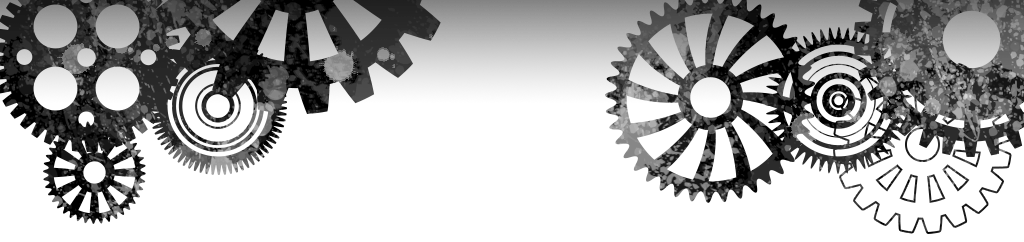孤独な鳳仙花
夢小説設定
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
「いい加減、教えてくれてもいいだろう」
「お答えしかねます」
隣に立つ私の腕を掴もうとした首領の手を避ける。本来であればこの行為は不敬に当たるが私の持つ異能力の性質上仕方のないことだ。
私には触れた相手の死の瞬間が見える。
それは5秒にも満たない短いものではあるけれど、死に顔や周囲の情景が今目の前で起きているかのように感じ取れる。
首領は自分の死の瞬間がどの様なものか知りたいようで、何度も私から聞き出そうとしてくるが私が答えることは決して無い。
「何故そんなにも知りたがるのですか?」
「当然の反応だと思うがね。それに自分のことなんだ、私にも知る権利はあるだろう?」
「自分の死に際なんて普通は知りたがりませんよ」
大概の人間は死ぬことを恐れる。いつ、どのように訪れるものなのか。そして死後に自分がどうなるかも分からないからだろう
けれど私にとっては誰かに触れる度に頭に浮かぶ最期の姿の方がずっと恐ろしい。その相手が大切な人であればあるほど、胸が締め付けられるように痛むのだから。
「君がそうして手を背に隠すのは、誰かに触れるのを拒む為だね」
「え・・・?」
不意に言われた言葉に目を開く。無意識の行動だった。つまりクセになってしまっているのだろう。誰にも触れないように、触れられないように。私なんかよりずっと聡い首領には私の考え程度お見通しというわけか。
「良いんです、触れなければ見えなくて済みます」
「なら、君のその手は一体誰がとるのかな」
「それは・・・」
「人は1人で生きていける程強くはない。だが君にとって誰かの温もりはそれ以上の悲しみを生んでしまうのだね」
背に回している手をギュッと強く握り締める。
「覚悟は、しています。だから首領以外との交流を避けて生きてきたのです」
「・・・そうか」
誰かの温もりを、優しさを求めない。最初から持たなければ欲しがることも無い。そう、自分に言い聞かせてきたのだ。
首領は悲しげに目を伏せながらひとつ溜息を吐いた。
「憐れな異能力だね。まるで呪いだ」
ズキン、とまた胸が痛む。
「本当に。自分でも、そう思います」
異能力なんて無ければ私も普通に生きられたのだろうか。誰かと手を取り合える、そんな未来があったのだろうか。
私の手は、今日もただ宙を泳ぐ。
「お答えしかねます」
隣に立つ私の腕を掴もうとした首領の手を避ける。本来であればこの行為は不敬に当たるが私の持つ異能力の性質上仕方のないことだ。
私には触れた相手の死の瞬間が見える。
それは5秒にも満たない短いものではあるけれど、死に顔や周囲の情景が今目の前で起きているかのように感じ取れる。
首領は自分の死の瞬間がどの様なものか知りたいようで、何度も私から聞き出そうとしてくるが私が答えることは決して無い。
「何故そんなにも知りたがるのですか?」
「当然の反応だと思うがね。それに自分のことなんだ、私にも知る権利はあるだろう?」
「自分の死に際なんて普通は知りたがりませんよ」
大概の人間は死ぬことを恐れる。いつ、どのように訪れるものなのか。そして死後に自分がどうなるかも分からないからだろう
けれど私にとっては誰かに触れる度に頭に浮かぶ最期の姿の方がずっと恐ろしい。その相手が大切な人であればあるほど、胸が締め付けられるように痛むのだから。
「君がそうして手を背に隠すのは、誰かに触れるのを拒む為だね」
「え・・・?」
不意に言われた言葉に目を開く。無意識の行動だった。つまりクセになってしまっているのだろう。誰にも触れないように、触れられないように。私なんかよりずっと聡い首領には私の考え程度お見通しというわけか。
「良いんです、触れなければ見えなくて済みます」
「なら、君のその手は一体誰がとるのかな」
「それは・・・」
「人は1人で生きていける程強くはない。だが君にとって誰かの温もりはそれ以上の悲しみを生んでしまうのだね」
背に回している手をギュッと強く握り締める。
「覚悟は、しています。だから首領以外との交流を避けて生きてきたのです」
「・・・そうか」
誰かの温もりを、優しさを求めない。最初から持たなければ欲しがることも無い。そう、自分に言い聞かせてきたのだ。
首領は悲しげに目を伏せながらひとつ溜息を吐いた。
「憐れな異能力だね。まるで呪いだ」
ズキン、とまた胸が痛む。
「本当に。自分でも、そう思います」
異能力なんて無ければ私も普通に生きられたのだろうか。誰かと手を取り合える、そんな未来があったのだろうか。
私の手は、今日もただ宙を泳ぐ。