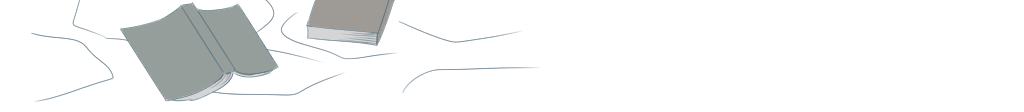二次log
それは、敵を一太刀で切り捨てた瞬間のことだった。胸の中心、奥深くに熱が灯り、じわりと指先にまで広がっていく感覚。思わず動きを止めてしまったせいで、二体目を手に掛けた隊長殿が何やら吠えている。悪い悪い、と軽い調子で返したのが悪かったのだろうか。先ほどよりも強い語調で諫められたような気もするのだが、聞き流すことにする。それよりも、内に生まれたものに意識を向けたかったのだ。一瞬で全身に広がってしまったらしく、喪失感のような、充足感のような、何とも言い表しがたいものが残るばかりであったが。
腑抜けているように見えたのか、飛んできた短刀を薙ぎ払い地に叩きつける。断末魔も上げず動かなくなったそれを飛び越え、駆ける。今ならばどこまでも走り抜けていけるような気がした。
本丸に戻ってからもどこか浮足立つ獅子王のことを、まるで顕現したばかりの頃のようだと評したのは誰であったか。薄い膜が周囲を覆ってしまっていて、向こう側からの声がぼやけてしまっている。泣きたいような、笑いたいような、叫びたいような、制御できない感情が暴れだしてしまわないように、暴れだしても構わないように。
感情の揺れは鵺にも伝播してしまったようで、ぐるる、と小さく低く響く唸りを宥めるように身体を撫でてやる。どうしたものか、と途方に暮れる獅子王の耳が軽い足音を拾い上げる。板張りの廊下を駆けてくる審神者もまた、どこか興奮した様子で獅子王を視界に捉えた。そして、獅子王はようやく感情の行く末を知る。紛れもなく、安堵であった。
獅子王は平安時代に打たれ、鵺退治の褒賞として天皇より下賜された刀であった。誇りと共に赤松家へと受け継がれた流れは、天下分け目の戦いにより行き先を変えることとなる。関ヶ原の戦いにおいて石田三成率いる西軍に名を連ね、されど西軍の敗北を知るや徳川家康に下った但馬国竹田城主、赤松広秀。西軍に属する鳥取城下を焼き払ったにもかかわらず、それを咎められ切腹を命じられた彼は最後の城主となり、そして獅子王は赤松家から「没収」となった。
竹田の城で、雲海に沈む城下を眺める眼差しを覚えている。民を慈しむ声を覚えている。民に愛されていた姿を覚えている。東軍へ寝返れという声への苦悩も、決断も、自刃を命じられた絶望も、忘れることができないのだ。だって、彼を愛していた。共に、次代への移ろいを見続けたいと願っていた。
勿論、次に持ち主となった土岐の家でも大切にされた。彼らもまた、赤松同様に源頼政の流れを汲む一族である。明治時代に皇室へ献上されたことだって、大切にされたが故のことであると分かっている。その時々の主を、獅子王は愛していた。愛されていると知っていた。元より褒賞として下賜された刀であるのだ。目出度い、愛でたい、めでたいと、主が変わることだって多かった。だから慣れている、はずだったのだ。最後に聞いた怨嗟の声があの場所であったから。主を奪い、そして獅子王 までも奪うのかと。嘆き苦しむ声に見送られ、旅立った場所であった。
西軍から東軍へと寝返りながら、切腹を命じられた敗者。
史実を辿る上ではただそれだけの扱いしかされない最後の城主、赤松広秀の名誉を今こそ回復しようと、奪われた獅子王の、せめて写し身だけでも取り戻すことができたならばと。審神者の存在が認知され始め、獅子王という刀剣男士の存在が火付け役になったのだとするのならば、これほどに嬉しいことはなかった。
戦場で何かが灯ったあの瞬間こそ、本霊にそれが伝えられた瞬間であったのだろう。写しが作られ、竹田城に奉納されるのだと。ああ、彼らは獅子王の存在を忘れていなかったのだと、未だに求め続けてくれていたのだと、写しの身とはいえ帰還が許される時代になったのだと、愛し子たちは最後の城主を今でも愛してくれているのだと。本丸中に触れ回ってやりたかった。赤松広秀は、獅子王は、民に愛されていた。いや、未だに愛されている。求められている。今ならば戦場をどこまでも駆け抜けていき、いくらでも敵を切り捨てることができるだろう。
「嬉しい、嬉しいなぁ鵺」
思わず漏れてしまったそれに応える言葉を持ち合わせていない鵺は、額を獅子王の頬にぐりぐりと押し付けた。少しして離れたその場所が薄らと水滴を纏っているのを見て、己が泣いていることを知る。泣いたことなど、いつぶりだろうか。喜びのあまりに泣いてしまったことなど、いつぶりだろうか。自覚してしまうと、もう駄目だった。
どのような言葉でも、この感情を言い表しきることなんてできないだろう。それでもどうにかして言葉にしたくて、嬉しい、と。足りない部分を埋めるように溢れる涙を拭うことなく、獅子王は鵺を抱き寄せる。ひらり、ひらりと花弁の舞う部屋の中でただじっと、身体の内に広がる熱に身を委ねていた。
二〇一八年、四月二十二日。江戸、明治、大正、昭和、そして平成。四百十八年ぶりの地は随分と様子が変わってしまっていた。あちらこちらに同じ顔が見える。どこかに本霊が紛れ込んでいるのかもしれないが、今日ばかりは許されるだろう。刀本来の使い方をされることなどないであろう、血を知らぬ白刃。青空の下で輝くそれに、ほっと息を吐く。未来への道を切り開き、歴史と絆を繋ぐ任を与えられた大切な子。これほどまでに愛され、望まれて生まれてきた愛し子に魂が宿る日も近いだろう。
おかえり、という声に花が舞う。
腑抜けているように見えたのか、飛んできた短刀を薙ぎ払い地に叩きつける。断末魔も上げず動かなくなったそれを飛び越え、駆ける。今ならばどこまでも走り抜けていけるような気がした。
本丸に戻ってからもどこか浮足立つ獅子王のことを、まるで顕現したばかりの頃のようだと評したのは誰であったか。薄い膜が周囲を覆ってしまっていて、向こう側からの声がぼやけてしまっている。泣きたいような、笑いたいような、叫びたいような、制御できない感情が暴れだしてしまわないように、暴れだしても構わないように。
感情の揺れは鵺にも伝播してしまったようで、ぐるる、と小さく低く響く唸りを宥めるように身体を撫でてやる。どうしたものか、と途方に暮れる獅子王の耳が軽い足音を拾い上げる。板張りの廊下を駆けてくる審神者もまた、どこか興奮した様子で獅子王を視界に捉えた。そして、獅子王はようやく感情の行く末を知る。紛れもなく、安堵であった。
獅子王は平安時代に打たれ、鵺退治の褒賞として天皇より下賜された刀であった。誇りと共に赤松家へと受け継がれた流れは、天下分け目の戦いにより行き先を変えることとなる。関ヶ原の戦いにおいて石田三成率いる西軍に名を連ね、されど西軍の敗北を知るや徳川家康に下った但馬国竹田城主、赤松広秀。西軍に属する鳥取城下を焼き払ったにもかかわらず、それを咎められ切腹を命じられた彼は最後の城主となり、そして獅子王は赤松家から「没収」となった。
竹田の城で、雲海に沈む城下を眺める眼差しを覚えている。民を慈しむ声を覚えている。民に愛されていた姿を覚えている。東軍へ寝返れという声への苦悩も、決断も、自刃を命じられた絶望も、忘れることができないのだ。だって、彼を愛していた。共に、次代への移ろいを見続けたいと願っていた。
勿論、次に持ち主となった土岐の家でも大切にされた。彼らもまた、赤松同様に源頼政の流れを汲む一族である。明治時代に皇室へ献上されたことだって、大切にされたが故のことであると分かっている。その時々の主を、獅子王は愛していた。愛されていると知っていた。元より褒賞として下賜された刀であるのだ。目出度い、愛でたい、めでたいと、主が変わることだって多かった。だから慣れている、はずだったのだ。最後に聞いた怨嗟の声があの場所であったから。主を奪い、そして
西軍から東軍へと寝返りながら、切腹を命じられた敗者。
史実を辿る上ではただそれだけの扱いしかされない最後の城主、赤松広秀の名誉を今こそ回復しようと、奪われた獅子王の、せめて写し身だけでも取り戻すことができたならばと。審神者の存在が認知され始め、獅子王という刀剣男士の存在が火付け役になったのだとするのならば、これほどに嬉しいことはなかった。
戦場で何かが灯ったあの瞬間こそ、本霊にそれが伝えられた瞬間であったのだろう。写しが作られ、竹田城に奉納されるのだと。ああ、彼らは獅子王の存在を忘れていなかったのだと、未だに求め続けてくれていたのだと、写しの身とはいえ帰還が許される時代になったのだと、愛し子たちは最後の城主を今でも愛してくれているのだと。本丸中に触れ回ってやりたかった。赤松広秀は、獅子王は、民に愛されていた。いや、未だに愛されている。求められている。今ならば戦場をどこまでも駆け抜けていき、いくらでも敵を切り捨てることができるだろう。
「嬉しい、嬉しいなぁ鵺」
思わず漏れてしまったそれに応える言葉を持ち合わせていない鵺は、額を獅子王の頬にぐりぐりと押し付けた。少しして離れたその場所が薄らと水滴を纏っているのを見て、己が泣いていることを知る。泣いたことなど、いつぶりだろうか。喜びのあまりに泣いてしまったことなど、いつぶりだろうか。自覚してしまうと、もう駄目だった。
どのような言葉でも、この感情を言い表しきることなんてできないだろう。それでもどうにかして言葉にしたくて、嬉しい、と。足りない部分を埋めるように溢れる涙を拭うことなく、獅子王は鵺を抱き寄せる。ひらり、ひらりと花弁の舞う部屋の中でただじっと、身体の内に広がる熱に身を委ねていた。
二〇一八年、四月二十二日。江戸、明治、大正、昭和、そして平成。四百十八年ぶりの地は随分と様子が変わってしまっていた。あちらこちらに同じ顔が見える。どこかに本霊が紛れ込んでいるのかもしれないが、今日ばかりは許されるだろう。刀本来の使い方をされることなどないであろう、血を知らぬ白刃。青空の下で輝くそれに、ほっと息を吐く。未来への道を切り開き、歴史と絆を繋ぐ任を与えられた大切な子。これほどまでに愛され、望まれて生まれてきた愛し子に魂が宿る日も近いだろう。
おかえり、という声に花が舞う。
8/27ページ