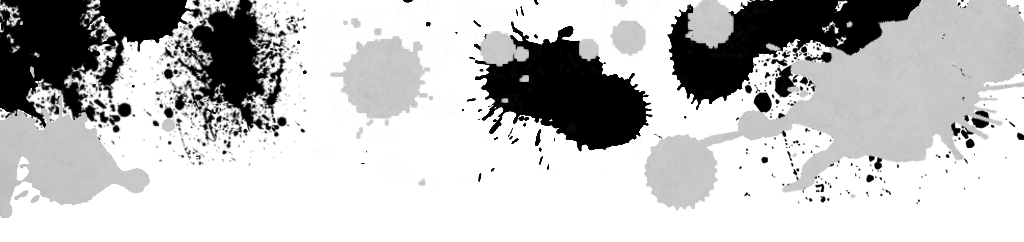はじまりの物語
ザァーーッ
大雨の日は全ての音が聞こえない。
聴こえないといけない音さえも聞こえなくなってしまう。
それを憎んでいた。
ずっとーーーーーーーーっ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
時は1925年。
ここはイギリスにあるコンツウェルド地方のモーリス村。
イギリスの中でも最も人口が最も少なく平和な村。
そこに住むのが僕、キャメロ・ワトソンだ。
今日は特別な日。
なぜなら今日は僕の中学校を卒業する日。
学校といっても人数は、20数名の男女。小学生と中学生合同の学校になっている。
村から学校まで20分ほどの場所にある。
そして、幼馴染であるヴァネッサに告白したくて式が終わってから告白しようと思う。
「今日まで2年間勉学によく励んできましたね。これから新しい学生生活がはじまります。
遠くの学校へ行く子もありますが、このまま仕事に出向く子もいます。」
校長先生の言葉が学校全体に響き渡る。
卒業式の式典が全て終わり、友人や先生に別れを告げ、ヴァネッサと一緒に帰宅した。
「…ヴァネッサ」
「どうしたの?そんな顔して」
「あのさ……、卒業したら引っ越すの?」
「そうだね。パパの転勤で中央区の方に行くことになったの」
……ここは地方の村。
僕の職場は南区のほうだった。中央区なんて都会だ。どうあがいても今日か引っ越しする日が最後に会える日になる。
「…………。」
僕は黙り込んでしまった。
すると、
「キャメロ、淋しいんでしょ。
いつも私がいる日常で、パパの転勤で引っ越しだもんね。
でも、いつか会えるから。それまでは、ね?」
「僕は寂しくないよ。全然。むしろ、元気でいてほしいよ。
たとえ、遠くへ行ってもね」
嘘だ。
本当は寂しいし、きっと次会う時は恋人なんてできているだろうって思う。
でも、これはけじめだし。
「ふふ、本当に?淋しいって顔してるよ」
「そんなんじゃないよ。そういえばさ、僕」
僕は告白する。これでヴァネッサとの友情が壊れようとも。
言うんだ、キャメロ!
すると、
「あれ、おかしくない?」
ヴァネッサは村の方を見た。平和だった村は火の海だった。
さっきまでの淡い青春とは裏腹に目の前は地獄のようだった。
火の海の中に黒い姿があった。そのヤツと目があった。
鋭い目つきに黄色い瞳。そこには殺意しかないように見えた。目が合った瞬間、奴は逃げた。
僕は奴を追いかけた。
「キャメロ!だめ!!」
ヴァネッサの声は耳に入ってこなかった。
奴は足が速くてとてもじゃないが、おいつくことができず、見失ってしまった。
近くには僕の家があった。
窓は割れ、木製のドアは壊されていて、ワトソン家の中は火が広がり、部屋は荒らされていた。
火の手が広がり、天井のは崩れ、瓦礫の下敷きになっている母さんを見つけた。
「母さん!!母さん!!」
そう叫んでいたところにヴァネッサが追いかけてきた。
「キャメロ…!」
「ヴァネッサ…、母さんが……」
大人たちは家の中で怪我をして逃げられずにいる人も、殺された人もいた。
助けてくれる大人はいなかった。子供ながらに自分の無力さを痛感し、落ち込んでいるとヴァネッサが思い出したかのように、
「…!パパとママは!」
そう言うと、ヴァネッサは自分の家に走り出した。
ヴァネッサの家はそこまで火の手があがっていなかったこともあり、ヴァネッサが家に入った瞬間、瓦礫が落ち、一気に火の手があがってしまった。ヴァネッサは気づかずに奥に入ってしまった。
どうしよう…。
僕には待ち続けることしかできない。
ポツ………
空を見上げると雨が降ってきた。
ザアーーー
雨だ。
しばらく雨の中外で立っていると、火事になっている家や火の海になっている道は鎮火された。
ヴァネッサの家はどうなったんだろうか。
家に入り、一階をずっと探した。すると、勝手口に倒れていた。足が瓦礫の下敷きだ。僕には何もできなかった…。
ヴァネッサの元に寄り添い、
「ヴァネッサ……、守ってやれなくてごめんね。
僕は弱いから。だから君を守れなかった。ごめんね…………」
そう言って僕は気絶してしまった———。
大雨の日は全ての音が聞こえない。
聴こえないといけない音さえも聞こえなくなってしまう。
それを憎んでいた。
ずっとーーーーーーーーっ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
時は1925年。
ここはイギリスにあるコンツウェルド地方のモーリス村。
イギリスの中でも最も人口が最も少なく平和な村。
そこに住むのが僕、キャメロ・ワトソンだ。
今日は特別な日。
なぜなら今日は僕の中学校を卒業する日。
学校といっても人数は、20数名の男女。小学生と中学生合同の学校になっている。
村から学校まで20分ほどの場所にある。
そして、幼馴染であるヴァネッサに告白したくて式が終わってから告白しようと思う。
「今日まで2年間勉学によく励んできましたね。これから新しい学生生活がはじまります。
遠くの学校へ行く子もありますが、このまま仕事に出向く子もいます。」
校長先生の言葉が学校全体に響き渡る。
卒業式の式典が全て終わり、友人や先生に別れを告げ、ヴァネッサと一緒に帰宅した。
「…ヴァネッサ」
「どうしたの?そんな顔して」
「あのさ……、卒業したら引っ越すの?」
「そうだね。パパの転勤で中央区の方に行くことになったの」
……ここは地方の村。
僕の職場は南区のほうだった。中央区なんて都会だ。どうあがいても今日か引っ越しする日が最後に会える日になる。
「…………。」
僕は黙り込んでしまった。
すると、
「キャメロ、淋しいんでしょ。
いつも私がいる日常で、パパの転勤で引っ越しだもんね。
でも、いつか会えるから。それまでは、ね?」
「僕は寂しくないよ。全然。むしろ、元気でいてほしいよ。
たとえ、遠くへ行ってもね」
嘘だ。
本当は寂しいし、きっと次会う時は恋人なんてできているだろうって思う。
でも、これはけじめだし。
「ふふ、本当に?淋しいって顔してるよ」
「そんなんじゃないよ。そういえばさ、僕」
僕は告白する。これでヴァネッサとの友情が壊れようとも。
言うんだ、キャメロ!
すると、
「あれ、おかしくない?」
ヴァネッサは村の方を見た。平和だった村は火の海だった。
さっきまでの淡い青春とは裏腹に目の前は地獄のようだった。
火の海の中に黒い姿があった。そのヤツと目があった。
鋭い目つきに黄色い瞳。そこには殺意しかないように見えた。目が合った瞬間、奴は逃げた。
僕は奴を追いかけた。
「キャメロ!だめ!!」
ヴァネッサの声は耳に入ってこなかった。
奴は足が速くてとてもじゃないが、おいつくことができず、見失ってしまった。
近くには僕の家があった。
窓は割れ、木製のドアは壊されていて、ワトソン家の中は火が広がり、部屋は荒らされていた。
火の手が広がり、天井のは崩れ、瓦礫の下敷きになっている母さんを見つけた。
「母さん!!母さん!!」
そう叫んでいたところにヴァネッサが追いかけてきた。
「キャメロ…!」
「ヴァネッサ…、母さんが……」
大人たちは家の中で怪我をして逃げられずにいる人も、殺された人もいた。
助けてくれる大人はいなかった。子供ながらに自分の無力さを痛感し、落ち込んでいるとヴァネッサが思い出したかのように、
「…!パパとママは!」
そう言うと、ヴァネッサは自分の家に走り出した。
ヴァネッサの家はそこまで火の手があがっていなかったこともあり、ヴァネッサが家に入った瞬間、瓦礫が落ち、一気に火の手があがってしまった。ヴァネッサは気づかずに奥に入ってしまった。
どうしよう…。
僕には待ち続けることしかできない。
ポツ………
空を見上げると雨が降ってきた。
ザアーーー
雨だ。
しばらく雨の中外で立っていると、火事になっている家や火の海になっている道は鎮火された。
ヴァネッサの家はどうなったんだろうか。
家に入り、一階をずっと探した。すると、勝手口に倒れていた。足が瓦礫の下敷きだ。僕には何もできなかった…。
ヴァネッサの元に寄り添い、
「ヴァネッサ……、守ってやれなくてごめんね。
僕は弱いから。だから君を守れなかった。ごめんね…………」
そう言って僕は気絶してしまった———。
1/3ページ