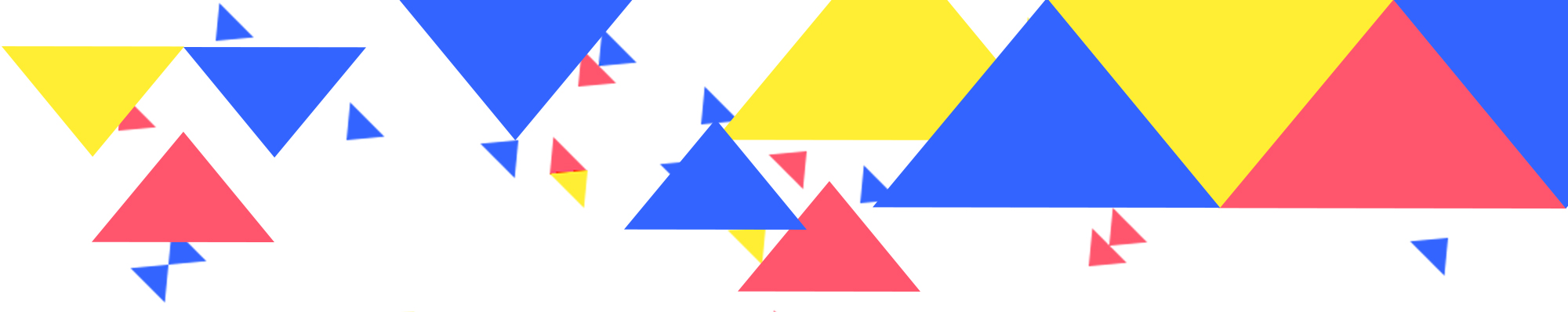一番になれたら
(平凡×不良/非王道)
俺のことを好きになる人は、いつも忘れられない人がいた。
いつも、と言っても、告白されたのはたったの2回なのだけど。前の彼氏に似ている、と言われたり、小学生の初恋の人に告白し続けていたり、きっとこの人の一番は俺じゃないんだろうな、と好きだという耳障りの良い言葉を聞きながら思った甘酸っぱい中学時代。
勿論本当のことは分からない。その時は俺のことを一番好きでいてくれたのかもしれないが、俺と忘れられない人を天秤に掛けたとしたら、向こうに傾いてしまうだろう。俺は踏み込むのが、自分が傷付くのが怖くて、一歩も踏み出せなかった。構わず踏み出してれば、童貞から脱することができたかもしれないのに、惜しいことをした。というわけで、俺は恋人いない歴と年齢が一致するに至っている。
場違いな金持ち学校に迷いこんでしまった高校生活も2年目。山奥の男子校に入ってからというもの、さらに恋人いない歴を更新中だ。
「平凡。あんたにお客。清城様に何かしたわけ?」
それはもうそこらの女の子より可愛いんじゃないかって顔をしかめて、俺の目の前で腕を組んだクラスメートに苦笑を溢す。確かに俺は、街を出歩いていないにも関わらず、昨日街にいたよね?なんて言われるようなどこにでもいる顔だが、平凡だなんて呼ばれ方は如何なものかと思う。そもそもこの学園の顔面偏差値が高いのだ。まぁ言い返すのも飽きたし、どうでもいいけど。
「してないはずだけど。誰?」
「菊沢様だよ。清城様の親衛隊長のさぁ。」
そんなのもしらないわけ?とでも聞こえてきそうな顔に、ごめんね、と先回りして謝ることにした。カバンのポケットからチョコレートを取り出して、何やらぷりぷりしているクラスメートの手のひらに置く。
「ありがとう。授業に遅れたら、先生に俺は体調不良ですって伝えておいてもらえる?」
「しょうがいないから引き受けてあげる。...、何かされたら連絡しなよ、日比野。」
「ん。」
あげたチョコレートをぎゅっと握って、心配してくれるクラスメートに見送られながら、俺は教室の扉近くに立っているやたら男前な人物の前に立った。金髪に着崩した制服。金持ちだらけの学校には珍しい、所謂不良に属する人物だ。腕っぷしが強いってもっぱらの噂。
「俺が日比野だけど。」
顎で付いてこい、とされて、あまり背の変わらない背中を追う。ざわざわと廊下の生徒たちがざわめいて、あの平凡は何をやらかしたんだ、とか、平凡が菊沢様と話すなんて、とかが聞こえてきた。学園の生徒たちは、山奥の男子校に小学生のころから入れられいるのがほとんどで、この学園には独自のルールと文化が存在する。親衛隊はその一つだ。
顔が綺麗な人物を心酔した生徒をまとめて、思春期の性欲やらなんやらから守ったりする親衛隊。この菊沢という人物はその1つを統率しているのだ。親衛対象である清城は色が白く綺麗な顔立ちで成績優秀で、そういえば生徒会の役員についていた気がする。笑うと笑窪が出来る、華やかで綺麗な人で、菊沢と並ぶとより一層華やかだった。まぁ直接会ったことも、ましてや話したことだってないんだけど。
菊沢は人の気配がなくなったところで立ち止まると、俺を振り返った。
「それで話って?」
一度口を開いたと思ったら直ぐに閉じて、俯いて唾を飲み込んだ菊沢の言葉をただ待つ。それにしても綺麗な人だな。光が当たった金髪はきらきらと輝いていて、本当に同じ人間なのかと場違いなことを思った。耳に穴の1つもなくて、拳だって綺麗なもんだし。不良だ、と聞いていたが、不良じゃないと言い張っている地元の友人のほうがよっぽど不良らしい。
「ピアスしないの?」
「あ?」
「あ、ごめん。思ってたことが口に出た。」
「...、いや。ピアス?ゆきが空けんなって言うから空けてねぇだけ。」
ゆきって誰だ、と思ったが、清城の下の名前は確か英幸だったと思い出した。親衛隊長というだけあって、菊沢の世界は清城を中心に回っているらしい。
「日比野 譲。好きだ。」
突然呼ばれたフルネームに、知られていたのかと驚いて、何か重大なことを聞き逃した気がする。...、嘘。ばっちり聞いた。
「...、えっと?」
「好きだから、付き合ってほしい。」
真っ直ぐ俺を見る少し垂れた目は、真剣過ぎて少しだけキツい。
「あー。ちょっと予想外だった。ちょっと待って。」
「...、もしかして制裁だと思ったのか?」
心外だ、と言いたげな菊沢に、慌てて顔の前で手を振った。思ってはいたが、傷付いたように眉を寄せる菊沢に言えるわけがない。親衛対象に相応しくないと認識された生徒は、親衛隊から制裁という名の呼び出しを食らうのだ。クラスメートが心配していたことはここにある。大抵が注意で終わらず、手が出たりすることがほとんどなのだ。
「俺はゆきの付き合う奴等に文句を言うつもりはねぇ。それはゆきの自由だし、他の奴等にも言ってある。それが徹底できねぇって言うんなら、俺の責任だな。」
「いや、さ?そういう噂は聞いたことないよ。ただ、菊沢、様が俺自身に用があるなんて思わなかったから。」
「...、様とかつけてんじゃねぇよ。」
む、とした顔の菊沢に、さっきから顔に感情が出やすいなと小さく笑う。
「そう?じゃあ菊沢って呼ぶわ。」
嬉しそうだが、少しだけ残念そう顔をした菊沢に、本当に俺のことが好きなんだな、とぼんやりと思った。それでもやっぱり俺のことを好きになる人は、俺のことを本当の一番にしてくれないらしい。
「菊沢はさ?」
俺の目を見つめている菊沢の髪に指を通して掻き上げ、右耳に触れた。菊沢の揺れる声が、俺の名前を呼ぶ。
「俺が穴を開けてって言ったら、開けてくれる?」
「え?」
「何てね。俺は菊沢のことを何も知らないから、友達からでもいい?答えは少し考えさせて。」
手を離そうとすれば、菊沢に手を掴まれて、頬を寄せられた。
「開ける。お前が開けろって言うんなら開ける。」
「大好きな清城様に泣かれるかもよ?」
「関係ねぇよ。」
あっさり言ってのけた菊沢に目を瞬かせれば、初めて笑った菊沢が俺の耳に手を伸ばす。耳にはめているピアスを指先で撫でると、目を真っ直ぐ見つめられた。
「なぁ。そしたらコレ、1つくれる?」
「...、いいよ。」
嬉しそうにはにかんだ菊沢に促されるまま、連絡先を交換すると、菊沢は軽い足取りで去っていった。画面に映し出された、菊沢 悠介の文字に何だか複雑な気分になる。踏み出していいものかと、目を閉じて、触れられていた耳たぶを撫でたのだった。
俺のことを好きになる人は、いつも忘れられない人がいた。
いつも、と言っても、告白されたのはたったの2回なのだけど。前の彼氏に似ている、と言われたり、小学生の初恋の人に告白し続けていたり、きっとこの人の一番は俺じゃないんだろうな、と好きだという耳障りの良い言葉を聞きながら思った甘酸っぱい中学時代。
勿論本当のことは分からない。その時は俺のことを一番好きでいてくれたのかもしれないが、俺と忘れられない人を天秤に掛けたとしたら、向こうに傾いてしまうだろう。俺は踏み込むのが、自分が傷付くのが怖くて、一歩も踏み出せなかった。構わず踏み出してれば、童貞から脱することができたかもしれないのに、惜しいことをした。というわけで、俺は恋人いない歴と年齢が一致するに至っている。
場違いな金持ち学校に迷いこんでしまった高校生活も2年目。山奥の男子校に入ってからというもの、さらに恋人いない歴を更新中だ。
「平凡。あんたにお客。清城様に何かしたわけ?」
それはもうそこらの女の子より可愛いんじゃないかって顔をしかめて、俺の目の前で腕を組んだクラスメートに苦笑を溢す。確かに俺は、街を出歩いていないにも関わらず、昨日街にいたよね?なんて言われるようなどこにでもいる顔だが、平凡だなんて呼ばれ方は如何なものかと思う。そもそもこの学園の顔面偏差値が高いのだ。まぁ言い返すのも飽きたし、どうでもいいけど。
「してないはずだけど。誰?」
「菊沢様だよ。清城様の親衛隊長のさぁ。」
そんなのもしらないわけ?とでも聞こえてきそうな顔に、ごめんね、と先回りして謝ることにした。カバンのポケットからチョコレートを取り出して、何やらぷりぷりしているクラスメートの手のひらに置く。
「ありがとう。授業に遅れたら、先生に俺は体調不良ですって伝えておいてもらえる?」
「しょうがいないから引き受けてあげる。...、何かされたら連絡しなよ、日比野。」
「ん。」
あげたチョコレートをぎゅっと握って、心配してくれるクラスメートに見送られながら、俺は教室の扉近くに立っているやたら男前な人物の前に立った。金髪に着崩した制服。金持ちだらけの学校には珍しい、所謂不良に属する人物だ。腕っぷしが強いってもっぱらの噂。
「俺が日比野だけど。」
顎で付いてこい、とされて、あまり背の変わらない背中を追う。ざわざわと廊下の生徒たちがざわめいて、あの平凡は何をやらかしたんだ、とか、平凡が菊沢様と話すなんて、とかが聞こえてきた。学園の生徒たちは、山奥の男子校に小学生のころから入れられいるのがほとんどで、この学園には独自のルールと文化が存在する。親衛隊はその一つだ。
顔が綺麗な人物を心酔した生徒をまとめて、思春期の性欲やらなんやらから守ったりする親衛隊。この菊沢という人物はその1つを統率しているのだ。親衛対象である清城は色が白く綺麗な顔立ちで成績優秀で、そういえば生徒会の役員についていた気がする。笑うと笑窪が出来る、華やかで綺麗な人で、菊沢と並ぶとより一層華やかだった。まぁ直接会ったことも、ましてや話したことだってないんだけど。
菊沢は人の気配がなくなったところで立ち止まると、俺を振り返った。
「それで話って?」
一度口を開いたと思ったら直ぐに閉じて、俯いて唾を飲み込んだ菊沢の言葉をただ待つ。それにしても綺麗な人だな。光が当たった金髪はきらきらと輝いていて、本当に同じ人間なのかと場違いなことを思った。耳に穴の1つもなくて、拳だって綺麗なもんだし。不良だ、と聞いていたが、不良じゃないと言い張っている地元の友人のほうがよっぽど不良らしい。
「ピアスしないの?」
「あ?」
「あ、ごめん。思ってたことが口に出た。」
「...、いや。ピアス?ゆきが空けんなって言うから空けてねぇだけ。」
ゆきって誰だ、と思ったが、清城の下の名前は確か英幸だったと思い出した。親衛隊長というだけあって、菊沢の世界は清城を中心に回っているらしい。
「日比野 譲。好きだ。」
突然呼ばれたフルネームに、知られていたのかと驚いて、何か重大なことを聞き逃した気がする。...、嘘。ばっちり聞いた。
「...、えっと?」
「好きだから、付き合ってほしい。」
真っ直ぐ俺を見る少し垂れた目は、真剣過ぎて少しだけキツい。
「あー。ちょっと予想外だった。ちょっと待って。」
「...、もしかして制裁だと思ったのか?」
心外だ、と言いたげな菊沢に、慌てて顔の前で手を振った。思ってはいたが、傷付いたように眉を寄せる菊沢に言えるわけがない。親衛対象に相応しくないと認識された生徒は、親衛隊から制裁という名の呼び出しを食らうのだ。クラスメートが心配していたことはここにある。大抵が注意で終わらず、手が出たりすることがほとんどなのだ。
「俺はゆきの付き合う奴等に文句を言うつもりはねぇ。それはゆきの自由だし、他の奴等にも言ってある。それが徹底できねぇって言うんなら、俺の責任だな。」
「いや、さ?そういう噂は聞いたことないよ。ただ、菊沢、様が俺自身に用があるなんて思わなかったから。」
「...、様とかつけてんじゃねぇよ。」
む、とした顔の菊沢に、さっきから顔に感情が出やすいなと小さく笑う。
「そう?じゃあ菊沢って呼ぶわ。」
嬉しそうだが、少しだけ残念そう顔をした菊沢に、本当に俺のことが好きなんだな、とぼんやりと思った。それでもやっぱり俺のことを好きになる人は、俺のことを本当の一番にしてくれないらしい。
「菊沢はさ?」
俺の目を見つめている菊沢の髪に指を通して掻き上げ、右耳に触れた。菊沢の揺れる声が、俺の名前を呼ぶ。
「俺が穴を開けてって言ったら、開けてくれる?」
「え?」
「何てね。俺は菊沢のことを何も知らないから、友達からでもいい?答えは少し考えさせて。」
手を離そうとすれば、菊沢に手を掴まれて、頬を寄せられた。
「開ける。お前が開けろって言うんなら開ける。」
「大好きな清城様に泣かれるかもよ?」
「関係ねぇよ。」
あっさり言ってのけた菊沢に目を瞬かせれば、初めて笑った菊沢が俺の耳に手を伸ばす。耳にはめているピアスを指先で撫でると、目を真っ直ぐ見つめられた。
「なぁ。そしたらコレ、1つくれる?」
「...、いいよ。」
嬉しそうにはにかんだ菊沢に促されるまま、連絡先を交換すると、菊沢は軽い足取りで去っていった。画面に映し出された、菊沢 悠介の文字に何だか複雑な気分になる。踏み出していいものかと、目を閉じて、触れられていた耳たぶを撫でたのだった。
1/1ページ