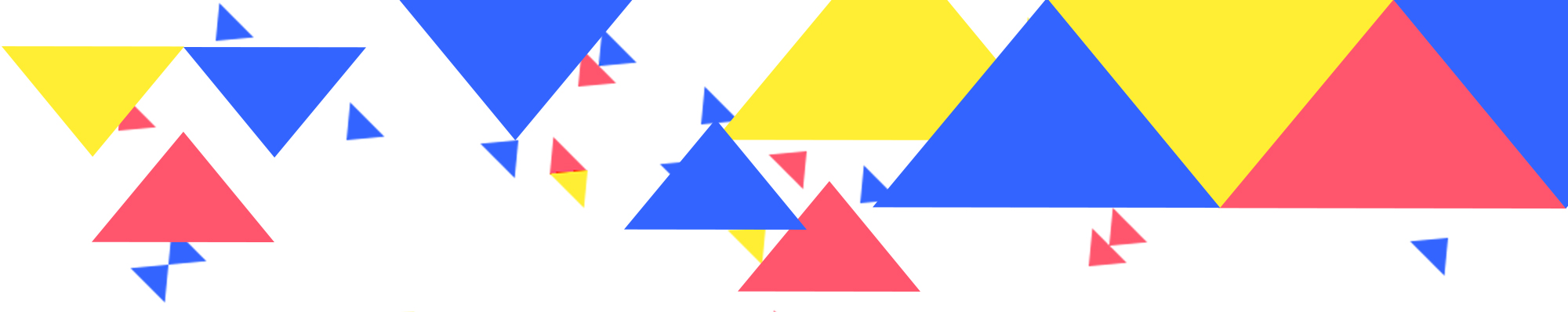あなたの心の中の小さな棘になればいい
(真面目×不良)
煙草が吸えないストレスを、ジッポの蓋を開け閉めして弄ぶことでやり過ごす昼休み。一口食べたパンのカスタードクリームは生温くて、怠さが倍増した。廊下のざわめきは、屋上の扉近くの踊り場からは遠くて、何だか全部が面倒くさくなる。もう今日はこのまま家に帰ってしまおうかなんて考えた。
「そういえばさ、はっしー。あの後、どうなったわけ?」
俺の隣で同じように怠そうに座っていた赤い前髪をカチューシャで上げた甘田がゆるい口調で問うと、金髪を掻きながら橋塚がおにぎりを頬張ってから、なんてことないように口を開く。
「付き合うことになったわ。」
「なんだよ。まじかよ。」
橋塚が女子に声を掛けられたのは昨日のことでそこには俺もいた。甘田は教師に呼び出されて、課題を出されたとかで置いて帰ったせいでいなかった。声を掛けてきた来た女子たちは、まつげはバサバサで化粧はケバい。香水付けすぎ。スカートは短くて、かかんだ時のことなんか考えてないんじゃねぇのかと思うし、そこから伸びた足は不健康に細い。媚びるように腕に回された指先を思い出して怠さが増した。
「お前はどうすんの?」
甘田が恨みがましげに俺を見るから、苦笑しながらパンを口に運ぶ。やっぱりカスタードクリームがぬるい。
「あー。俺はパス。真面目な彼女がほしい。黒髪で本好きなでスカートが長い子。」
「世界が違う系?お前がこの学校にいる限りないわ。」
「うるせぇわ。」
家から近いという理由で選んだ高校は男子校で、外に出会いを求めるしかないが、俺の好みのタイプはまず近くに寄ってきてくれないのだ。
「そういう子は、まず同じ学校で距離詰めるしかないでしょうよ。外で見つけるとか奇跡が起こんない限り無理じゃん。」
「...、もう転校すっか。」
半ば本気で呟けば、二人からは爆笑が返ってきて、八つ当たりで甘田の頭を叩く。
と。
缶コーヒーと文庫本を片手に階段を上ってきた黒髪に黒いフレームの眼鏡をかけた生徒は、垂れた目を細めて小さく笑った。
「あ。やっぱりここにいた。甘田、先生が呼んでたよ。課題を白紙で出したんだって?」
「やべ!行ってくる!ありがとう!佐藤っち!」
「職員室だから。」
バタバタと駆けていく甘田に、俺と橋塚は残りの昼飯を口に放ると後を追う。佐藤と呼ばれた生徒の横を通るときに、ちらりと彼を横目に見た。上まできっちり上げられたネクタイ。シャツもスラックスも校則通りに着こなして、いかにも真面目そうな彼は、甘田の言葉を借りれば世界が違うという言葉が当てはまる。こういう奴は大抵俺たちをはなっから嫌っていたりするもんだが、こいつはそうでもないらしい。これから関わることもないからどうでもいいかとそのまま横を通りすぎて、階段を下りた。
「あいつ馬鹿じゃねぇの。」
「もとからだろ。」
俺の呆れた苦笑に、橋塚は欠伸をしながら甘田が聞いたら口を尖らせて拗ねそうなことを言い放つ。汗を掻いた紙パックのストローに口をつけてカフェオレを飲めば、中身が僅かだったようでぐしゃりと紙パックを潰した。
「どうする?授業出るか?」
橋塚が面倒くさげに首を傾げるのをちらりと見てから、足元に視線を落とす。
「次なんだっけ?」
「英語だろ。」
「英語か。まだ単位大丈夫だわ。」
どっかで煙草吸ってくる、と言いかけて、自分がジッポを忘れてきたことに気が付いて溜め息を吐いた。
「忘れもんした。先行っといて。」
「了解。」
来た道を戻って、先ほど昼飯を食べていた場所に案の定置きっぱなしになっていたジッポを手に取る。ふと。そこで感じだ風に顔を上げれば、先ほどまで鍵がしまっていて開かなかった屋上への扉が開いていて、目を瞬かせた。錆び付いた扉のドアノブに手をかけてゆっくりと押せば、佐藤がちょうど咥えた煙草に火を付けようとしたところだった。
「あれ?行ったと思ってたのに。」
困ったように笑う佐藤に、小さく笑う。きっちり上まで留められていたカッターシャツのボタンが今は一番上が外されて、ネクタイも弛めてあった。佐藤の近くまで歩いていくと、口に咥えていた煙草にジッポの火を向ける。楽しげに唇の端が笑い、佐藤が煙草を俺が差し出したジッポで火を付けた。中指と薬指の間に煙草を挟んで持ち、口元を覆うようにして煙を吐き出した佐藤は、それ格好いいね、と小さく笑いながら俺のジッポを指差す。メタルプレートにスカルをモチーフにした絵柄が描かれたこれは、俺のお気に入りだ。
「ああ。これ?いいだろ。」
「うん。俺も買おっかな。いくらした?」
「一万ちょっと。」
「やっぱり結構高いな。」
「バイト代注ぎ込んだ。」
バイトかぁ、と独り言ちながら佐藤は自分のライターを眺め、ゆっくり煙を吐き出す。
「1本いる?」
「貰う。」
佐藤はスラックスのポケットから、長い間大切に使われているのだうかがえるシルバーのケースを取り出した。開いたケースには煙草が並んでいる。
「それも格好いいじゃん。」
「ありがと。これ、死んだじいさんの形見でさ、若い頃にイギリスでもらったやつらしい。」
よく見れば、所々傷があったり浅くへこんだりしていた。佐藤はへこんだ箇所を大切そうになぞると、煙草を1本手に取り俺に差し出す。礼を言って受け取り、火を付けた。煙を吐き出すと、一人分ほど空けた隣に腰を下ろす。
「真面目くんでも煙草とか吸うんだな。」
「言うほど真面目じゃないよ。見えるとこだけ。」
苦笑しながら目を細めた佐藤は、ゆっくり煙を吐き出した。指の間から見えた顎の黒子をぼんやりと眺めながら、指先でジッポを弄ぶ。
「不良くんはサボり?」
「...、俺は自分が不良だとか思ったことねぇんだけど。まあな。」
吹き出すように笑った佐藤はコンクリートの床に手をつくと、俺の方に手を伸ばしてきた。何となく避けずにその手を受け入れれば、佐藤の指先が俺の髪をすくった。
「オレンジ色してますけど。」
「甘田に染められたんだよ。」
「ああ。」
納得したように俺の髪から手を離すと、佐藤は携帯灰皿に煙草の灰を落とす。もう少し触れられていたかったと一瞬でも思った自分が馬鹿らしくて、頭を掻く。
「つかこの屋上開くって知らなかったんだけど。」
「真面目くんしてると、先生に甘やかされたりするんだよ。」
いたずらっ子のように笑って俺に鍵を振って見せた佐藤に狡い奴と呟けば、笑みが濃くなった。
「真壁は真っ直ぐだよなぁ。」
何だか噛み締めるように言った佐藤は、少しだけ空っぽな顔をして煙草の煙を吐き出す。俺が口を開こうとしたときに、急にこちらを見たので危うく煙草を落としそうになった。
「どうして真壁だけ戻ってきたわけ?」
「忘れもんしたんだよ。」
ジッポを振って見せれば、佐藤は納得したように頷いた。1本吸い終わると、シャツの一番上のボタンを留めてネクタイを上に上げた佐藤を煙を吐きながら眺める。
「お前さぁ。そんなんで疲れない?」
「...、俺が真面目くんしてるのは、怒られたくないからだよ。だってその方が面倒だろ。それなら怒られそうな要因を表面上はなくした方が楽っていうのが俺の持論。」
「ふーん。」
その考え方も疲れそうだと言えば、佐藤は困ったように苦笑した。わざとらしく笑みを浮かべた佐藤が、そういえばと声を上げたのを横目で見つめる。
「真面目な彼女が欲しいんだって?」
「...、聞いてた?」
「まあ聞こえるよね。なんでそんな子がいいの?」
「可愛いだろ。」
「即答かよ。夢みてんねぇ。」
佐藤は我慢できないというように吹き出すと、目元の涙を拭う。舌打ちをして携帯灰皿に煙草を押し潰すと、ちらりとこちらを見た佐藤と目が合った。
「じゃあ俺が女だったらタイプな訳だ。」
「...、お前みたいな小賢しい奴やだよ。」
「そ。真壁にいい子が現れんの願ってるよ。 」
楽しげに笑って立ち上がった佐藤は、俺の目を見つめるとゆっくりと目を細める。
「ケンカもサボりもほどほどにしとけよ。」
大きなお世話だろうけど、と小さく呟やくと、佐藤は俺に何かを投げてきた。
「鍵?」
「俺のサボり場、真壁にやるよ。」
「...、佐藤はもう来ないのかよ。」
「なんか来て欲しいみたいに聞こえるね。」
ゆるく唇が弧を描いて、スラックスのポケットに手を突っ込むと佐藤は俺に目線を合わせるように上体を曲げる。甘い香りに混じって微かに煙草の臭いがした。俺の目を真っ直ぐと見る楽しげに細められた垂れた目が、琥珀色をしていることに気付く。
「さあ?俺は真面目くんだから。」
それだけ言って俺の言葉を待たずに勝手に歩きだすと、扉のノブに手を掛けた佐藤が俺を振り向いてにこりと笑った。
「またね、真壁。」
俺を置いてさっさと歩いて行った背中を見つめて溜め息を吐くと、あぐらに肘をついて顔を覆う。何もかも見透かしたような琥珀色をした目を思い出して、顔を上げた。ふと目に入った佐藤が忘れていった本を手に取り、スラックスのポケットからスマートフォンを取り出す。
「ああ。甘田?先生からの小言は終わったか?ちょっと頼みたいことあんだけど。...、ああ。佐藤ってやつの連絡先教えて。」
笑みを浮かべた自分の口元を手のひらで撫でてから、心の中に浮かび始めた感情の名前にまだ気付かないふりをしながらジッポを弄んだのだった。
煙草が吸えないストレスを、ジッポの蓋を開け閉めして弄ぶことでやり過ごす昼休み。一口食べたパンのカスタードクリームは生温くて、怠さが倍増した。廊下のざわめきは、屋上の扉近くの踊り場からは遠くて、何だか全部が面倒くさくなる。もう今日はこのまま家に帰ってしまおうかなんて考えた。
「そういえばさ、はっしー。あの後、どうなったわけ?」
俺の隣で同じように怠そうに座っていた赤い前髪をカチューシャで上げた甘田がゆるい口調で問うと、金髪を掻きながら橋塚がおにぎりを頬張ってから、なんてことないように口を開く。
「付き合うことになったわ。」
「なんだよ。まじかよ。」
橋塚が女子に声を掛けられたのは昨日のことでそこには俺もいた。甘田は教師に呼び出されて、課題を出されたとかで置いて帰ったせいでいなかった。声を掛けてきた来た女子たちは、まつげはバサバサで化粧はケバい。香水付けすぎ。スカートは短くて、かかんだ時のことなんか考えてないんじゃねぇのかと思うし、そこから伸びた足は不健康に細い。媚びるように腕に回された指先を思い出して怠さが増した。
「お前はどうすんの?」
甘田が恨みがましげに俺を見るから、苦笑しながらパンを口に運ぶ。やっぱりカスタードクリームがぬるい。
「あー。俺はパス。真面目な彼女がほしい。黒髪で本好きなでスカートが長い子。」
「世界が違う系?お前がこの学校にいる限りないわ。」
「うるせぇわ。」
家から近いという理由で選んだ高校は男子校で、外に出会いを求めるしかないが、俺の好みのタイプはまず近くに寄ってきてくれないのだ。
「そういう子は、まず同じ学校で距離詰めるしかないでしょうよ。外で見つけるとか奇跡が起こんない限り無理じゃん。」
「...、もう転校すっか。」
半ば本気で呟けば、二人からは爆笑が返ってきて、八つ当たりで甘田の頭を叩く。
と。
缶コーヒーと文庫本を片手に階段を上ってきた黒髪に黒いフレームの眼鏡をかけた生徒は、垂れた目を細めて小さく笑った。
「あ。やっぱりここにいた。甘田、先生が呼んでたよ。課題を白紙で出したんだって?」
「やべ!行ってくる!ありがとう!佐藤っち!」
「職員室だから。」
バタバタと駆けていく甘田に、俺と橋塚は残りの昼飯を口に放ると後を追う。佐藤と呼ばれた生徒の横を通るときに、ちらりと彼を横目に見た。上まできっちり上げられたネクタイ。シャツもスラックスも校則通りに着こなして、いかにも真面目そうな彼は、甘田の言葉を借りれば世界が違うという言葉が当てはまる。こういう奴は大抵俺たちをはなっから嫌っていたりするもんだが、こいつはそうでもないらしい。これから関わることもないからどうでもいいかとそのまま横を通りすぎて、階段を下りた。
「あいつ馬鹿じゃねぇの。」
「もとからだろ。」
俺の呆れた苦笑に、橋塚は欠伸をしながら甘田が聞いたら口を尖らせて拗ねそうなことを言い放つ。汗を掻いた紙パックのストローに口をつけてカフェオレを飲めば、中身が僅かだったようでぐしゃりと紙パックを潰した。
「どうする?授業出るか?」
橋塚が面倒くさげに首を傾げるのをちらりと見てから、足元に視線を落とす。
「次なんだっけ?」
「英語だろ。」
「英語か。まだ単位大丈夫だわ。」
どっかで煙草吸ってくる、と言いかけて、自分がジッポを忘れてきたことに気が付いて溜め息を吐いた。
「忘れもんした。先行っといて。」
「了解。」
来た道を戻って、先ほど昼飯を食べていた場所に案の定置きっぱなしになっていたジッポを手に取る。ふと。そこで感じだ風に顔を上げれば、先ほどまで鍵がしまっていて開かなかった屋上への扉が開いていて、目を瞬かせた。錆び付いた扉のドアノブに手をかけてゆっくりと押せば、佐藤がちょうど咥えた煙草に火を付けようとしたところだった。
「あれ?行ったと思ってたのに。」
困ったように笑う佐藤に、小さく笑う。きっちり上まで留められていたカッターシャツのボタンが今は一番上が外されて、ネクタイも弛めてあった。佐藤の近くまで歩いていくと、口に咥えていた煙草にジッポの火を向ける。楽しげに唇の端が笑い、佐藤が煙草を俺が差し出したジッポで火を付けた。中指と薬指の間に煙草を挟んで持ち、口元を覆うようにして煙を吐き出した佐藤は、それ格好いいね、と小さく笑いながら俺のジッポを指差す。メタルプレートにスカルをモチーフにした絵柄が描かれたこれは、俺のお気に入りだ。
「ああ。これ?いいだろ。」
「うん。俺も買おっかな。いくらした?」
「一万ちょっと。」
「やっぱり結構高いな。」
「バイト代注ぎ込んだ。」
バイトかぁ、と独り言ちながら佐藤は自分のライターを眺め、ゆっくり煙を吐き出す。
「1本いる?」
「貰う。」
佐藤はスラックスのポケットから、長い間大切に使われているのだうかがえるシルバーのケースを取り出した。開いたケースには煙草が並んでいる。
「それも格好いいじゃん。」
「ありがと。これ、死んだじいさんの形見でさ、若い頃にイギリスでもらったやつらしい。」
よく見れば、所々傷があったり浅くへこんだりしていた。佐藤はへこんだ箇所を大切そうになぞると、煙草を1本手に取り俺に差し出す。礼を言って受け取り、火を付けた。煙を吐き出すと、一人分ほど空けた隣に腰を下ろす。
「真面目くんでも煙草とか吸うんだな。」
「言うほど真面目じゃないよ。見えるとこだけ。」
苦笑しながら目を細めた佐藤は、ゆっくり煙を吐き出した。指の間から見えた顎の黒子をぼんやりと眺めながら、指先でジッポを弄ぶ。
「不良くんはサボり?」
「...、俺は自分が不良だとか思ったことねぇんだけど。まあな。」
吹き出すように笑った佐藤はコンクリートの床に手をつくと、俺の方に手を伸ばしてきた。何となく避けずにその手を受け入れれば、佐藤の指先が俺の髪をすくった。
「オレンジ色してますけど。」
「甘田に染められたんだよ。」
「ああ。」
納得したように俺の髪から手を離すと、佐藤は携帯灰皿に煙草の灰を落とす。もう少し触れられていたかったと一瞬でも思った自分が馬鹿らしくて、頭を掻く。
「つかこの屋上開くって知らなかったんだけど。」
「真面目くんしてると、先生に甘やかされたりするんだよ。」
いたずらっ子のように笑って俺に鍵を振って見せた佐藤に狡い奴と呟けば、笑みが濃くなった。
「真壁は真っ直ぐだよなぁ。」
何だか噛み締めるように言った佐藤は、少しだけ空っぽな顔をして煙草の煙を吐き出す。俺が口を開こうとしたときに、急にこちらを見たので危うく煙草を落としそうになった。
「どうして真壁だけ戻ってきたわけ?」
「忘れもんしたんだよ。」
ジッポを振って見せれば、佐藤は納得したように頷いた。1本吸い終わると、シャツの一番上のボタンを留めてネクタイを上に上げた佐藤を煙を吐きながら眺める。
「お前さぁ。そんなんで疲れない?」
「...、俺が真面目くんしてるのは、怒られたくないからだよ。だってその方が面倒だろ。それなら怒られそうな要因を表面上はなくした方が楽っていうのが俺の持論。」
「ふーん。」
その考え方も疲れそうだと言えば、佐藤は困ったように苦笑した。わざとらしく笑みを浮かべた佐藤が、そういえばと声を上げたのを横目で見つめる。
「真面目な彼女が欲しいんだって?」
「...、聞いてた?」
「まあ聞こえるよね。なんでそんな子がいいの?」
「可愛いだろ。」
「即答かよ。夢みてんねぇ。」
佐藤は我慢できないというように吹き出すと、目元の涙を拭う。舌打ちをして携帯灰皿に煙草を押し潰すと、ちらりとこちらを見た佐藤と目が合った。
「じゃあ俺が女だったらタイプな訳だ。」
「...、お前みたいな小賢しい奴やだよ。」
「そ。真壁にいい子が現れんの願ってるよ。 」
楽しげに笑って立ち上がった佐藤は、俺の目を見つめるとゆっくりと目を細める。
「ケンカもサボりもほどほどにしとけよ。」
大きなお世話だろうけど、と小さく呟やくと、佐藤は俺に何かを投げてきた。
「鍵?」
「俺のサボり場、真壁にやるよ。」
「...、佐藤はもう来ないのかよ。」
「なんか来て欲しいみたいに聞こえるね。」
ゆるく唇が弧を描いて、スラックスのポケットに手を突っ込むと佐藤は俺に目線を合わせるように上体を曲げる。甘い香りに混じって微かに煙草の臭いがした。俺の目を真っ直ぐと見る楽しげに細められた垂れた目が、琥珀色をしていることに気付く。
「さあ?俺は真面目くんだから。」
それだけ言って俺の言葉を待たずに勝手に歩きだすと、扉のノブに手を掛けた佐藤が俺を振り向いてにこりと笑った。
「またね、真壁。」
俺を置いてさっさと歩いて行った背中を見つめて溜め息を吐くと、あぐらに肘をついて顔を覆う。何もかも見透かしたような琥珀色をした目を思い出して、顔を上げた。ふと目に入った佐藤が忘れていった本を手に取り、スラックスのポケットからスマートフォンを取り出す。
「ああ。甘田?先生からの小言は終わったか?ちょっと頼みたいことあんだけど。...、ああ。佐藤ってやつの連絡先教えて。」
笑みを浮かべた自分の口元を手のひらで撫でてから、心の中に浮かび始めた感情の名前にまだ気付かないふりをしながらジッポを弄んだのだった。
1/1ページ