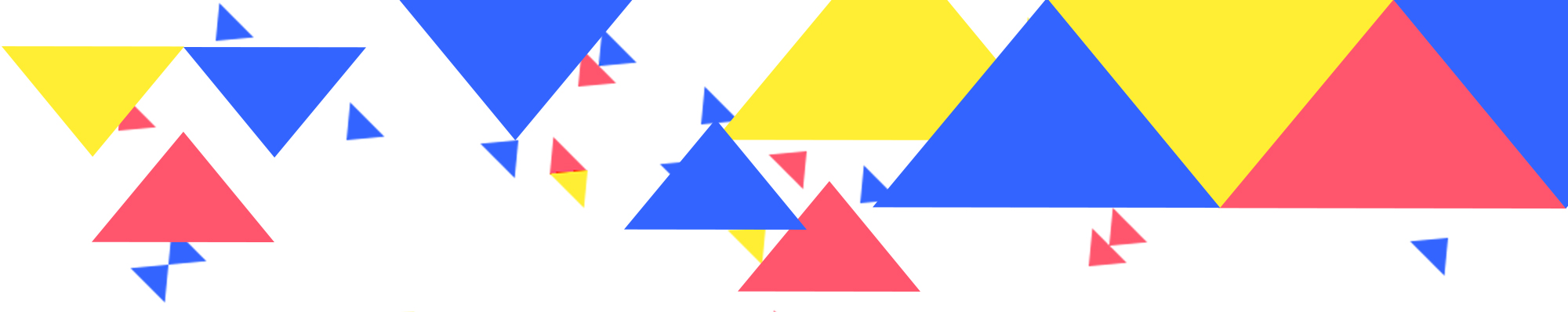君は恋にうるさい
(チャラ男×人気者)
「好きです。」
よくある風景。
「ごめん。気持ちに答えられない。」
よくある返事。
欠伸を溢して、目の前で繰り広げられる光景に目をつぶる。女子に告白されている男が、俺にとって他人であったら、ただの傍観者で無関心のままで居られたのに。少し気まずいだろうけど、その日学校から帰る頃には忘れているレベルのことだ。だけど恋人なら話は別だ。顔だけは平気なように装って、その実は腹が煮えくり返りそうなほどの気持ちを抑えようと奥歯を噛み締めた。
彼らから少し離れたベンチで、サンドイッチを右手に掴んだままぼんやりと眺める昼休み。裏庭にて。
俺と彼の関係は、主に俺のせいで学校中に広まってるはずなのに告白とはよくやる。好奇心も嫌悪も織り混ぜだけど。
「佳津くん、あんなやつに関わっちゃダメだよ。早く別れたがいい。」
明らかにこちらへ向けられる女の子のきつい目に小さく笑って、手をひらひらと振った。さらにしかめられる顔に、顔だけじゃなく性格もブスのようだと心のなかで毒吐く。つうか人の恋人を名前で呼ぶんじゃねぇよ。
だがしかし今や俺の評判は、直接恋人に関わるのだ。
もともとの噂というか現状というか、そういうのが悪かったから、男前で硬派のこの男の印象を、ただでさえ落としているという自覚はきちんとある。
「なんと言おうと、あれは俺の恋人だから。俺はあいつのことを大切にしてるから、あんまりそういうのは言わないでくれると嬉しい。」
苦笑を溢す彼に、サンドイッチを一口食む。ああ、幸せだ、と思う。とても。
そもそも俺と佳津の出会いは1年の夏休み一週間前。彼、村上佳津にその時俺が付き合っていた彼女が惚れた事による。あのときの俺は、別に彼女が特別好きだと言うこともなく、ただ単に所有物を取られただとか、そんな幼稚で最低な理由だったと思う。それで彼に会いに行った。
『あんたが噂の男前?』
意思の強そうな黒い目。甘い笑み。俺より高い背。しっかりした体躯。
『俺と付き合わない?』
それで彼をこっぴどく振ってやれば、俺のちっぽけなプライドが満たせるかと思ったのだ。たったそれだけ。
『へぇ?俺と?楽しそうだな。』
ニヤリと笑う悪気な笑みに、ざわつく心臓に気づかないふりを決め込んで、ただ笑ったあの日の俺。
リンゴジュースのストローを口に加えて、ちゅうと吸う。
「(ま。惚れてしまったら世話はないのだけど。)」
彼のほうはどうか知らないけれど。彼は今日も変わらずフェミニストで、相も変わらず俺以外には酷く甘いのだ。この佳津という男は。それが特別だと思えれば楽なのだけど、ざわつく心はそれを良しとしない。俺にも優しかったとしたら、それはそれで嫌なのだろうけど。恋をすると面倒くさい。
「かっくん。まだ終わらないの?」
佳津の首に腕を回しながら、女の子ににっこりと笑う。相変わらず冷たい彼の体温に少し目を細めるが、俺の頭を優しく撫でる指先に、にぃと笑う。
「ごめんね?かっくんは俺のってこと。」
「最低。」
「最低なのは俺の前で俺のものを奪おうとしてるあんただろ?」
笑みを消せば、目の前の子の顔が朱に染まった。それでも強気で口を開こうとしてる彼女みたいな子は、嫌いじゃない。嫌いじゃないけど佳津に手を出すとなると、話は別。
「俺の前から消えてよ。佳津は君みたいな子嫌いだよ。」
睨みつけて走り去る女の子に、するりと佳津の首から腕を外した。
「本当お前は可愛い顔してえげつない。」
「そういうところ、好きでしょう?」
頬を撫でる指先に一瞬首を竦めて、ただ笑顔で何事もないように装う。こんなとこでも、俺のプライドが邪魔をする。本当はでろでろに甘やかして、甘やかされたい。
「ああ。好きだな。」
いたずらっぽく笑って俺を置いてベンチへと歩き出した佳津を見つめた。早く俺だけ、を見ればいいのに。
そうしたら俺も俺の全部を捧げれるのに。
「好きです。」
よくある風景。
「ごめん。気持ちに答えられない。」
よくある返事。
欠伸を溢して、目の前で繰り広げられる光景に目をつぶる。女子に告白されている男が、俺にとって他人であったら、ただの傍観者で無関心のままで居られたのに。少し気まずいだろうけど、その日学校から帰る頃には忘れているレベルのことだ。だけど恋人なら話は別だ。顔だけは平気なように装って、その実は腹が煮えくり返りそうなほどの気持ちを抑えようと奥歯を噛み締めた。
彼らから少し離れたベンチで、サンドイッチを右手に掴んだままぼんやりと眺める昼休み。裏庭にて。
俺と彼の関係は、主に俺のせいで学校中に広まってるはずなのに告白とはよくやる。好奇心も嫌悪も織り混ぜだけど。
「佳津くん、あんなやつに関わっちゃダメだよ。早く別れたがいい。」
明らかにこちらへ向けられる女の子のきつい目に小さく笑って、手をひらひらと振った。さらにしかめられる顔に、顔だけじゃなく性格もブスのようだと心のなかで毒吐く。つうか人の恋人を名前で呼ぶんじゃねぇよ。
だがしかし今や俺の評判は、直接恋人に関わるのだ。
もともとの噂というか現状というか、そういうのが悪かったから、男前で硬派のこの男の印象を、ただでさえ落としているという自覚はきちんとある。
「なんと言おうと、あれは俺の恋人だから。俺はあいつのことを大切にしてるから、あんまりそういうのは言わないでくれると嬉しい。」
苦笑を溢す彼に、サンドイッチを一口食む。ああ、幸せだ、と思う。とても。
そもそも俺と佳津の出会いは1年の夏休み一週間前。彼、村上佳津にその時俺が付き合っていた彼女が惚れた事による。あのときの俺は、別に彼女が特別好きだと言うこともなく、ただ単に所有物を取られただとか、そんな幼稚で最低な理由だったと思う。それで彼に会いに行った。
『あんたが噂の男前?』
意思の強そうな黒い目。甘い笑み。俺より高い背。しっかりした体躯。
『俺と付き合わない?』
それで彼をこっぴどく振ってやれば、俺のちっぽけなプライドが満たせるかと思ったのだ。たったそれだけ。
『へぇ?俺と?楽しそうだな。』
ニヤリと笑う悪気な笑みに、ざわつく心臓に気づかないふりを決め込んで、ただ笑ったあの日の俺。
リンゴジュースのストローを口に加えて、ちゅうと吸う。
「(ま。惚れてしまったら世話はないのだけど。)」
彼のほうはどうか知らないけれど。彼は今日も変わらずフェミニストで、相も変わらず俺以外には酷く甘いのだ。この佳津という男は。それが特別だと思えれば楽なのだけど、ざわつく心はそれを良しとしない。俺にも優しかったとしたら、それはそれで嫌なのだろうけど。恋をすると面倒くさい。
「かっくん。まだ終わらないの?」
佳津の首に腕を回しながら、女の子ににっこりと笑う。相変わらず冷たい彼の体温に少し目を細めるが、俺の頭を優しく撫でる指先に、にぃと笑う。
「ごめんね?かっくんは俺のってこと。」
「最低。」
「最低なのは俺の前で俺のものを奪おうとしてるあんただろ?」
笑みを消せば、目の前の子の顔が朱に染まった。それでも強気で口を開こうとしてる彼女みたいな子は、嫌いじゃない。嫌いじゃないけど佳津に手を出すとなると、話は別。
「俺の前から消えてよ。佳津は君みたいな子嫌いだよ。」
睨みつけて走り去る女の子に、するりと佳津の首から腕を外した。
「本当お前は可愛い顔してえげつない。」
「そういうところ、好きでしょう?」
頬を撫でる指先に一瞬首を竦めて、ただ笑顔で何事もないように装う。こんなとこでも、俺のプライドが邪魔をする。本当はでろでろに甘やかして、甘やかされたい。
「ああ。好きだな。」
いたずらっぽく笑って俺を置いてベンチへと歩き出した佳津を見つめた。早く俺だけ、を見ればいいのに。
そうしたら俺も俺の全部を捧げれるのに。
2/2ページ