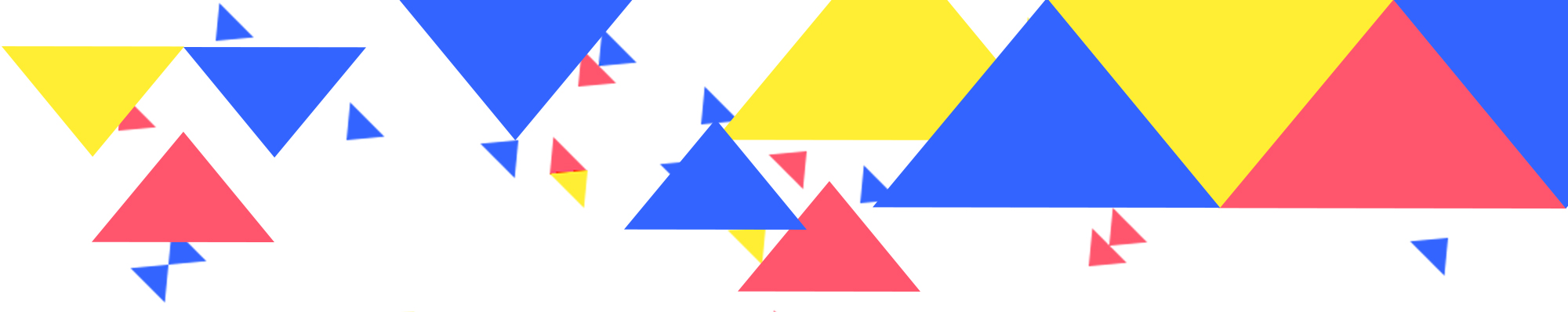こんなに嬉しいことはない
寮に入ると管理人からカードキーを貰い、説明を受ける。このカードキーはお財布にもなる優れものらしい。なくさないように、と言う言葉を会話の中で5回ほど聞いた。ちなみに寮と言うよりもホテルみたいだった寮の内観に、開いた口が暫く閉じることができなかったのは想像に難くないと思う。3階の部屋だし階段を登ろうと階段を見上げれば手すりさえ豪華で目を見張り、廊下を歩けば高級そうな絨毯に腰が引け、金を掛けるところがおかしいと涙が出そうだ。
「...、310。310。ここだ。」
同室者だろう人物の名前の下には、自分の名前のネームプレートが間違いなく差し込まれていて、ドアベルを鳴らす。暫く待っても誰も来る気配がなく、恐る恐るカードキーをかざした。すると鍵の開く音がして、ドアノブに手を掛けドアを押す。
シン、と静かな部屋。思っていたよりも室内は落ち着いた印象で、少しだけほっとした。正直シャンデリアでもぶら下がっているんじゃないかとビクビクしてたのだ。取り敢えず荷物を解いてから、トレーニング室に行ってみようかと計画を立てる。夕飯はやっぱり学食か、それともコンビニか。
「学食どこか聞くの忘れた。」
笑顔の綺麗な副会長が、おかしそうに笑う姿が姿が頭に浮かんでは消えた。まあ、いいか、と段ボールが積まれている自分の部屋に入りながら、ジャージに着替えて軽く伸び。荷物はお気に入りで読み返している数冊の本だったり、数着の私服だったり、学校に必要なものだったり、片付けるものは少なくて、すぐ終わってしまった。当初の計画通りに行こうかと携帯と財布、カードキーを手に部屋を出ると、寮内にあるというトレーニング室を目指す。
部活に入らない予定の俺が、何故トレーニング室を気にするのかというと、ただ単に俺の日課が体を鍛えることだったからだ。今、中学生の弟がいるが、その弟が初めて見たボクシングの試合でボクシングに目覚めて、一緒にジムに通っていたのだ。
俺の方は今はやっていないが、そこからなんとなく体を鍛えることが日課になった。その他に姉と一緒に習っていたピアノもしていたし、小説家である母親の影響で始めた読書に至ってはもう俺から切り離せないものだ。つまりは今の俺を作っているのは、他からの巻き添えや影響ってわけだ。
それが嫌だとか言うわけでもないけど、自分でこれがしたいって強く思ったことがあまりないのは確かだと思う。
ふわふわした赤い絨毯を踏み続けて、ようやくたどり着いたトレーニング室に足を踏み入れれば、あまりの広さに言葉を失った。いや、ある程度広いの予想はしていたが、寮のトレーニング室だし、と舐めていた。
「おぉ...。」
なんか見たことないトレーニング器具もあるし。あれはこの間テレビで見た最新のやつだ、と地味にテンションを上げながら、ランニングマシーンでウォーミングアップを始めつつ、人間観察。
ゆっくり歩いて腕を回しながら、やけに顔面偏差値の高い男たちを眺めた。いくら可愛くて、声が高くて、やだぁ重ぉい、使い方分からないから教えてぇ、だとか可愛い子ぶっていても男しかいない。なんだあれ。背が高くてがたいがいいイケメンに群がっていたって、男しかいない。
ランニングマシーンのスピードを少し上げながら、指で眉間を揉んだ。何だか少しだけ、姉が言っていたトレーニングジムでの婚活を思い出した。男しかいない環境で婚活のことを思い出すのも可笑しな話だが。
ゆっくりため息をついて、ランニングマシーンから降りると、あの、と近くを通った人の腕を掴んだ。直ぐに手を離して、自分の背より低いその人の顔を覗き込めば、予想外に綺麗な顔立ちで、内心おののきつつも笑みを浮かべる。
「突然すみません。サンドバッグとかパンチングボールとかってここにありますか?」
「えっと、あ、と。」
何だか可哀想なくらい慌ててしまった彼に、どうしようかと途方に暮れていれば、急に人が俺と彼の間に割って入ってきて驚き過ぎて、一瞬心臓が止まるかと思った。固まったままの困り眉美人より背の低い、女の子のように可愛いその人は、親の敵を見るような目付きで俺をギロリと睨んでいる。普通に怖いので止めてほしい。
「あんた何。」
「あ、待って薫。この人、俺に場所を聞いてきただけだよ。」
「下心見え見えなんだよ。気を付けてよ、珠樹。あと近寄んな。もっと下がれ、平凡。」
初対面で困ったもんだ、と頭を掻いて、顔面偏差値の高いコンビを眺めた。薫、と呼ばれた人は珠樹と呼ばれた人を庇うように前に立って、俺を威嚇してくる。その姿は何だか騎士とお姫様のようで、微笑ましいけれど敵役の俺はどうしたもんか。
「ん?見ない顔だけど、あんたが帰国子女の編入生?」
「帰国子女、じゃないけど、多分合ってる。」
「つまんないな、平凡じゃないの。」
ふん、と鼻で笑った薫くんに、苦笑した。さっきから平凡平凡と言われるが、ただ単にこの学園の顔面偏差値が高いだけだと思う。それになんでここまで帰国子女だって広まってるんだ。
「ご期待に添えなくて申し訳ないんだけど、取り敢えずサンドバッグとパンチングボールがあるかどうかだけ教えてもらって良い?」
「薫。さっきから失礼だよ。この人格好いいよ?あ、サンドバッグとパンチングボールはあっちのブースにあるよ。」
「ありがとう。」
「珠樹は目が悪いんじゃない?」
少し照れたように笑う珠樹くんに、思わず照れれば薫くんからに毒吐かれる。取り敢えず二人にお礼を言って、サンドバッグとパンチングボールがあるというブースへ向かった。そこでしばらく汗を流して、シャワーでも浴びて帰ろうかと思ったが、着替えを忘れたことを思い出す。
「部屋に戻るか。」
元来た道を帰りながら、トレーニングをしている層がきゃぴきゃぴした女の子ような男子生徒とアイドルから、真面目そうな体育会系になっていたことに驚きながらトレーニングルームから出た。
自室の扉の鍵を開けて部屋に入れば、ウルフカットされた短髪を金色に染めた目付きの鋭い男がこちらを見ていて、思わず出ていきそうになった足をどうにか止める。
「今日から同室になる、花房優人です。よろしく。」
俺の笑顔を浮かべた自己紹介を華麗に無視した同室者は、自分の部屋へと入っていった。扉を蹴りつけてやろうかと思ったが、痛いだけだし後が怖いので止めておくことにして、風呂場へと向かう。この学園でやっていこうと無理やり保っていたやる気は、正直無理なんじゃないだろうかというほうへ傾いてる。
服を乱暴に脱ぎ捨てて洗濯かごに投げ入れながら、うきうきとドイツへと移住した親を恨む。親に寮があるこの学園をすすめられ、どうにか学費免除を勝ち得た俺は、ここにいる。ここにいるのだが、どうにも場違いで泣けてくるのだ。
取り敢えずシャワーで汗を洗い流すだけにして、バスタオルでがしがしと体を拭いている段階でふと気付く。そういえば俺は着替えを用意したっけ。
「...、してねぇな。」
しょうがなくバスタオルを腰に巻いて脱衣所を出れば、何故か同室者が部屋から出てきてリビングのソファにいて驚いた。
「...、あんたってどこのチーム?」
「チーム?何それ、スポーツクラブとか?」
「ちげぇよ。暴走族だよ。」
「いや入ってないけど。」
ふーん、と言ってきた同室者に、一体なんだとソファを通り過ぎて自分の部屋を目指せば、腕を掴まれる。そのまま腕を揉むように触られ、どうしたものかと厳つい顔を見つめた。眉間に寄ったシワと鋭い目付きを考慮しても、整った顔立ちには違いなくて、本当にここの学校は顔面偏差値が高過ぎると嫌になる。
「体つきいいけど、なんで。」
「中学までボクシングしてたからじゃない?もういい?」
「ああ。俺の名前は部屋んとこ見れば分かると思うけど、我妻 武ね。これ、寮長がお前に渡せって言ってた書類。目、通しとけよ。」
それだけ言うと部屋に入ろうとする我妻に、慌ててありがとうと言えば、手をひらひらと振られた。意外に良い奴かも、と思いつつ、書類を眺めると、俺も部屋に入ったのだった。部屋で仮眠を取っていれば、部屋の扉を乱暴に蹴られて何事かと慌てて扉を開けた俺に、飯食いに行くぞと、いけしゃあしゃあと言ってのけた我妻に、再びやっていけるか不安になったのはまた別の話である。
「...、310。310。ここだ。」
同室者だろう人物の名前の下には、自分の名前のネームプレートが間違いなく差し込まれていて、ドアベルを鳴らす。暫く待っても誰も来る気配がなく、恐る恐るカードキーをかざした。すると鍵の開く音がして、ドアノブに手を掛けドアを押す。
シン、と静かな部屋。思っていたよりも室内は落ち着いた印象で、少しだけほっとした。正直シャンデリアでもぶら下がっているんじゃないかとビクビクしてたのだ。取り敢えず荷物を解いてから、トレーニング室に行ってみようかと計画を立てる。夕飯はやっぱり学食か、それともコンビニか。
「学食どこか聞くの忘れた。」
笑顔の綺麗な副会長が、おかしそうに笑う姿が姿が頭に浮かんでは消えた。まあ、いいか、と段ボールが積まれている自分の部屋に入りながら、ジャージに着替えて軽く伸び。荷物はお気に入りで読み返している数冊の本だったり、数着の私服だったり、学校に必要なものだったり、片付けるものは少なくて、すぐ終わってしまった。当初の計画通りに行こうかと携帯と財布、カードキーを手に部屋を出ると、寮内にあるというトレーニング室を目指す。
部活に入らない予定の俺が、何故トレーニング室を気にするのかというと、ただ単に俺の日課が体を鍛えることだったからだ。今、中学生の弟がいるが、その弟が初めて見たボクシングの試合でボクシングに目覚めて、一緒にジムに通っていたのだ。
俺の方は今はやっていないが、そこからなんとなく体を鍛えることが日課になった。その他に姉と一緒に習っていたピアノもしていたし、小説家である母親の影響で始めた読書に至ってはもう俺から切り離せないものだ。つまりは今の俺を作っているのは、他からの巻き添えや影響ってわけだ。
それが嫌だとか言うわけでもないけど、自分でこれがしたいって強く思ったことがあまりないのは確かだと思う。
ふわふわした赤い絨毯を踏み続けて、ようやくたどり着いたトレーニング室に足を踏み入れれば、あまりの広さに言葉を失った。いや、ある程度広いの予想はしていたが、寮のトレーニング室だし、と舐めていた。
「おぉ...。」
なんか見たことないトレーニング器具もあるし。あれはこの間テレビで見た最新のやつだ、と地味にテンションを上げながら、ランニングマシーンでウォーミングアップを始めつつ、人間観察。
ゆっくり歩いて腕を回しながら、やけに顔面偏差値の高い男たちを眺めた。いくら可愛くて、声が高くて、やだぁ重ぉい、使い方分からないから教えてぇ、だとか可愛い子ぶっていても男しかいない。なんだあれ。背が高くてがたいがいいイケメンに群がっていたって、男しかいない。
ランニングマシーンのスピードを少し上げながら、指で眉間を揉んだ。何だか少しだけ、姉が言っていたトレーニングジムでの婚活を思い出した。男しかいない環境で婚活のことを思い出すのも可笑しな話だが。
ゆっくりため息をついて、ランニングマシーンから降りると、あの、と近くを通った人の腕を掴んだ。直ぐに手を離して、自分の背より低いその人の顔を覗き込めば、予想外に綺麗な顔立ちで、内心おののきつつも笑みを浮かべる。
「突然すみません。サンドバッグとかパンチングボールとかってここにありますか?」
「えっと、あ、と。」
何だか可哀想なくらい慌ててしまった彼に、どうしようかと途方に暮れていれば、急に人が俺と彼の間に割って入ってきて驚き過ぎて、一瞬心臓が止まるかと思った。固まったままの困り眉美人より背の低い、女の子のように可愛いその人は、親の敵を見るような目付きで俺をギロリと睨んでいる。普通に怖いので止めてほしい。
「あんた何。」
「あ、待って薫。この人、俺に場所を聞いてきただけだよ。」
「下心見え見えなんだよ。気を付けてよ、珠樹。あと近寄んな。もっと下がれ、平凡。」
初対面で困ったもんだ、と頭を掻いて、顔面偏差値の高いコンビを眺めた。薫、と呼ばれた人は珠樹と呼ばれた人を庇うように前に立って、俺を威嚇してくる。その姿は何だか騎士とお姫様のようで、微笑ましいけれど敵役の俺はどうしたもんか。
「ん?見ない顔だけど、あんたが帰国子女の編入生?」
「帰国子女、じゃないけど、多分合ってる。」
「つまんないな、平凡じゃないの。」
ふん、と鼻で笑った薫くんに、苦笑した。さっきから平凡平凡と言われるが、ただ単にこの学園の顔面偏差値が高いだけだと思う。それになんでここまで帰国子女だって広まってるんだ。
「ご期待に添えなくて申し訳ないんだけど、取り敢えずサンドバッグとパンチングボールがあるかどうかだけ教えてもらって良い?」
「薫。さっきから失礼だよ。この人格好いいよ?あ、サンドバッグとパンチングボールはあっちのブースにあるよ。」
「ありがとう。」
「珠樹は目が悪いんじゃない?」
少し照れたように笑う珠樹くんに、思わず照れれば薫くんからに毒吐かれる。取り敢えず二人にお礼を言って、サンドバッグとパンチングボールがあるというブースへ向かった。そこでしばらく汗を流して、シャワーでも浴びて帰ろうかと思ったが、着替えを忘れたことを思い出す。
「部屋に戻るか。」
元来た道を帰りながら、トレーニングをしている層がきゃぴきゃぴした女の子ような男子生徒とアイドルから、真面目そうな体育会系になっていたことに驚きながらトレーニングルームから出た。
自室の扉の鍵を開けて部屋に入れば、ウルフカットされた短髪を金色に染めた目付きの鋭い男がこちらを見ていて、思わず出ていきそうになった足をどうにか止める。
「今日から同室になる、花房優人です。よろしく。」
俺の笑顔を浮かべた自己紹介を華麗に無視した同室者は、自分の部屋へと入っていった。扉を蹴りつけてやろうかと思ったが、痛いだけだし後が怖いので止めておくことにして、風呂場へと向かう。この学園でやっていこうと無理やり保っていたやる気は、正直無理なんじゃないだろうかというほうへ傾いてる。
服を乱暴に脱ぎ捨てて洗濯かごに投げ入れながら、うきうきとドイツへと移住した親を恨む。親に寮があるこの学園をすすめられ、どうにか学費免除を勝ち得た俺は、ここにいる。ここにいるのだが、どうにも場違いで泣けてくるのだ。
取り敢えずシャワーで汗を洗い流すだけにして、バスタオルでがしがしと体を拭いている段階でふと気付く。そういえば俺は着替えを用意したっけ。
「...、してねぇな。」
しょうがなくバスタオルを腰に巻いて脱衣所を出れば、何故か同室者が部屋から出てきてリビングのソファにいて驚いた。
「...、あんたってどこのチーム?」
「チーム?何それ、スポーツクラブとか?」
「ちげぇよ。暴走族だよ。」
「いや入ってないけど。」
ふーん、と言ってきた同室者に、一体なんだとソファを通り過ぎて自分の部屋を目指せば、腕を掴まれる。そのまま腕を揉むように触られ、どうしたものかと厳つい顔を見つめた。眉間に寄ったシワと鋭い目付きを考慮しても、整った顔立ちには違いなくて、本当にここの学校は顔面偏差値が高過ぎると嫌になる。
「体つきいいけど、なんで。」
「中学までボクシングしてたからじゃない?もういい?」
「ああ。俺の名前は部屋んとこ見れば分かると思うけど、我妻 武ね。これ、寮長がお前に渡せって言ってた書類。目、通しとけよ。」
それだけ言うと部屋に入ろうとする我妻に、慌ててありがとうと言えば、手をひらひらと振られた。意外に良い奴かも、と思いつつ、書類を眺めると、俺も部屋に入ったのだった。部屋で仮眠を取っていれば、部屋の扉を乱暴に蹴られて何事かと慌てて扉を開けた俺に、飯食いに行くぞと、いけしゃあしゃあと言ってのけた我妻に、再びやっていけるか不安になったのはまた別の話である。
3/3ページ