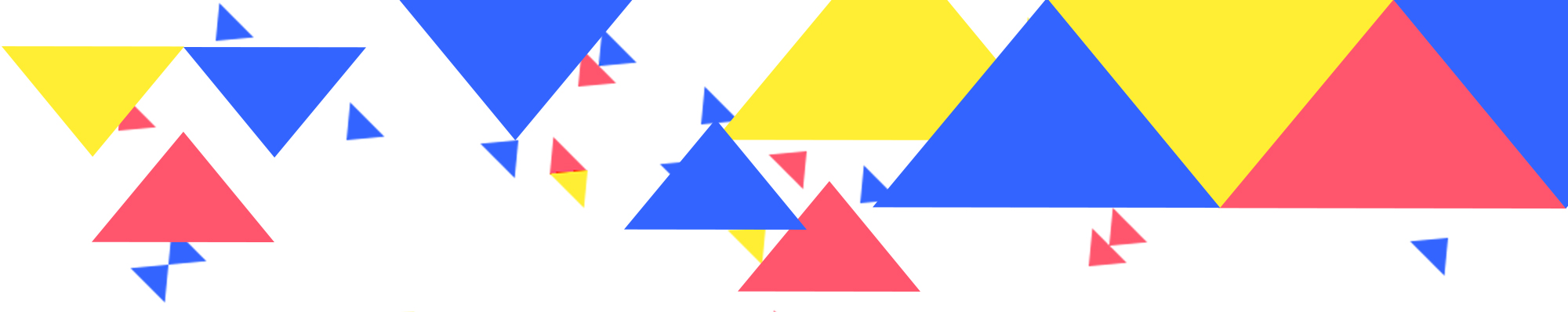ベイビー・ドント・クライ
生徒会役員が生徒会室へ帰って来た。平謝りした会計たち。副会長にいたっては土下座でもしそうな勢いで酷いことを言って傷付けてすみません、しばらく休んでくださいと、言うから圧倒されながら頷く。
「いや、戻ってきてくれて嬉しいんだけど、急にどうしたんだ?」
「諭されたんです。」
ぽつりと呟いた副会長に、目を瞬かせて眉を寄せた。
「諭された?風紀委員長か?」
「ううん。平凡だったよ?」
「...、背が高くて、バスケ部の部長だって言ってたけど。」
「うん?」
会計と書記の言葉にさらに眉を寄せて、頬杖をつく。再度謝ると俺のデスクから一人ひとり書類を持つといそいそと席についていった。
職権濫用だが、それが本当なら礼に行くのが筋だろうとパソコンでバスケ部の部長は誰なのかを調べていれば、『霜月 鳴海』という名前が出てくる。学年とクラスを確認しながら、明日教室に行くかと体を伸ばして今日は約束通りすぐに帰るか、と最近泣いている時によく会う彼を思い浮かべて小さく笑った。
*****
「すまない。霜月 鳴海はいるか?」
昼休みに3-Bの教室を訪れ、一人を引っ掴まえて問えば、教室を見渡すこともなく相手は首を振る。
「鳴海ならこの時間はもっぱら体育館で自主練だからいないんだよね。用なら放課後にバスケ部訪ねるといいんじゃねぇの?絶対会えるよ。」
「そうか、ありがとう。」
「どういたしまして。あとお疲れ様。」
もう一度ありがとう、と言って笑い返すと、放課後にバスケ部を覗いて見ようと、学食へと足を向け直した。
学園は平然を取り戻しつつあるようで、挨拶をしてくれる生徒も笑顔が多い。彼に報告をしたくて浮き足立つも、こんな日に限って会えず、何だか泣きたくなって目を擦った。最初に出会った日も俺は泣いていたが、彼は泣く俺を幻滅するでもなく、動揺して変なことを口走った俺に引くでもなく、ただ涙を脱ぐってハンカチをくれた。俺を抱ける、じゃなく、俺を抱きたいと言った彼。俺も高い方だが、彼は俺が見上げるほど背が高くて、でも俺よりも自分の背が低かったとしても抱きたいと言ってくれた。それがとても嬉しくて、嬉しくて、悲しくなくても涙は出るのだと知ったのだ。
あの日俺は付き合っていた副会長に別れを告げられ、俺よりも転校生は背も低くて可愛くて、俺では違うのだと言われた。馬鹿だとは思うが、俺はそのときに副会長が俺とは一線を越えない理由を知ったのだ。
『僕より背の高いあなたのことを、抱きたいと思えないんです。』
すがりついてしまいたくても、あまりの衝撃に頭は働かなくて気づけば副会長は去った後だった。そんな衝撃に追い付けない頭で聞いた彼の声は、まるで抱き締められているみたいで、あまりの心地よさに一層涙を誘った。この人が俺のことを好きだったらどんなに幸せだろうと思ったら、泣いているときばかりに会う彼のことをどんどん俺のほうが好きになっていった。
『霜月 鳴海』が彼だったらいいのに、なんて淡い期待を抱くほどには俺は彼を好きで好きでしょうがない。
訪れた放課後にバスケ部の部室に行くと、部室にいたバスケ部員たちがかわいそうなくらい慌てながらも、俺を部室の中へ招ききれてくれた。正直とてもおかしい。
「部活前にすまないな。部長はいるか?」
「部長ですか?部長はもう体育館で練習始めちゃってますね。部長にお話ですか?」
「ああ。ひとつ聞きたいんだが部長はどんな人だ?」
そう言った途端に目を輝かせた目の前のバスケ部員と、俺を遠巻きに見ていた他の部員たち。
「部長は本当にすごい人です!身長は190㎝は越えてるし、体だって引き締まってて超格好いいんス!それに外で試合すると他校の女子たちが応援に来てすぐ囲まれて、モテモテで俺たちの憧れなんですよ!」
「うちじゃ美形だらけのせいで平凡なんて言われてますけど、十分顔整ってるよね。バスケ雑誌でイケメン注目選手で特集組まれてたし。」
見せられた雑誌を見てみれば、淡い期待を抱いていたその人に違いなくて、あまりの嬉しさに顔が綻ぶ。
「ああ。すごく格好いいな。」
やべ会長のお墨付きだぞ、とさらに騒ぎ出したバスケ部員たちは、目を輝かせて口々にいかに部長に憧れているかを話し出した。
「どこからでも点決めちゃう。」
「後輩のフォローも欠かさないし。」
「バスケ愛し過ぎちゃってるのがたまに傷だけどね。」
と。
「あ。やべもうこんな時間かよ!副部長にどやされる!会長、部長は自主練遅くまでやってますよ。急ぎじゃなければそれからがいいと思います。部長、失礼ですけどバスケ馬鹿なので!」
「会長、部長に恋人いませんよ!」
「でもバスケが恋人みたいなとこあるんで、気を付けてくださいね!」
慌ただしく去っていったバスケ部員たちに苦笑を溢しながら、ほっと息を吐く。霜月の写った写真を眺めた。バスケに真剣に向き合っているのが伝わってくるインタビュー内容に小さく笑いながら、やっぱり好きだなぁと思う。
立ち上がって電気の付いた体育館を目指して歩くと、階段を登って2階に上がると、部活している姿をぼんやりと見つめた。何て言おうか。まずは感謝と謝罪。それから...、告白をしたら霜月はどう思うだろうか。最初に副会長にフラれて泣いていたのに、心変わりが早すぎると思われるだろうか。でも、霜月に引かれることも幻滅されることもないんじゃないかと変な自信がある。だって醜態はもう大分見せているし。
「好きだなぁ。」
汗を拭う姿にへらりと笑いながら、頭を掻いた。副会長のことを好きだったときが霞むくらいの胸の高鳴りに苦笑しながら、きらきらと眩しい彼に目を細める。霜月を眺めているうちに終わった練習時間は、終了を告げる霜月の号令が体育館に響いたことで知った。片付けをして体育館から出ていく部員たちを見送る霜月は、再びボールを手にとってゴールと向き合う。俺は階段を降りて1階に降りて、霜月を眺めていれば、彼が俺の方を振り向いて小さく微笑んだ。
「寝れてる?」
「ああ。...、あー。ありがとう。役員たちを諭してくれたんだろう?俺には出来ないことだったから、本当に助かった。手間をかけてすまなかったな。」
「光石が役員たちとちゃんと向き合ってたから、俺の話が分かったんだよ。俺は何もしてない。それに俺は俺で、バスケ部の後輩を叱りに行ったから、俺の用事。」
「俺は霜月のおかげだと思ってる。...、というかな?役員のやつらが諭されたって神妙な顔して言ってたんだよ。だからその相手を探してて、霜月に行き当たった。俺、本当に嬉しかったんだ。」
少し困ったような顔をした霜月に、もう一度俺は嬉しかったんだと笑みを浮かべた。
「好きだ。霜月のことが好きだ。」
目を真っ直ぐ見つめれば、霜月が俺から目を反らしてゴールを見上げた。
「俺ってさ?今まで付き合った人に、バスケのことしか考えてないってフラれてばっかだったんだ。それってバスケよりも優先したいくらい愛せる人がいなかったってことなんだけど。」
霜月の手から軽く投げられたバスケットボールが、綺麗な弧を描いてゴールを揺らす。
「俺はいつも昼休みにはここに来て自主練をするんだけど、初めてバスケよりも優先して誰かのために動いたんだ。これって俺にとっては重要なことでさ?つまり光石は、俺の初恋ってことになるね。重いかな?」
俺の方に顔を向けると、酷く優しく目を細められて頭をぶんぶんと振った。
「好きだよ。あなたを初めて会ったときから好きでした。絶対に泣かないあなたが俺の前でだけ泣く姿がいつだって俺の頭をいっぱいにする。」
声も出ないで、こくこくと頷いて、溢れてきた涙を拭う。霜月の、光石は泣き虫だなぁと優しい声が耳の横で囁かれて、抱き締められた。しがみついて好きだと言う度に、俺も好きだよと返されるあまりの幸せに涙が止まらない。
ふと。
「あのとき言った通り、俺は光石を抱きたいと思ってるんだけど、そこのところ大丈夫?」
小さく呟かれた言葉に笑いながら、霜月から体を離すと止まった涙を拭って、頬を手のひらで挟むと少し背伸びをして霜月の唇と自分のそれをくっつけた。
「霜月じゃないと嫌だ。」
「...、ずるい。」
「こんな俺は嫌か?」
「本当ずるい!」
声を上げて笑いながら霜月の首に腕を伸ばせば、腰に腕を回されて首もとに顔を埋められる。名前を呼ぶ、優しすぎるその声にありったけの愛を込めて名前を呼び返したのだった。
(完)
「いや、戻ってきてくれて嬉しいんだけど、急にどうしたんだ?」
「諭されたんです。」
ぽつりと呟いた副会長に、目を瞬かせて眉を寄せた。
「諭された?風紀委員長か?」
「ううん。平凡だったよ?」
「...、背が高くて、バスケ部の部長だって言ってたけど。」
「うん?」
会計と書記の言葉にさらに眉を寄せて、頬杖をつく。再度謝ると俺のデスクから一人ひとり書類を持つといそいそと席についていった。
職権濫用だが、それが本当なら礼に行くのが筋だろうとパソコンでバスケ部の部長は誰なのかを調べていれば、『霜月 鳴海』という名前が出てくる。学年とクラスを確認しながら、明日教室に行くかと体を伸ばして今日は約束通りすぐに帰るか、と最近泣いている時によく会う彼を思い浮かべて小さく笑った。
*****
「すまない。霜月 鳴海はいるか?」
昼休みに3-Bの教室を訪れ、一人を引っ掴まえて問えば、教室を見渡すこともなく相手は首を振る。
「鳴海ならこの時間はもっぱら体育館で自主練だからいないんだよね。用なら放課後にバスケ部訪ねるといいんじゃねぇの?絶対会えるよ。」
「そうか、ありがとう。」
「どういたしまして。あとお疲れ様。」
もう一度ありがとう、と言って笑い返すと、放課後にバスケ部を覗いて見ようと、学食へと足を向け直した。
学園は平然を取り戻しつつあるようで、挨拶をしてくれる生徒も笑顔が多い。彼に報告をしたくて浮き足立つも、こんな日に限って会えず、何だか泣きたくなって目を擦った。最初に出会った日も俺は泣いていたが、彼は泣く俺を幻滅するでもなく、動揺して変なことを口走った俺に引くでもなく、ただ涙を脱ぐってハンカチをくれた。俺を抱ける、じゃなく、俺を抱きたいと言った彼。俺も高い方だが、彼は俺が見上げるほど背が高くて、でも俺よりも自分の背が低かったとしても抱きたいと言ってくれた。それがとても嬉しくて、嬉しくて、悲しくなくても涙は出るのだと知ったのだ。
あの日俺は付き合っていた副会長に別れを告げられ、俺よりも転校生は背も低くて可愛くて、俺では違うのだと言われた。馬鹿だとは思うが、俺はそのときに副会長が俺とは一線を越えない理由を知ったのだ。
『僕より背の高いあなたのことを、抱きたいと思えないんです。』
すがりついてしまいたくても、あまりの衝撃に頭は働かなくて気づけば副会長は去った後だった。そんな衝撃に追い付けない頭で聞いた彼の声は、まるで抱き締められているみたいで、あまりの心地よさに一層涙を誘った。この人が俺のことを好きだったらどんなに幸せだろうと思ったら、泣いているときばかりに会う彼のことをどんどん俺のほうが好きになっていった。
『霜月 鳴海』が彼だったらいいのに、なんて淡い期待を抱くほどには俺は彼を好きで好きでしょうがない。
訪れた放課後にバスケ部の部室に行くと、部室にいたバスケ部員たちがかわいそうなくらい慌てながらも、俺を部室の中へ招ききれてくれた。正直とてもおかしい。
「部活前にすまないな。部長はいるか?」
「部長ですか?部長はもう体育館で練習始めちゃってますね。部長にお話ですか?」
「ああ。ひとつ聞きたいんだが部長はどんな人だ?」
そう言った途端に目を輝かせた目の前のバスケ部員と、俺を遠巻きに見ていた他の部員たち。
「部長は本当にすごい人です!身長は190㎝は越えてるし、体だって引き締まってて超格好いいんス!それに外で試合すると他校の女子たちが応援に来てすぐ囲まれて、モテモテで俺たちの憧れなんですよ!」
「うちじゃ美形だらけのせいで平凡なんて言われてますけど、十分顔整ってるよね。バスケ雑誌でイケメン注目選手で特集組まれてたし。」
見せられた雑誌を見てみれば、淡い期待を抱いていたその人に違いなくて、あまりの嬉しさに顔が綻ぶ。
「ああ。すごく格好いいな。」
やべ会長のお墨付きだぞ、とさらに騒ぎ出したバスケ部員たちは、目を輝かせて口々にいかに部長に憧れているかを話し出した。
「どこからでも点決めちゃう。」
「後輩のフォローも欠かさないし。」
「バスケ愛し過ぎちゃってるのがたまに傷だけどね。」
と。
「あ。やべもうこんな時間かよ!副部長にどやされる!会長、部長は自主練遅くまでやってますよ。急ぎじゃなければそれからがいいと思います。部長、失礼ですけどバスケ馬鹿なので!」
「会長、部長に恋人いませんよ!」
「でもバスケが恋人みたいなとこあるんで、気を付けてくださいね!」
慌ただしく去っていったバスケ部員たちに苦笑を溢しながら、ほっと息を吐く。霜月の写った写真を眺めた。バスケに真剣に向き合っているのが伝わってくるインタビュー内容に小さく笑いながら、やっぱり好きだなぁと思う。
立ち上がって電気の付いた体育館を目指して歩くと、階段を登って2階に上がると、部活している姿をぼんやりと見つめた。何て言おうか。まずは感謝と謝罪。それから...、告白をしたら霜月はどう思うだろうか。最初に副会長にフラれて泣いていたのに、心変わりが早すぎると思われるだろうか。でも、霜月に引かれることも幻滅されることもないんじゃないかと変な自信がある。だって醜態はもう大分見せているし。
「好きだなぁ。」
汗を拭う姿にへらりと笑いながら、頭を掻いた。副会長のことを好きだったときが霞むくらいの胸の高鳴りに苦笑しながら、きらきらと眩しい彼に目を細める。霜月を眺めているうちに終わった練習時間は、終了を告げる霜月の号令が体育館に響いたことで知った。片付けをして体育館から出ていく部員たちを見送る霜月は、再びボールを手にとってゴールと向き合う。俺は階段を降りて1階に降りて、霜月を眺めていれば、彼が俺の方を振り向いて小さく微笑んだ。
「寝れてる?」
「ああ。...、あー。ありがとう。役員たちを諭してくれたんだろう?俺には出来ないことだったから、本当に助かった。手間をかけてすまなかったな。」
「光石が役員たちとちゃんと向き合ってたから、俺の話が分かったんだよ。俺は何もしてない。それに俺は俺で、バスケ部の後輩を叱りに行ったから、俺の用事。」
「俺は霜月のおかげだと思ってる。...、というかな?役員のやつらが諭されたって神妙な顔して言ってたんだよ。だからその相手を探してて、霜月に行き当たった。俺、本当に嬉しかったんだ。」
少し困ったような顔をした霜月に、もう一度俺は嬉しかったんだと笑みを浮かべた。
「好きだ。霜月のことが好きだ。」
目を真っ直ぐ見つめれば、霜月が俺から目を反らしてゴールを見上げた。
「俺ってさ?今まで付き合った人に、バスケのことしか考えてないってフラれてばっかだったんだ。それってバスケよりも優先したいくらい愛せる人がいなかったってことなんだけど。」
霜月の手から軽く投げられたバスケットボールが、綺麗な弧を描いてゴールを揺らす。
「俺はいつも昼休みにはここに来て自主練をするんだけど、初めてバスケよりも優先して誰かのために動いたんだ。これって俺にとっては重要なことでさ?つまり光石は、俺の初恋ってことになるね。重いかな?」
俺の方に顔を向けると、酷く優しく目を細められて頭をぶんぶんと振った。
「好きだよ。あなたを初めて会ったときから好きでした。絶対に泣かないあなたが俺の前でだけ泣く姿がいつだって俺の頭をいっぱいにする。」
声も出ないで、こくこくと頷いて、溢れてきた涙を拭う。霜月の、光石は泣き虫だなぁと優しい声が耳の横で囁かれて、抱き締められた。しがみついて好きだと言う度に、俺も好きだよと返されるあまりの幸せに涙が止まらない。
ふと。
「あのとき言った通り、俺は光石を抱きたいと思ってるんだけど、そこのところ大丈夫?」
小さく呟かれた言葉に笑いながら、霜月から体を離すと止まった涙を拭って、頬を手のひらで挟むと少し背伸びをして霜月の唇と自分のそれをくっつけた。
「霜月じゃないと嫌だ。」
「...、ずるい。」
「こんな俺は嫌か?」
「本当ずるい!」
声を上げて笑いながら霜月の首に腕を伸ばせば、腰に腕を回されて首もとに顔を埋められる。名前を呼ぶ、優しすぎるその声にありったけの愛を込めて名前を呼び返したのだった。
(完)
2/2ページ