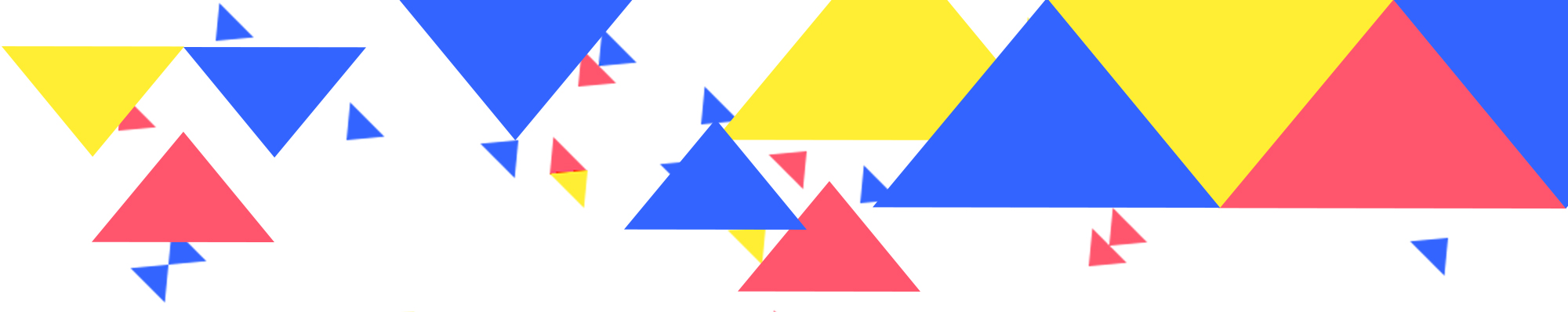ベイビー・ドント・クライ
(平凡×会長/非王道)
あ、泣いてしまう、と思った。視線の先にいる憧れてやまないその人は、呆然としたまま静かに瞬く。重力に逆らいきれず、頬を濡らしていくその涙を拭きたいと上げかけた腕は、溢れている涙の綺麗さに下ろしたままだ。緩慢な仕草で俺を映した黒目がちな目は、悲しさと熱がゆらりと揺らぐ。
「お前は、」
一度視線を下げた後、俺をもう一度眺めた。
「お前は俺を抱けるか。」
縫い止められていた足を動かして、涙を流し続けている彼の前に立つ。抱き締めたい。抱き締めたいけれど、彼が思う腕は俺じゃない。それは分かりきっていること。例え傷つけられて泣いていても、彼の心にいる人は変わらずあの人だ。
「俺は抱きたいと思うよ。もし背があなたよりも低くても、俺はあなたを抱きたいと思う。あなたはとても魅力的な人だから。」
「そうか。」
先程よりも涙をぽろぽろと溢して、泣いてしまう彼の頬を手のひらで挟んで目を覗き込む。頬を濡らしている涙を親指で拭うと、眉を下げた。
「泣かないで。」
「嬉しいんだよ。」
困ったように微笑んだ彼は、ありがとう、と言ってから俺が差し出したハンカチを受けとると、背筋を伸ばして颯爽と去っていった。
*****
俺が彼、光石 薫に会ったのは、入学式の時だった。周りは持ち上がり組ばかりで、外部生の俺が珍しいのか見られるばかりで話しかけられることもなくて辟易していた頃、首席として壇上に上がった光石は、背筋を伸ばして颯爽と皆の前に立つと、よく通る声で挨拶をした。それはもうあっという間に心を奪われてしまったのだ。生徒会長に選ばれて挨拶をした姿にもそれはもう目を奪われたのだけど。
眉目秀麗。成績優秀。スポーツ万能。何をさせても器用にこなして見せるが、かといってそれを鼻にかけることもなく、人に手を貸すことにも嫌な顔ひとつしない人柄の良さから、生徒から愛されてやまない生徒会長。この学園の中に光石を悪くいない、なんて学校生活はある日脆くも崩れ去ってしまったのだけど。
『俺が友達になってやる!』
季節外れの2年生に来た転校生は金髪に碧眼、綺麗な顔立ち、まさに天使のような外見に加え、魔法の言葉と天真爛漫な笑顔で、どんどん色んな人を虜にしていった。あの真っ青で澄んだ目に見つめられて、特別になるなんて言われたらひとたまりもないのかもしれない。ただそれが、光石の邪魔になったり傷付けたりすることの理由にはならないのだけど。
ふと見つけた丸まった背中に小さく笑うと、その人の前に回り込んで顔を覗き込んだ。少し驚いて目を丸くした光石に、ハンカチを差し出す。
「最近はあなたの泣いているところによく遭遇するな。」
「...、お前か。」
我慢することは止めたんだ、と涙を指先で拭うと俺へ笑いかけた光石が、俺の手からハンカチを受け取った。
「今日はどうして泣いてたの?」
「仕事がきついんだ。」
不貞腐れたように唇を尖らせた光石に苦笑しながら、いつもの完璧主義なところも好きだけど、こっちの光石も好きだなぁと暢気に考えて隣に座る。
「生徒会役員が仕事していないんだっけ。」
「だから仕事が多すぎるし、あいつらに電話しても駄目、会いに行っても駄目。それに寝不足にあの声はきついぞ。会ったことあるか?」
「ないな。そんなにうるさいわけ?」
「あれは騒音だぞ。」
息を吐いた光石に笑えば、笑い事じゃないと肩を押された。
「そういえば、まだ授業中じゃないのか?生徒会長の前で堂々とサボりとはな。度胸があるな。」
「授業が早めに終わって、教室に帰るところだったんだよ。」
「こんなところ通ってか?」
「偶然偶然。...、そっちは最近授業受けれてないよね?」
俺の肩に触れたままだった腕を掴めば、不意に悲しみを覆い隠したような笑みが返される。思わず腕を掴んだ手に力を込めても、光石の表情は変わらないまま。
「受けれてないな。うーん。まぁ。こうも忙しいと色々忘れられていいけどな。」
「あなたがそれでいいなら、俺は何も言うことないけど。」
初めて泣いている光石に会ったときは、付き合っていたという副会長にフラれたところだったらしい、というのは3度目に泣いているところに出会したときに聞いた話だ。
「でもこれ以上は無理をしないように。あなたが倒れてどうするの?」
「分かってる。」
「心配なんだよ。俺はたまに会って心配をしていることを伝えることしかできないけど、俺みたいにあなたを心配している人はもっと多いはずだからさ。」
何だか嬉しそうに目を細めた光石に、少しは伝わっているのかもしれないと、口角を上げて笑う。ちらりと腕時計を見た光石が、もうそろそろ昼休みだぞ、と追い立てるように俺の背中を叩いた。
「ありがとうな。今日は早く帰ることにするよ。元気出たよ。」
疲れがとれて目の下にあるクマが少しは薄くなればいいなと思いながら、ポケットを探ってチョコレートを安物だけど、と苦笑いして光石の手のひらに置く。手のひらに置かれたチョコレートに光石は、はにかむように笑って、ありがとう、とチョコレートの包み紙を眺めた。
「またね。」
「またな。」
手を振りながら光石に背を向けて、スマートフォンを取り出す。後輩へと送ったメールはまだ返ってきていなかった。光石は決して、もうやれないとか限界だとは言わないけれど、もう見ていられないなと何も出来ない自分を恨む。頭をがしがしと掻きながら、取り敢えず出来ることと責任を果たそうと、後輩が向かっているであろう食堂に向けて歩き出した。
後少しで食堂というところで、目立つ集団が前の方から歩いてきていて、大きなざわめきを掻くように進んで先頭へと出る。
「翔。」
蕩けそうな笑みを浮かべて転校生を見つめる副会長に思わず舌打ちをしそうになったが、心を落ち着けるためにゆっくりと溜め息を吐くと立ち止まった。傷つけられて泣いている光石の前で、土下座でもさせたい、というのが今の心境だが今は仕方ない。
「山本。話がある。」
「部長。」
気まずげな顔で俺から顔を反らした部活の後輩である山本に、転校生は目くじらを立てて俺を睨みつけた。
「お前誰だよ!用があるんならお前が来いよ!」
「翔。」
「俺は山本が所属しているバスケ部の部長。エースが無断で部活をここずっと休んでいるから、連絡をとって俺の教室へ来るように約束を、昨日していたはずだけど、いくら待っても来なかったから、わざわざ俺から出向いたわけなんだけど。山本、言い訳があるんなら聞いてやる。」
押し黙った山本とまだ何か喚いている転校生。皆の前で話すことを避けようと思っていたが、山本がその気ならどうでもいいかと腕を組む。
「山本。」
「...、すみません。」
「謝罪は聞いてない。山本が部活に来なくても、それは山本の選択だ。だけど、無断はよくない。上級生の自覚を持て。言われなきゃわからないわけじゃないだろ。俺が見てきたお前は。」
唇を噛んでうつ向いたままの山本に、ゆっくり息を吐いた。
「どうして雅也ばっかり責めるんだ!部活がきつくて雅也を苛めてるのも、今だって言い負かして雅也を苛めてるのもお前じゃないか!雅也は悪くない!悪いのは全部お前だ!」
山本から俺を指差した転校生の方に視線を向けて、目を細める。
「お前は友達か?」
「そうだ!俺は雅也の友達だ!」
「甘やかして庇うだけが、友じゃないと思うけど。ずれていると思うことがあったのなら、そこを諭すのも友の役目だ。少し口うるさく感じてもね。」
ぬるま湯はいずれ冷めるよ、とちらりと転校生の後ろを見やれば少しは思うところがあったのか、それぞれうつ向いていた。
「山本。一度部活に出てこい。あと授業にも出ろ。さすがに俺も庇いきれなくなる。」
はっとしたような顔をした山本と、生徒会の役員たち。今さら回りに支えられていたから、この現状が危ないけれど保たれていたのだと知っても遅い。
「遊びたいから遊ぶ。勉強も部活もきついからやらなくていい。自己満足を叶えるためだけの関係を続けるのもいいが、果てには自分を本当に思ってくれる人を傷付けることを自覚しろ。」
「うるさい!うるさい!!うるさい!!!学生だから遊んだっていいだろ!お前なんかに何が分かる!こいつらの気持ちを分かってやれるのも、一緒にいてやれるのも俺だけだ!俺以外に大切な人なんているはずがない!」
「転校生。お前は、もし苛々したからという理由で人を殴った友人がいたら、お前は悪くない、苛々させた相手が悪いんだとお前もその相手を殴るのか?」
押し黙った転校生に、畳み掛けるように口を開いた。
「一緒に悩んで、相談に乗って、向き合うのが友人じゃないのか?生徒会役員。お前らが転校生ばかりにかまけて、生徒たちから孤立していっているのを必死に止めようと叱ってくれて、生徒会でたった一人で頑張りながら戻ってくれるのを待っている人がいるんじゃないのか。そんな人をお前らは友達と呼ばないのか。自分に優しい言葉ばかりを言ってくれる友達のがそりゃ心地いいけど、違うだろ。」
本当に唯一自分を見てくれたのが転校生なのか、と呟けば、泣きそうに顔を歪ませた生徒会役員たちが転校生に謝るとどこかへと走っていった。きっと生徒会室だろう。絶望した顔の転校生に、向き合うと安心させるように小さく笑う。
「皆に好かれなくてもいいでしょ。皆がみんな友達じゃなくても、それだけがお前の価値じゃないと思う。」
ぽろぽろと泣き出した転校生の背中を、すぐ後ろにいた生徒が撫でた。山本はもう一度謝ると、力強く今日から部活に参加しますと力強く宣言する言葉に頷く。ああもう時間がないなと時計を確認して、頭を掻いた。大切なあの人が、辛くて泣くことが減ればいい。俺はきっかけしか作れないけれど。どさくさに紛れて光石に告白すればよかったかな、と少しだけ思いながらも、ただただ少し照れたようなあの笑顔に思いを馳せたのだった。
あ、泣いてしまう、と思った。視線の先にいる憧れてやまないその人は、呆然としたまま静かに瞬く。重力に逆らいきれず、頬を濡らしていくその涙を拭きたいと上げかけた腕は、溢れている涙の綺麗さに下ろしたままだ。緩慢な仕草で俺を映した黒目がちな目は、悲しさと熱がゆらりと揺らぐ。
「お前は、」
一度視線を下げた後、俺をもう一度眺めた。
「お前は俺を抱けるか。」
縫い止められていた足を動かして、涙を流し続けている彼の前に立つ。抱き締めたい。抱き締めたいけれど、彼が思う腕は俺じゃない。それは分かりきっていること。例え傷つけられて泣いていても、彼の心にいる人は変わらずあの人だ。
「俺は抱きたいと思うよ。もし背があなたよりも低くても、俺はあなたを抱きたいと思う。あなたはとても魅力的な人だから。」
「そうか。」
先程よりも涙をぽろぽろと溢して、泣いてしまう彼の頬を手のひらで挟んで目を覗き込む。頬を濡らしている涙を親指で拭うと、眉を下げた。
「泣かないで。」
「嬉しいんだよ。」
困ったように微笑んだ彼は、ありがとう、と言ってから俺が差し出したハンカチを受けとると、背筋を伸ばして颯爽と去っていった。
*****
俺が彼、光石 薫に会ったのは、入学式の時だった。周りは持ち上がり組ばかりで、外部生の俺が珍しいのか見られるばかりで話しかけられることもなくて辟易していた頃、首席として壇上に上がった光石は、背筋を伸ばして颯爽と皆の前に立つと、よく通る声で挨拶をした。それはもうあっという間に心を奪われてしまったのだ。生徒会長に選ばれて挨拶をした姿にもそれはもう目を奪われたのだけど。
眉目秀麗。成績優秀。スポーツ万能。何をさせても器用にこなして見せるが、かといってそれを鼻にかけることもなく、人に手を貸すことにも嫌な顔ひとつしない人柄の良さから、生徒から愛されてやまない生徒会長。この学園の中に光石を悪くいない、なんて学校生活はある日脆くも崩れ去ってしまったのだけど。
『俺が友達になってやる!』
季節外れの2年生に来た転校生は金髪に碧眼、綺麗な顔立ち、まさに天使のような外見に加え、魔法の言葉と天真爛漫な笑顔で、どんどん色んな人を虜にしていった。あの真っ青で澄んだ目に見つめられて、特別になるなんて言われたらひとたまりもないのかもしれない。ただそれが、光石の邪魔になったり傷付けたりすることの理由にはならないのだけど。
ふと見つけた丸まった背中に小さく笑うと、その人の前に回り込んで顔を覗き込んだ。少し驚いて目を丸くした光石に、ハンカチを差し出す。
「最近はあなたの泣いているところによく遭遇するな。」
「...、お前か。」
我慢することは止めたんだ、と涙を指先で拭うと俺へ笑いかけた光石が、俺の手からハンカチを受け取った。
「今日はどうして泣いてたの?」
「仕事がきついんだ。」
不貞腐れたように唇を尖らせた光石に苦笑しながら、いつもの完璧主義なところも好きだけど、こっちの光石も好きだなぁと暢気に考えて隣に座る。
「生徒会役員が仕事していないんだっけ。」
「だから仕事が多すぎるし、あいつらに電話しても駄目、会いに行っても駄目。それに寝不足にあの声はきついぞ。会ったことあるか?」
「ないな。そんなにうるさいわけ?」
「あれは騒音だぞ。」
息を吐いた光石に笑えば、笑い事じゃないと肩を押された。
「そういえば、まだ授業中じゃないのか?生徒会長の前で堂々とサボりとはな。度胸があるな。」
「授業が早めに終わって、教室に帰るところだったんだよ。」
「こんなところ通ってか?」
「偶然偶然。...、そっちは最近授業受けれてないよね?」
俺の肩に触れたままだった腕を掴めば、不意に悲しみを覆い隠したような笑みが返される。思わず腕を掴んだ手に力を込めても、光石の表情は変わらないまま。
「受けれてないな。うーん。まぁ。こうも忙しいと色々忘れられていいけどな。」
「あなたがそれでいいなら、俺は何も言うことないけど。」
初めて泣いている光石に会ったときは、付き合っていたという副会長にフラれたところだったらしい、というのは3度目に泣いているところに出会したときに聞いた話だ。
「でもこれ以上は無理をしないように。あなたが倒れてどうするの?」
「分かってる。」
「心配なんだよ。俺はたまに会って心配をしていることを伝えることしかできないけど、俺みたいにあなたを心配している人はもっと多いはずだからさ。」
何だか嬉しそうに目を細めた光石に、少しは伝わっているのかもしれないと、口角を上げて笑う。ちらりと腕時計を見た光石が、もうそろそろ昼休みだぞ、と追い立てるように俺の背中を叩いた。
「ありがとうな。今日は早く帰ることにするよ。元気出たよ。」
疲れがとれて目の下にあるクマが少しは薄くなればいいなと思いながら、ポケットを探ってチョコレートを安物だけど、と苦笑いして光石の手のひらに置く。手のひらに置かれたチョコレートに光石は、はにかむように笑って、ありがとう、とチョコレートの包み紙を眺めた。
「またね。」
「またな。」
手を振りながら光石に背を向けて、スマートフォンを取り出す。後輩へと送ったメールはまだ返ってきていなかった。光石は決して、もうやれないとか限界だとは言わないけれど、もう見ていられないなと何も出来ない自分を恨む。頭をがしがしと掻きながら、取り敢えず出来ることと責任を果たそうと、後輩が向かっているであろう食堂に向けて歩き出した。
後少しで食堂というところで、目立つ集団が前の方から歩いてきていて、大きなざわめきを掻くように進んで先頭へと出る。
「翔。」
蕩けそうな笑みを浮かべて転校生を見つめる副会長に思わず舌打ちをしそうになったが、心を落ち着けるためにゆっくりと溜め息を吐くと立ち止まった。傷つけられて泣いている光石の前で、土下座でもさせたい、というのが今の心境だが今は仕方ない。
「山本。話がある。」
「部長。」
気まずげな顔で俺から顔を反らした部活の後輩である山本に、転校生は目くじらを立てて俺を睨みつけた。
「お前誰だよ!用があるんならお前が来いよ!」
「翔。」
「俺は山本が所属しているバスケ部の部長。エースが無断で部活をここずっと休んでいるから、連絡をとって俺の教室へ来るように約束を、昨日していたはずだけど、いくら待っても来なかったから、わざわざ俺から出向いたわけなんだけど。山本、言い訳があるんなら聞いてやる。」
押し黙った山本とまだ何か喚いている転校生。皆の前で話すことを避けようと思っていたが、山本がその気ならどうでもいいかと腕を組む。
「山本。」
「...、すみません。」
「謝罪は聞いてない。山本が部活に来なくても、それは山本の選択だ。だけど、無断はよくない。上級生の自覚を持て。言われなきゃわからないわけじゃないだろ。俺が見てきたお前は。」
唇を噛んでうつ向いたままの山本に、ゆっくり息を吐いた。
「どうして雅也ばっかり責めるんだ!部活がきつくて雅也を苛めてるのも、今だって言い負かして雅也を苛めてるのもお前じゃないか!雅也は悪くない!悪いのは全部お前だ!」
山本から俺を指差した転校生の方に視線を向けて、目を細める。
「お前は友達か?」
「そうだ!俺は雅也の友達だ!」
「甘やかして庇うだけが、友じゃないと思うけど。ずれていると思うことがあったのなら、そこを諭すのも友の役目だ。少し口うるさく感じてもね。」
ぬるま湯はいずれ冷めるよ、とちらりと転校生の後ろを見やれば少しは思うところがあったのか、それぞれうつ向いていた。
「山本。一度部活に出てこい。あと授業にも出ろ。さすがに俺も庇いきれなくなる。」
はっとしたような顔をした山本と、生徒会の役員たち。今さら回りに支えられていたから、この現状が危ないけれど保たれていたのだと知っても遅い。
「遊びたいから遊ぶ。勉強も部活もきついからやらなくていい。自己満足を叶えるためだけの関係を続けるのもいいが、果てには自分を本当に思ってくれる人を傷付けることを自覚しろ。」
「うるさい!うるさい!!うるさい!!!学生だから遊んだっていいだろ!お前なんかに何が分かる!こいつらの気持ちを分かってやれるのも、一緒にいてやれるのも俺だけだ!俺以外に大切な人なんているはずがない!」
「転校生。お前は、もし苛々したからという理由で人を殴った友人がいたら、お前は悪くない、苛々させた相手が悪いんだとお前もその相手を殴るのか?」
押し黙った転校生に、畳み掛けるように口を開いた。
「一緒に悩んで、相談に乗って、向き合うのが友人じゃないのか?生徒会役員。お前らが転校生ばかりにかまけて、生徒たちから孤立していっているのを必死に止めようと叱ってくれて、生徒会でたった一人で頑張りながら戻ってくれるのを待っている人がいるんじゃないのか。そんな人をお前らは友達と呼ばないのか。自分に優しい言葉ばかりを言ってくれる友達のがそりゃ心地いいけど、違うだろ。」
本当に唯一自分を見てくれたのが転校生なのか、と呟けば、泣きそうに顔を歪ませた生徒会役員たちが転校生に謝るとどこかへと走っていった。きっと生徒会室だろう。絶望した顔の転校生に、向き合うと安心させるように小さく笑う。
「皆に好かれなくてもいいでしょ。皆がみんな友達じゃなくても、それだけがお前の価値じゃないと思う。」
ぽろぽろと泣き出した転校生の背中を、すぐ後ろにいた生徒が撫でた。山本はもう一度謝ると、力強く今日から部活に参加しますと力強く宣言する言葉に頷く。ああもう時間がないなと時計を確認して、頭を掻いた。大切なあの人が、辛くて泣くことが減ればいい。俺はきっかけしか作れないけれど。どさくさに紛れて光石に告白すればよかったかな、と少しだけ思いながらも、ただただ少し照れたようなあの笑顔に思いを馳せたのだった。
1/2ページ