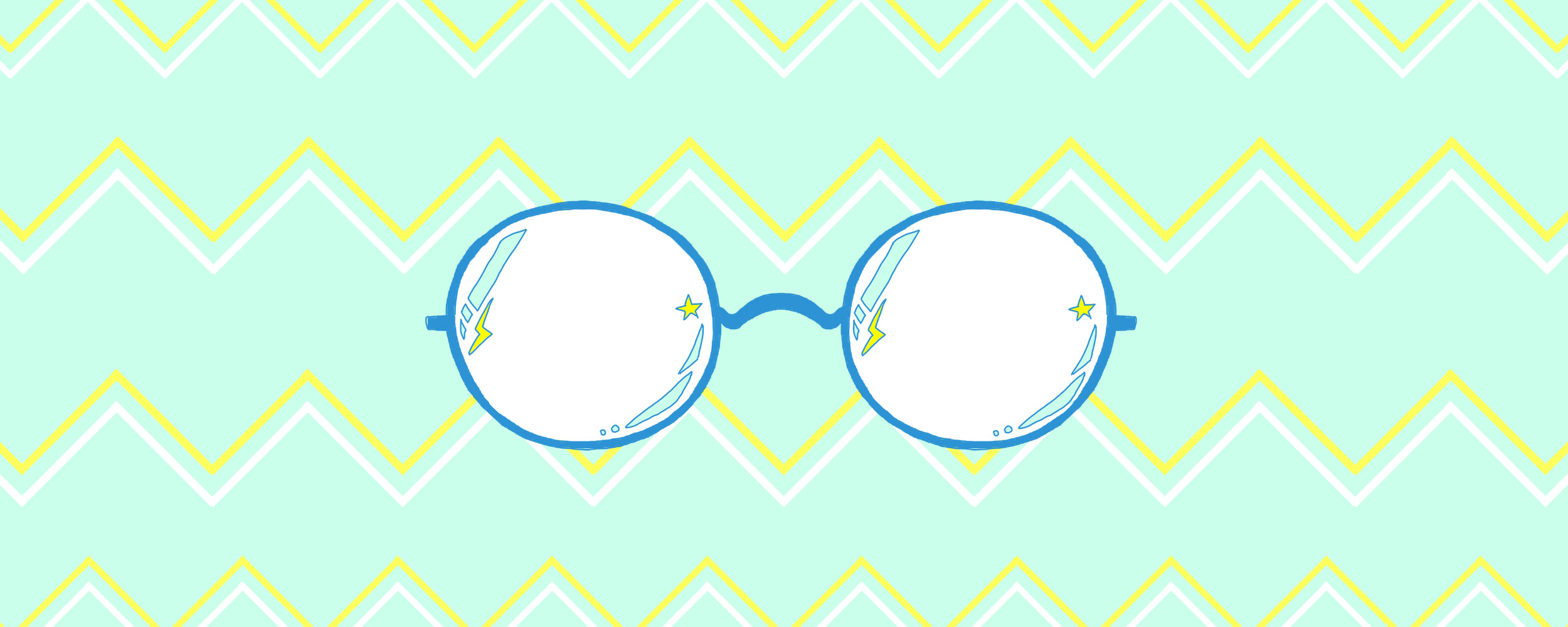となりの花屋さん
赤、青、黄色、紫、黒、緑、オレンジ。薄く張られた水に小さな種が浸されている。並んだそれは生命を孕み、膨らんで、自らの殻を破ろうとしている。
薄暗い店の奥、レジの横に置かれたそれにポタポタと小さな波紋が広がる。緑間はうっすらと浮かぶ容器の縁をじっと見下ろしていた。
となりが花屋さん
朝の光に照らされている店先の花は水滴を纏ってよりキラキラと輝いて見える。水をやる主人のエプロンのポケットに小さなテディベアが二つ並んで頭を出している。
こぶりのジョウロを片手に緑間は隣人である高尾の姿を捕えて、目を見開いた。高尾の隣には知らない女が居た。そして緑間は目を瞑り、足速に店の中へ入っていった。
まだ肌寒い夏の朝、店の奥で緑間は昨日アイロンをかけた白いシャツが背筋に滲んだ汗をしっとりと吸い込むのを感じた。足元には、ジョウロから零れた水が拡がっていた。
昨晩は飲み会がある、という理由で高尾は作り置きのカレーを用意して行った。冷たい鍋を火に掛けて焦げないようにおたまで必死にルーを掻き混ぜていたのは緑間の記憶に新しい。
飲み会があると言っていたのだから、終電に間に合わなかった同僚や友人が泊まっていくのはよくあることだろう。しかし緑間が見たのは、高尾と知らない女だ。つまりは、そういう事なのだろうと思った。
高尾と異性の話をした事は本当に少ない。それ故に、お互い恋愛事情を知らなかった。緑間は知った事が嫌だったのか、知らなかった事が嫌だったのかはわからないが、痛む胸をギュッと掴んだ。
「真ちゃん、朝会わなかったけどどったの?」
夕方になり、高尾が夕飯の買い物を済ませて来た。ガサガサと袋を鳴らしながらレジにいる緑間へと近付く。もう一度真ちゃん、と呼びながらレジに肘を着き、緑間の顔を覗く。
緑間は高尾の顔を見ると、眉間の皺を深めた。
「……」
「なんか不機嫌じゃね?」
もしかして、これ?と、レジに小さなテディベアをひとつ置いた。高尾の指で転がされるそれを見ると、緑間ははっとしてエプロンのポケットに手をやった。確かに朝ふたつ並んでいたそれはひとつしかなかった。緑間はラッキーアイテムに気が回らない程、朝の光景が頭から離れなかったのだ。
「朝店の前に落ちてたんだけど、真ちゃんいないし俺も急いでたしで渡せなかったんだよな。もう落とすなよー」
高尾は緑間の手を取ってテディベアを返そうとする。しかし、それは持ち主にはきちんと返らなかった。代わりにパシ、と乾いた音が響いた。手を払う音だった。
緑間は無意識に高尾を拒絶していた。そして、はっと我に返った時には既に目の前の高尾は動揺していた。少し悲しいような、寂しそうな目だった。テディベアも横たわって緑間の方をじっと見ていた。
「え、っと……」
「こ、肥やしを弄った、から、汚いのだよ」
緑間は見え透いた嘘を言う。肥やしを今日は弄っていない。弄ったとしても素手では扱わないし、絶対に手を洗う緑間の手が汚いわけがない。ただ自分が朝の件で苛立っている事を悟られないように、必死で隠していたのだ。
わかったと頷いた高尾は、じゃあ風呂入っちゃいなよ、と笑って優しかった。
「飯の準備しとくからさ」
いつものように店の奥、緑間の生活空間に入っていく高尾。その横顔が何処となく哀しげに見えたのは、緑間の心持ちが違ったからかもしれない。
レジに残されたテディベアを指で摘むと、すっかりそれは冷たくなってひんやりとしていた。
ガシガシと乾いたタオルで濡れた髪を拭く。風呂から出たばかりの緑間は毛先から水滴を垂らす。上裸のまま洗面所へ迎う。そして、眼鏡を外し、ドライヤーで髪を乾かす。以前はこの独特な音が得意ではなかった緑間は、ドライヤーを気紛れに使っていた。だが、高尾が一度だけドライヤーをかけてくれたときから、毎日使うようにしている。折角綺麗な髪なんだから、と女に向かう台詞が嬉しくなかったといえば嘘になるが、それ以上に頭に触れた手の感触が忘れられなかった。
「真ちゃん、ご飯できたよ」
ひょいとやってきた高尾が鏡越しに緑間を覗く。綺麗になったな、と言ってリビングに戻っていった。
その日のメインは魚だった。生の白身魚を薄切りにしてスダチに漬け、彩りのいい生野菜と盛り付けてあるさっぱりとした料理だった。かかっていた和風のドレッシングも作ったと高尾は言っていた。
どうしてこんなに器用なのだろうと緑間は考えた。自ら辿り着いた答えは、恋人の存在だった。たぶん、高尾に恋人がいることが嫌なのだろうと、緑間は気が付いた。
そして、目の前にいる彼の名前を呼んだ。
薄暗い店の奥、レジの横に置かれたそれにポタポタと小さな波紋が広がる。緑間はうっすらと浮かぶ容器の縁をじっと見下ろしていた。
となりが花屋さん
朝の光に照らされている店先の花は水滴を纏ってよりキラキラと輝いて見える。水をやる主人のエプロンのポケットに小さなテディベアが二つ並んで頭を出している。
こぶりのジョウロを片手に緑間は隣人である高尾の姿を捕えて、目を見開いた。高尾の隣には知らない女が居た。そして緑間は目を瞑り、足速に店の中へ入っていった。
まだ肌寒い夏の朝、店の奥で緑間は昨日アイロンをかけた白いシャツが背筋に滲んだ汗をしっとりと吸い込むのを感じた。足元には、ジョウロから零れた水が拡がっていた。
昨晩は飲み会がある、という理由で高尾は作り置きのカレーを用意して行った。冷たい鍋を火に掛けて焦げないようにおたまで必死にルーを掻き混ぜていたのは緑間の記憶に新しい。
飲み会があると言っていたのだから、終電に間に合わなかった同僚や友人が泊まっていくのはよくあることだろう。しかし緑間が見たのは、高尾と知らない女だ。つまりは、そういう事なのだろうと思った。
高尾と異性の話をした事は本当に少ない。それ故に、お互い恋愛事情を知らなかった。緑間は知った事が嫌だったのか、知らなかった事が嫌だったのかはわからないが、痛む胸をギュッと掴んだ。
「真ちゃん、朝会わなかったけどどったの?」
夕方になり、高尾が夕飯の買い物を済ませて来た。ガサガサと袋を鳴らしながらレジにいる緑間へと近付く。もう一度真ちゃん、と呼びながらレジに肘を着き、緑間の顔を覗く。
緑間は高尾の顔を見ると、眉間の皺を深めた。
「……」
「なんか不機嫌じゃね?」
もしかして、これ?と、レジに小さなテディベアをひとつ置いた。高尾の指で転がされるそれを見ると、緑間ははっとしてエプロンのポケットに手をやった。確かに朝ふたつ並んでいたそれはひとつしかなかった。緑間はラッキーアイテムに気が回らない程、朝の光景が頭から離れなかったのだ。
「朝店の前に落ちてたんだけど、真ちゃんいないし俺も急いでたしで渡せなかったんだよな。もう落とすなよー」
高尾は緑間の手を取ってテディベアを返そうとする。しかし、それは持ち主にはきちんと返らなかった。代わりにパシ、と乾いた音が響いた。手を払う音だった。
緑間は無意識に高尾を拒絶していた。そして、はっと我に返った時には既に目の前の高尾は動揺していた。少し悲しいような、寂しそうな目だった。テディベアも横たわって緑間の方をじっと見ていた。
「え、っと……」
「こ、肥やしを弄った、から、汚いのだよ」
緑間は見え透いた嘘を言う。肥やしを今日は弄っていない。弄ったとしても素手では扱わないし、絶対に手を洗う緑間の手が汚いわけがない。ただ自分が朝の件で苛立っている事を悟られないように、必死で隠していたのだ。
わかったと頷いた高尾は、じゃあ風呂入っちゃいなよ、と笑って優しかった。
「飯の準備しとくからさ」
いつものように店の奥、緑間の生活空間に入っていく高尾。その横顔が何処となく哀しげに見えたのは、緑間の心持ちが違ったからかもしれない。
レジに残されたテディベアを指で摘むと、すっかりそれは冷たくなってひんやりとしていた。
ガシガシと乾いたタオルで濡れた髪を拭く。風呂から出たばかりの緑間は毛先から水滴を垂らす。上裸のまま洗面所へ迎う。そして、眼鏡を外し、ドライヤーで髪を乾かす。以前はこの独特な音が得意ではなかった緑間は、ドライヤーを気紛れに使っていた。だが、高尾が一度だけドライヤーをかけてくれたときから、毎日使うようにしている。折角綺麗な髪なんだから、と女に向かう台詞が嬉しくなかったといえば嘘になるが、それ以上に頭に触れた手の感触が忘れられなかった。
「真ちゃん、ご飯できたよ」
ひょいとやってきた高尾が鏡越しに緑間を覗く。綺麗になったな、と言ってリビングに戻っていった。
その日のメインは魚だった。生の白身魚を薄切りにしてスダチに漬け、彩りのいい生野菜と盛り付けてあるさっぱりとした料理だった。かかっていた和風のドレッシングも作ったと高尾は言っていた。
どうしてこんなに器用なのだろうと緑間は考えた。自ら辿り着いた答えは、恋人の存在だった。たぶん、高尾に恋人がいることが嫌なのだろうと、緑間は気が付いた。
そして、目の前にいる彼の名前を呼んだ。