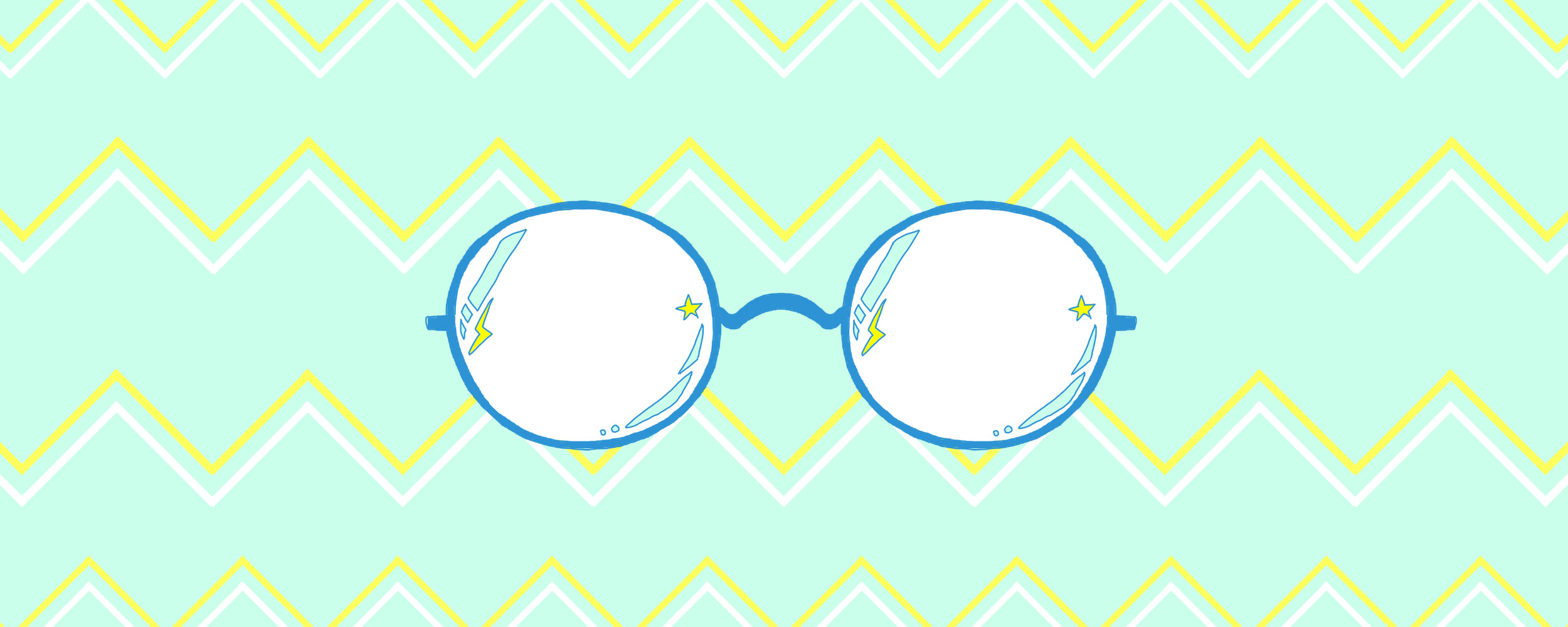となりの花屋さん
隣の花屋には変人がいる。
変人というと何だか語弊がある気がするが、おは朝信者で毎日占いのラッキーアイテム持ってて、ついでに語尾がなのだよ、じゃまあそこそこ変人か。ラッキーアイテムが手に入らなかったりすると、入手したいんだろうが店空ける訳にはいかないからかなり沈んでる。来る客来る客にラッキーアイテム持ってませんか?と聞いている姿はこの店の名物だったりする。
そんな隣の花屋さんは、今日もラッキーアイテムであろう金のブタの貯金箱を大事そうに持っていた。
となりは花屋さん
あれから何回目になるだろうか、二人で顔を会わせてご飯を囲むのは。
以前、高尾が仕事帰りにハンカチのお礼だと夕食に誘ったが、花屋は遅くまで仕事があるとやんわりとした断りに取れるような返事を緑間からもらった。だが、外食でないなら、と高尾の意に反し緑間からの提案があり、花屋兼緑間の家でご飯を作って食べることになった。早速高尾は買い出しへ、緑間は迅速に仕事をこなした。
定番のカレーを同じ空間で食すという、いつも以上に話す時間を得た二人だったが、高尾はなんだか見合いのような質問を、緑間は食事中話さないらしく、彼から話を振ることはなかった。
しかし、緑間は料理が苦手だという事実を知ることができた。高尾は都合のあう日だけでも夕飯を一緒に食べようと緑間に言った。始めは渋っていた緑間だったが、高尾が一人で飯を食うのは寂しい、と言えば眉を下げて笑い、許してくれた。これが大きな収穫だった。
「真ちゃん、できたよー」
店の奥から食欲を誘う匂いと共に高尾が顔を出す。仕事を終えていた緑間は手に浅い皿のようなものを持っていた。皿に水を敷き、黒い種のようなものを浸していた。
「なにそれ?」
「アサガオの種なのだよ」
少ししたら土に埋めるのだよ、とレジ横に置く。緑間が持っていた他にも種を浸したものが並んでいた。膨らんだ小さな身体から芽を出すのを楽しみに、微かに笑みを溢した。
手を洗った緑間を横目に見ると、ハンドクリームを塗りこんでいた。彼の白く柔かな手が荒れていないのは忠実に手入れをしているからだ。現に、高尾が料理皿を手渡しするときに、緑間の手が触れたが、彼の手は本当に綺麗だ。
「今日はパスタか、いただきますなのだよ」
緑間がきちんと手を合わせると、つられて高尾も手を合わせる。フォークを持ち、立てて回せば、鮮やかな彩りの野菜とパスタが絡む。
緑間が左利きだと知ったのは、こういう事をするようになってからだった。高尾は思い返せば、緑間は左手を使う事が多かったなと気付いた。
「真ちゃん、ちょっと晩酌付き合ってよ」
お互いの料理が終わる頃に高尾が言った。
「ご飯が終わってしまうのだよ」
「つまみが飯ってのもなんかな」
頬を緩め高尾は言った。片付けて待ってるから、先に風呂入って来なよ、と緑間を促せば、彼は素直に足を向かわせた。シャワーの音が聞こえているうちに、高尾は片付けとお酒の用意を済ませた。
アルコールが回った緑間は饒舌だった。傍から見て酔っていると解るような酔い方ではないが、如何せん喋る。口を開けばおは朝おは朝。他にないのか、と高尾が問えば、お前の飯は美味いのだよ、と言った。不意打ちだが褒められた高尾は嬉しかった。そして、緑間の隣に座っている高尾は、ひんやりとしたテーブルに頬を着け、そのまま緑間を見上げた。
「真ちゃん」
「何だ、にやにやして気持ち悪いのだよ」
「いっつも、そう思ってたの?」
高尾は自らの目に真っ直ぐ緑間を映し、言った。レンズ越しに絡む緑色の視線に高尾は期待せずには居られなかった。
「ああ、いつも感謝しているのだよ」
微笑む彼の表情は何よりも綺麗で、高尾は顔が紅潮するのを感じた。何だか居たたまれない気持ちになってしまった高尾は頭を抱えて言った。
「真ちゃん、ズルい、……」
小さく言ったありがとう、が緑間に聞こえていればいいと高尾は思った。
変人というと何だか語弊がある気がするが、おは朝信者で毎日占いのラッキーアイテム持ってて、ついでに語尾がなのだよ、じゃまあそこそこ変人か。ラッキーアイテムが手に入らなかったりすると、入手したいんだろうが店空ける訳にはいかないからかなり沈んでる。来る客来る客にラッキーアイテム持ってませんか?と聞いている姿はこの店の名物だったりする。
そんな隣の花屋さんは、今日もラッキーアイテムであろう金のブタの貯金箱を大事そうに持っていた。
となりは花屋さん
あれから何回目になるだろうか、二人で顔を会わせてご飯を囲むのは。
以前、高尾が仕事帰りにハンカチのお礼だと夕食に誘ったが、花屋は遅くまで仕事があるとやんわりとした断りに取れるような返事を緑間からもらった。だが、外食でないなら、と高尾の意に反し緑間からの提案があり、花屋兼緑間の家でご飯を作って食べることになった。早速高尾は買い出しへ、緑間は迅速に仕事をこなした。
定番のカレーを同じ空間で食すという、いつも以上に話す時間を得た二人だったが、高尾はなんだか見合いのような質問を、緑間は食事中話さないらしく、彼から話を振ることはなかった。
しかし、緑間は料理が苦手だという事実を知ることができた。高尾は都合のあう日だけでも夕飯を一緒に食べようと緑間に言った。始めは渋っていた緑間だったが、高尾が一人で飯を食うのは寂しい、と言えば眉を下げて笑い、許してくれた。これが大きな収穫だった。
「真ちゃん、できたよー」
店の奥から食欲を誘う匂いと共に高尾が顔を出す。仕事を終えていた緑間は手に浅い皿のようなものを持っていた。皿に水を敷き、黒い種のようなものを浸していた。
「なにそれ?」
「アサガオの種なのだよ」
少ししたら土に埋めるのだよ、とレジ横に置く。緑間が持っていた他にも種を浸したものが並んでいた。膨らんだ小さな身体から芽を出すのを楽しみに、微かに笑みを溢した。
手を洗った緑間を横目に見ると、ハンドクリームを塗りこんでいた。彼の白く柔かな手が荒れていないのは忠実に手入れをしているからだ。現に、高尾が料理皿を手渡しするときに、緑間の手が触れたが、彼の手は本当に綺麗だ。
「今日はパスタか、いただきますなのだよ」
緑間がきちんと手を合わせると、つられて高尾も手を合わせる。フォークを持ち、立てて回せば、鮮やかな彩りの野菜とパスタが絡む。
緑間が左利きだと知ったのは、こういう事をするようになってからだった。高尾は思い返せば、緑間は左手を使う事が多かったなと気付いた。
「真ちゃん、ちょっと晩酌付き合ってよ」
お互いの料理が終わる頃に高尾が言った。
「ご飯が終わってしまうのだよ」
「つまみが飯ってのもなんかな」
頬を緩め高尾は言った。片付けて待ってるから、先に風呂入って来なよ、と緑間を促せば、彼は素直に足を向かわせた。シャワーの音が聞こえているうちに、高尾は片付けとお酒の用意を済ませた。
アルコールが回った緑間は饒舌だった。傍から見て酔っていると解るような酔い方ではないが、如何せん喋る。口を開けばおは朝おは朝。他にないのか、と高尾が問えば、お前の飯は美味いのだよ、と言った。不意打ちだが褒められた高尾は嬉しかった。そして、緑間の隣に座っている高尾は、ひんやりとしたテーブルに頬を着け、そのまま緑間を見上げた。
「真ちゃん」
「何だ、にやにやして気持ち悪いのだよ」
「いっつも、そう思ってたの?」
高尾は自らの目に真っ直ぐ緑間を映し、言った。レンズ越しに絡む緑色の視線に高尾は期待せずには居られなかった。
「ああ、いつも感謝しているのだよ」
微笑む彼の表情は何よりも綺麗で、高尾は顔が紅潮するのを感じた。何だか居たたまれない気持ちになってしまった高尾は頭を抱えて言った。
「真ちゃん、ズルい、……」
小さく言ったありがとう、が緑間に聞こえていればいいと高尾は思った。