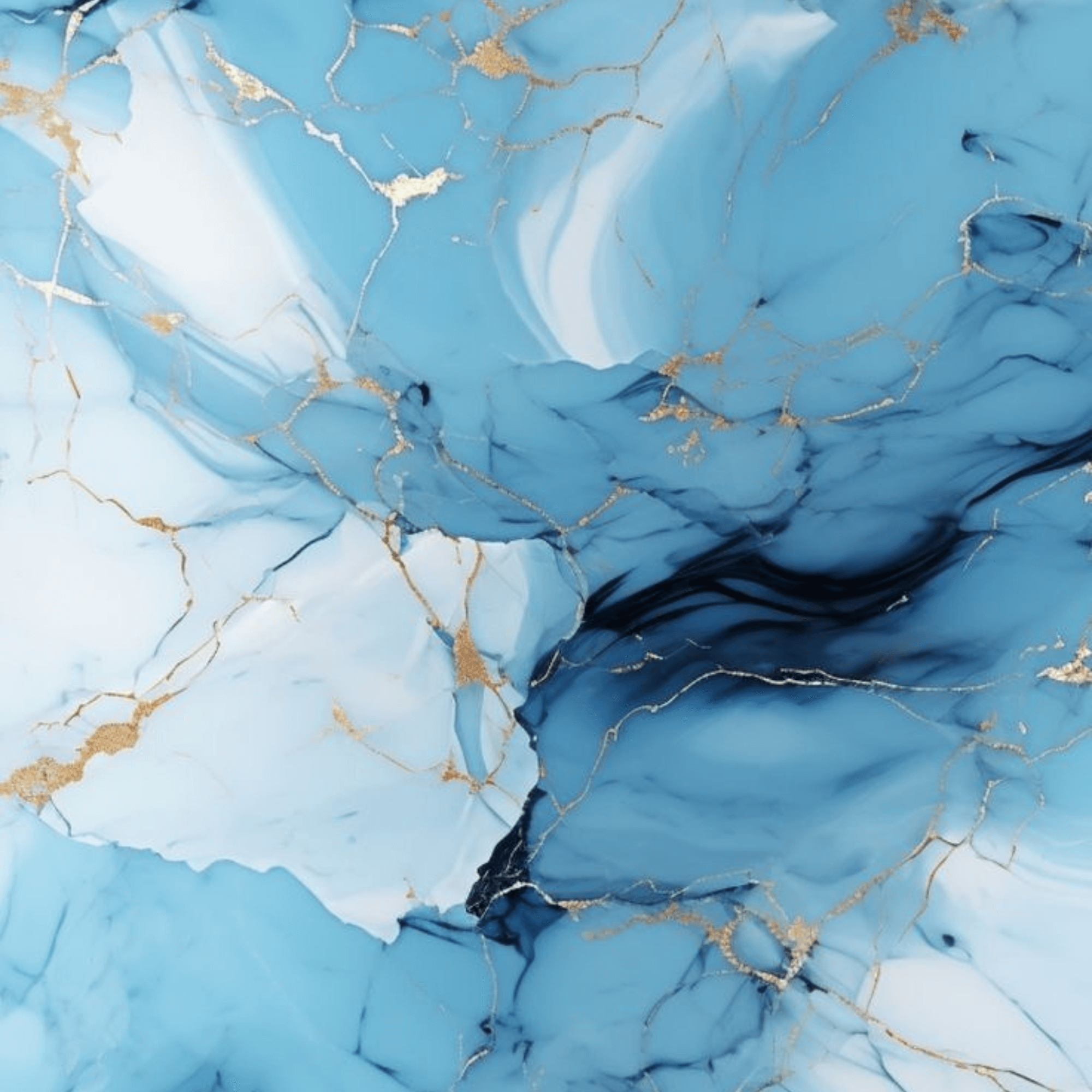春の鴉は天使になれない(高杉晋作)
name
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
どうして生きているのだろう。
どうして息をしているのだろう。
どうして生まれてきてしまったのだろう。
どうしてこんな生き方しかできないのだろう。
頭の中を巡り廻る“どうして”の数々のどれひとつにも答えを出せず、今日も酸素を吸っては二酸化炭素を吐き出している。非生産的な行いを繰り返すばかりの人間、それが“私”だ。
誰に必要とされることもなく、誰かの邪魔にならないよう部屋の隅、足ふたつ分の空間にしか居場所を見つけられない陰鬱な人間、それが私“小鳥遊 初花”だった。
何度かリタイアしそうになりながらも、なんとか歩み続け────いや、歩みを止める勇気すらなく、惰性で生き続けて、大学に入りはした。家事なんて滅多に手伝いもしなかったツケが回りに回ったような1Kでつい先日、私は二十歳を迎えた。家族以外には、家族も同然の友人ひとりからしか祝いのメッセージは届かなかった寂しい人間だ。
けれど、家族もいて、これ以上ないと思えるほど親しい友人もいる。自分なんかよりもっと辛い思いをしているひとなんて世界中探せばいくらでも見つかる。なのに足りないと人目を忍んで涙を流すこともある。その程度の人間だ。どこにでもいる、矮小で愚かで、生きていることに何の意味も、価値もない人間。
私はこんな私の人生を二十年も続けるつもりはなかった。何年続けようが特色もない、味気もない人生に違いないと十年前から悟っていたからだ。
だと言うのに、意気地もない私は、私の人生を終わらせられなかった。本当に、仕様もない人間だ。こんな人間の一生なんか早く終わってしまえば良いのに。
そんな鬱々とした気持ちを抱えたまま歩いていると、顔の見えない誰かが向かいから歩いてくる。すれ違う瞬間、その誰かは刃物のようなもので私の胸を突き刺した。
貫かれた胸から、手足の指先に向かって、焼けるような痛みが駆け抜けていく。
経験したことのない痛みに私は思わず顔を顰め────、
そこで、目が覚めた。思わず胸に手を当てるが、そこに傷はなく、私は講義で扱われた資料を探しに大学の図書館に来ていたことを思い出した。伏せていた顔を上げると、すぐ伸びては視界を薄暗く覆う前髪が眼球に突き刺さる。
「ったぁ……」
努めて声を押し殺したつもりが、静まり返っている図書館では響き渡ってしまう。
恥ずかしさを誤魔化すように、前髪を払おうとした手が何かにぶつかった。それは、少し乾燥しているようで、瑞々しさも感じるような、熱を持っているような、まるで────
────まるで、ひとの手のような。何か。
「キミ、酷い顔色だぞ。何か悪い夢でも見たのか?」
ここがどこだろうが、周りに誰がいようが、関係ないと言わんばかりの声量。親しい友人のような距離感から聞こえてきたそれは、間違いなく私に向かって発せられていた。
ぶつかって机に落ちた私の手の代わりに、そのひとの手が、指が、長い前髪を横へと退ける。開けた視界の先には、朱殷の色が広がっていた。
「な、え……? だ、だっ……!? ……!?」
変色した血のような髪のそのひとは、まるで彼岸花のようだ。なんて、現実逃避しかける頭では上手く言葉が出てこない。
誰とか、何でとか、何が起こってるのかとか、たくさんたくさん言いたいことはあるのに、上手く言葉が出てこない。どこを見て良いのかも分からない。行き場をなくした視線がグルグルと回って、何も分からないまま私は席を立った。
「す、すみません、大丈夫です、ほんとに、大丈夫なので」
慌てて荷物を引っ掴んで、そのひとの横を駆け足で通り抜ける。すると、出口に向かう階段を駆け降りようとして、ようやく私は自分の置かれた異様な状況に気が付いた。
何で電気が付いていないんだろう? 何で誰もいないんだろう? 何で誰も起こしてくれなかったんだろう? 何で私とあのひとだけ取り残されていたんだろう?
まるで、寝る前によく見るホラーゲームの実況のような展開に、嫌な汗が止まらない。私は自分の中から聞こえる心音が足音のように聞こえ、自分を追い立てる幻聴から逃げるように、半ば足を縺れさせながら出口へと走った。
大学の門の外まで出て、校舎を振り返ると、大学全体……どの教室も、廊下も、電気が消されているのか真っ暗な状態で、異様な雰囲気を漂わせている。
目の前の光景が何ひとつとして信じられなかった。
きっと何か悪い夢でも見ているに違いない。そう、そうに決まっている。これはさっき見ていた夢の続きなんだ。そうでなければ、あんなひと、現実にいるわけがない。あんな、あんな────
「置いて行くなんて酷いじゃないか」
「ワ゚ァ────!?」
全速力で自室まで帰ってきた瞬間、つい先程確かに自分しか周囲にいないことを確認して鍵までかけて閉めたはずの扉の内側────自分と扉の間から突然第三者の声が投げかけられ、自身の喉からおよそ人間のものとは思えない声が出た。どこからどうやって出たんだあの声は。
一人暮らし用マンションの玄関にしては広いとはいえ、突然のことにテンパっている人間にとってはそんなこと関係ない。意味はなくともとにかく侵入者から距離を取ろうと、身体を無理矢理動かして、土間の段差に躓く。私は、私が知る中で最も鈍臭く、おっちょこちょいな人間だと自負していた。
「はっ離して!! 誰か助けっモガ……」
「待て待て待て! 落ち着きたまえ! 自分で言うのも癪だが僕はキミの使い魔!! キミが喚び出したアーチャーのサーヴァントだ!!」
顔面を廊下の床に叩きつける前に、腹部に回された腕が私の身体を捕らえた。ではせめて思いっ切り騒ぎ立てて近隣住民に助けてもらおうと考えたが、口まで塞がれてしまいそれは叶わなくなる。
万事休す。こんなことになるなら、先週末は実家に帰っておくべきだった。もっと母の料理を食べておくべきだった。嫌がられても、家族を抱き締めておくべきだった。
すぐ傍までやってきた死に、涙がポロポロと溢れては頬を伝い、口を塞ぐ背後のひとの手を濡らしていく。
次の瞬間、身体がふわりと浮き、ドタドタという足音と共に視界がリビングへと移り変わった。騒がないなら離してやる、と言うひとの声に頷くと、敷きっ放しの薄い布団にそっと降ろされた。
「最初にちゃんと説明しなかった僕にも非はあるが……キミも魔術師なら分かるだろ? 自分で喚び出したサーヴァントくらい」
適当にフローリング張りの床に座り込んだそのひと────どう見ても図書館で出会ったあのひと────は、やれやれと言う風に話し出した。しかし、私はその話の内容がほとんど意味が分からなかった。
私もそれなりにファンタジーものは嗜んできた。某魔法学校の作品だって結構好きな方だ。だから、単語の意味は分かる。分かるが、それは紙の上や画面の向こう側の話であって、間違っても、現実で、自分に向かって、聞かせられる話ではない。そもそも、どこの誰とも分からないひとを部屋に上げている時点でもうありえない。
何も喋らない私に、そのひとは少し待っていてくれたが、痺れを切らしたように膝を叩いて口を開いた。
「分からないなら分からないって言ってくれ!」
「あっはいわからないです」
「何が」
「えっと……全部……」
切れ長の目を丸々と見開き、そのひとは“信じられない”と言うような視線を私に向ける。
「まさか、キミ、魔術師じゃないのか……?」
「私、ただの大学生です……というか、魔法使いなんて実在するわけ……」
いたたまれなくなって床に目を逸らすと、それはそれは大きな笑い声が聞こえてきた。私は笑えるほどの余裕を持ち合わせていない。となると、消去法的に目の前のひとが大爆笑しているのだろう。どうしてかなんて分かるはずもないが。
「この僕が! 長州の英傑ともあろう僕、高杉晋作が! 魔術師ですらない凡人に喚び出されるなんてな!」
「高杉……晋作……?」
「おっと、まさか僕のことすら知らないだなんて言わないよな?」
もちろん知っている。義務教育を通ってきた日本人ならその名を知らない人間はいないだろう。だが、彼のひとは幕末の日本を生きたひとのはずだ。それくらい社会系科目に疎い私でも知っている。
つまり、とっくに死んでいるはずだ。生きているわけが、こうして喋っているわけがないのだ。このひとが本当に高杉晋作そのひとだと言うのなら。
ならば、考えられる線はひとつ。目の前の人物が自分を幕末志士だと思い込んでいる頭のヤバい不法侵入者だということだ。
「キミ、今失礼なこと考えてるだろ」
「……ありえません。信じられるわけがない。だって、高杉晋作って言ったら、あの……幕末のひとでしょう? いま、生きているわけがない」
至極真っ当な、マトモなことを言ったつもりだったが、彼は至極面倒臭そうに溜息を吐いて足を組み直した。
「本当にただの凡人なんだな、キミは。────この僕が一から説明してやるから、よく聞きたまえよ」
そのひと────高杉晋作はそう言って、何も知らない私に“聖杯戦争”という、聞くも恐ろしい催しについて語って聞かせた。
────“聖杯戦争”。それは、七人のマスター……魔術師と、七騎のサーヴァント……英霊による、己が欲望で他者の欲望を蹴落とし、“万能の願望器”である聖杯の使用権を勝ち取ることを目的とした“殺し合い”である。聖杯に選ばれし魔術師は、死後人々に祀り上げられた英雄の霊を自身の使い魔として召喚し、己が夢想を現実へとするため、最後の一組になるまで血を流し続ける────。
「つまるところ、キミは他でもないキミ自身の望みを叶えるために、他のマスターやサーヴァント……キミの望みの邪魔をする悉くを殺し尽くさなければならないってコトだ」
僕は僕で、僕自身の望みを叶えるために、僕の邪魔をする悉くを潰して回らなければならない。と何でもないように話して、そのひとはどうにも胡散臭く見える笑みを浮かべた。
「も、もし、本当にそんなものがこの世に存在するんだとして、私は魔術……なんて使えないどころかたった今知ったくらいですし……そんなことをしてまで叶えたい願いなんて」
「じゃあ、それは一体何なんだ?」
冷ややかにも思える笑みを口に湛えたまま、彼が私の手を指差す。ゆっくり視線を落とすと、私の右手の甲に赤い赤い、何かが刻まれていた。
「キミは何も知らないだろうから、僕が代わりに答えてやるよ。それは令呪だ。キミがマスターである証であり、キミが僕を喚び、その声に僕が応えた証だ」
「れい……じゅ……」
何かの模様、ロゴのようなそれは、擦っても薄れることはない。書かれたのでも、染められたのでもない。それは間違いなく、この手に刻まれたものだった。
これから流される血を表したような痕は、私に望みがあることを証明し、目の前で私を見つめるひととの繋がりを証明するものだとこのひとは言った。
その話を未だに受け入れられない気持ちはある。けれど、突然現れた痕も、目の前のひとのことも、その話を信じなければ説明がつかない。
「巻き込まれたのは気の毒だが、自分の不運を恨みたまえ! なに、心配せずとも戦うのは僕だし、キミのことは死なせないさ。僕もマスターがいなければこの世に留まれないからな。ただキミは、大舟に乗ったつもりで僕に魔力を回しさえすれば良い」
「は、はぁ……」
先程とは打って変わった、そのひとのニコッとした笑みに気の抜けたような声が出る。最初から最後まで、あまりに現実味のない話だったから。心がついてこないのだ。
「僕にとって重要なのは、キミが何者なのかなんてことより、キミがこの先何を為すかってこと。この一点だけだ」
目の前のひとは私を見つめて、人の良さそうな笑みを浮かべているように見える。
けれど、そう見えるだけだ。そう見せているだけで、このひとは私のことなんかを見てはいないのだろう。期待なんて一ミリもしていないのだろう。分かる。私も私なんかに期待はしないし、できないから。
期待は、重い。向けられた期待にどうにか応えようと必死になって藻掻くことも、期待に応えられないことも、それでガッカリさせてしまうことも、とても苦しい。
それならいっそ、初めから期待なんかされない方がよっぽど呼吸が楽だ。
「何はともあれ、僕とキミは……そうだな、当世風に言うならビジネスパートナーみたいなものだ。しばらくの間よろしく頼むよ」
差し出された手と、直視し難い顔を交互に見やり、恐る恐る私も手を差し出した。大きな手は私の手をぎゅっぎゅっと握ると、軽く上下に振りながら不意にピタリと動きを止める。
「そう言えば、キミの名前を聞いていなかったな」
言われてから、名乗るタイミングなんてなかったな、とこれまでの流れを思い返した。
幽霊のような存在のはずなのに、皮膚越しに伝わってくる温もりを不思議に思いながら、彼の問いに答えるべく私は浅く息を吸った。
「……ぁ、その、小鳥遊……初花、です」
数回、吸っては吐いてを繰り返して、ようやく音になった息はちゃんと届いただろうか。聞き返されたらどうしよう。
握られた手を凝視するしかできない私には、目の前のひとがどんな表情を浮かべているかなんて分からなかったけれど、ふ、と息が漏れる音に続いて、思いの外柔らかな声が聞こえた。
「良い名じゃないか」
これは、春のように儚くも苛烈で、小憎らしくも愛おしい彼────高杉晋作と、私の、覚悟と救いと望みを問う物語だ。
2/2ページ