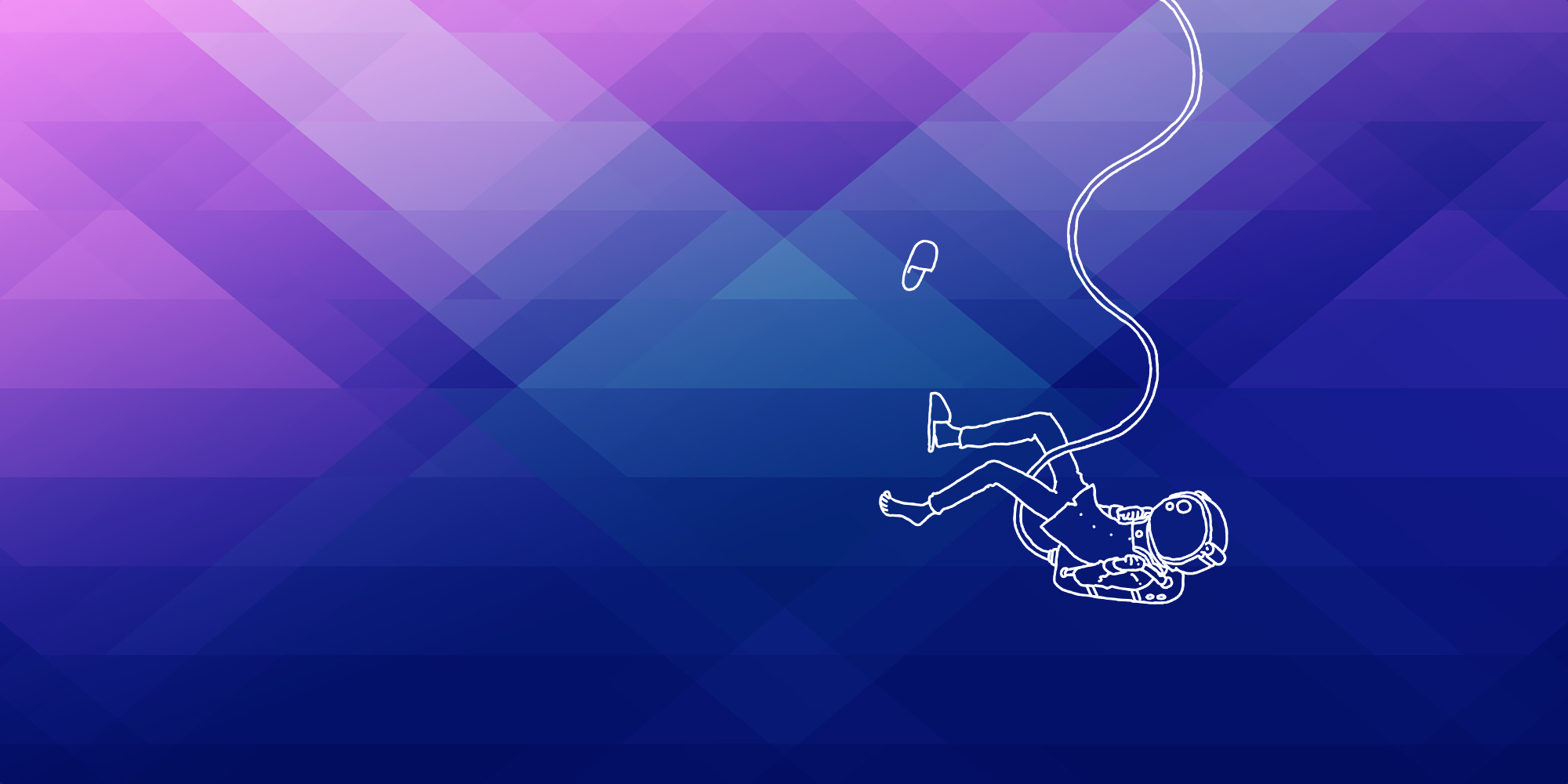凡人の遥かなる夢
夢小説設定
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
口の中に入れたキャンディーが、ガリッと音を立てて砕ける。ほぼ無意識の内に、口の中にある固形物を噛みながら、目を閉じた。
目を閉じ、思い浮かぶのは、ハンターだった両親の最期。2人して、手をつなぎながら横たわる姿は今でも鮮明に覚えている。とても冷え切った身体だとは思えないような、穏やかな顔をしていた。
ーー恨んではいない。
ただ、いったい誰が。なんのために。平凡な我が家を手にかけたのだと不思議なだけだ。
手がかりは、ハンターライセンスのみで入ることのできるデーターベースと、自宅に残されてた両親の携帯履歴だ。だが、それを見るのにも、ハンターライセンスが必要。
「私、ハンターになりたい。母のような父のようなハンターに」
夢を語る子どもが愚者だと、他人は笑うだろう。そんなばかな、叶いっこないって。高みを目指しすぎだと。身の程を知れと言うのだ。
ーー凡人が、無理な話だ。
だなんて、言わせるものか。
口の中のキャンディが粉々に砕けた所で、ゆっくりと目を開けた。そうだ、こんなところで、億劫になってはいけない。
「(なんか神経質になってるな。それもこれも全部あのオジサンのせいだ…)」
他人に擦りつけるなんて、最低なことをしながら、”あのオジサン”を睨みつける。あのオジサンというのは、入り口で話しかけてきた小柄で小太りの男。
彼は、気さくに話しかけてきただけでなく、差し入れと言って缶ジュースを差し出してきたのだが、あまりにもその場で飲むことを進めてくるものだから、流石に怪しいと感じた。だから、「のど乾いてたのでありがたいです、後で飲みますね」と、懐に入れ、素直に受け取る振りをして持ち帰ったが、チッと舌打ちしたのを聞き逃さなかった。
さっそく潰し合いかよとため息が出た。
「オネーサンさ」
「ん、?」
「さっきからガリガリ何食ってんの?」
声がした。
手元にある缶ジュースをおろし、声を辿ると、そこには銀髪の、癖っ毛の男の子が立っていた。
「あーっと、うん、キャンディ。ごめんね、煩わしかった?」
ガリガリ音が聞こえていたのかと思うと、少し恥ずかしくなり、左耳に髪をかけながら答える。すると銀髪の少年は一瞬目をパチクリさせると、「フーン」と言うと、両手ポケットに手を突っ込んだ。そうして「よっと」と言うと、スケボーを持ち直して、私が壁に寄りかかってるのと同じように、隣にやってきて、壁に寄りかかる。
「俺キルア、オネーサンは?」
「シオ」
「シオね。シオさぁ、なんでそのジュース飲まなかったの?」
クリクリのネコ目が、ジッとこちらを見た。その目はまるでさっきあのオジサンに舌打ちされた自分が、彼への不信感を抱かせたことを見抜いてるかのようでもあった。
「うーん…、怪しくて?」
「怪しい?」
「そ。ルーキーに優しい受験者って、ね。なんか毒とか入ってそうでさー」
やになっちゃうね、とキルアに笑いかけると、キルアは喉の奥でクックと笑った。
「そうそう、それただの毒入りジュース」
「あーやっぱりかーー…、って、え?」
右手に持っていた缶ジュースは、いつの間にかなくて。その代わり聞こえたのはプシュッと缶を開ける音だった。唖然として、ゴクゴクと飲み干しているキルアを見る。
「ど、毒入りって…‼︎キルアだめ、今すぐ吐き出して!なんで…!」
毒入りと分かってて飲むなど、自殺行為だ。目の前で”毒入り”と認めた缶ジュースを飲み干したキルアは片手で缶を握り締める。
「ぐっ……!」
「ッ…!!キルア、吐き出して。無理ならツボ押す、」
グシャアと缶が潰れた音と共に、キルアが呻き声をあげた。こんな少年に、毒なんて。まさに毒だ。
背中を丸めて口を抑え、震えているキルアの背中を叩き、吐き出させるため、口に手を入れようと顔を覗き混むーーー。
「っップ、あははは!!」
「!?」
「だ、だめだ、オネーサン慌てすぎ、ブッ」
「え、」
クククッと笑い、平気そうに顔を上げたキルアにきょとんとする。え?だって、毒入り…?ひとしきり笑ったキルアは、はぁーと最後に息を吐き出すと、大きな猫目をニンマリと丸めて再びポケットに手を突っ込む。
「…心配?」
「っ、当たり前じゃない、毒入りって、」
「毒じゃ死なない、って言ったらどうする?」
相変わらずキルアの表情は笑顔で。人の反応を楽しんでいる顔をしていた。こんな、少年までもが。毒に耐性があるなんて、小さい頃から慣らされているということだろうか。
そんな、世界もあるというのか。
「……キルア、手出して」
「ん?何、なんかくれんの?」
「はい、キャンディあげる」
「お!サンキュー」
手のひらにコロリと飴を載せるとキルアは疑うこともなく、ヒョイと受け取り、ポーンと弧を描かせて口の中に放り込んだ。
そんな姿を見て、それが彼の、キルアの日常なのだなと自己完結をし、自分も新しいキャンディを口にする。たとえそれが毒でも、死なない自信がある。
キルアは、自信に満ちているんだ。
そんなことを考えていると、また無意識のうちにガリッと口にあったキャンディが音を立てる。
「そうだ、」
「ん、?」
クイクイっと服を引っ張ってきたキルアに、少し身長を合わせて屈むとキルアは猫のように目を爛々とさせ、楽しそうに口を開いた。
「キャンディすぐ噛む人って、欲求不満らしいぜ?」
その瞬間、キャンディが音を立てて砕け散った。
「ぎゃあぁーーーーッ‼︎‼︎」
凄まじい断末魔が会場に響く。反射的に声のした方へ顔を向け、ゾッとした。そこには、両腕が無い、男の人が、1人。
そして向かい合うもう一人の、男。
「アーラ不思議♡腕が消えちゃった♠︎」
「お、オ、オ レ の ォォォオーーー」
「気をつけようね♦︎人にぶつかったら謝らなくちゃ♣︎」
腕を、消した。
ぶつかって、謝らなかったことで。彼は両腕を失った。
なんだ、あいつは。
ブワリと悪寒が全身を走り、両腕を消した男の背中を見つめる。つぅっと嫌な汗が背中に流れた。
「……何?ビビってんの?」
「、す、少し。ゾッとした」
「……フーン」
「だって。血さえ、出てないなんて」
「!」
切り口が綺麗ということは、それだけ切ることに美学があって、手慣れているということだ。あまりの衝撃的な出来事に、絶句する。
「あっ、いたいた。トンパさんだ」
「え、あ。っげ、」
「じゃあオレジュースもらってくるから。またな、シオ」
「、ん、また、」
また、会えるだろうか。
あんな、危ない、そっちのプロがいる中で。たたたっと後ろを振り返らないで、あのオジサンこと、トンパのもとへ向かっていくキルアの背中を見送る。
キルア、あの光景を見ても動じてなかった。冷や汗すらも。
「これが、ハンター試験の、受験者」
キルアと別れてから数分後がたつと、雰囲気がピリッと閉まった。ジリリリリリリリリリリリリリリリ、とベルの音が、会場に響き渡る。
「ただ今を持って受付け時間を終了いたします。では、これよりハンター試験を開始いたします」
張り詰めた雰囲気が、ビリビリと自分を突き刺した。
「こちらへどうぞ」
そう言って、皆を先導して先を歩いていく、髭面の男性。彼は、ハンター試験の試験官。名をサトツと言うらしい。
「二次試験まで 私に付いてくること。 これが一次試験でございます」
サトツさんは歩いているだけだが、ぐんぐんスピードを上げていき、皆が小走りにまでなったなおも、サトツさんは歩いている。
ドドドドと足音が変わったのを感じ、ハンター試験がついに始まったのだと、顔をあげた。
fin