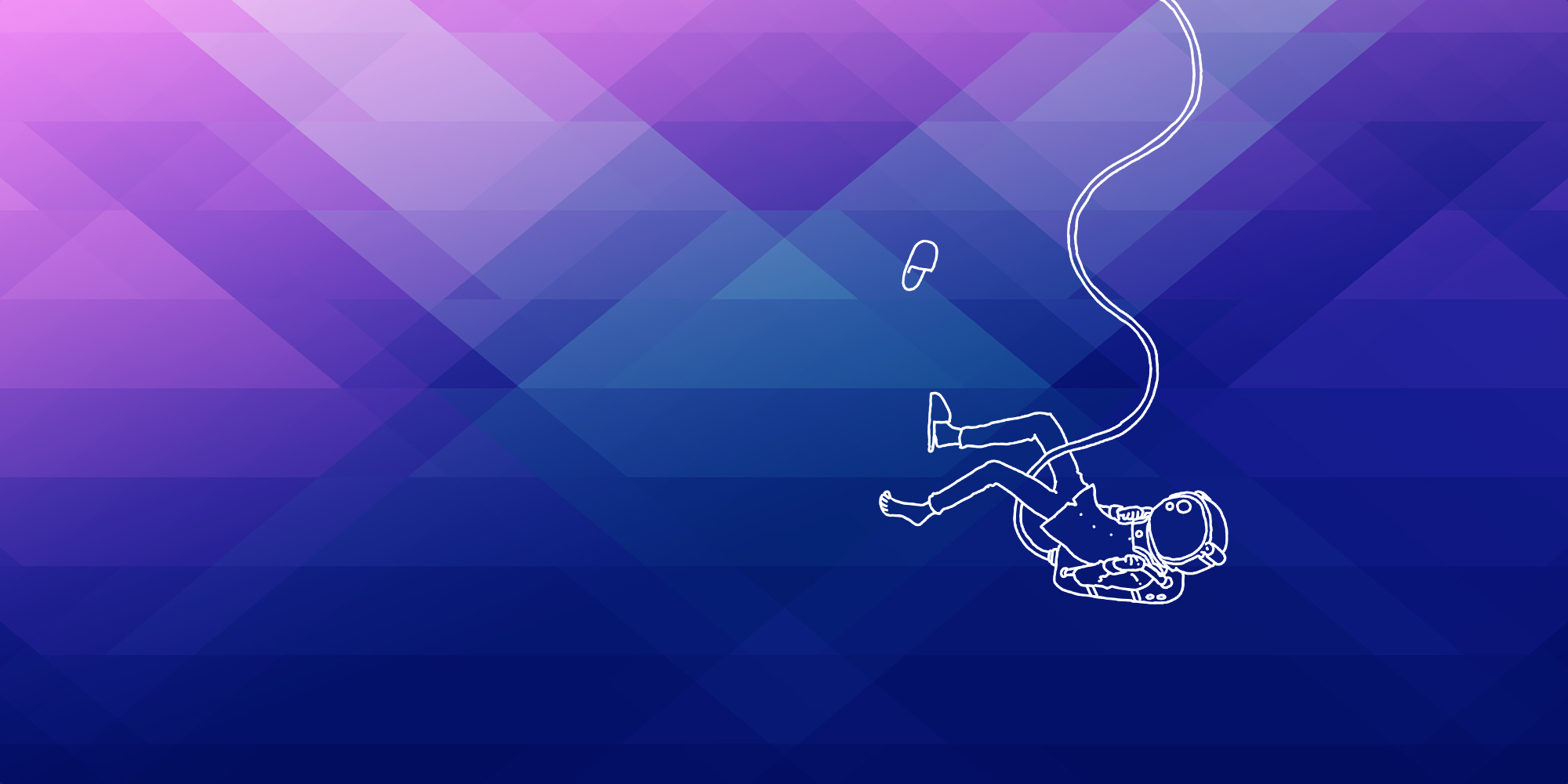凡人の遥かなる夢
夢小説設定
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
1万人に1人・3年に1人と聞いて、何を思い浮かべるだろう。
難病に掛かる確率?それとも、生き残れる確率?
はたまた、宝くじに当たる倍率だろうか。
「ザバン市の、ツバシ町2ー5ー10はっと、あそこの建物だな」
その数字は、応募者がのべ数百万人もいるというハンター試験の倍率である。1万人に1人の確率で会場にたどり着け、3年に1人、初受験者が合格する確率だという。
余りにも桁違いの数値に、幾ら何でも盛りすぎだろうと笑う奴もいるだろう。
「なんだァ?驚きすぎてリアクションもでないか」
『そう、ですね。意外すぎて』
「カッカッカ!見た目に寄らず素直だな」
その1万人に1人に入っている自分が、今でも信じられない。今、私が向かっているのが、ハンター試験会場だと言うのだ。
扉を開けばそこには視界がかすむぐらいの煙がもくもくと篭っていた。でも、決して焦げ臭いにおいが漂っているわけではなく、むしろ香ばしく、食欲をそそる匂いが部屋中に広がっている。
ジュージューと、焼ける音がまた腹の虫を呼び寄せる。
「普通の、定食屋…?」
「そう思うだろ?まぁ見てなってお嬢さん」
ご飯でも食べるのか?と疑問を抱く自分をよそに、ここまで案内してくれた人がニヤリを笑顔を浮かべて、店長らしき男に顔を向ける。
「いらっしぇー!ご注文は?」
「"ステーキ定食"」
人差し指をあげて、そう言うと、店主さんはピクリと耳を動かした。そこで察する、もしかしてこれは、会場に行くための合言葉、もしくは文言ではないか、と。
「………焼き方は?」
「弱火で、じっくり」
先行くナビゲーターさんはにっこりと笑顔を浮かべて、私を店主に見せる。すると、店主さんがじっと見てくるものだから、私も負けじとじっと見つめ返す。それが何かの合図かのように、店主はニッと笑って奥の方を指さした。
「お客さん、奥の部屋に入んな」
その一言で予測が確信へと変わる。きっとこの先に進めば、私の目的地、試験会場であろう。察した自分は、くるりとかかとを返し、ここまで案内してくれた彼・ナビゲーターさんに会釈をする。
『ナビゲーターさん、ありがとう』
「!、いや、いいってことよ。幸運を祈るぜ」
「まぁ無理だろうがな」とグッと立てられた親指に、笑みを浮かべながらここまで案内してくれたナビゲーターさんとお別れをする。
そうして、自分は案内された奥の部屋へと向かった。
通された部屋はとてつもなく広いエレベーターのようだが、机と椅子が用意されており、先ほど注文したステーキが鉄板の上でジュウジュウと音を立てているではないか。
「ではいってらっしゃいませ」
『どうも…、』
唖然としている暇もなく、エレベーターの扉が閉まり、下へとゆっくり下がっていった。
1階からB1へと数字が変わったことから、どんどん下がっているのを確認する。まだ、実感が湧かない。本当に自分は試験会場に向かっているのだろうか。
そうして、部屋の中心にあるステーキに視線を落とした。じぃいいいい、と数十秒間ステーキ定食と睨めっこしてみる。香ばしい匂いに誘われて「食べてもいいよね」とステーキ定食に向けて合掌をした。
『いただきます、』
フォークとナイフを使って一口サイズに切り、口に含んだ。その間でも部屋は下り続ける
(なにこれめっちゃ美味しい)
思えば、ナビゲーターさんが自分を案内してくれることになったのは、たまたま偶然泊まっていたザバン市内のホテルで、暴動が起きたことだった。
それはディナー中のことで。
たまたま、宿泊者のひとりにハンター試験受験者がいて。会場が分からず、バスもずっと来ないといちゃもんつけていて。ストレスの限界に達したのか、そいつが拳銃を乱発。フロントに拳銃を振りかざしながら「ハンター試験会場まで案内しろ」と叫びだしたことが発端だった。その騒動に乗じて、他の宿泊者の中にも会場の場所がわからずイライラしていた輩が加わり、ちょっとしたデモのようになっていた。
ザバン市まで来たことで疲れていたのに、なんたる不幸だ。と思いつつ、ディナーを中断した。しばらくして、また別の輩がレストランにやってきて、発砲。びちゃりとホテルのビュッフェ台に置いてあった、美味しそうな料理の中に入り、崩れていく。逃げる宿泊者とサービス員。追い討ちをかけるように発砲し、従業員に命中した。
そこで違和感を覚えた。
最初の主犯は銃を乱発していたのに、人には当たっていないし、ホテルの従業員は無傷である。施設も対して崩壊していなかったことを思い出す。逆に、後から加わった受験者の方が横暴で、施設内を崩壊させ、従業員を怪我させたあげく、料理まで無駄にしているではないか。
ハンター試験会場がわからずむしゃくしゃしていた主犯が、ここまで繊細で落ち着いた発砲ができるわけがない。
何かが、おかしい。
せっかくのディナーだったのに、と後悔しながら、シルバーフォークを拝借し、主犯の拳銃に向かって投げつけた。その結果、主犯はあっさり拳銃を捨てた。そんな主犯を捕まえ、後から加わった受験者たちに向けて「ハンター会場ならこいつが知っている」と言って主犯の首にフォークを突きつけると、主犯は大爆笑し、「お見事」と一言。
で、その主犯が今回の試験のナビゲーターの1人だったわけだが。
「僅かなヒントを見逃さない観察力・考察力・そしてその行動力、評価に値するよ。え?このホテル?もちろんハンター試験専用営業さ。おかげで宿泊者は全員受験者でな、まさかまともな奴が一人だけなのは意外だったがな」
もちろん、その後から加勢してきたバカな受験者たちは、ホテル側の人間に制裁を食らっていた。施設の修理費・料理の損害賠償・怪我を負わせた慰謝料などを突きつけられており、その金額に白目を向いていたっけ。
そんなことを思い出しながら、最後の一口は白米と一緒に、良く噛み締めてから、ゴクリと飲み込んだ。お肉の肉汁と、ほかほかの白米の相性の良さに思わずほおを抑え、両目をつぶる。
ふーっと息を吐いて、再び合掌。
『ご馳走様でした』
ステーキ定食美味しかったなと思いながら、エレベーターが目的地に到着するのを待った。
──チン
誰もが聞いたことのある音がした。B100と書かれた表示にギョッとしながらも、左右に開いた扉の向こう側を覗き込む。
むわんとした独特な空気感に、人口密度の高さを匂わせる。ジロジロと突き刺さる視線に、嫌な汗が背中を流れる。
『(………入っていいのかな)』
「ごほんっ!」
『うわ!?』
周りばかり見ていて、目の前にいた(いつからいたのか分からない)人を見る。が、これまたびっくり
「お疲れ様です。私はマーメンと申します。これがあなた様のナンバープレートです」
『あ、はい。どうもです』
可愛らしいまん丸の瞳を持つ彼女…いやいや声的に男性じゃ…?いや。もやは性別不明…、というか人であるかさえ危ういかもしれない
「──以上になります」
ナンバープレートを渡し終えたその人は、ナンバープレートについての諸注意的なものを一通り説明してくれた。
「あと、早くエレベーターから降りてください」
『あ、ああ!す、すみません』
はっとしてエレベーターから一歩踏み出して扉の奥へと踏み出した。すると彼(?)はさっさとどこかへ行ってしまった。
ナンバープレートをもらった体制のまま、ぽかんとする私。あの人でさえ、たじたじしてしまう私が嫌になる。第一、なぜあんなにも個性を持っているのか…うらやましいくらいだ。あまってるなら少しほど分けてほしい。
はぁ、とため息をつい。だって、未だに自分の足の震えが止まらないからだ。自暴自棄に陥らないわけがない。1万人に1人だと?笑わせる、今年の受験者はイレギュラーばかりだとでも言うのか。こんなにも、もうすでに集まってきているではないか。
自分のナンバープレートと、同じ人数が。
会場の中でぎょろぎょろと周りを見渡している受験者の面構えから、ここに来るまでの人たちとはあきらかに違うのだと悟る。勢いや名誉、富だけが目的の人の集まりってわけじゃないんだ。
私がここまで来れたのは、きっと自分の運が良かっただけかもしれない。
『(それでも……)』
叶えたい夢のために
ぎゅっと、緊張を隠すために拳を握り一歩前へと踏み出した。改めてもらったナンバープレートに初めて視線を落とす
──"295"。
数百万人の応募から、たったの295人しかたどり着けていないのかと数字だけ見れば感じるかもしれない。だが、それでも、295人もすでに会場にたどり着くことができているなんて、今年の受験者は凄まじいのではないかと、いらぬ詮索までしてしまう自分が嫌になった。
落ち着け、自分。
ここまでこれたんだ、自分の限界まで頑張ろう。と心に決め、前へと足を進めた。
fin
1/8ページ