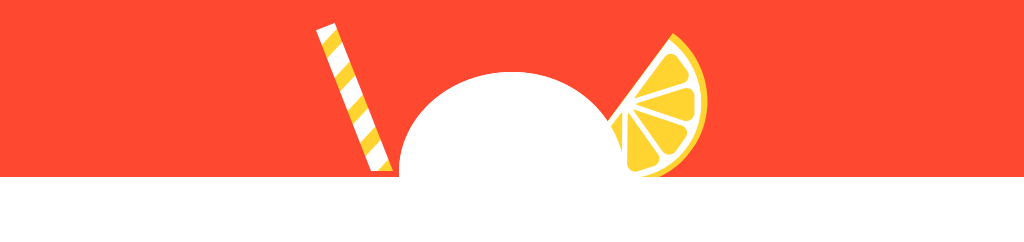。
DB
夢小説設定
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
適当な岩場に腰掛けた。
何をするわけでもなく、ただぼんやりと空を眺めていたら、大好きな気を感じた。
その気は、私のすぐ側に座ると、その大きな手で優しく髪をかきあげられた。
「…お嬢」
「ん?どうしたのブロリー」
「いい匂いが、する」
「…私から?」
「多分。」
「え、どんな匂い?」
「…甘い」
「甘い匂いか…、多分それ、この香水だと思うよ」
「香水…?」
「そう。これはバニラの匂いなんだってさ」
「バニラ、か」
「この間買ったの。通販なんだけどね、地球の製品なんだよ」
「……。」
手招きされて、ブロリーと向かい合う形で膝に腰掛けると、首筋に顔を埋めながら抱き締められた。
首筋に感じる微かな息遣いに、心拍数が急上昇するのが分かる。
「ブロリー、」
「何…」
「呼んでみただけ」
「……。」
「ブロリーが積極的なんて、珍しいよね」
「…お嬢。」
「なに?」
「食っていいか」
「え…」
何を、と問う前に首筋を舐められ、思わず息を飲む。
「…っ、あ」
「甘くない」
「当たり前でしょ…っ」
「でも、いい声出すんだな」
「…ちがっ、あっ」
「何が違うんだ?」
「ひ…っ、くすぐった…ん、からぁ…」
「…カワイイ」
食べるという言葉通り、首筋に噛み付き、軽く歯を立てながら舐められる。
咀嚼するように動く唇がこそばゆくて、身体を捩って悶えてしまう。
「ん、や…」
「…お嬢」
「うあ、…なに?」
「勃った」
「ばっ!」
尻に当たっている熱の正体を知らされ、羞恥心から身体を引こうとすれば、しっかりと腰を抱かれていて身動きがとれない。
「何考えてんの…」
「…声が、」
「声?」
「感じてる時みたいだ」
「そんっ、そんな事ない!」
「…俺には、そう聞こえた」
「今のは…、ちょっとだけ気持ちよかったけど…」
「なら、あってるだろ」
「…知らないっ」
照れ隠しに、ブロリーの腰に腕をまわして抱き付く。
胸板に顔を埋めて、赤くなった頬を隠すように俯く。
「お嬢…っ」
「…なによ」
「息が、くすぐったい」
「え?」
「…お嬢の、息が」
「もしかしてブロリー、胸元弱いの?」
「……。」
「あ、谷間?ブロリー胸大きいもんね」
「…?」
「そこは『胸筋だァ』って突っ込んでくれなきゃ」
「…突っ込んでいいのか」
「待って待ってブロリーの考えてる意味じゃないよ。」
「…そうか」
会話しながらさり気なく身を引こうとすると、やはりしっかり抱えられて動けなかった。
「…ブロリー」
「なぁ、ヤりたい」
「っ、ダメ…、今は駄目」
「…なんでだ」
「今日は…可愛い下着じゃないから…」
「?」
「いつもはちゃんと可愛いの着けてるんだけど、今日は…その…」
「構わない。」
「私は構うの!」
いつも応じる行為をここまで拒絶するのには、下着の可愛らしさ以前の問題があった。
「俺の用は、下着ではなくお嬢だ」
「…そう、だろうけど…」
「嫌なのか?」
「嫌じゃなくて…、だって、この下着見られたら…ブロリーに軽蔑されそうで」
「何、着てるんだ」
「…言っても、軽蔑しない?」
「勿論、」
「嫌いにならない?」
「絶対だ」
「あ…あのね、私今、ブロリーのパンツ…履いてて…」
「…俺のをか?」
「洗濯したんだけど、ブロリーの匂いがしたから…つい、」
「……。」
「や、やっぱりこんな女嫌だよね!ごめんなさい、」
「…見せろ」
「え、」
「見たいんだ、お嬢が、俺のパンツ履いてるのを」
真剣な顔で言われて断れるはずも無く、無意識に頷いていた。
身体を持ち上げられて、器用にボトムスを脱がされ、普段着の下にトランクスという珍妙な格好になり、なんとなく恥ずかしかった。
「…案外、似合うな」
「え…本当?」
「ああ、可愛い」
「…ありがと」
「これで、俺の匂いとお嬢の甘い匂いが混ざったな」
「な…っ、これは香水の匂いだよ?」
「…どうだか、」
「何が言いたいの?」
「お嬢自身が、甘く匂ってるのかもな」
「…そんな事、自分じゃ分かんないよ」
「俺には分かる、お嬢が、甘いのは」
「ん、だって、ブロリーしか知り得ないんだから」
「…よかった」
紅くなった頬を撫でられて、額に口付けられた。
「…ブロリー、」
「?」
「ブロリーも、いい匂いがする」
「…そうなのか」
「私が大好きな匂い。他に喩えられない、ブロリーだけの匂い」
「…お嬢も、だ」
「好いてくれる?」
「もちろん、」
「ならいいや」
「…。」
「たまには、こうやってほのぼのするのも良いよね?」
「…そう、だな」
『甘い匂いと甘い君』
(…そろそろズボン履きたいんですけど)
(まだ、そのままがいい)
(じゃあ…いいよ)
(…可愛い)
END
何をするわけでもなく、ただぼんやりと空を眺めていたら、大好きな気を感じた。
その気は、私のすぐ側に座ると、その大きな手で優しく髪をかきあげられた。
「…お嬢」
「ん?どうしたのブロリー」
「いい匂いが、する」
「…私から?」
「多分。」
「え、どんな匂い?」
「…甘い」
「甘い匂いか…、多分それ、この香水だと思うよ」
「香水…?」
「そう。これはバニラの匂いなんだってさ」
「バニラ、か」
「この間買ったの。通販なんだけどね、地球の製品なんだよ」
「……。」
手招きされて、ブロリーと向かい合う形で膝に腰掛けると、首筋に顔を埋めながら抱き締められた。
首筋に感じる微かな息遣いに、心拍数が急上昇するのが分かる。
「ブロリー、」
「何…」
「呼んでみただけ」
「……。」
「ブロリーが積極的なんて、珍しいよね」
「…お嬢。」
「なに?」
「食っていいか」
「え…」
何を、と問う前に首筋を舐められ、思わず息を飲む。
「…っ、あ」
「甘くない」
「当たり前でしょ…っ」
「でも、いい声出すんだな」
「…ちがっ、あっ」
「何が違うんだ?」
「ひ…っ、くすぐった…ん、からぁ…」
「…カワイイ」
食べるという言葉通り、首筋に噛み付き、軽く歯を立てながら舐められる。
咀嚼するように動く唇がこそばゆくて、身体を捩って悶えてしまう。
「ん、や…」
「…お嬢」
「うあ、…なに?」
「勃った」
「ばっ!」
尻に当たっている熱の正体を知らされ、羞恥心から身体を引こうとすれば、しっかりと腰を抱かれていて身動きがとれない。
「何考えてんの…」
「…声が、」
「声?」
「感じてる時みたいだ」
「そんっ、そんな事ない!」
「…俺には、そう聞こえた」
「今のは…、ちょっとだけ気持ちよかったけど…」
「なら、あってるだろ」
「…知らないっ」
照れ隠しに、ブロリーの腰に腕をまわして抱き付く。
胸板に顔を埋めて、赤くなった頬を隠すように俯く。
「お嬢…っ」
「…なによ」
「息が、くすぐったい」
「え?」
「…お嬢の、息が」
「もしかしてブロリー、胸元弱いの?」
「……。」
「あ、谷間?ブロリー胸大きいもんね」
「…?」
「そこは『胸筋だァ』って突っ込んでくれなきゃ」
「…突っ込んでいいのか」
「待って待ってブロリーの考えてる意味じゃないよ。」
「…そうか」
会話しながらさり気なく身を引こうとすると、やはりしっかり抱えられて動けなかった。
「…ブロリー」
「なぁ、ヤりたい」
「っ、ダメ…、今は駄目」
「…なんでだ」
「今日は…可愛い下着じゃないから…」
「?」
「いつもはちゃんと可愛いの着けてるんだけど、今日は…その…」
「構わない。」
「私は構うの!」
いつも応じる行為をここまで拒絶するのには、下着の可愛らしさ以前の問題があった。
「俺の用は、下着ではなくお嬢だ」
「…そう、だろうけど…」
「嫌なのか?」
「嫌じゃなくて…、だって、この下着見られたら…ブロリーに軽蔑されそうで」
「何、着てるんだ」
「…言っても、軽蔑しない?」
「勿論、」
「嫌いにならない?」
「絶対だ」
「あ…あのね、私今、ブロリーのパンツ…履いてて…」
「…俺のをか?」
「洗濯したんだけど、ブロリーの匂いがしたから…つい、」
「……。」
「や、やっぱりこんな女嫌だよね!ごめんなさい、」
「…見せろ」
「え、」
「見たいんだ、お嬢が、俺のパンツ履いてるのを」
真剣な顔で言われて断れるはずも無く、無意識に頷いていた。
身体を持ち上げられて、器用にボトムスを脱がされ、普段着の下にトランクスという珍妙な格好になり、なんとなく恥ずかしかった。
「…案外、似合うな」
「え…本当?」
「ああ、可愛い」
「…ありがと」
「これで、俺の匂いとお嬢の甘い匂いが混ざったな」
「な…っ、これは香水の匂いだよ?」
「…どうだか、」
「何が言いたいの?」
「お嬢自身が、甘く匂ってるのかもな」
「…そんな事、自分じゃ分かんないよ」
「俺には分かる、お嬢が、甘いのは」
「ん、だって、ブロリーしか知り得ないんだから」
「…よかった」
紅くなった頬を撫でられて、額に口付けられた。
「…ブロリー、」
「?」
「ブロリーも、いい匂いがする」
「…そうなのか」
「私が大好きな匂い。他に喩えられない、ブロリーだけの匂い」
「…お嬢も、だ」
「好いてくれる?」
「もちろん、」
「ならいいや」
「…。」
「たまには、こうやってほのぼのするのも良いよね?」
「…そう、だな」
『甘い匂いと甘い君』
(…そろそろズボン履きたいんですけど)
(まだ、そのままがいい)
(じゃあ…いいよ)
(…可愛い)
END