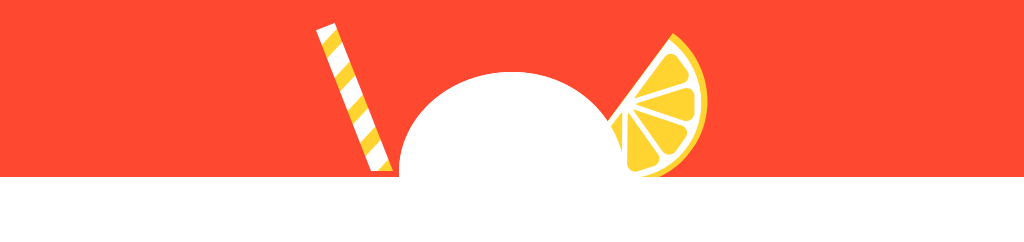SDガンダム
夢小説設定
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
「お嬢姫…今日も美しい」
「ゼロのほうがよっぽど美しいよ」
「フフ、口説き返されると些か気恥しいな」
「だって事実だもの」
ゼロは女性に対しては例外なく紳士だとは知っているんだが、
「でもゼロにとっては誰でも美しいんじゃないの?」
「わたしは美しい者にしか言わないが」
「私にも言うから眉唾なのよ」
「お嬢だって美しい女性じゃないか?」
褒められ慣れていないせいで素直に受け入れられない、美しい、というワード。
決して彼を疑っているわけではないが、恋焦がれている彼から褒められると必要以上に浮かれてしまって正直ニヤける。
「まぁ女ってだけで褒めてもらえるのはおいしい」
「だから実際美しいと言っているだろう」
「うん、まあそこまで言うなら…ありがとう」
「素直でよろしい」
「でも気をつけた方がいいよ?」
「何をだ?」
「そんなに誰もかも褒めてたら、いつか嫉妬の炎で焼かれちゃうかも」
「嫉妬…」
「ゼロの恋人になるような人がさ、他の子に美しいなんて言わないで!って言うかも」
「そんな風に言わせるつもりは無いさ」
「え、どういうこと?」
自信満々と言った顔で微笑まれる。
そういう嫉妬する程度の相手とは付き合わない、ということだろうか?
「わたしと両想いになるような女性には、そんな不安など抱かせない」
「すごい自信だね」
「当たり前だ、伴侶を一番愛していると信じさせられなくて何が騎士だというものさ」
「すっ…素敵ぃ」
「だからお嬢、自信を持つといい」
「え?」
屈まれて目線を合わされ、一輪の薔薇を差し出された。
反射的に受け取るとそのまま手を握られ、半歩ほど距離を詰められる。
「わたしが他の女性に美しいと言う間も、一番美しくて愛しいのは貴女だから」
「えっ、え?何言っ」
「他の誰を褒めようと気にならないほど愛してみせる」
「待って…それまさか」
「わたしからの愛の告白だ」
「なるほど…なるほど?つまりそういう告白で…相手に自信をつけさせると?」
「!?」
まさか告白の実践を見せられるとは、と硬直した。
こんな熱い告白されたら誰でも落ちてしまいそうだし、される人が羨ましい。
驚いた顔をして固まるゼロ。
いつまで手を握っているのだろうか?
「お嬢…まさかわたしの告白を…空振りさせるのか」
「空振りったって、今したのは素振りみたいなものかと」
「違う!これはわたしの本気の告白だ!」
「…誰へ?」
「お嬢へだ!」
「ええ!?」
「何故そんなに驚くんだ…」
「だってまさかそんな、こんな、好かれてる?とか…気付かなかったし」
「お嬢…意外と鈍いんだな」
「だって何がアピールだったのか分からん…」
会った時は花を渡されるがそれも女性になら誰にでもしているし、
帰る時に送られるのは彼が紳士的であるからだと思っていたし、
やたらと目が合うのは私が見すぎなんだと思っていた、と正直に伝えた。
彼は何度か瞬きをすると、ひとつ溜息をこぼした。
「鈍いにも程がある…」
「そう言われましても…言葉にしてくれないとそういうの分かりづらいよ」
「…確かに言葉足らずだったか」
「まぁ、えーと?言われてみれば確かにーって思うことは多々」
多々、そう多々あった。
両想いが非現実すぎて見えてなかっただけで、実際あったというのに驚きを隠せない。
そして逆に気になることがある。
「ゼロは私の好意に気付いてた?」
「えっ」
「えっ?」
「お嬢姫もわたしを…?」
「うん、あの…好きです」
「なんて奇跡だ」
「奇跡って程ではなくない?」
「では運命か?」
「そうだとロマンチックだけども」
運命とか奇跡とかそんなに大袈裟ではなく偶然だとは思うが、愛しの彼から言われると何だか
嬉し恥ずかしいようなむず痒さを覚える。
「そういえば先程嫉妬の話が出ていたが」
「あぁ、うんそうだったね」
「…お嬢はわたしが他の女性に花を贈ると、嫌な気分になるだろうか?」
「いや?そうじゃなきゃゼロじゃないような気分になるかな」
「そうか…良かった」
「さっきあんなに自信満々だったのにどうしたの?」
「…いざ恋仲となると、不慣れなのでつい、な」
「不慣れなの?」
「まぁ、誤魔化しても仕方ないから正直に言うが…こういうのは初めてでな」
「ゼロの初めて貰っちゃったわけね」
「その言い方は何処か意味深だな」
「そう?」
せっかく正直に話してくれたなら、こちらも伝えるべきだろうか
「私もこういうの初めてだよ」
「!…そうか、そうなのだな」
「ゼロ嬉しそうね」
「当たり前だ。どんなお嬢でも愛しているが、初めて愛し合うのがわたしだなんて嬉しいに決まっている」
声色から喜びが滲み出ていて耳が幸せになる。
何だか夢でも見ているような気分になって、本当に夢だったらどうしよう、と自分の頬をつねる。
「どうした?」
「これ夢じゃないよね?」
「夢であってたまるか、やっと結ばれたのだぞ」
「ふふ、そうだね」
ふと目を合わせると、改まった認識のせいで何だか彼がとても眩しくて
なんだろうこの恥ずかしい気分。
今までどんな顔で彼を見つめていたか思い出せない。
「…お嬢?」
「ファッ、あ、はい?」
「そんな真っ赤な顔で見つめられると少々恥ずかしいぞ…」
「えあ…あー、赤くなっちゃいますよこんなの」
「なんて愛らしいんだ」
「今褒められると心臓がもたないです…」
「しかし褒めずにいられると思うか?」
「…いじわる」
「そういう所がだな…自覚がないのか?」
ずい、と距離が詰まり、顎に指を添えられ目を合わせられる。
「ゼロ?」
「…どうか拒まないでくれるか?」
ふわりと彼の香りを感じる。
唇に感じる体温と彼の味は一瞬で離れたが、遅れて顔に集まる熱が感覚を狂わせる。
「…ゼロは薔薇の味がするのね」
「うん?」
気の利いたコメントができない。
口付けられたのは理解できるのにそれを脳が処理できずにいるようで
「えー…と、あの、ごちそうさま?」
「それは此方の台詞…じゃなくてだな」
「ハイ…」
「まだごちそうさましてもらっては困る」
「えっ」
「もっとお嬢を頂きたい」
「ゼロ、うん、あの…私ももっと」
言いかけた所に再び彼の味。
甘いのと幸福感と、徐々に上がる熱に体が浮くような感覚。
錯覚かと思えば本当に浮き上がってきていた。
「ぜ…ゼロ、浮いてる」
「なっ…すまない、舞い上がってしまった」
「物理的にとは思わなかった…」
「色々と抑えられそうになくてな」
「もう…地に足着いたら、続きしてよね」
「…っ」
ゆっくりと着地したものの、大きくバランスが崩れ彼を押し倒してしまった事で余計に昂ってしまって。
この熱は何を燃やすのか、何を溶かすのか。
『こいに点火』
(故意に恋に)
(寝る時間溶けた)
終
2021/08/13
「ゼロのほうがよっぽど美しいよ」
「フフ、口説き返されると些か気恥しいな」
「だって事実だもの」
ゼロは女性に対しては例外なく紳士だとは知っているんだが、
「でもゼロにとっては誰でも美しいんじゃないの?」
「わたしは美しい者にしか言わないが」
「私にも言うから眉唾なのよ」
「お嬢だって美しい女性じゃないか?」
褒められ慣れていないせいで素直に受け入れられない、美しい、というワード。
決して彼を疑っているわけではないが、恋焦がれている彼から褒められると必要以上に浮かれてしまって正直ニヤける。
「まぁ女ってだけで褒めてもらえるのはおいしい」
「だから実際美しいと言っているだろう」
「うん、まあそこまで言うなら…ありがとう」
「素直でよろしい」
「でも気をつけた方がいいよ?」
「何をだ?」
「そんなに誰もかも褒めてたら、いつか嫉妬の炎で焼かれちゃうかも」
「嫉妬…」
「ゼロの恋人になるような人がさ、他の子に美しいなんて言わないで!って言うかも」
「そんな風に言わせるつもりは無いさ」
「え、どういうこと?」
自信満々と言った顔で微笑まれる。
そういう嫉妬する程度の相手とは付き合わない、ということだろうか?
「わたしと両想いになるような女性には、そんな不安など抱かせない」
「すごい自信だね」
「当たり前だ、伴侶を一番愛していると信じさせられなくて何が騎士だというものさ」
「すっ…素敵ぃ」
「だからお嬢、自信を持つといい」
「え?」
屈まれて目線を合わされ、一輪の薔薇を差し出された。
反射的に受け取るとそのまま手を握られ、半歩ほど距離を詰められる。
「わたしが他の女性に美しいと言う間も、一番美しくて愛しいのは貴女だから」
「えっ、え?何言っ」
「他の誰を褒めようと気にならないほど愛してみせる」
「待って…それまさか」
「わたしからの愛の告白だ」
「なるほど…なるほど?つまりそういう告白で…相手に自信をつけさせると?」
「!?」
まさか告白の実践を見せられるとは、と硬直した。
こんな熱い告白されたら誰でも落ちてしまいそうだし、される人が羨ましい。
驚いた顔をして固まるゼロ。
いつまで手を握っているのだろうか?
「お嬢…まさかわたしの告白を…空振りさせるのか」
「空振りったって、今したのは素振りみたいなものかと」
「違う!これはわたしの本気の告白だ!」
「…誰へ?」
「お嬢へだ!」
「ええ!?」
「何故そんなに驚くんだ…」
「だってまさかそんな、こんな、好かれてる?とか…気付かなかったし」
「お嬢…意外と鈍いんだな」
「だって何がアピールだったのか分からん…」
会った時は花を渡されるがそれも女性になら誰にでもしているし、
帰る時に送られるのは彼が紳士的であるからだと思っていたし、
やたらと目が合うのは私が見すぎなんだと思っていた、と正直に伝えた。
彼は何度か瞬きをすると、ひとつ溜息をこぼした。
「鈍いにも程がある…」
「そう言われましても…言葉にしてくれないとそういうの分かりづらいよ」
「…確かに言葉足らずだったか」
「まぁ、えーと?言われてみれば確かにーって思うことは多々」
多々、そう多々あった。
両想いが非現実すぎて見えてなかっただけで、実際あったというのに驚きを隠せない。
そして逆に気になることがある。
「ゼロは私の好意に気付いてた?」
「えっ」
「えっ?」
「お嬢姫もわたしを…?」
「うん、あの…好きです」
「なんて奇跡だ」
「奇跡って程ではなくない?」
「では運命か?」
「そうだとロマンチックだけども」
運命とか奇跡とかそんなに大袈裟ではなく偶然だとは思うが、愛しの彼から言われると何だか
嬉し恥ずかしいようなむず痒さを覚える。
「そういえば先程嫉妬の話が出ていたが」
「あぁ、うんそうだったね」
「…お嬢はわたしが他の女性に花を贈ると、嫌な気分になるだろうか?」
「いや?そうじゃなきゃゼロじゃないような気分になるかな」
「そうか…良かった」
「さっきあんなに自信満々だったのにどうしたの?」
「…いざ恋仲となると、不慣れなのでつい、な」
「不慣れなの?」
「まぁ、誤魔化しても仕方ないから正直に言うが…こういうのは初めてでな」
「ゼロの初めて貰っちゃったわけね」
「その言い方は何処か意味深だな」
「そう?」
せっかく正直に話してくれたなら、こちらも伝えるべきだろうか
「私もこういうの初めてだよ」
「!…そうか、そうなのだな」
「ゼロ嬉しそうね」
「当たり前だ。どんなお嬢でも愛しているが、初めて愛し合うのがわたしだなんて嬉しいに決まっている」
声色から喜びが滲み出ていて耳が幸せになる。
何だか夢でも見ているような気分になって、本当に夢だったらどうしよう、と自分の頬をつねる。
「どうした?」
「これ夢じゃないよね?」
「夢であってたまるか、やっと結ばれたのだぞ」
「ふふ、そうだね」
ふと目を合わせると、改まった認識のせいで何だか彼がとても眩しくて
なんだろうこの恥ずかしい気分。
今までどんな顔で彼を見つめていたか思い出せない。
「…お嬢?」
「ファッ、あ、はい?」
「そんな真っ赤な顔で見つめられると少々恥ずかしいぞ…」
「えあ…あー、赤くなっちゃいますよこんなの」
「なんて愛らしいんだ」
「今褒められると心臓がもたないです…」
「しかし褒めずにいられると思うか?」
「…いじわる」
「そういう所がだな…自覚がないのか?」
ずい、と距離が詰まり、顎に指を添えられ目を合わせられる。
「ゼロ?」
「…どうか拒まないでくれるか?」
ふわりと彼の香りを感じる。
唇に感じる体温と彼の味は一瞬で離れたが、遅れて顔に集まる熱が感覚を狂わせる。
「…ゼロは薔薇の味がするのね」
「うん?」
気の利いたコメントができない。
口付けられたのは理解できるのにそれを脳が処理できずにいるようで
「えー…と、あの、ごちそうさま?」
「それは此方の台詞…じゃなくてだな」
「ハイ…」
「まだごちそうさましてもらっては困る」
「えっ」
「もっとお嬢を頂きたい」
「ゼロ、うん、あの…私ももっと」
言いかけた所に再び彼の味。
甘いのと幸福感と、徐々に上がる熱に体が浮くような感覚。
錯覚かと思えば本当に浮き上がってきていた。
「ぜ…ゼロ、浮いてる」
「なっ…すまない、舞い上がってしまった」
「物理的にとは思わなかった…」
「色々と抑えられそうになくてな」
「もう…地に足着いたら、続きしてよね」
「…っ」
ゆっくりと着地したものの、大きくバランスが崩れ彼を押し倒してしまった事で余計に昂ってしまって。
この熱は何を燃やすのか、何を溶かすのか。
『こいに点火』
(故意に恋に)
(寝る時間溶けた)
終
2021/08/13