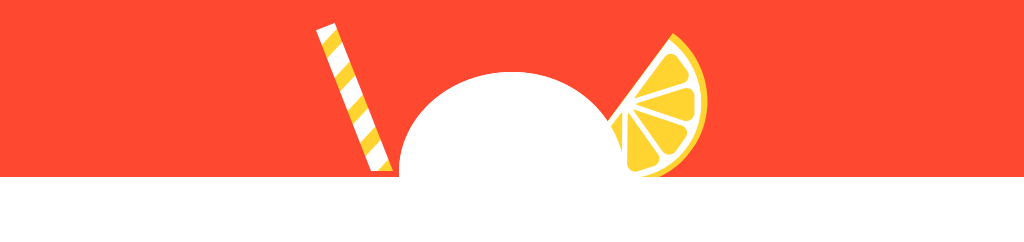SDガンダム
夢小説設定
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
「はぁ?厠に付いて来てくれ?」
「…面目次第もない」
「なんでまた…怖い話でも聞いたの?」
「如何にも。なんでも最近は丑の刻に単独行動は良くないと…」
「っても、なんで私に頼むのさ」
「……俺とて恥じらいくらいある、ゼロやキャプテンにこんな事頼めないだろう」
消灯からそれなりの時間が経っているのに不意に訪ねてきたかと思えばそういう事か、と少し呆れもしたが、大の男といえ怖いものは怖い。と以前から伺っていたのでそういう野暮は言わないことにした。
「でも珍しいね、こんな時間に起きてたなんて」
「どうにも寝付きが悪くてな、そうこうしている内に催してしまったのだ」
「私の部屋を経由するなら真っ直ぐ厠に行けばよかったのに?」
「…言わせてくれるな、お嬢に会いに来たとは思ってくれないのか?」
「あんまり思わない、ほら行こう」
「…。」
季節に関係なく夜の廊下は暗くてひんやりしている。空調ありきだが。
先刻私に会いに来たなんて言われたが、恋仲でもない異性にわざわざ、それも夜中に会いたがるなんて無いだろう。出歩くのも怖いくらいなのに。
爆熱丸との付き合いも決して短くはないが、まさか彼が恋愛感情を向けてきているのならばそれはかなり衝撃と言うか。
決して嫌いじゃないし実際好きだからむしろ恋愛なら歓迎なのだが。
そういう甘酸っぱい感情は肌に合わないわけで
面と向かって告白でもされたならば照れやら混乱でうっかり拒否しかねない。
などと考えているうちに厠に辿り着いた。
「置いて帰らないでくれよ?」
「そんな真似しないよ、多分ね」
「はは、多分か…待つのが嫌なら一緒に入るか」
「何言ってんで」
「いやすまない忘れてくれ」
「…私に後ろから襲われたいなら、ご同行致しましょう?」
「えっ」
「…冗談よ冗談、ちゃんと待ってるよ」
武士を後ろから襲うなんてそんな外道な事はしないが。
性的な意味でなら後ろからの方が何かと都合が良い、なんていうのは当人に言えるはずもなく。
意中の異性を個室に連れ込んで致す、なんてそんな度胸があったらさっさと告白すれば良いんだが。度胸が無いから妄想に留まるばかりである。
…物理的には留まっているが精神的には妄想も膨らむばかりで、もし彼を抱き締めたなら、彼に口付けたなら、なんて考えてから冷静になると毎回恥じらいに頭を抱える。
「…本当に襲ったら何て言うのかな、爆熱丸」
「何だ、呼んだか?」
「えあっ、いやいや何でもないよ、戻ってくるの早くて吃驚した」
「ああ、何となくお嬢の様子が気になったからな」
「…私?」
「もしや疲れているのか?それとも悩みでも有るのか?」
「どうしてそう思ったの…」
「先刻俺を襲うとか言っていたから、てっきり不満があるんだとばっかり」
「もう、そういう襲うじゃなくて…」
廊下に人目は無い。
でもここで試みて嫌われたら大惨事だ。
勝算はある?無くても当たって砕ける?
深く考えるのは苦手。
好奇心と恋心のどちらに傾いても、致すことは大差無いのである。
「…お嬢?」
「……襲う、っていうのは…ね、」
襟を掴み、唇の触れないギリギリの距離まで顔を寄せた。
吐息すら感じる距離に心音も高鳴る、うっかり背けそうになる目線をぐっと堪えて、爆熱丸の瞳を真っ直ぐ見詰めた。
驚嘆したのか何なのか、彼も目線を外さなかった。
目を瞑れば口付けを交わせそうな感覚に、思わず生唾を飲んだ。
「…爆熱、丸…っ」
「お嬢…お主…!」
「!…っごめん、やっぱり今のは…ちょっと魔が差したというか…」
「魔が…?いや、そうではなくお主熱があるんじゃないか?」
「…へ?」
「だって顔が赤いぞ…動悸までしているようだ、流行りの風邪か?」
「ち、違うの…この赤いのはそういうのじゃなくて…」
「…なら、どういう事なんだ」
「これはその…ああ、もう!」
どうにでもなれ、と半ば自棄になって彼の首に腕を回し顔を寄せた。
きゅっと目を瞑り、それでも外さないようにその頬に唇を押し付けた。
一呼吸置いてから唇を離し、首もとに顔を埋めてから自分の顔が恐ろしく熱を持っているのに気が付いた。
「…こういうの、の先までしたくて…って事」
「……。」
「爆熱丸…?」
「っ、あぁ…すまない。いや少し驚いたぞ」
「ごめんごめん…で、どう?これ…この先は、襲う扱いかな」
「あいや、待たれい…今は顔色を見ないでくれ…」
「…照れてるんだ?私なんかにされたのに?」
「お嬢なんか、という言い方は好かんな…、…見抜かれついでに一つ教えてやろう」
「なになに?」
「…こういうのは男からするものだ」
片手でぐっと抱き寄せられ、不意の圧迫感に息を飲んだ。
空いている手で手を握られて思わず身を引くと、目に入るのは紅く染まった頬。
視線が交わるとどちらともなく目を瞑り、唇に感覚が集中する。
ふに、と柔らかく唇が重なると、まだ足りないと言いたげに後頭部を押さえられた。
壁際に追い詰められ、食われるような不器用な口付けに応じつつひとつ息継ぎをした。
その薄く開いた唇を閉じさせまいと言いたげに食い付かれ、歓喜のような感情に息が詰まり、地上で溺れかける…など此の夢のような事態を直視できずにも居た。
「…ばく、ねつ…ま、る」
「は…っお嬢…」
心音が五月蝿すぎて頭がぼうっとする。
吐く息と一緒に彼の名を呼ぶと、熱っぽい声が呼び返してくれた。
口付けひとつでこんなに蕩けそうになるなんて、ああやはり、好きなんだなと自覚する。
舌先から溶けて混ざってしまいそうな熱を飲み下し、ゆっくりと唇が離れた。
と同時に、此処が自室でもなんでもない廊下であることを思い出す。
咄嗟に肩を押して顔と顔の距離を離した。
「あっ…ごめん私、調子乗っちゃった…」
「いや、その…謝ることはないぞ」
「でもこんな…恋人みたいなキスしてくれるとは思わなかったよ…」
「…まあ、好きだからしたんだが…」
「え…あぁ、好きなの?キスするの」
「接吻は好ましい相手としかせんだろう、…皆まで言わんと分からないか?」
「分かんない…事もない、けど、それが本当なら…嬉しいな、私も爆熱丸の事…んっ」
好き、の音を遮るようにもう一度口付けられた刹那、人気の無くなった厠の照明が自動的に落ちた。
ふっと暗くなった廊下で彼が肩を揺らすほど動揺している気配を感じて、思わず笑いを漏らしてしまった。
「わ…笑ってくれるなお嬢…」
「だって爆熱丸、そんなびっくりしなくてもいいのに…ふふ」
「…仕方がないだろう、暗闇の水回りには幽霊の類いが居るとか居ないとか」
「もう、…じゃあ爆熱丸に面白い事教えてあげる」
「面白い事?」
「幽霊ってね、破廉恥な空間には寄り付かないんだって」
「…つまり、どういう事だ?」
此処まで来て引き返すつもりは毛程もない。
想いのまま吐き出して、それでも爆熱丸が好いていてくれるならば、と今までひた隠していた願望を溢し始める。
「つまり……爆熱丸の部屋で、秘め事しちゃう?って事」
「なっ!何を言い出すんだ…女子の口からそんな言葉はでるべきじゃないぞ」
「でもしたらもうお化け出ないかもよ?」
「……いやいや、しかし致すにも互いの気持ちもあるだろう…」
「私達、両想いだと思うけどな…」
「う…だがこういうものには順序があると聞くぞ、初日が初夜だなどと…不純だろう」
「…爆熱丸は、私とはしたくない?」
「ないわけないだろう!…あっ」
「へへ…嬉しい」
「全く…お嬢には敵わんな」
「じゃあ、早速お邪魔しに行っちゃおうかな」
「…しかし今は駄目だ」
「えっ、どうして?」
「もう夜が遅すぎる、いくら何でももう眠るべきだ」
「き…規則正しい…でも確かに、眠いって気付いちゃったから…」
気が弛んだのか、急に眠気に襲われて思わず大きな欠伸がでた。
これから自室に歩いて戻るのも、なんとなく面倒くさく感じてしまう。
思えば此処からなら彼の部屋の方が近い。
この暗がりを送るという口実もある。
「…ねぇ、爆熱丸の部屋で寝たい」
「はっ?いや、それは先程言ったが」
「違うよ寝るだけ、それともそっちしか想像しなかったの?えっち」
「ぐ…寝るだけと言ってもだな、恋仲の男女が同室というのは…」
嫌でも無いのに拒まれる、というのは少し複雑な気分だ。
しかし裏を返せば、好きだからこそ、というのもあり得る訳で。
「…ごめん、これ想像なんだけどさ、もしかして爆熱丸…私に手を出すの我慢できそうにない…とか?」
「!…何故それを…」
「本当ごめん…今気付いちゃった…爆熱丸、ここ」
「っあ…、こ、こら、触るんじゃな…っ」
「すっごい、硬くなってる…よ?」
「う…っ、お嬢と…あんな口付けしたら、こうなるに決まっているだろう…」
「私のせい?…じゃあ、責任とらないと」
装甲の中に手を入れ、熱り立ったそれを緩く握る。
それだけでぴくりと反応する彼自身に内心嬉しくなりつつ、濡れていないと扱いたときに痛いかもしれない、と少し考え込むと、爆熱丸に手首を掴まれ握る手を離されてしまった。
「…駄目だ、お嬢…」
「でも…このままじゃ寝られないでしょ」
「自分でする、構わなくて良いんだ」
「…どうしてそんな、嫌なの?」
「違う!…これでは身体目当ての様ではないか…齢を考えて清く有れとは言わないが…もっと其方を大事にしたいんだ…」
「爆熱丸…そんなに想っててくれたんだ」
「分かってくれたか?」
「うん、嬉しい…私、爆熱丸が好きでよかった」
「お嬢…」
「…でもね爆熱丸、そんな想いを裏切るようで悪いんだけど…」
「えっ…」
「もう、貴方が欲しくて欲しくて仕方ないの…」
彼のそれを触った時点で、そういうスイッチが入ってしまったのだ。
身体はあの熱さを、あの質量を、愛しい彼を受け入れたくて疼いていた。
爆熱丸の手を取り秘部に擦り付けると、下着の張り付くべとっとした感触と、触った瞬間に彼の手が強張るのが分かった。
とんだ変態だと思われたかもしれない、と少し後悔もしたが、そんな雑念を振り払うように彼の目を見据えた。
そこには自分と同じように熱を持った瞳。
漸くタガが外れてくれたらしい、下着越しに触れていた手はその奥へと指を進め、寄せた唇に再び食い付かれる。
薄暗い廊下に熱っぽい吐息が反響する。
唇を離し溢れた唾液を拭うと、腰に手を回され促すように歩み始める。
「…今更後悔してくれるなよ」
「そっちこそ…でも一個だけお願いがあるの」
「?」
「…あんな誘いかたしたけど、実は初めてだから、優しくしてね…」
「……善処する」
当然ながらかなり苦労した。
手付きこそ優しかったが、肝心の彼の質量は初めてに宛がうには優しくなかったのである。
「お嬢、大丈夫か?」
「…すごかった」
「ああ、頑張ったな…偉かったぞ」
「そういう褒め方されると幸せになっちゃうからやめて…」
「そ、そうか…」
「うそうそ止めないで…ちょっと幸せ過ぎて反動が怖いだけ」
「安心しろ、不幸になんて俺がさせない」
「…へへ、好きだよ、爆熱丸」
「俺もだ、ありがとう」
それから夢心地で眠りにつくも、外が既に明るくなり始めていると焦るのは、此処から二時間後位の話である。
『眠気に勝るは』
(寝過ごしたからキャプテンが起こしに来ちゃった!)
(隠す関係でも無いし構わないだろう)
(そうだけどこの事後感恥ずかしい…)
「…面目次第もない」
「なんでまた…怖い話でも聞いたの?」
「如何にも。なんでも最近は丑の刻に単独行動は良くないと…」
「っても、なんで私に頼むのさ」
「……俺とて恥じらいくらいある、ゼロやキャプテンにこんな事頼めないだろう」
消灯からそれなりの時間が経っているのに不意に訪ねてきたかと思えばそういう事か、と少し呆れもしたが、大の男といえ怖いものは怖い。と以前から伺っていたのでそういう野暮は言わないことにした。
「でも珍しいね、こんな時間に起きてたなんて」
「どうにも寝付きが悪くてな、そうこうしている内に催してしまったのだ」
「私の部屋を経由するなら真っ直ぐ厠に行けばよかったのに?」
「…言わせてくれるな、お嬢に会いに来たとは思ってくれないのか?」
「あんまり思わない、ほら行こう」
「…。」
季節に関係なく夜の廊下は暗くてひんやりしている。空調ありきだが。
先刻私に会いに来たなんて言われたが、恋仲でもない異性にわざわざ、それも夜中に会いたがるなんて無いだろう。出歩くのも怖いくらいなのに。
爆熱丸との付き合いも決して短くはないが、まさか彼が恋愛感情を向けてきているのならばそれはかなり衝撃と言うか。
決して嫌いじゃないし実際好きだからむしろ恋愛なら歓迎なのだが。
そういう甘酸っぱい感情は肌に合わないわけで
面と向かって告白でもされたならば照れやら混乱でうっかり拒否しかねない。
などと考えているうちに厠に辿り着いた。
「置いて帰らないでくれよ?」
「そんな真似しないよ、多分ね」
「はは、多分か…待つのが嫌なら一緒に入るか」
「何言ってんで」
「いやすまない忘れてくれ」
「…私に後ろから襲われたいなら、ご同行致しましょう?」
「えっ」
「…冗談よ冗談、ちゃんと待ってるよ」
武士を後ろから襲うなんてそんな外道な事はしないが。
性的な意味でなら後ろからの方が何かと都合が良い、なんていうのは当人に言えるはずもなく。
意中の異性を個室に連れ込んで致す、なんてそんな度胸があったらさっさと告白すれば良いんだが。度胸が無いから妄想に留まるばかりである。
…物理的には留まっているが精神的には妄想も膨らむばかりで、もし彼を抱き締めたなら、彼に口付けたなら、なんて考えてから冷静になると毎回恥じらいに頭を抱える。
「…本当に襲ったら何て言うのかな、爆熱丸」
「何だ、呼んだか?」
「えあっ、いやいや何でもないよ、戻ってくるの早くて吃驚した」
「ああ、何となくお嬢の様子が気になったからな」
「…私?」
「もしや疲れているのか?それとも悩みでも有るのか?」
「どうしてそう思ったの…」
「先刻俺を襲うとか言っていたから、てっきり不満があるんだとばっかり」
「もう、そういう襲うじゃなくて…」
廊下に人目は無い。
でもここで試みて嫌われたら大惨事だ。
勝算はある?無くても当たって砕ける?
深く考えるのは苦手。
好奇心と恋心のどちらに傾いても、致すことは大差無いのである。
「…お嬢?」
「……襲う、っていうのは…ね、」
襟を掴み、唇の触れないギリギリの距離まで顔を寄せた。
吐息すら感じる距離に心音も高鳴る、うっかり背けそうになる目線をぐっと堪えて、爆熱丸の瞳を真っ直ぐ見詰めた。
驚嘆したのか何なのか、彼も目線を外さなかった。
目を瞑れば口付けを交わせそうな感覚に、思わず生唾を飲んだ。
「…爆熱、丸…っ」
「お嬢…お主…!」
「!…っごめん、やっぱり今のは…ちょっと魔が差したというか…」
「魔が…?いや、そうではなくお主熱があるんじゃないか?」
「…へ?」
「だって顔が赤いぞ…動悸までしているようだ、流行りの風邪か?」
「ち、違うの…この赤いのはそういうのじゃなくて…」
「…なら、どういう事なんだ」
「これはその…ああ、もう!」
どうにでもなれ、と半ば自棄になって彼の首に腕を回し顔を寄せた。
きゅっと目を瞑り、それでも外さないようにその頬に唇を押し付けた。
一呼吸置いてから唇を離し、首もとに顔を埋めてから自分の顔が恐ろしく熱を持っているのに気が付いた。
「…こういうの、の先までしたくて…って事」
「……。」
「爆熱丸…?」
「っ、あぁ…すまない。いや少し驚いたぞ」
「ごめんごめん…で、どう?これ…この先は、襲う扱いかな」
「あいや、待たれい…今は顔色を見ないでくれ…」
「…照れてるんだ?私なんかにされたのに?」
「お嬢なんか、という言い方は好かんな…、…見抜かれついでに一つ教えてやろう」
「なになに?」
「…こういうのは男からするものだ」
片手でぐっと抱き寄せられ、不意の圧迫感に息を飲んだ。
空いている手で手を握られて思わず身を引くと、目に入るのは紅く染まった頬。
視線が交わるとどちらともなく目を瞑り、唇に感覚が集中する。
ふに、と柔らかく唇が重なると、まだ足りないと言いたげに後頭部を押さえられた。
壁際に追い詰められ、食われるような不器用な口付けに応じつつひとつ息継ぎをした。
その薄く開いた唇を閉じさせまいと言いたげに食い付かれ、歓喜のような感情に息が詰まり、地上で溺れかける…など此の夢のような事態を直視できずにも居た。
「…ばく、ねつ…ま、る」
「は…っお嬢…」
心音が五月蝿すぎて頭がぼうっとする。
吐く息と一緒に彼の名を呼ぶと、熱っぽい声が呼び返してくれた。
口付けひとつでこんなに蕩けそうになるなんて、ああやはり、好きなんだなと自覚する。
舌先から溶けて混ざってしまいそうな熱を飲み下し、ゆっくりと唇が離れた。
と同時に、此処が自室でもなんでもない廊下であることを思い出す。
咄嗟に肩を押して顔と顔の距離を離した。
「あっ…ごめん私、調子乗っちゃった…」
「いや、その…謝ることはないぞ」
「でもこんな…恋人みたいなキスしてくれるとは思わなかったよ…」
「…まあ、好きだからしたんだが…」
「え…あぁ、好きなの?キスするの」
「接吻は好ましい相手としかせんだろう、…皆まで言わんと分からないか?」
「分かんない…事もない、けど、それが本当なら…嬉しいな、私も爆熱丸の事…んっ」
好き、の音を遮るようにもう一度口付けられた刹那、人気の無くなった厠の照明が自動的に落ちた。
ふっと暗くなった廊下で彼が肩を揺らすほど動揺している気配を感じて、思わず笑いを漏らしてしまった。
「わ…笑ってくれるなお嬢…」
「だって爆熱丸、そんなびっくりしなくてもいいのに…ふふ」
「…仕方がないだろう、暗闇の水回りには幽霊の類いが居るとか居ないとか」
「もう、…じゃあ爆熱丸に面白い事教えてあげる」
「面白い事?」
「幽霊ってね、破廉恥な空間には寄り付かないんだって」
「…つまり、どういう事だ?」
此処まで来て引き返すつもりは毛程もない。
想いのまま吐き出して、それでも爆熱丸が好いていてくれるならば、と今までひた隠していた願望を溢し始める。
「つまり……爆熱丸の部屋で、秘め事しちゃう?って事」
「なっ!何を言い出すんだ…女子の口からそんな言葉はでるべきじゃないぞ」
「でもしたらもうお化け出ないかもよ?」
「……いやいや、しかし致すにも互いの気持ちもあるだろう…」
「私達、両想いだと思うけどな…」
「う…だがこういうものには順序があると聞くぞ、初日が初夜だなどと…不純だろう」
「…爆熱丸は、私とはしたくない?」
「ないわけないだろう!…あっ」
「へへ…嬉しい」
「全く…お嬢には敵わんな」
「じゃあ、早速お邪魔しに行っちゃおうかな」
「…しかし今は駄目だ」
「えっ、どうして?」
「もう夜が遅すぎる、いくら何でももう眠るべきだ」
「き…規則正しい…でも確かに、眠いって気付いちゃったから…」
気が弛んだのか、急に眠気に襲われて思わず大きな欠伸がでた。
これから自室に歩いて戻るのも、なんとなく面倒くさく感じてしまう。
思えば此処からなら彼の部屋の方が近い。
この暗がりを送るという口実もある。
「…ねぇ、爆熱丸の部屋で寝たい」
「はっ?いや、それは先程言ったが」
「違うよ寝るだけ、それともそっちしか想像しなかったの?えっち」
「ぐ…寝るだけと言ってもだな、恋仲の男女が同室というのは…」
嫌でも無いのに拒まれる、というのは少し複雑な気分だ。
しかし裏を返せば、好きだからこそ、というのもあり得る訳で。
「…ごめん、これ想像なんだけどさ、もしかして爆熱丸…私に手を出すの我慢できそうにない…とか?」
「!…何故それを…」
「本当ごめん…今気付いちゃった…爆熱丸、ここ」
「っあ…、こ、こら、触るんじゃな…っ」
「すっごい、硬くなってる…よ?」
「う…っ、お嬢と…あんな口付けしたら、こうなるに決まっているだろう…」
「私のせい?…じゃあ、責任とらないと」
装甲の中に手を入れ、熱り立ったそれを緩く握る。
それだけでぴくりと反応する彼自身に内心嬉しくなりつつ、濡れていないと扱いたときに痛いかもしれない、と少し考え込むと、爆熱丸に手首を掴まれ握る手を離されてしまった。
「…駄目だ、お嬢…」
「でも…このままじゃ寝られないでしょ」
「自分でする、構わなくて良いんだ」
「…どうしてそんな、嫌なの?」
「違う!…これでは身体目当ての様ではないか…齢を考えて清く有れとは言わないが…もっと其方を大事にしたいんだ…」
「爆熱丸…そんなに想っててくれたんだ」
「分かってくれたか?」
「うん、嬉しい…私、爆熱丸が好きでよかった」
「お嬢…」
「…でもね爆熱丸、そんな想いを裏切るようで悪いんだけど…」
「えっ…」
「もう、貴方が欲しくて欲しくて仕方ないの…」
彼のそれを触った時点で、そういうスイッチが入ってしまったのだ。
身体はあの熱さを、あの質量を、愛しい彼を受け入れたくて疼いていた。
爆熱丸の手を取り秘部に擦り付けると、下着の張り付くべとっとした感触と、触った瞬間に彼の手が強張るのが分かった。
とんだ変態だと思われたかもしれない、と少し後悔もしたが、そんな雑念を振り払うように彼の目を見据えた。
そこには自分と同じように熱を持った瞳。
漸くタガが外れてくれたらしい、下着越しに触れていた手はその奥へと指を進め、寄せた唇に再び食い付かれる。
薄暗い廊下に熱っぽい吐息が反響する。
唇を離し溢れた唾液を拭うと、腰に手を回され促すように歩み始める。
「…今更後悔してくれるなよ」
「そっちこそ…でも一個だけお願いがあるの」
「?」
「…あんな誘いかたしたけど、実は初めてだから、優しくしてね…」
「……善処する」
当然ながらかなり苦労した。
手付きこそ優しかったが、肝心の彼の質量は初めてに宛がうには優しくなかったのである。
「お嬢、大丈夫か?」
「…すごかった」
「ああ、頑張ったな…偉かったぞ」
「そういう褒め方されると幸せになっちゃうからやめて…」
「そ、そうか…」
「うそうそ止めないで…ちょっと幸せ過ぎて反動が怖いだけ」
「安心しろ、不幸になんて俺がさせない」
「…へへ、好きだよ、爆熱丸」
「俺もだ、ありがとう」
それから夢心地で眠りにつくも、外が既に明るくなり始めていると焦るのは、此処から二時間後位の話である。
『眠気に勝るは』
(寝過ごしたからキャプテンが起こしに来ちゃった!)
(隠す関係でも無いし構わないだろう)
(そうだけどこの事後感恥ずかしい…)