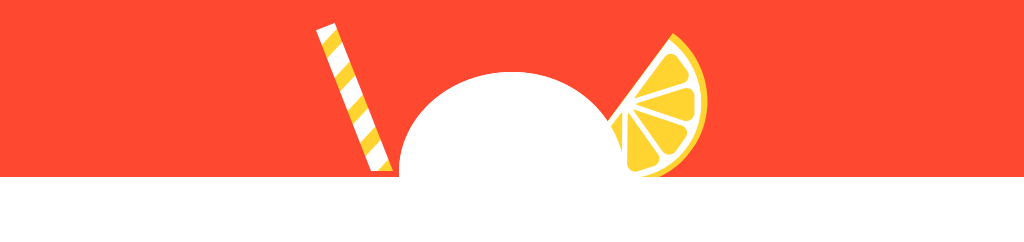SDガンダム
夢小説設定
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
ポケットティッシュから金銀財宝まで、運び屋リガズィにお任せ!なんてCMを時々見る。
大丈夫、大丈夫がキャッチコピーなのか、毎回繰り返される音が耳に焼き付く。
なんていい声、素敵な声。
恋すると世の中が鮮やかになるとはよく言ったものだ。
「ごめんくださーい」
「どなたー?」
この、どなた?の返事も好きだ。
「宅配お願いしたいんですが」
「はいはい、宛先書いてね」
「貴方のハートに私の気持ちを届けてほしいんです…」
「ん、大丈夫?お嬢さん熱でもあるの?」
「あぁ…その、大丈夫が聞きたくて…」
「なるほど、病気だね」
「恋煩いです!」
「あらまぁ」
「…いけませんか?」
「つまり俺と付き合いたいの?」
「はい!」
ふむ、と腕を組んで考えてくれている。
仕事中だろうに風船ガムを食べているせいで口元がもぐもぐしているのもたまらなく好きだ。
「俺は君のことよく知らないよ?」
「じゃあせめて結婚を前提にお友達から…」
「せっかちな性格ってだけ分かった」
「だってそのくらい好きなんです…」
「そこまで熱を込めてお願いされるとなぁ」
「本気なんです、お願いします!」
「じゃあこうしよう」
「?」
オレンジ色のツナギを手渡された。
状況は読めないがいい香りがする。
「それ着て、今日1日俺のお手伝いして。それで相性が良さそうだったら付き合ってみよう」
「本当ですか!」
「言っておくけどこう見えて重労働だからね?」
「頑張ります、期待しててください!」
この時は適当にあしらって、疲れさせて帰らせようと思っていた。
彼女がどこまで本気なのか見てみよう、という好奇心もあっての事だ。
とはいえ暇な職場だ。
今日の依頼も1件、手伝いなんて正直不要だがまぁいいか。
「今日は彼女連れて配達か?」なんて茶化されて、それで終わり。
茶化された彼女はというと、「彼女じゃないです」なんて真面目な顔してて
「もっと騒いじゃうと思った」
「私がですか?」
「君以外に誰が騒ぐの」
「すいません…」
「…なんか借りてきた猫みたいになってるけど、どした?」
「だってここで下手こいたら失恋するんですよ…今だけでも夢見てたっていいじゃないですか」
「なるほどね」
「さて、次は何をすればいいですか?」
「おわり」
「へ?」
「今日はこれでおわり、もう帰るよ」
「はっや…」
帰りの車内で他愛ない会話をする。
「そういえば、どうして俺に惚れてるの?」
「それはですね、…声がとても好みだったんです」
「声?会話したことあったっけ」
「あのCMで…」
「CMったって俺、大丈夫大丈夫しか喋ってないけど」
「その!大丈夫、に惚れたんです」
「マニアックだなぁ」
「…だめですか?」
「だめではないよ、ちょっと引いたけど」
「うう…」
こんな風に一喜一憂してくれるのは、本当に惚れられてる証拠だろうか?
正直悪い気はしないが、だからって恋仲になるほどの好意があるわけでもない。
こちらの好意もないまま付き合うのはそれはかなり失礼だと思う、下手したらキュベレイにシバかれる。
「でも好きなんです」
「うーん…俺ってこんなに押しに弱いタイプだったかな」
「根負けしそうですか?」
「うん」
「なんちゃっ、て…って言うとこ…ですよ」
「だってなんかどんどん可愛く見えるからさぁ」
「かわっ…」
「うん、付き合おう」
「えっ!」
「キミが飽きるのが先か、俺が落ちるのが先か、結果が出るまで付き合ってあげる」
「そういう付き合うですか…」
もう半分以上落ちてるというのは伏せる。
しかしこんな安い挑発で彼女の気が俺から離れるのは些か寂しい気もする。
「どうする?」
「どうするも何も、最初にお願いしたように私の気持ちを貴方のハートに届けてほしいんです」
「つまり?」
「リガズィさんに私の想いを届けるまで依頼し続けますよ」
「…そういうとこが可愛いんだよなぁ」
落ちてると明かさずに駆け引きするのも良いかもしれない、彼女の可愛いところがいくつも見られそうだ。
「そんなに可愛いですか?」
「俺的にはね」
「…やっぱり可愛い子が好きですか?」
「どうかな、どうだとうれしい?」
「可愛くない私も好いてほしいです」
「…ずるいなぁ、そんな言い方」
話しているうちに運び屋の事務所に帰ってきた。
貸していた作業着を回収して、流れで彼女を家まで送ることになった。
送り届けて、帰る寸前に呼び止められた。
「リガズィさん、またお手伝いしに行ってもいいですか?」
「うん、大丈夫 大丈夫」
「今日とっても楽しかったです」
「それは何よりだね」
「…もうお別れで寂しいです…まだ帰りたくないなぁ」
「……俺もだよ」
「え」
彼女を抱き寄せて口付けた。
半ば無意識だったが、なんだかとても愛おしい気分になって、やってしまった。
自分でもやってから驚いたが、彼女はそれ以上に驚き過ぎているようで 真っ赤になって逃げていった。
フーセンガムよりも甘い彼女の唇の残り香に思わず舌舐めずりした。
「あー…忘れてた、次に会ったら名前聞かなきゃ」
心音が早すぎて痛いほどだ。
どうして口付けられたのか理解できなくて逃げてしまった、と反省した。
彼の唇があまりにも熱くて甘くて、どうにも顔の熱が冷めない。
フーセンガムの味と、唇に残った熱さが嬉しくて恥ずかしくて仕方ない。
「もう顔見れる気がしない…」
次回はいつ会いに行けるだろうか、今日は眠れるだろうか、恋とはこんなにも鮮やかで手に負えないな、と再認識した。
『フーセンガムは甘すぎる』
(叶った恋ぐらい甘い)
大丈夫、大丈夫がキャッチコピーなのか、毎回繰り返される音が耳に焼き付く。
なんていい声、素敵な声。
恋すると世の中が鮮やかになるとはよく言ったものだ。
「ごめんくださーい」
「どなたー?」
この、どなた?の返事も好きだ。
「宅配お願いしたいんですが」
「はいはい、宛先書いてね」
「貴方のハートに私の気持ちを届けてほしいんです…」
「ん、大丈夫?お嬢さん熱でもあるの?」
「あぁ…その、大丈夫が聞きたくて…」
「なるほど、病気だね」
「恋煩いです!」
「あらまぁ」
「…いけませんか?」
「つまり俺と付き合いたいの?」
「はい!」
ふむ、と腕を組んで考えてくれている。
仕事中だろうに風船ガムを食べているせいで口元がもぐもぐしているのもたまらなく好きだ。
「俺は君のことよく知らないよ?」
「じゃあせめて結婚を前提にお友達から…」
「せっかちな性格ってだけ分かった」
「だってそのくらい好きなんです…」
「そこまで熱を込めてお願いされるとなぁ」
「本気なんです、お願いします!」
「じゃあこうしよう」
「?」
オレンジ色のツナギを手渡された。
状況は読めないがいい香りがする。
「それ着て、今日1日俺のお手伝いして。それで相性が良さそうだったら付き合ってみよう」
「本当ですか!」
「言っておくけどこう見えて重労働だからね?」
「頑張ります、期待しててください!」
この時は適当にあしらって、疲れさせて帰らせようと思っていた。
彼女がどこまで本気なのか見てみよう、という好奇心もあっての事だ。
とはいえ暇な職場だ。
今日の依頼も1件、手伝いなんて正直不要だがまぁいいか。
「今日は彼女連れて配達か?」なんて茶化されて、それで終わり。
茶化された彼女はというと、「彼女じゃないです」なんて真面目な顔してて
「もっと騒いじゃうと思った」
「私がですか?」
「君以外に誰が騒ぐの」
「すいません…」
「…なんか借りてきた猫みたいになってるけど、どした?」
「だってここで下手こいたら失恋するんですよ…今だけでも夢見てたっていいじゃないですか」
「なるほどね」
「さて、次は何をすればいいですか?」
「おわり」
「へ?」
「今日はこれでおわり、もう帰るよ」
「はっや…」
帰りの車内で他愛ない会話をする。
「そういえば、どうして俺に惚れてるの?」
「それはですね、…声がとても好みだったんです」
「声?会話したことあったっけ」
「あのCMで…」
「CMったって俺、大丈夫大丈夫しか喋ってないけど」
「その!大丈夫、に惚れたんです」
「マニアックだなぁ」
「…だめですか?」
「だめではないよ、ちょっと引いたけど」
「うう…」
こんな風に一喜一憂してくれるのは、本当に惚れられてる証拠だろうか?
正直悪い気はしないが、だからって恋仲になるほどの好意があるわけでもない。
こちらの好意もないまま付き合うのはそれはかなり失礼だと思う、下手したらキュベレイにシバかれる。
「でも好きなんです」
「うーん…俺ってこんなに押しに弱いタイプだったかな」
「根負けしそうですか?」
「うん」
「なんちゃっ、て…って言うとこ…ですよ」
「だってなんかどんどん可愛く見えるからさぁ」
「かわっ…」
「うん、付き合おう」
「えっ!」
「キミが飽きるのが先か、俺が落ちるのが先か、結果が出るまで付き合ってあげる」
「そういう付き合うですか…」
もう半分以上落ちてるというのは伏せる。
しかしこんな安い挑発で彼女の気が俺から離れるのは些か寂しい気もする。
「どうする?」
「どうするも何も、最初にお願いしたように私の気持ちを貴方のハートに届けてほしいんです」
「つまり?」
「リガズィさんに私の想いを届けるまで依頼し続けますよ」
「…そういうとこが可愛いんだよなぁ」
落ちてると明かさずに駆け引きするのも良いかもしれない、彼女の可愛いところがいくつも見られそうだ。
「そんなに可愛いですか?」
「俺的にはね」
「…やっぱり可愛い子が好きですか?」
「どうかな、どうだとうれしい?」
「可愛くない私も好いてほしいです」
「…ずるいなぁ、そんな言い方」
話しているうちに運び屋の事務所に帰ってきた。
貸していた作業着を回収して、流れで彼女を家まで送ることになった。
送り届けて、帰る寸前に呼び止められた。
「リガズィさん、またお手伝いしに行ってもいいですか?」
「うん、大丈夫 大丈夫」
「今日とっても楽しかったです」
「それは何よりだね」
「…もうお別れで寂しいです…まだ帰りたくないなぁ」
「……俺もだよ」
「え」
彼女を抱き寄せて口付けた。
半ば無意識だったが、なんだかとても愛おしい気分になって、やってしまった。
自分でもやってから驚いたが、彼女はそれ以上に驚き過ぎているようで 真っ赤になって逃げていった。
フーセンガムよりも甘い彼女の唇の残り香に思わず舌舐めずりした。
「あー…忘れてた、次に会ったら名前聞かなきゃ」
心音が早すぎて痛いほどだ。
どうして口付けられたのか理解できなくて逃げてしまった、と反省した。
彼の唇があまりにも熱くて甘くて、どうにも顔の熱が冷めない。
フーセンガムの味と、唇に残った熱さが嬉しくて恥ずかしくて仕方ない。
「もう顔見れる気がしない…」
次回はいつ会いに行けるだろうか、今日は眠れるだろうか、恋とはこんなにも鮮やかで手に負えないな、と再認識した。
『フーセンガムは甘すぎる』
(叶った恋ぐらい甘い)