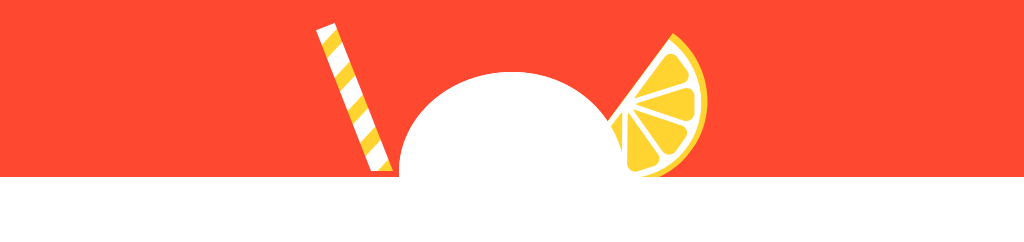ポップン
夢小説設定
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
色々訳あって彼の家にお邪魔する事になった。
これは所謂、お家デートってやつなんだろうか。
二人きり、密室。
そういう雰囲気になる可能性も勿論あるとは思うが、心の準備っていうものが全くできていない。
ほぼ初対面みたいな仲で(こちらの片想い期間は除く)部屋に招かれるって、どうなんだ。
「どうしたお嬢、上がらないのか?」
「いっ、いえ…お邪魔します…」
「散らかってて悪いな」
「お構いなく…急に来てしまったんで」
「まあ適当に座っててくれ」
緊張しか感じなくて喉がカラカラに渇く。
もっとこう、気の利いた事は言えないものかと我ながら思う。
適当にと言われても敷きっぱなしらしい布団か、机の前に一枚だけある座布団しかないが。
迷わず座布団に座った。
「…しまった、茶菓子とか買ってないぞ」
「あのっ、本当に大丈夫ですよ?」
「しかし…その、彼女を招き入れといてこの扱いじゃあんまりだろう?」
「…今じゃ何出されても喉通らないですよ…」
「気分でも悪いのか!?」
「違くて…えっと、これ言ったら引かれそうだなぁ…」
「今更引かないぞ、どんと来い」
「…いいいいさんの匂いで、胸いっぱいなんですよ、もうキャパオーバー寸前です」
「匂い!?臭かったか!?」
「じゃなくて……だ、抱き締められたら、こんな匂いかな、みたいな?あの、堪らないです正直…」
「なんかヘンタイっぽいぞお嬢…」
「ごめんなさいごめんなさい、口が勝手に」
おどけていないと恥ずかしさで身が持たない。
そんな努力も虚しく、不意に目の前に座られ、目線を合わせられた。
「口が勝手に、なぁ?」
「なん…」
「じゃあ俺も、…口が勝手に」
片手で顎を掴まれ、空いている手でマスクをずらすと、ぐっと顔が迫ってくる。
あと3センチ、という所で思わず目を瞑ると、気配はふっと遠退いた。
「なんて…な、ちょっとまだ早かったすまん」
「やっ…やってて恥ずかしくなって逃げないでください!…期待しちゃったじゃないですか」
「!…お嬢ッ、あんまり煽られると我慢できないんだが!?」
「我慢してほしく無いんですが!」
「押し倒すぞこらァァ!?」
「ば…バッチ恋ですよ!」
「言ったな…ッ!」
がっと肩を掴まれ、不意の浮遊感に襲われるとそのまま布団に運ばれたらしい。
仰向けに寝転がされ、顔の横に手を置いて這い被さるように顔を覗き込まれた。
俗に言う床ドンというやつだろうか。
「…お嬢」
「っ…いいいい、さん」
「キスするぞ、本当にいいのか…?」
「きっ、聞かないでください…」
「嫌なら嫌と…」
「嫌なわけないですよ、…ただかなり、恥ずかしくなってきました」
「同感だ。…でも、したいぞ」
「して、ください……好きですから、いいいいさんの事」
「お嬢…俺も、その…」
「…いいいいさん顔が真っ赤じゃないですかやだー…私いま緊張で気絶しちゃいそうですよ…」
「い…やだか?俺も頭が煮えそうなんだが…」
「急かす気はないんですが現状いっぱいいっぱいなんです…嫌よ嫌よも好きの内、照れ隠しですから気にせずどうぞ…」
「そういう物か…しかし目が、そうだ目を瞑ってくれ」
「わっ、わかりました…」
緊張すると口数が増えるタイプである。
言われた通りに目を瞑ると、今度こそ距離が縮まって来る。
ちゅ、と柔らかい感触がした。しかしそれを感じたのは一瞬であった。
「…っ、は…お嬢…」
「ん…」
一度じゃ足りない、と言うように口付けが続く。
角度を変えながら徐々に交わる時間が長くなる。
彼の掌が頬を撫でながら後頭部へ周る。そのまま掻き抱くように指先に力が入ってくるのを感じた。
無意識に彼の首に腕を回し、その肩にしがみつく様に抱き付いた。
息継ぎをする度に吐息と一緒に甘い声が漏れてしまう。
唇が離れると甘えたような声で名前を呼ばれて背筋がぞくぞくと痺れる。
「…お嬢…、お嬢……好きだ」
「ん…っん、や、…は…ずかし…」
「なぁ…もっと、もっとしたいんだが…」
「だから…っ聞かないでくださいって…」
「じゃあ良いんだな?…ん」
「ぁ、…んっ、む」
半開いていた唇に舌が割って入ってくる。
乾いた喉に生暖かい唾液が染み入る気がする。
舌先で探るように口腔内を撫でられ、応えようとその舌に自分の舌先を絡める。
唾液の混ざった味、耳から頭に直に響くような水音、先刻から鼻腔いっぱいに感じる彼の匂い。
触れた箇所からどんどん熱くなるような感覚に、処理落ち寸前と言っても過言ではない。
崩れ落ちないようにしがみつく手に力を込めようにも、頭の奥が痺れて上手くいく筈もなく。
口端から涎を溢しつつ、布団に倒れこむように顔を離した。
「…ふっ、は……い、いいさ…んっ」
「なん…だっ、大丈夫か!?」
「は…っはぁ…っ、まあ…」
「すまない加減が…お嬢!死ぬな!」
「しにませんが…あの、ちょっと…あはは、こ…」
「こ…?」
「こんなキス…初めてで、…イっちゃうかと、思いました」
「イっ…!?」
「いいいいさんの味も、好かったです…」
「あ…味ッ!?」
「…流石に、レモンの味はしないんですね」
「それは…どういう意味だ」
「少女漫画とかでよく言いません?ファーストキスはレモン味…みたいな」
「…そうだな、お嬢はお嬢の味がする。レモンじゃあない」
「…なんか味とか言われると恥ずかしいですね」
「お嬢が先に言ったんだぞ…」
「そうですけども…っていうかいいいいさん髪ふわっふわですね」
「ひっ、ん、こそばいぞお嬢」
柔らかく癖のある赤毛を堪能しつつ、顔にかかる前髪を撫でると、彼の熱っぽい瞳や白い肌に思わず生唾を飲みかける。
「あと肌が真っ白…今はちょっと赤いですけど」
「そんなまじまじと見るなァ!」
「そんな顔で言われても…」
「顔!?生まれつきだぞォ!?」
「や、あの…目付きって言えば伝わります?」
「悪いって言いたいのか…?」
「違ッ、目付きも大好きです!…じゃなくて、あの、貴方の目が、欲情の色をですね…」
「…大好き…だとォ」
「あっそこ拾っちゃいます?」
「拾っちゃまずいのか?」
「う…ちょっと恥ずかしい、です」
「……可愛い」
「えっ」
「可愛い、お嬢可愛いぞ」
「やっ、やめてくださ…」
「お嬢、俺も…俺も大好きだ」
「待って…待っ、あっ」
抱き寄せられて息が詰まる。
先程よりもその欲の色を強くした瞳に、少しの恐怖を覚えた。
シャツの襟元を弛められ、曝された喉元に歯を立てられる。
食らうように噛み付かれ、その痛みに反射的に抵抗しようとするも敵わない。
ざらりとした舌の感触を動脈の辺りに感じる。
痺れる様な感覚が血液と一緒に身体中に回ってしまいそうだ。
感じたことの無いような感覚に、不覚にも喉は震え瞳が潤む。
「いっ、いいい、さ…ん、やめ…」
「ッどうした!?そんなに痛かったか?」
「ちが、います…けど、あの…本当にこういうの初めてで…」
「…それは俺もだが」
「こわ、くはないんですけど…本当にキャパオーバーしてて…」
「つ、つまり?」
「もう頭のなか爆発しちゃってるんです…いまこれ以上されたら、壊れちゃいそうなんです」
「それは困る!…が、俺も爆発寸前なんだが…」
「えっ…あ…っ!?」
下腹部に押し付けられた硬さに、思わず硬直してしまう。
ぐりぐりと布越しに感じる質量を、熱を、感触を想像してしまい、咄嗟に顔を背けた。
「…お嬢」
「いいいい…さん、の、あの…あああ当たって…ますが」
「当ててんだが。…なぁ、どうすればいい?」
「…私を好きにしてしまえばいいのでは?」
「それは、できないだろ…本当に壊れたら俺は…それこそ戦士失格だ」
「じゃあ…最後まではしない…とか」
「…なるほど」
「えーと…あの、触られると恥ずかしくてダメなんですが…私から触るなら何とか…」
「触…って、くれるのか?」
「でででも上手くはできないですよ?」
「上手かったら複雑なんだが」
「ですよね…正直見たこともないのに触りかたなんて…」
「…無理強いはしないぞ」
「いえ…せっかくなんでさせてください」
「そ、そうか?…じゃあ」
ベルトを弛める音が聞こえた。
窮屈なズボンから解放されたそれは、下着越しに形が分かるくらい大きくなっていて。
初めて直視したそれは想像よりも腫れたような色で、噎せるような匂いがした。
「…痛そうな色なんですが大丈夫なんです?」
「正直痛い。こんな痛いほど勃つの初めてだ…」
「こ…興奮してるって事ですか」
「ああ、かなり」
余程余裕が無いのか、言葉数が少なくなっているようだ。
「あの、これ…触っても大丈夫ですか…?」
「いや待ってくれ…お嬢に触られたらもう出る気がする」
「いっそ出した方が良い気もしますが…」
「……早漏とか思われたくない」
(速いのは自転車だけで充分って事かな)
「…早いも何も、比べる相手も居ないのに」
「今後…比べさせる予定は無いがな」
「ずっと離さないで居てくれるんですか?」
「当たり前だ」
「ん…な、あの、うれしいです…」
照れ隠しに彼の腰に抱きつくと、心音でない脈を胸元に感じて身を起こした。
べっとりと服に吐き出された液を、指先に絡めてから察しがついた。
「こっ…これ、あの」
「ちが、っちがうんだ、お嬢…俺はいつもはこんなに、早くはなくてだな…」
「あ、いやその…これは…舐めた方がいいやつですか…?」
「何言ってんだッ、すぐ拭いて始末しないとシミになるぞ!」
「えっ!?たいへん!」
慌ててティッシュで拭い、洗うためにシャツを脱ぎ捨てた。
何か大事なことを忘れている気が、
「俺の前で脱ぐんじゃあないッ!」
「きゃぁあ!ごめんなさぁい!」
どたばたと片付ける間に、張り詰めていた緊張感がかなり和らいでることに気付いた。
というのもおかしな話ではあるが、女だけ脱がせる訳にはと戦士も脱いでくれた為、一周まわって冷静になれてしまったという。
このどさくさで彼に触れ、最後まで事を運ぶつもりだったが断念した。
体目当てだと思われるのはお互い嫌なのである。
数日後にお互い避妊具を用意してからデートに臨むのはまた別のお話であった。
『密室、炸裂、疾走感』
(爽やかさとかけ離れたアツい恋)
これは所謂、お家デートってやつなんだろうか。
二人きり、密室。
そういう雰囲気になる可能性も勿論あるとは思うが、心の準備っていうものが全くできていない。
ほぼ初対面みたいな仲で(こちらの片想い期間は除く)部屋に招かれるって、どうなんだ。
「どうしたお嬢、上がらないのか?」
「いっ、いえ…お邪魔します…」
「散らかってて悪いな」
「お構いなく…急に来てしまったんで」
「まあ適当に座っててくれ」
緊張しか感じなくて喉がカラカラに渇く。
もっとこう、気の利いた事は言えないものかと我ながら思う。
適当にと言われても敷きっぱなしらしい布団か、机の前に一枚だけある座布団しかないが。
迷わず座布団に座った。
「…しまった、茶菓子とか買ってないぞ」
「あのっ、本当に大丈夫ですよ?」
「しかし…その、彼女を招き入れといてこの扱いじゃあんまりだろう?」
「…今じゃ何出されても喉通らないですよ…」
「気分でも悪いのか!?」
「違くて…えっと、これ言ったら引かれそうだなぁ…」
「今更引かないぞ、どんと来い」
「…いいいいさんの匂いで、胸いっぱいなんですよ、もうキャパオーバー寸前です」
「匂い!?臭かったか!?」
「じゃなくて……だ、抱き締められたら、こんな匂いかな、みたいな?あの、堪らないです正直…」
「なんかヘンタイっぽいぞお嬢…」
「ごめんなさいごめんなさい、口が勝手に」
おどけていないと恥ずかしさで身が持たない。
そんな努力も虚しく、不意に目の前に座られ、目線を合わせられた。
「口が勝手に、なぁ?」
「なん…」
「じゃあ俺も、…口が勝手に」
片手で顎を掴まれ、空いている手でマスクをずらすと、ぐっと顔が迫ってくる。
あと3センチ、という所で思わず目を瞑ると、気配はふっと遠退いた。
「なんて…な、ちょっとまだ早かったすまん」
「やっ…やってて恥ずかしくなって逃げないでください!…期待しちゃったじゃないですか」
「!…お嬢ッ、あんまり煽られると我慢できないんだが!?」
「我慢してほしく無いんですが!」
「押し倒すぞこらァァ!?」
「ば…バッチ恋ですよ!」
「言ったな…ッ!」
がっと肩を掴まれ、不意の浮遊感に襲われるとそのまま布団に運ばれたらしい。
仰向けに寝転がされ、顔の横に手を置いて這い被さるように顔を覗き込まれた。
俗に言う床ドンというやつだろうか。
「…お嬢」
「っ…いいいい、さん」
「キスするぞ、本当にいいのか…?」
「きっ、聞かないでください…」
「嫌なら嫌と…」
「嫌なわけないですよ、…ただかなり、恥ずかしくなってきました」
「同感だ。…でも、したいぞ」
「して、ください……好きですから、いいいいさんの事」
「お嬢…俺も、その…」
「…いいいいさん顔が真っ赤じゃないですかやだー…私いま緊張で気絶しちゃいそうですよ…」
「い…やだか?俺も頭が煮えそうなんだが…」
「急かす気はないんですが現状いっぱいいっぱいなんです…嫌よ嫌よも好きの内、照れ隠しですから気にせずどうぞ…」
「そういう物か…しかし目が、そうだ目を瞑ってくれ」
「わっ、わかりました…」
緊張すると口数が増えるタイプである。
言われた通りに目を瞑ると、今度こそ距離が縮まって来る。
ちゅ、と柔らかい感触がした。しかしそれを感じたのは一瞬であった。
「…っ、は…お嬢…」
「ん…」
一度じゃ足りない、と言うように口付けが続く。
角度を変えながら徐々に交わる時間が長くなる。
彼の掌が頬を撫でながら後頭部へ周る。そのまま掻き抱くように指先に力が入ってくるのを感じた。
無意識に彼の首に腕を回し、その肩にしがみつく様に抱き付いた。
息継ぎをする度に吐息と一緒に甘い声が漏れてしまう。
唇が離れると甘えたような声で名前を呼ばれて背筋がぞくぞくと痺れる。
「…お嬢…、お嬢……好きだ」
「ん…っん、や、…は…ずかし…」
「なぁ…もっと、もっとしたいんだが…」
「だから…っ聞かないでくださいって…」
「じゃあ良いんだな?…ん」
「ぁ、…んっ、む」
半開いていた唇に舌が割って入ってくる。
乾いた喉に生暖かい唾液が染み入る気がする。
舌先で探るように口腔内を撫でられ、応えようとその舌に自分の舌先を絡める。
唾液の混ざった味、耳から頭に直に響くような水音、先刻から鼻腔いっぱいに感じる彼の匂い。
触れた箇所からどんどん熱くなるような感覚に、処理落ち寸前と言っても過言ではない。
崩れ落ちないようにしがみつく手に力を込めようにも、頭の奥が痺れて上手くいく筈もなく。
口端から涎を溢しつつ、布団に倒れこむように顔を離した。
「…ふっ、は……い、いいさ…んっ」
「なん…だっ、大丈夫か!?」
「は…っはぁ…っ、まあ…」
「すまない加減が…お嬢!死ぬな!」
「しにませんが…あの、ちょっと…あはは、こ…」
「こ…?」
「こんなキス…初めてで、…イっちゃうかと、思いました」
「イっ…!?」
「いいいいさんの味も、好かったです…」
「あ…味ッ!?」
「…流石に、レモンの味はしないんですね」
「それは…どういう意味だ」
「少女漫画とかでよく言いません?ファーストキスはレモン味…みたいな」
「…そうだな、お嬢はお嬢の味がする。レモンじゃあない」
「…なんか味とか言われると恥ずかしいですね」
「お嬢が先に言ったんだぞ…」
「そうですけども…っていうかいいいいさん髪ふわっふわですね」
「ひっ、ん、こそばいぞお嬢」
柔らかく癖のある赤毛を堪能しつつ、顔にかかる前髪を撫でると、彼の熱っぽい瞳や白い肌に思わず生唾を飲みかける。
「あと肌が真っ白…今はちょっと赤いですけど」
「そんなまじまじと見るなァ!」
「そんな顔で言われても…」
「顔!?生まれつきだぞォ!?」
「や、あの…目付きって言えば伝わります?」
「悪いって言いたいのか…?」
「違ッ、目付きも大好きです!…じゃなくて、あの、貴方の目が、欲情の色をですね…」
「…大好き…だとォ」
「あっそこ拾っちゃいます?」
「拾っちゃまずいのか?」
「う…ちょっと恥ずかしい、です」
「……可愛い」
「えっ」
「可愛い、お嬢可愛いぞ」
「やっ、やめてくださ…」
「お嬢、俺も…俺も大好きだ」
「待って…待っ、あっ」
抱き寄せられて息が詰まる。
先程よりもその欲の色を強くした瞳に、少しの恐怖を覚えた。
シャツの襟元を弛められ、曝された喉元に歯を立てられる。
食らうように噛み付かれ、その痛みに反射的に抵抗しようとするも敵わない。
ざらりとした舌の感触を動脈の辺りに感じる。
痺れる様な感覚が血液と一緒に身体中に回ってしまいそうだ。
感じたことの無いような感覚に、不覚にも喉は震え瞳が潤む。
「いっ、いいい、さ…ん、やめ…」
「ッどうした!?そんなに痛かったか?」
「ちが、います…けど、あの…本当にこういうの初めてで…」
「…それは俺もだが」
「こわ、くはないんですけど…本当にキャパオーバーしてて…」
「つ、つまり?」
「もう頭のなか爆発しちゃってるんです…いまこれ以上されたら、壊れちゃいそうなんです」
「それは困る!…が、俺も爆発寸前なんだが…」
「えっ…あ…っ!?」
下腹部に押し付けられた硬さに、思わず硬直してしまう。
ぐりぐりと布越しに感じる質量を、熱を、感触を想像してしまい、咄嗟に顔を背けた。
「…お嬢」
「いいいい…さん、の、あの…あああ当たって…ますが」
「当ててんだが。…なぁ、どうすればいい?」
「…私を好きにしてしまえばいいのでは?」
「それは、できないだろ…本当に壊れたら俺は…それこそ戦士失格だ」
「じゃあ…最後まではしない…とか」
「…なるほど」
「えーと…あの、触られると恥ずかしくてダメなんですが…私から触るなら何とか…」
「触…って、くれるのか?」
「でででも上手くはできないですよ?」
「上手かったら複雑なんだが」
「ですよね…正直見たこともないのに触りかたなんて…」
「…無理強いはしないぞ」
「いえ…せっかくなんでさせてください」
「そ、そうか?…じゃあ」
ベルトを弛める音が聞こえた。
窮屈なズボンから解放されたそれは、下着越しに形が分かるくらい大きくなっていて。
初めて直視したそれは想像よりも腫れたような色で、噎せるような匂いがした。
「…痛そうな色なんですが大丈夫なんです?」
「正直痛い。こんな痛いほど勃つの初めてだ…」
「こ…興奮してるって事ですか」
「ああ、かなり」
余程余裕が無いのか、言葉数が少なくなっているようだ。
「あの、これ…触っても大丈夫ですか…?」
「いや待ってくれ…お嬢に触られたらもう出る気がする」
「いっそ出した方が良い気もしますが…」
「……早漏とか思われたくない」
(速いのは自転車だけで充分って事かな)
「…早いも何も、比べる相手も居ないのに」
「今後…比べさせる予定は無いがな」
「ずっと離さないで居てくれるんですか?」
「当たり前だ」
「ん…な、あの、うれしいです…」
照れ隠しに彼の腰に抱きつくと、心音でない脈を胸元に感じて身を起こした。
べっとりと服に吐き出された液を、指先に絡めてから察しがついた。
「こっ…これ、あの」
「ちが、っちがうんだ、お嬢…俺はいつもはこんなに、早くはなくてだな…」
「あ、いやその…これは…舐めた方がいいやつですか…?」
「何言ってんだッ、すぐ拭いて始末しないとシミになるぞ!」
「えっ!?たいへん!」
慌ててティッシュで拭い、洗うためにシャツを脱ぎ捨てた。
何か大事なことを忘れている気が、
「俺の前で脱ぐんじゃあないッ!」
「きゃぁあ!ごめんなさぁい!」
どたばたと片付ける間に、張り詰めていた緊張感がかなり和らいでることに気付いた。
というのもおかしな話ではあるが、女だけ脱がせる訳にはと戦士も脱いでくれた為、一周まわって冷静になれてしまったという。
このどさくさで彼に触れ、最後まで事を運ぶつもりだったが断念した。
体目当てだと思われるのはお互い嫌なのである。
数日後にお互い避妊具を用意してからデートに臨むのはまた別のお話であった。
『密室、炸裂、疾走感』
(爽やかさとかけ離れたアツい恋)