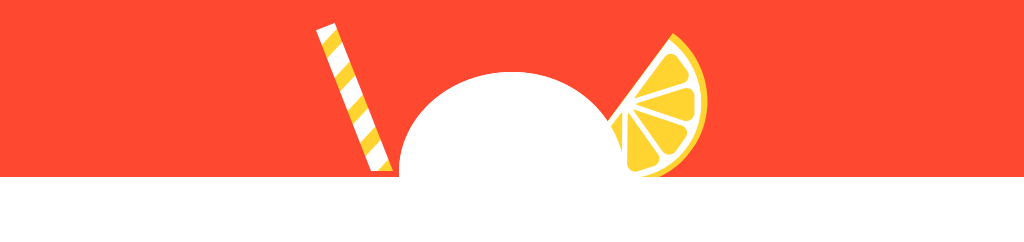ポップン
夢小説設定
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
「つよしさん、好きです」
「…え」
「私の…こっ、恋人になってください!」
…告白してしまった!
遂に、遂に言ってしまった!
思えばこうしてデートに至るまでも長かった。
最初に声をかけたのはどちらからだっただろうか…。
いつも通る場所で、いつも目を奪われていた。偶然を装って目を合わせると、彼は柔らかく微笑みを返してくれた。
しかしそこから進展するなど当時は考えられなかった。
私が一目惚れという概念なんて信じないタイプだからである。
目を奪われるのは、彼がとても美しく見えたからだと思っていた。
遠くからでもキラキラしているのが分かる程だ。
このキラキラが恋だと気付いてしまうともうそれからは大変だった。
だらしなく弛む口角や紅くなる頬を隠す為に、彼から隠れる様に、いつもの道を歩く時間もずらしていた。
しかし彼はそこに居た。それはそれは寒い日で、すっかり夜だったのにである。
キラキラ、キラキラと眩しくて、とうとう我慢できなくて声をかけたんだった。
「もしもしそこのお兄さん」
「…僕でございますか?」
「そう貴方です、…王子様?」
「はい、王子でございますよ」
声がとても甘く聞こえる。
これが所謂恋の魔法が掛かってるってヤツだろうか。
「へえ…あ、私怪しい者じゃなくて…えーと…よく、お会いしますよね?と思って」
「あっ、そ…それは僕が…」
「?」
「いやその…あー…偶然でございますね!」
「ね。…この後お時間とかありません?良かったら一緒にお酒でも…」
「え?」
「違っ、間違い…これじゃ逆ナンですよね失礼しました」
「…時間ありますよ、僕」
「本当にですか…」
「貴女みたいな素敵な人のお誘い、断る理由もありません」
「いやいや貴方の方がよっぽど素敵で…」
近くで見ると一段と輝いている気がする。
金色い髪は夜の闇でも霞まず。長い睫毛が作る影がとても色っぽく見える。
目を合わせられると翠の瞳に飲み込まれそうで落ち着かない。
と同時に完全に魅入ってしまい、ほんのり漂う色香に生唾を飲んでしまう。
「…どうかしましたか?」
「ふぁっ!?あっ、…何でもないです」
「そんなに見つめられると照れちゃうでございますよ…」
「ごっごめんなさい…すごく、綺麗だなって思って」
「!…もう、それは僕の台詞ですよ」
「えっ」
「…いつも、貴女と目が合うのが僕の楽しみで」
「えあ、あの…っ」
「そういえば僕は、貴女…えーと」
「あ、私お嬢と申します!」
「お嬢さん、僕はお嬢さんにお願いがあるんです」
「どういったお願いでしょうか」
「…僕の悩みを聞いてほしいんでございます」
「勿論いいですよ、じゃあ何処かゆっくり話せる所で」
「僕の馴染みの店がありますよ、此処からちょっと歩きますけど」
「良いじゃないですか、行きましょう!」
「ではこちらでございます」
何だかエスコートされてるみたいだ、と浮かれてしまう。
しかしこの時に飲んだお酒の味は、緊張で全然覚えていないのだった。
そんな事もあったなと記憶が甦る。
告白の返事を待つのが怖くて、まるで走馬灯のように一瞬で色々思い出してしまった。
「…お嬢さん」
「ハイッ」
思わず声も上擦ってしまう。
「ありがとう、とっても嬉しいでございます」
「王子…!」
「でも」
「で、でも?」
不安が頭を掠める。
今回告白したのも、王子から好意的な印象があると自信が少しあったからだ。
しかし急ぎすぎただろうか…
「お嬢さんからの告白、喜んでお受けしたいですが」
「ですが」
「…そういうのは僕からも、後だしですが格好つけさせてもらってもいいですか?」
「え、…えっ、」
片膝をつき、私の手をとり微笑む王子。
鼓動が高鳴り過ぎて、周りの音が何も聴こえなくなる。
夢か幻か、世界で二人きりになってしまったような感覚。
「僕も貴女を愛しています、お嬢さん…僕の想いを受け取っていただけますか?」
「つよしさん…っ」
感極まって視界が滲む
早く、早く答えたいのに喉が震えてしまう。
「…よ、よっ、よろしくお願いします」
「こちらこそ、でございます」
余裕のないなりに王子の顔色を伺うと、私と同じかそれ以上に真っ赤になっていて
綺麗な緑色が潤んで零れてしまいそうになっていた。
「な…なんか、恋ってこんなに感極まっちゃうんですね」
「同感でございます…告白でこれでは、婚約を申し込むときにはどうなってしまうやら」
「婚約…?」
「あっ」
「えっ」
「あの…今のはその…聞かなかったことに」
「えーと、…無理です」
「無理…っ!?」
「…聞かなかったことになんてできません、これからも永く…よろしくお願いしたいです」
「こちらこそ…」
ふわりと微笑んでくれた顔が愛おしい。
緊張の糸が切れ、思わずその場にへたり込みそうになったその時、王子に抱き寄せられた。
心臓の音が早すぎて逆に止まってるのかと錯覚しそうになる。
ようやくと彼の背に手をまわし抱き返す。
途端に二人同時に響く弱々しい音。
「あぁ…安心したらお腹が空いてしまったのでございます」
「私もですよ…あ、じゃあこれからご飯行きましょうよ」
「賛成でございます、僕お嬢さんと初めて行ったお店に行きたいな」
「いいですね、またエスコートしてくれますか?」
「勿論、今度は僕のお姫様として隣に居てもらいますね」
気恥ずかしさで赤くなりながらも手を取って微笑んでくれるのが嬉しくて、
恋人として隣に並べるのが嬉しくて、
私は結局しばらく抱きついたまま顔を上げられなかったのであった。
『甘くて甘くて少し酸っぱい』
(キスするタイミング逃した気がする)
「…え」
「私の…こっ、恋人になってください!」
…告白してしまった!
遂に、遂に言ってしまった!
思えばこうしてデートに至るまでも長かった。
最初に声をかけたのはどちらからだっただろうか…。
いつも通る場所で、いつも目を奪われていた。偶然を装って目を合わせると、彼は柔らかく微笑みを返してくれた。
しかしそこから進展するなど当時は考えられなかった。
私が一目惚れという概念なんて信じないタイプだからである。
目を奪われるのは、彼がとても美しく見えたからだと思っていた。
遠くからでもキラキラしているのが分かる程だ。
このキラキラが恋だと気付いてしまうともうそれからは大変だった。
だらしなく弛む口角や紅くなる頬を隠す為に、彼から隠れる様に、いつもの道を歩く時間もずらしていた。
しかし彼はそこに居た。それはそれは寒い日で、すっかり夜だったのにである。
キラキラ、キラキラと眩しくて、とうとう我慢できなくて声をかけたんだった。
「もしもしそこのお兄さん」
「…僕でございますか?」
「そう貴方です、…王子様?」
「はい、王子でございますよ」
声がとても甘く聞こえる。
これが所謂恋の魔法が掛かってるってヤツだろうか。
「へえ…あ、私怪しい者じゃなくて…えーと…よく、お会いしますよね?と思って」
「あっ、そ…それは僕が…」
「?」
「いやその…あー…偶然でございますね!」
「ね。…この後お時間とかありません?良かったら一緒にお酒でも…」
「え?」
「違っ、間違い…これじゃ逆ナンですよね失礼しました」
「…時間ありますよ、僕」
「本当にですか…」
「貴女みたいな素敵な人のお誘い、断る理由もありません」
「いやいや貴方の方がよっぽど素敵で…」
近くで見ると一段と輝いている気がする。
金色い髪は夜の闇でも霞まず。長い睫毛が作る影がとても色っぽく見える。
目を合わせられると翠の瞳に飲み込まれそうで落ち着かない。
と同時に完全に魅入ってしまい、ほんのり漂う色香に生唾を飲んでしまう。
「…どうかしましたか?」
「ふぁっ!?あっ、…何でもないです」
「そんなに見つめられると照れちゃうでございますよ…」
「ごっごめんなさい…すごく、綺麗だなって思って」
「!…もう、それは僕の台詞ですよ」
「えっ」
「…いつも、貴女と目が合うのが僕の楽しみで」
「えあ、あの…っ」
「そういえば僕は、貴女…えーと」
「あ、私お嬢と申します!」
「お嬢さん、僕はお嬢さんにお願いがあるんです」
「どういったお願いでしょうか」
「…僕の悩みを聞いてほしいんでございます」
「勿論いいですよ、じゃあ何処かゆっくり話せる所で」
「僕の馴染みの店がありますよ、此処からちょっと歩きますけど」
「良いじゃないですか、行きましょう!」
「ではこちらでございます」
何だかエスコートされてるみたいだ、と浮かれてしまう。
しかしこの時に飲んだお酒の味は、緊張で全然覚えていないのだった。
そんな事もあったなと記憶が甦る。
告白の返事を待つのが怖くて、まるで走馬灯のように一瞬で色々思い出してしまった。
「…お嬢さん」
「ハイッ」
思わず声も上擦ってしまう。
「ありがとう、とっても嬉しいでございます」
「王子…!」
「でも」
「で、でも?」
不安が頭を掠める。
今回告白したのも、王子から好意的な印象があると自信が少しあったからだ。
しかし急ぎすぎただろうか…
「お嬢さんからの告白、喜んでお受けしたいですが」
「ですが」
「…そういうのは僕からも、後だしですが格好つけさせてもらってもいいですか?」
「え、…えっ、」
片膝をつき、私の手をとり微笑む王子。
鼓動が高鳴り過ぎて、周りの音が何も聴こえなくなる。
夢か幻か、世界で二人きりになってしまったような感覚。
「僕も貴女を愛しています、お嬢さん…僕の想いを受け取っていただけますか?」
「つよしさん…っ」
感極まって視界が滲む
早く、早く答えたいのに喉が震えてしまう。
「…よ、よっ、よろしくお願いします」
「こちらこそ、でございます」
余裕のないなりに王子の顔色を伺うと、私と同じかそれ以上に真っ赤になっていて
綺麗な緑色が潤んで零れてしまいそうになっていた。
「な…なんか、恋ってこんなに感極まっちゃうんですね」
「同感でございます…告白でこれでは、婚約を申し込むときにはどうなってしまうやら」
「婚約…?」
「あっ」
「えっ」
「あの…今のはその…聞かなかったことに」
「えーと、…無理です」
「無理…っ!?」
「…聞かなかったことになんてできません、これからも永く…よろしくお願いしたいです」
「こちらこそ…」
ふわりと微笑んでくれた顔が愛おしい。
緊張の糸が切れ、思わずその場にへたり込みそうになったその時、王子に抱き寄せられた。
心臓の音が早すぎて逆に止まってるのかと錯覚しそうになる。
ようやくと彼の背に手をまわし抱き返す。
途端に二人同時に響く弱々しい音。
「あぁ…安心したらお腹が空いてしまったのでございます」
「私もですよ…あ、じゃあこれからご飯行きましょうよ」
「賛成でございます、僕お嬢さんと初めて行ったお店に行きたいな」
「いいですね、またエスコートしてくれますか?」
「勿論、今度は僕のお姫様として隣に居てもらいますね」
気恥ずかしさで赤くなりながらも手を取って微笑んでくれるのが嬉しくて、
恋人として隣に並べるのが嬉しくて、
私は結局しばらく抱きついたまま顔を上げられなかったのであった。
『甘くて甘くて少し酸っぱい』
(キスするタイミング逃した気がする)