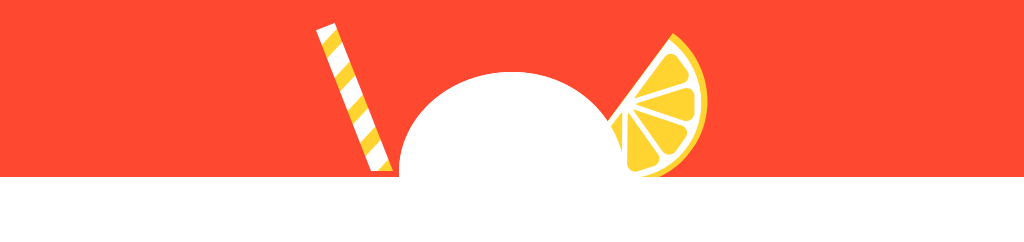SDガンダム
夢小説設定
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
「大丈夫、大丈夫」
と口癖を呟いた。
彼女は抱かれるのを初めてだと言った。
嬉しく思う反面、怖がらせてはいけないと使命感に駆られた。
「リガズィ、さん…」
「ん、大丈夫?」
不安げに見つめられ、こちらも少々緊張する。
胡座をかいた姿勢で彼女を膝に乗せ、後ろから抱きかかえるように腰を支える。
目尻にキスを落とし、下へと這わせていた手で太股を撫で上げると、彼女の身体はぴくりと反応して見せた。
「…手が、くすぐったい」
「そう?君が敏感なだけだと思うな」
「ちが、っ……意地悪」
「あー…、あんまり煽らないで」
焦らすような愛撫のせいか、ただ濡れやすいだけなのか。
すでに潤っている蜜口に指を這わせた。
「ん…っ、」
「ちゃんと濡れてる、俺の手で感じてるんだ?」
「やっ…音立てないで…」
わざとらしく水音を立てながら指を挿せば、
思いの外するりと中へ呑まれる。
「ん、…んっ」
「…自分で触ったことあるの?」
「少し、だけ…。でも…」
「でも?」
「……まだ、全然感じなくて、ちょっと痛くて」
「うんうん」
「まあ、指一本が限界かな…って」
「大丈夫、大丈夫。ちゃんと柔らかいからもっと行けるよ」
少しずつ解すように指を曲げると、圧迫感からか彼女は苦しげに顔を歪めた。
「痛い?」
「…あんまり、痛くないけど…変な感じ」
「嫌だと思ったら直ぐに言ってね」
「ん、…うん」
もう一本、と指を増やし、浅く抜き挿すだけでも
水音はどんどんと増して行った。
二本の指をゆっくりと根元まで入れると、開いていた脚が何かから逃げるように閉じた。
膝を擦り合わせ、熱っぽい息を吐く彼女は
何とも言えないような目でこちらの手の動きを見つめていた。
「…は、…んっ、」
「あー、……可愛い」
「っ?!」
「?、今の気持ちよかったかな、中がきゅってしたけど」
「えっ、あっ…やだ……言わないで…」
「…すごい、また溢れてきた」
ーーーーー
可愛いなんて唐突に言われ、思わず心臓が跳ねる。
慣れているかのような手付きで、自身がどんどん蕩けさせられているのが分かる。
「…っ、リガズィ…さん」
「ん、痛かったかな」
「違っ…あの、わたっ、私、も…」
「いっちゃいそう?」
「分かんな…、あっ、やっ…!」
浅い所を攻められると、中が指を吸い込むようにうごめいてしまう。
未開発の内側に、じわじわと波が押し寄せる気がした。
すっかり解された身体は、時折やってくる強い快楽から逃げるように腰を動かす。
「あっ、はっ…声、いやっ…」
「大丈夫、可愛い」
「んあぁ…っ!」
優しく優しく秘部を弄る指に物足りなさを感じ始めた途端、愛液でぬめぬめの指が肉芽をきゅっと摘まんだ。
「あっ、あっ…だめっ、それだめ…っ!」
「いいよ、いって?」
「ッ…!う、やああぁあ!」
びくびくと身体が震える。
稲妻のような快楽が頭を真っ白にする。
呼吸が整わない。
中がトロトロと潤う感覚と、浅く刺さっている指の感覚ははっきりと分かる。
「…は……ぁ、あっ、」
「大丈夫?」
「…だい、じょぶ、……かも」
「ねえ、これオカズにしていい?」
「え…?」
ーーーーー
流石に最初から挿入できるなんて思っていない訳だが。
興奮してしまったコレばっかりはどうしようもなく。
指を引き抜けば中からたっぷりと溢れてきた愛液がローションのように俺の脚を濡らして垂れていた訳だから。
訳だから。
「だから、君のをコレに使って抜きたいんだけど、いい?」
「えっ、……入れないんですか?」
「うん、まだちょっと苦しいと思うし、…ちょっと俺が興奮しちゃってるから…」
「…から?」
「歯止めが、効く自信も無い」
今のの何処にときめいたのか、彼女の愛液はどんどん溢れていた。
「あの…じゃあ私が」
「ん?」
「私が、…その、それ……なんとかします」
「なんとか」
「…手で!、…ぬ、抜きます、よ?」
言っている本人が一番恥ずかしいんだろうな。
可愛い。
「じゃあ、触ってみる?」
無意識にそんなことを言っていた。
体勢を少し動かし、彼女の手をとりナニを握るように導いた。
きゅ、と緩く掴まれるだけでイきそうになる程、己は興奮してパンパンになっていた。
「…あ、熱い…ですね」
「どうする?俺のこんなになっちゃうくらい君に欲情してる」
「っ…!」
添えた手に力を込めて彼女の手ごと何度か扱くように動かすと、それに抵抗するように手を止めようとされた。
流石に初見で手コキっていうのは辛いのかな、と思う。
「ん、嫌だった?ごめん」
「…いやじゃない…です、その、私が、自力でしますから…手を、離してもらっても…大丈夫です」
「…本当に?」
「本当に、です、…下手だったら言ってください」
言うなり先程よりもしっかりとナニを握られ、自分のよりも小さな手の感触と、煽るように真っ赤になる彼女の顔に正直なところかなり限界が近かった。
時折物欲しそうに腰を揺らす彼女の首筋にそっとキスを落とすと、びくっと身体を揺らして反応するのが面白い。
彼女の甘い味がするような熱さが、触れている箇所から、握られた自身から、全身に染みてくるような感覚。
慣れない手つき故か焦らされる様に斑にやってくる快楽に腰が浮きそうになる。
必死に堪えつつ彼女を見れば、何やら複雑な眼差しと目が合った。
「…リガズィさんっ」
「ん…っ、なに」
「なんでそんな、余裕なんですか…」
「…余裕、なんて…ないけど」
「やっぱり下手ですかね…?」
「違う…っ、はぁ、もう…」
「えっ」
「もう出る、から…離して…ッ」
本当は彼女にぶちまけたい気もするが、汚してしまうのは気が引けた。
しかし彼女は手を離すどころかぐっしょり濡れた自身を擦り付けてきた。
不意の素股に完全に動揺し、俺は彼女の腹に精液をぶちまけた。
「う…っ!く、は……ぁ…」
「わぁ…こんなに、出るんですね」
「…はぁ、は、あ…ごめん、かけちゃった…」
「精液ってこんなに濃いんだ…知らなかった」
「あっ、何やってんの」
ぶちまけたそれを、指に絡ませるように遊ばれて何だか恥ずかしくなる。
ねっとりと彼女の指先を汚すそれは、普段処理するときに見慣れている物だ。しかしそれを彼女が、それで彼女を汚していると思うと途端に興奮するというものである。
「リガズィさん、これ…舐めても良いですか?」
「…ばっちぃから駄目。拭くからじっとしてて」
舐めたり飲んだりされるのはシチュエーション的には憧れるが、だからって初夜にされるのは少し違うわけで。
上手く言えないが、彼女にAV女優の真似をさせるなんてのは許し難いと言うべきか。
何にせよ今夜での発展は此処までにしようと思う。
「…はい、とりあえず拭けたからあとはシャワー浴びてきなね」
「え、今日はここまでですか?」
「一旦ね。続きはまた今度しよう」
「あっ…じゃあ締めに、キスしてください」
「ん、じゃあ目瞑って…」
「……んむ」
ついでに舌も入れたら今更腰が砕けたらしいので、シャワーも同行する事になった。
発展は此処までとか思ったが、本当に我慢できるのか俺は。
正直な所、自信は皆無だったりする。
『サクセス』
性行で成功するかって話。
end
と口癖を呟いた。
彼女は抱かれるのを初めてだと言った。
嬉しく思う反面、怖がらせてはいけないと使命感に駆られた。
「リガズィ、さん…」
「ん、大丈夫?」
不安げに見つめられ、こちらも少々緊張する。
胡座をかいた姿勢で彼女を膝に乗せ、後ろから抱きかかえるように腰を支える。
目尻にキスを落とし、下へと這わせていた手で太股を撫で上げると、彼女の身体はぴくりと反応して見せた。
「…手が、くすぐったい」
「そう?君が敏感なだけだと思うな」
「ちが、っ……意地悪」
「あー…、あんまり煽らないで」
焦らすような愛撫のせいか、ただ濡れやすいだけなのか。
すでに潤っている蜜口に指を這わせた。
「ん…っ、」
「ちゃんと濡れてる、俺の手で感じてるんだ?」
「やっ…音立てないで…」
わざとらしく水音を立てながら指を挿せば、
思いの外するりと中へ呑まれる。
「ん、…んっ」
「…自分で触ったことあるの?」
「少し、だけ…。でも…」
「でも?」
「……まだ、全然感じなくて、ちょっと痛くて」
「うんうん」
「まあ、指一本が限界かな…って」
「大丈夫、大丈夫。ちゃんと柔らかいからもっと行けるよ」
少しずつ解すように指を曲げると、圧迫感からか彼女は苦しげに顔を歪めた。
「痛い?」
「…あんまり、痛くないけど…変な感じ」
「嫌だと思ったら直ぐに言ってね」
「ん、…うん」
もう一本、と指を増やし、浅く抜き挿すだけでも
水音はどんどんと増して行った。
二本の指をゆっくりと根元まで入れると、開いていた脚が何かから逃げるように閉じた。
膝を擦り合わせ、熱っぽい息を吐く彼女は
何とも言えないような目でこちらの手の動きを見つめていた。
「…は、…んっ、」
「あー、……可愛い」
「っ?!」
「?、今の気持ちよかったかな、中がきゅってしたけど」
「えっ、あっ…やだ……言わないで…」
「…すごい、また溢れてきた」
ーーーーー
可愛いなんて唐突に言われ、思わず心臓が跳ねる。
慣れているかのような手付きで、自身がどんどん蕩けさせられているのが分かる。
「…っ、リガズィ…さん」
「ん、痛かったかな」
「違っ…あの、わたっ、私、も…」
「いっちゃいそう?」
「分かんな…、あっ、やっ…!」
浅い所を攻められると、中が指を吸い込むようにうごめいてしまう。
未開発の内側に、じわじわと波が押し寄せる気がした。
すっかり解された身体は、時折やってくる強い快楽から逃げるように腰を動かす。
「あっ、はっ…声、いやっ…」
「大丈夫、可愛い」
「んあぁ…っ!」
優しく優しく秘部を弄る指に物足りなさを感じ始めた途端、愛液でぬめぬめの指が肉芽をきゅっと摘まんだ。
「あっ、あっ…だめっ、それだめ…っ!」
「いいよ、いって?」
「ッ…!う、やああぁあ!」
びくびくと身体が震える。
稲妻のような快楽が頭を真っ白にする。
呼吸が整わない。
中がトロトロと潤う感覚と、浅く刺さっている指の感覚ははっきりと分かる。
「…は……ぁ、あっ、」
「大丈夫?」
「…だい、じょぶ、……かも」
「ねえ、これオカズにしていい?」
「え…?」
ーーーーー
流石に最初から挿入できるなんて思っていない訳だが。
興奮してしまったコレばっかりはどうしようもなく。
指を引き抜けば中からたっぷりと溢れてきた愛液がローションのように俺の脚を濡らして垂れていた訳だから。
訳だから。
「だから、君のをコレに使って抜きたいんだけど、いい?」
「えっ、……入れないんですか?」
「うん、まだちょっと苦しいと思うし、…ちょっと俺が興奮しちゃってるから…」
「…から?」
「歯止めが、効く自信も無い」
今のの何処にときめいたのか、彼女の愛液はどんどん溢れていた。
「あの…じゃあ私が」
「ん?」
「私が、…その、それ……なんとかします」
「なんとか」
「…手で!、…ぬ、抜きます、よ?」
言っている本人が一番恥ずかしいんだろうな。
可愛い。
「じゃあ、触ってみる?」
無意識にそんなことを言っていた。
体勢を少し動かし、彼女の手をとりナニを握るように導いた。
きゅ、と緩く掴まれるだけでイきそうになる程、己は興奮してパンパンになっていた。
「…あ、熱い…ですね」
「どうする?俺のこんなになっちゃうくらい君に欲情してる」
「っ…!」
添えた手に力を込めて彼女の手ごと何度か扱くように動かすと、それに抵抗するように手を止めようとされた。
流石に初見で手コキっていうのは辛いのかな、と思う。
「ん、嫌だった?ごめん」
「…いやじゃない…です、その、私が、自力でしますから…手を、離してもらっても…大丈夫です」
「…本当に?」
「本当に、です、…下手だったら言ってください」
言うなり先程よりもしっかりとナニを握られ、自分のよりも小さな手の感触と、煽るように真っ赤になる彼女の顔に正直なところかなり限界が近かった。
時折物欲しそうに腰を揺らす彼女の首筋にそっとキスを落とすと、びくっと身体を揺らして反応するのが面白い。
彼女の甘い味がするような熱さが、触れている箇所から、握られた自身から、全身に染みてくるような感覚。
慣れない手つき故か焦らされる様に斑にやってくる快楽に腰が浮きそうになる。
必死に堪えつつ彼女を見れば、何やら複雑な眼差しと目が合った。
「…リガズィさんっ」
「ん…っ、なに」
「なんでそんな、余裕なんですか…」
「…余裕、なんて…ないけど」
「やっぱり下手ですかね…?」
「違う…っ、はぁ、もう…」
「えっ」
「もう出る、から…離して…ッ」
本当は彼女にぶちまけたい気もするが、汚してしまうのは気が引けた。
しかし彼女は手を離すどころかぐっしょり濡れた自身を擦り付けてきた。
不意の素股に完全に動揺し、俺は彼女の腹に精液をぶちまけた。
「う…っ!く、は……ぁ…」
「わぁ…こんなに、出るんですね」
「…はぁ、は、あ…ごめん、かけちゃった…」
「精液ってこんなに濃いんだ…知らなかった」
「あっ、何やってんの」
ぶちまけたそれを、指に絡ませるように遊ばれて何だか恥ずかしくなる。
ねっとりと彼女の指先を汚すそれは、普段処理するときに見慣れている物だ。しかしそれを彼女が、それで彼女を汚していると思うと途端に興奮するというものである。
「リガズィさん、これ…舐めても良いですか?」
「…ばっちぃから駄目。拭くからじっとしてて」
舐めたり飲んだりされるのはシチュエーション的には憧れるが、だからって初夜にされるのは少し違うわけで。
上手く言えないが、彼女にAV女優の真似をさせるなんてのは許し難いと言うべきか。
何にせよ今夜での発展は此処までにしようと思う。
「…はい、とりあえず拭けたからあとはシャワー浴びてきなね」
「え、今日はここまでですか?」
「一旦ね。続きはまた今度しよう」
「あっ…じゃあ締めに、キスしてください」
「ん、じゃあ目瞑って…」
「……んむ」
ついでに舌も入れたら今更腰が砕けたらしいので、シャワーも同行する事になった。
発展は此処までとか思ったが、本当に我慢できるのか俺は。
正直な所、自信は皆無だったりする。
『サクセス』
性行で成功するかって話。
end