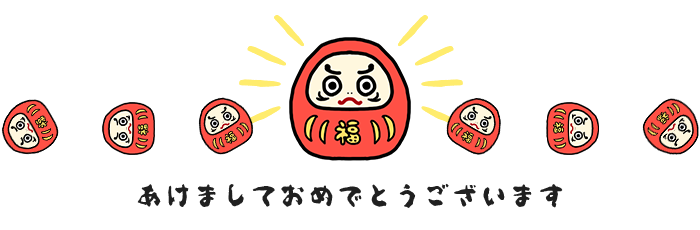DC 原作沿い
「パリジャン」
『んー?キューちゃん?』
声をかければ振り返る。揺れた金色の髪はいつもと変わらず、顔色も変わらない。
だからこそ、違和感が強くて。
持っていたそれを投げつければ難なく受け取った。
『あ!おにぎり!』
「しっかり食べなさい。残したら許さないわ」
『うん!ありがとう!キューちゃん!』
口を開けてきゃっきゃと喜ぶ姿に息を吐いて、足を引いて背を向ける。歩き出せば後ろからもう一度ありがとうと声が聞こえてそれを無視して廊下を進む。
私がこの組織に戻ってきてしまったのは彼奴のせいだけれど、彼奴がいなければ私は生きていられなかったというから皮肉な話だ。
あの日、知ってはいけないことを記憶してしまった私は命惜しさに逃亡した。その場所は誰も知らないはずの、私ですら行ったことのない場所なのにあっさりとお迎えだよーと現れたパリジャンはまさしく死神で、抵抗する間もほとんど与えられず抑えられて、気絶。目が覚めたときには拘束されていた。
記憶の抹消をと組織の研究員が言葉にしていて、いざ、その処置が行われようとしたところで、地獄から声が響いた。
結果として、より一層の組織への貢献を条件にラムに拾われた私は組織を抜け出すことは更に困難になり、絶望しているところにへらへらと笑う死神が影を伴って現れた。
『キューちゃんが元気に生きていけるように!』
そう笑ったパリジャンは連れていた男をアイくんと紹介し、アイリッシュという古参で中心に近いメンバーを私の師としてつけた。
アイリッシュは稽古だと武術をメインに私を扱いて、比喩ではなく何度も吐かされて、意識を飛ばし、三途の川を渡りかけた。
そうやって鍛えられた私は、ちょっと力のある一般人には負けない程度だったものが、大抵の鍛えた人間ならば数手内に行動不能にしたり必要に応じてどんな道でも逃亡できるだけの身のこなしを習得した。
それをパリジャンはキューちゃんが楽しそうでよかったと笑って見ていて、仕返しも兼ねて手合わせをしたけれど、惨敗を喫して、アイリッシュには復讐なら辞めとけと笑われた。
「彼奴は俺の一番弟子だ。お前じゃ当面は勝てねぇよ」
「…ちっ」
手合わせの後に仕事だからーと部屋を出ていってしまって、体が痛くて転がっている私にアイリッシュは頬杖をついてにやにやと口元を歪めてる。
見るからに筋肉隆々のアイリッシュの力が強いのは理解できる。一撃一撃に重さを乗せられて放たれる攻撃は当たれば手足ならばしばらくしびれて使い物にならないし、急所に入れば立っていることもままならない。
そんなアイリッシュとは見た目が正反対のパリジャンは、見目は優男だ。多少身長はあれど華奢に見える体をしていて、特に隣にアイリッシュやジンが並ぼうものならばその線の細さが顕になる。
大きな虹彩のはまった瞳は目尻が垂れていて、口元には常にゆるい笑みで保たれてる。髪は肩を超えるほどの長さで、日にもよるけれど大抵は降ろされているかゆるく一つに纏められている。私と同じくらい白い肌は日焼け知らずで、黙っていれば美しく、話せば花が綻ぶように笑んで、無邪気にはしゃぐ姿は周りを照らすように明るく可愛らしい。
そんな甘い男が放つ一撃は、アイリッシュ仕込みの殺意を伴った攻撃で、ノーモーションからの異様なまでのスピード感で放たれ、それが的確に急所を壊しにくるから、本当にあれは食事を食べきれずアイリッシュに半分こしようと強請ってた男なのかと混乱する。
私でさえ、パリジャンの存在は半信半疑だった。
この組織に入り、大きめの仕事を割り当てられるようになった頃。仕事を失敗したという同業者が殺されると震えていて、翌日には消えていた。
不思議に思い情報を集めたところ、あっさりとその答えは開示される。
この組織には仕事を失敗した場合と裏切り者が現れたときにのみ仕事をするパリジャンという処刑人がいる。
まことしやかに語られるそれに眉根を寄せて、真偽を確かめるより早く、その男と出会った。
「、」
仕事終わり、盗み出したそれを預けるために立ち寄った組織の拠点の一つ。ずるずると何か重たいものを引きずる音が向かいから聞こえてきて、近づいてきていたそれは片手に電話を、片手に人を引きずりながらにこにこと歩いていた。
『いまついたところ!ん?…うん!ジンくんが言ってたから殺さないで持って帰ってきたよ!偉いでしょ!』
ふふんっと鼻を鳴らし上機嫌に歩く姿。引きずられてる人は意識はないようで口元から泡を吹いていて、そして、あるはずの足の先も、なかった。
零れそうになった声にすぐさま口元を押さえて物陰に身を隠す。
『大丈夫!止血してある!自分で切って逃げようとするなんてすごいよね〜!怒ったジンくんがすっごく怖かったんだね!』
あははと笑う姿は世間話でもするようで、どっどっと大きく動きすぎてる心臓の音が聞こえてしまうんじゃないかと息を詰めて、ずるずると聞こえてるそれが離れていって、何も聞こえなくなってしばらくしてからふっと体から力が抜けて床に座り込んだ。
パリジャンなんて、都市伝説と一緒だと思ってた。
この組織に忠誠を誓わせて、逃げるなんて選択肢をあたえないためだけのシステム。
それがあんなにイカレた奴でこんな身近にいるなんて。
『ねぇねぇ』
「!!!!」
聞こえた声に飛び上がる。いつの間にか目の前にいたのは恐怖対象のそれで、心臓の痛みは強すぎて感覚が麻痺してる。
警戒しかできない私にパリジャンはにぱっと笑って、口を開いた。
『これから夜ご飯食べに行くんだけど、何がいいと思う?』
「………は、…?」
『葉っぱ?うーん、サラダかぁ』
野菜苦手なんだよなぁと唸るパリジャンはあ、と言葉をこぼすとすぐに顔を上げて、にこにことしながら歩き出した。
『夜ご飯決まった!ありがと!ばいばーい!』
「………、ええ」
なんとか返した言葉にパリジャンはすたすたと歩いていって、背中が見えなくなったところで胸を押さえた。
「なに、あの生き物…」
いまだ落ち着かない心拍にここから動くことはできそうにない。
意味がわからない言動。理解の及ばないあれはもう人間ではなく動物かと、呼吸を繰り返し無理やり鼓動を正して、建物から出る頃には10分も経ってた。
二度と会いたくない生き物に、その半年後に会って捕まってしまったのだから、人生は悲劇でしかない。
ふと、そこで目を開ける。
「お、起きたか?」
聞こえた声に目を向ければ携帯を触りながら煙草をふかしてるアイリッシュがいて、じわじわと熱を放っている腹に攻撃を受けて意識が飛んだのかと体を起こした。
更に強くなった痛みを息を吐いて逃す。最近は少しずつとはいて地力がついていたから意識を飛ばしたのは久々で、立ち上がって服をはたき前を見据える頃にはアイリッシュも両手を空けた状態に落ち着いてた。
「今日はここでしまいだ」
「…そう」
「お大事になー」
気絶をさせた人間の言葉ではないそれを残して訓練場を出ていくアイリッシュに、姿が確認できなくなったところで腹を押さえる。
「ったく、痛いったらありゃしないわ」
自然とこもった顔の力。じんじんと熱を響かせてる腹に骨でも折れてたらどうしてくれようかとまた息を吐いて、アイリッシュの消えていった先の扉を睨みつける。
こんなふうにヘマをするのは本当に久々だけれど、最初の頃は毎回気絶させられていた。
女が相手だからなんて躊躇いは一切なし。こっちは諜報メインだというのに筋肉に物を言わせた的確な打撃を受ければ私は簡単にふっとばされて壁に頭をぶつけて気絶のコースだ。
月に一、ニ度ほどのそれをしばらく続け、初めて、ぎりぎり気絶せずに済んだ訓練。息も絶え絶えに床に膝をついてる私をアイリッシュは見おろした。
「キュラソー」
「…っ、なに、よ」
「お前には攻撃の受け流し方を教える」
「…はぁ?…いま、やってること、でしょ」
「攻撃は力だけじゃねぇ」
「……?」
「力だけでのし上がったり逃げ切ったりできるような簡単な世界じゃねぇ。一回失敗したお前はそれがわかってるはずだ」
「、」
「お前にはスピードとその頭がある。でも武力への対策が足りてなさすぎた。だから、お前にはまず武力を退ける術を身に着けさせる」
「………なに、アンタ組織を抜ける気なの…?」
「はぁ?んなわけあるか」
小馬鹿にしたようなあっさりとした言葉を吐いたアイリッシュは目を細める。
「俺は根っからの組織の人間だ。気に食わねぇことがあっても今更出ていく気はねぇ」
「ならなんで…」
「俺が裏切らなくても、いつか俺は死ぬ」
「、」
「病か、寿命か、任務中の事故か、失敗して殺されるか」
「……………」
「病気も寿命も、てめぇの身体のことはわかるから準備ができる。でもあとの二つは誰にも推測できねぇ」
「…………なんの、準備よ」
「今後も彼奴を護るための準備だ」
まっすぐ言い放たれたそれに目を瞠る。アイリッシュはどこまでも真面目で、ただただ、彼奴のことだけを想ってるらしい。
「彼奴は記憶がない。だから生まれたときからこの組織にいる。怪我も完治しねぇ、満足に状況も把握させられてねぇ状態で刷り込むように鍛えられて処刑人として自身の立場を確立させられて、失敗したならば殺されると覚え込ませられてる」
パリジャンのことは、連れ戻されてから初めて詳細を聞いた。
底抜けに明るく、知識の少し足りていないその様子に、馬鹿なのかと冷ややかな目を向けたこともあったし、なにがあろうと仕事を遵守する姿は気が狂っていると思っていたけど、中身が五歳ほどの子供と同等ならば、それも仕方ないことだ。
理由も知らず大きすぎる怪我を負って体の自由も利かないのに、体を酷使させられて、うまくできなければ殺すと脅されて、いくらサイズが乳幼児ではないからとは言え、中身はまだ言葉を話せるかどうかも怪しい齢の子供にそんなことをして、まともに育つわけがない。
さすがの私ですらその年齢の頃は月並みの人生を送っていたし、あまりに大きすぎる怪我をすれば仕事を後回しにしたり誰かに押し付けることを考える頭があるけれど、きっと彼奴は違うんだろう。
「俺もベルモットも常に側にいるわけじゃねぇけど、俺達がいるって示すことである程度抑制が働いてる。でも、片方が欠けたら、このバランスはあっさり壊れる」
「…海外と表が仕事場のベルモットじゃ見きれないでしょうね」
「ああ」
アイリッシュとベルモットが何故、こんなにも彼奴を大事にしているのかは知らない。
けれどそんな悲惨な五歳児をずっと見ていたのなら、哀れみを超えたなにかが生まれて、そのうち庇護欲を抱かせるのかもしれない。
「俺が消えたら、代わりに彼奴を逃してやってくれ」
「、彼奴が…私が何か言ったところで逃げるの?」
「わからねえ」
「なら、私に何をさせる気なの」
「彼奴がここを出たいって思ったときに逃してやってほしいだけだ」
「…………」
「まぁお前もお前の命がかかってんから無理にとは言わねぇけどな」
「………私が私の命がかかるような場所にいるのは彼奴が私を連れ戻したせいよ」
「それもそうだ」
あっさりと笑ったアイリッシュに眉根を寄せる。アイリッシュはまぁそういうことだと勝手に話を締めて、背を向けるとこの部屋唯一の扉に向かっていった。
「覚えたもんはお前のもんだ。彼奴に使わねぇでお前が使ってもいい」
「…自分の物じゃなかったらこんなきつい稽古受けないわよ」
「おー。身にするために次もがんばれよー」
ひらりと少し上げた右手を振って、そのまま扉から出ていく。
視界から消えた筋肉だるまに息を吐いて、ばたりと背中を地面につけて寝転がる。
妙なことに巻き込まれた。そう思わざるをえない。
「………あのとき、逃げなければよかったのかしら」
今更言ったところでどうなることでもないけれど、誰も聞いていないのだから愚痴を零して、目を瞑った。
「私の力は私のために使うわよ、アイリッシュ」
.
52/52ページ