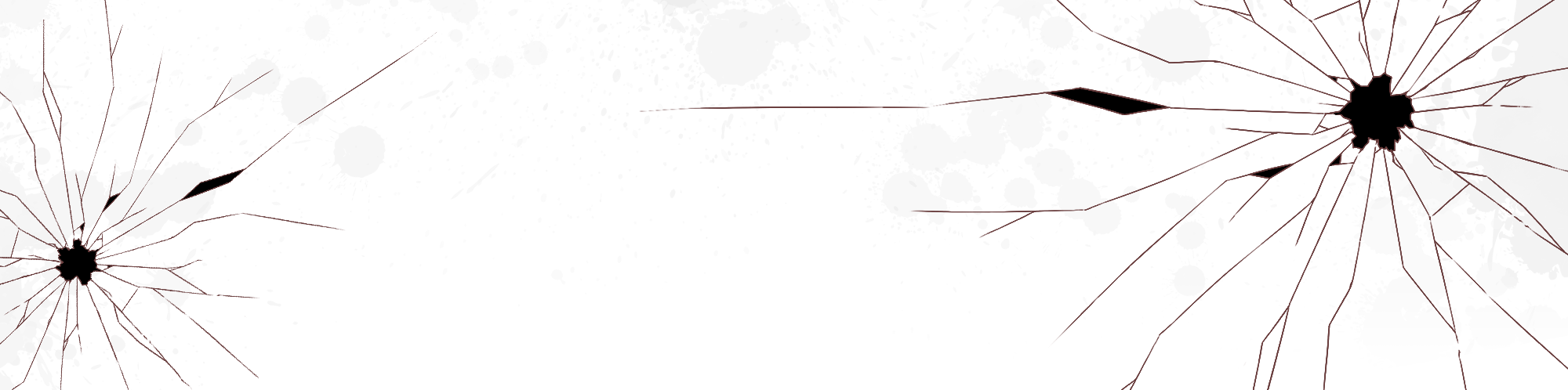二章 コランバインのバラード【前半】
「ふふ、雨祈さんはしっかり者なんですね。」
「ローゼンさんほどじゃなか。……それに、シスターとして当たり前のことばしちょるだけじゃけん」
なんだか二人の周りがほわほわしている。和んでいるなぁ。あんなことがあった後だけど少しずつ皆打ち解けてきている。
それは、なんとなく良い傾向なんじゃないか。
普通は仲良い人を殺そうなんて、思わないだろう?
「それにしてもどうして調理室なんかに……」
少し離れたところで、その様子を見つめながら談笑している架束と鑑がいた。
「前まで行けなかった所が開放されてたから、気になってさ。出口さん達もそうだったみたいだからし。」
なるほど、としか言えない。
なんだってオレだって同じ理由でここに来たわけだ。
「まぁ、この様子だと暫くしたら他の皆も来そうだな」
「有り得ることですね。そういえば、こちらをどうぞ。調理準備室にジャスミンティーの茶葉がありましたので」
鑑に礼を言い、ティーカップを受け取る。
いれたばかりのそれの芳ばしい香りが鼻腔をくすぐる。
「いやぁ、やっぱりあったかいお茶は飲むと安心するな。でも普通調理準備室に茶葉なんてあるもんなのか?」
調理準備室の横に調理室。その隣に被服室がある。
授業でしか料理をしないようなこの教室に、茶葉なんて嗜好品があることに違和感を覚える。
「私の以前通っておりました学校には、そのような物はありませんでしたが……架束様の母校ではどうでしたか?」
「……俺のところは無かったよ。調理実習自体そんな無かったし。というか準備室は生徒は入れなかった。」
「……まぁ、嗜好品なんて無い所が普通だよな。」
以前、ここの担当の教師がこっそり自分の趣味のものを集めていたのかもしれない。頭を捻ったところで何かを得られるわけでも無いので、オレは考えるのをやめた。
未だにお喋りを続けている出口とローゼンを眺めながら、世間話のようなものを三人でする。
「でもさ、伊織さんの件が起きた時はどうなるかと思ってたけど、皆立ち直りつつあるし安心したよ」
「架束様の仰る通りですね。シェリアお嬢様も御友人ができたようで、良かったです」
そう言ってローゼンに投げかける鑑の視線は優しいものだ。大切に思っているのがよく伝わる。
「友人かー……。オレ、まだあまり皆と馴染めてない気がする……。」
数日しか経ってないとはいえ、あまり心を開ける相手がいない。
「心配ありませんよ。超高校級の皆様が集まっているのですから、個性がぶつかり合うのは自然なことです。」
「鑑さんに賛成。俺も、仲がいいと言い切れるのはローゼンさんや儚火さんだけかな」
「なるほどな。確かに皆超高校級だった。」
学級裁判などに気を取られ、そんなことは忘れていた。
ここにいる人達もその称号を手にしているのだ。
鑑は執事、架束はイラストレーター 。
そして出口はシスターでローゼンは女王、そしてオレは幸運……。うん?
「待て、メンツが濃すぎないか!?」
「「え、今更(ですか)!?」」
確かに今更過ぎたかもしれない。
個性の強い十四人全員と仲良くしようなんて、ちょっと無謀な気もしてきていた。
でも、オレは諦めないぞ!仲良くなれるはずだ!