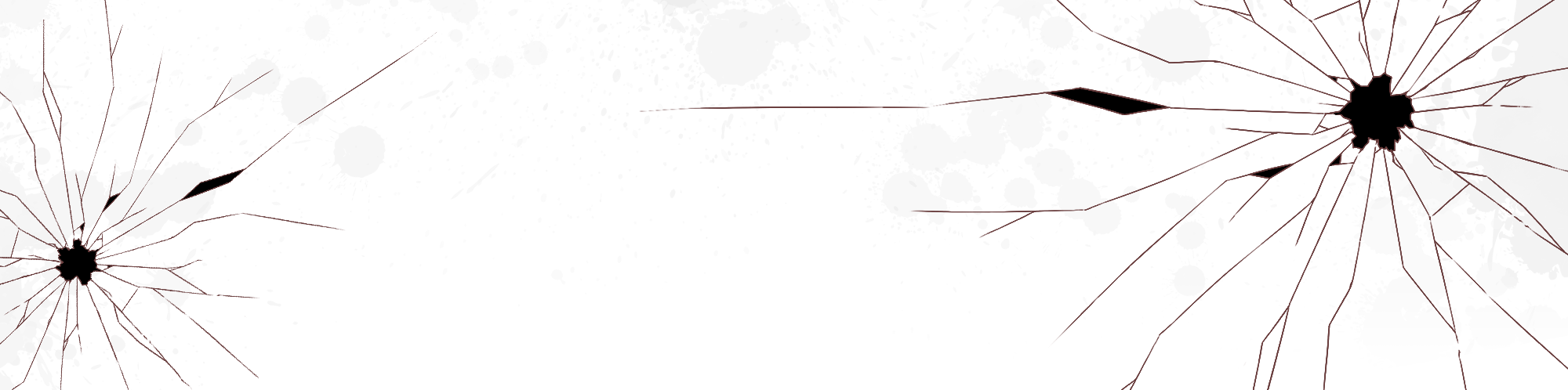二章 コランバインのバラード【前半】
少し眠気も出てくるほどに、十分に腹ごしらえをした。ついさっきまで探索で気を張っていたし、部屋に戻ってゴロッとしたいところだが我慢をする。今は呑気している暇は無い。
今日は雲一つない晴れ空で、やわらかい春風が吹いている。折角の天気だ、校庭へと走る。きれいな砂の上に花壇に続く真新しい足跡を見つけ、追ってみる。
「あ、大原さんもお花を見に来たんですか?今、かわいい花が咲いていますよ」
花壇では儚火が花の手入れをしていた。
「華道家って……庭師みたいなこともするのか?」
その手つきがあまりにも手馴れている感じだったので、不思議に思った。
オレの問いに儚火は、
「華道家だからというよりは私個人がやりたくてやっているんです。普通はこのようなことはしないと思います」
とにこにこと教えてくれた。流石超高校級がつくだけあって、植物への想いが大きい。
「今、ここの花壇にはダチュラが咲いています。でも少し寂しい気がして……何か植えたら楽しいんじゃないかなって。大原さんは何の花が良いと思いますか?」
突然オレの意見を聞かれ、少し慌てる。
「うーん……オレは花にあまり詳しくないからなぁ」
この季節はどんな花が咲いていたか、今までの記憶を辿ってみる。花はきれいだと思うが、いちいち観察するために足を止めるほどの興味はない。思い出そうにもなかなか難しい。
四月の花……春だから沢山咲いていると思うが、何がある?オレの人生で一番色濃く残っている花の記憶はないか?……。そういえば母の日は五月だな。一年に一度、母の日だけ花屋に足を運んだことを思い出した。
「カーネーション。まだ四月だからあるか分からないけど……咲いていたら、きっと華やかなんじゃないか?」
頑張って出した答えに、儚火はなるほど、と手を打った。
「それなら、四月から六月にかけての花なので大丈夫です!それにしても、そのチョイスは驚きました。私は、カーネーションと言ったら育てるというよりは購入する方を思い浮かべちゃいます」
でも、自分で育ててみるのも粋ですね、と儚火が笑う。華道家の彼女だが、魂自体が花で構成されているんじゃないかと思うくらい笑顔が眩しい。
「ダチュラは俯いているので、隣に上を向いているカーネーションを咲かせるのはいい対比になると思います。黄色のこの花には……白色のカーネーションが似合うかな」
そう言って儚火は、ダチュラに手を伸ばした。触ると被れることもあるみたいなので樹液などには一応注意しないといけない。そんな豆知識も話しながら。
そして儚火は不意にこちらを見て、
「その苗があるかは分からないのですが、モノゴンに言えばきっと用意してくれますよね。だって、こんな生活を強いられているんだからこれくらい許してくれないと!」
と怒り気味に話した。
「今まで死なんてほど遠い生活をしていたのに急にこんなことになるなんて。死が近づいて来るなら、私は生で対抗してやりますから!」
植物だって生きているんですよ、それを見て皆も活力を得てほしいんです。
悲しそうにしながらもそう意気込む彼女を見て、何とも言えない気持ちになった。
……。
「そういえば昔西に爆弾が落ちた後、そこの土地は数十年は緑が生えないって言われてたらしいな」
昔西に旅行した時、現地の人から聞いた話を思い出した。もう何年も前だが、少しのことで思い出すことができるほど、印象に残った話だったように思う。
「有名な話ですよね、でも戦後に崩れた瓦礫の間から赤い一輪の花が咲きました。それを見た人々は希望を抱き復興へと歩んでいったという……」
そうだ、その話だ。初めて聞いた時、オレはまだ幼かったのに感動したことを覚えている。どんな状況でも、希望があれば人は生きていけるのだと。
「希望を見出すものがあれば……か。それ、育てきったら儚火が生け花にするんだろ?楽しみだな」
希望はあるならあるだけいい。ここの花壇一帯に色んな花が咲き誇っているのを想像する。花について無学なオレでも楽しめる……小さくて、でも完璧な花畑だ。
「もちろんです!でも、生け花にするのはここを出てからですよ。育ちきるまでここにいるわけにもいきませんからね!」
ご尤もだな。
そう二人で笑った。ついでにオレも花壇の手入れの手伝いを約束した。
……。
「じゃ、またな」
そう言って、オレは第一校舎の方へと歩を進める。
そういえば、今までそっちにはあまり行っていなかったことを思い出したのだ。
「あ、大原さーん!」
花壇から数メートルほど離れたところで、何かを伝え忘れたのか儚火の声が飛んでくる。
「白いカーネーションの花言葉、知ってますか~!?『尊敬』に『純粋な愛』ですよ!今の私たちに必要な言葉ですよねー!」
それを知っていて提案したのか―そう期待しているような彼女の弾んだ声色。表情もよく見えないが輝いている気がする。だが生憎オレはそう言った言葉には疎いんだ。
そんな思いを引っ込めて、大きな声で彼女に返す。
「確かに、必要だな~!」
そうですよねー!
そんな彼女の声を背に、今度こそ第一校舎へと向かった。
25/25ページ