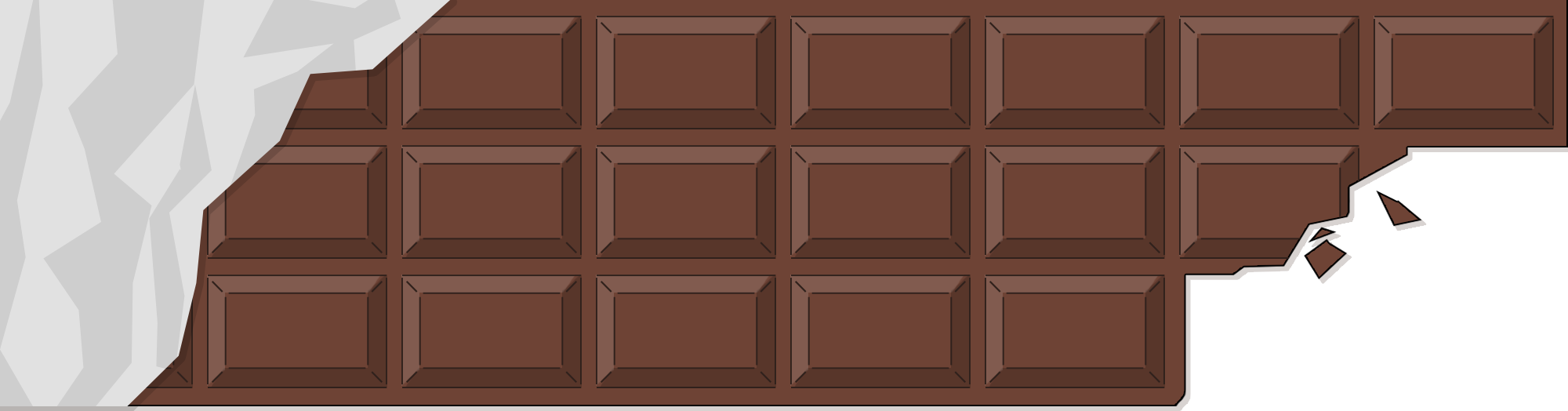チョコレートはキスの味
バレンタインデー。普段は持ち込み禁止のお菓子が見つかっても黙認してもらえたりするちょっと特別な日──というのは、甘酸っぱい青春を送る乙女だけのもの。
「聖。珍しいもの食ってんな」
──と、思っていた時期もあった。
世間がすっかりチョコレートの甘い香りを纏ったこの季節、南條がその菓子を買ったのはそれが理由と言えばそうであり、そうでないと否定するのもまた嘘にはならない。コンビニに行けば百円かそこらで買える値段のチョコレート菓子を、飲み物や軽食に紛れさせて一袋だけレジへと運んだのは気まぐれだった。
菓子を手にしたのは、なんとなく甘いものが食べたい気分だったから。その中でもチョコレート系のものを選んだのは、バレンタインデーだったから。
思惑通りとでも言うべきか、意中の相手の部屋でわざとらしくその菓子を食べていたら、そいつはちゃんと声をかけてくれた。南條は甘いのを飲み込み、想い人──北原に微笑みかけた。
「んー…なんとなく、甘いものが食べたいなって気分だったからね」
「へえ。テメーにも、んな気分の時があるんだな」
「あはは、それ偏見じゃない? 廉にはないの? 甘いものの気分、って時」
「甘いものの気分…か」
ふむ、と考え始めた北原を見ながら、もう一粒口に運ぶ。小さくて食べやすい大きさのそれはやっぱり甘くて、ビターにしておけばよかったかな、と思った。気持ち的には、ある意味ちょうどいいくらいの甘さかもしれない。
北原がじっと南條の手元を見つめた。正確には、手元の袋。そこから取り出された菓子が南條の口の中へと消えるまでを視線が追いかけてくる。
「なに? 甘いものの気分になっちゃった?」
「見てたら食いたくなってきた。味見させろ」
「味見、ねえ。ま、いいけど」
──と、そこまではいい。しかし北原はそう言って、口をパカリと開けたのだ。
え、とうっかり声を漏らしてしまったのも仕方ないと思う。自分で食べればいいのに、勝手に取ればいいのに。差し出すべきは手であって、口ではない。
なんと無防備なことだろうか。警戒心が薄い奴、とは常々感じているが、もしもこのチョコレートに毒が仕込まれていたらなんて疑念を抱くという発想すらないのだろう。自分の手で触れて硬さを確かめるとか、ビターなのかスウィートなのか色で想像してみるとか、そういうことは一切なしに南條の手を信じている。
目の前で袋を開けて食べ始めたものとはいえ、信用しすぎではないかと思う。もしもそれを告げたなら、テメーが疑いすぎだって言われそうだとも思うけれども。未開封なのか一度開けた袋なのかどうかは北原には確かめられない。一度開けて、一粒に、南條だけにわかる印をつけて何かを仕込んでおくことだってできるのだ。
例えばこの、ちょっと形が歪なやつに。
──好きだよ。
って、気持ち。
パカッと空いた間抜けな口の中へ、ポーンと放り込んでやった。
「ん。……んー…甘えな。テメーなんか入れたか?」
「チョコレートなんてそんなものだろ。ビターじゃないし、これ」
ドキリ。心臓が変な音を立てた。見抜かれたのかと思って笑顔で誤魔化す。好きって気持ちでチョコレートが甘くなるはずがない。
北原はそれきり黙って口を動かしていた。小さな一粒、あっという間に噛み砕いたらしい。
「……気分、ってだけじゃねーだろ」
再び開いた口は、そんなことを言った。また、心臓が変な音を立てて加速する。
これだから、北原が好きなのだ。
こっちを信用しているくせに、妙に鋭い。良からぬことを考えている時は絶対にバレる。良からぬこと、と言っても、自分の利益を最優先させる程度のことで、北原が不利益を被るような内容ではないが。いや、今回は、不利益かもしれない。
なんて言って誤魔化そうかなと、とりあえずの笑顔を貼り付けた。
「バレた? 実はそれ、廉にやろうと思って買ったんだよね」
「ハ? テメー自分で食い始めただろーが、有罪」
「まあまあ。甘いものの気分だったのも事実だし、食べたくなっちゃったからお先にいただこうかと思ってね」
「んだよそれ。俺にくれる気あったなら自分用と別にしとけよ」
「えー、そんなにたくさんはいらないし。というわけで、はい。残りはお前にやるよ。じゃあまた明日ね〜」
「あ、おい」
袋を押し付けて、ヒラヒラと振った手を掴まれることもなくドアの前までたどり着く。しかし部屋を出る直前、北原が、聖、と南條を呼んで引き留めた。
律儀に止まって振り返ってやると。
「そういや今日…、バレンタインだな」
──何を考えて、わざわざそう言ったのか。
読めない奴だと言われるのはこっちのはずで、脳みそと口が直結しているような北原の方ではないはずなのに。読めない奴だ、と南條は思った。
バレンタインにチョコレートなんて、友だちに渡すにしても、女の子じゃあるまい。ましてや南條がそんなタイプだとは北原だって思っていないだろうし、南條だってそんなつもりはない。なんにも知らないあいつにこの日チョコレートを渡した、という自己満足に浸るための安い菓子だった。男子校だし、話にも上がらなかったし、バレンタインなんて意識していないかと思っていたのに。
ああそういえば、こいつのルームメイトは年中バレンタインみたいな奴だっけ。
「そうだっけ? もう二月も半ば、か。道理でチョコレートが目につくわけだよなあ」
「ハッ、しらばっくれてんな。テメーが日付感覚なくす奴かよ、ボケたか?」
「んー、まだまだ十代だけど。お前の俺に対する絶大な信頼ってどこ由来? じゃあそれ、俺からの本命チョコってことで」
「安い本命だな」
「お高いチョコがよかった? それとも今から作ってやろうか、板チョコ溶かして固めただけのやつ」
「あ? 別にいらねーよ」
──あ、いらないんだ。
だよな、と納得したのも束の間、北原が眉をひそめる。
「テメーなんか勘違いしてんだろ。もうもらったからいらねーって意味だからな」
「あ…そうなの。いや、それってどういう意味? 廉にしては、結構回りくどいこと言ってるね」
「聖の回りくどさにゃ負けるぜ?」
「あはは、そうでもないよ? 俺は結構素直だって」
「じゃあ、聞かせろ」
北原はニヤリと笑った。その場から一歩も近づいてこないで、だけど引き寄せるみたいな目をして笑っていた。
南條は北原を見つめ返して、続きを待った。聞かせろって何を、と。テキトーにはぐらかして外に出てしまえばいいものを、甘ったるい魔法でもかけられてしまったのか。
「聖、俺にこれくれる気だったんだろ。これがチョコだってのと、今日がバレンタインデーだっての……関係あるなら、こっち来い」
「…………関係、なかったら?」
「ア? 有罪だ」
なにそれ。
アッハッハッ、と思わず笑ってしまった。間違いなく自分のところへと来ると、それさえも疑ってない。ああ、本当に、北原廉って奴は。
一歩、踏み出した。もう一歩、もう一歩。長い脚で狭い部屋、あっという間に北原の目の前へと戻ってきた。ポーカーフェイスじゃないところがいっそポーカーフェイスだよな、なんて考えながら前に立つ。ニヤニヤと笑っている北原の、チョコレート菓子の袋を持たされた方の手首を掴んでやった。
何すんだよ、と声を上げる北原の鼓動はきっと、南條ほどではなくても普段よりかは速いはず。速い、気がする。速い、と思う。いや、速い。
「……脈アリ、ってこと?」
「ハ?」
「俺、惚れ薬は仕込んでないはずなんだけど」
「はぁ??」
「やっぱり俺が甘くしちゃったのかもなあ、そのチョコ。悪いねえ」
「回りくどいのはやめる気ねーんだな。素直ってどの口が言ったんだ? 有罪」
「ちなみに俺的には、一応避けてやってるだけなんだけど。俺たち、友だちだろ?」
「似合わねー台詞吐きやがって。俺が用意する気もなかったけどな、テメーがこういうことするなんてもっと思ってなかったんだよ。こっちに来たっつーことは、関係あんだろ? 言わせてやる」
「俺がこっちに来ないって思ってなかったくせによく言うよねえ」
ガサリ、中の菓子を取ろうとしたら思ったよりも大きな音がした。一つ摘まんで、見せつけるように持ち上げる。動きを目で追いかけるところ、野生動物みたいだなあと思ってクスッと笑った。
次のアクションを待ってくれているらしい。黙ったままの唇に、チョコレート菓子でキスをした。
「俺の気持ち、受け取って」
薄っすら開いたところへ、甘いモノを滑り込ませて。はっきりと告げてやってもいいけれど、今日はこの甘さに想いを込める日だからあえては言わない。
「……甘えな」
ニヤリと笑ったその顔が、やっぱり好きだなあ、と思った。両想いだったらいいなあ、と夢見たことがないわけじゃない。両想いのはずがないと決めつけたこともなかったわけじゃない。だけどそういうのを置いといて、こいつはずっと傍にいるんだろうなあ、とは確信していた。南條が、それを望んでいるから。
だけどまさか、そう、やっぱり"まさか"、こういう展開になるとは思わなかった。予想外、ある意味いつものこと。どこまで見透かしての行動なのだろうかと探ってみても、それを知るのは北原本人だけだ。ここまできたらいっそ、返事としてキスの一つでもしてくれたらいいのに──と思った時には──、。
1/1ページ