拝啓、風見鶏だった僕へ。
センリが休職に入ってひと月。
休みの延長が決定して、会社から連絡が入った。
休みの延長を許可しないという返事が来るのかと身構えたが、相手が人事課の蛇場見で安堵の息を吐いた。
休職後に事務課の誰からも連絡がなかったのは、個々が連絡しないようにと通達していたかららしい。
数名からバラバラに連絡が入ると一回一回返信しなければならないし、それは負担になる。だから連絡は蛇場見が責任を持って一手に引き受けることにしていた。
『秤の主治医の初田に確認をとって、そうしろと言われたんだ。あれでもちゃんと医者だな』
「……そう、だったんですね」
知らないところで先生や人事課長に守られていた事を知り、感謝と申し訳無さが同時に押し寄せる。
田井多はともかく、事務課には世話焼きなおばさんや専務もいるから、彼らのうち誰かしらが「早く戻ってね」「まだ治らないのか」と急かすような連絡をして来るものと思っていた。
『その後、体調はどうだ』
蛇場見の声音はセンリを労るもので、不覚にも泣きそうになる。
「すみません、まだ、起きているのが、やっとの日もあります」
『そうか。こちらは大丈夫だから、ゆっくり休め。復帰後の仕事も、体調が安定するまで勤務時間の短縮と別の部署に移動するようにと言っていたから、秤が嫌でないなら製造部に移るといい。そこなら障害者枠があるから、サポート体制が整っている』
「製造部、ですか」
センリの働く会社は製造、デザイン、マーケティングや事務、営業、販売など多様な部署で成り立っている。
あまり他の部署との交流はないため、製造部にどういう人がいるのかはわからない。
障害者枠もあるなら、そう負担の大きな仕事をふられるわけではないと思う。
「はい、それでお願いします」
『わかった。こちらで準備をしておく。詳しくはまた日が近くなってから話そう』
「ありがとうございます」
電話が切れて、肩の荷が下りた。
少なくとも、復帰してすぐまた八時間フルタイム勤務ということはない。
初田も言っていた。
うつ病に限らず、休職があけたあと多くの人は復帰してしばらくは三、四時間の軽い業務から慣らしていくものらしい。
「なーぅ」
豆大福がネズミのおもちゃをくわえて持ってきた。センリの膝に乗って、遊んでほしいとせがんでいる。
センリが家にいる時間が増えたから、いつも上機嫌だ。
喉の下に触れると、ゴロゴロと喉を鳴らしてセンリにすり寄る。
「センリ、電話終わったの?」
「ばあちゃん。うん。人事課長が、部署移動させてくれるって」
「それは良かったわ。事務だとセンリは残業ばかりで、いつも疲れた顔をしていたもの。次の部署は負担の少ないところだといいわねぇ」
チヨの言葉に、センリは心から頷く。
「お昼ごはん、食べられそう? 今日は暑いから冷汁にしてみたんだけど」
「少しなら、たぶん」
治療前よりは、固形物を食べられるようになってきた。味覚がすぐに戻るわけではないから、味のないガムを食べるような違和感はまだ残っている。
食事とサプリメントで補うことで、時間をかけて改善されると初田は言っていた。
ビタミンAが不足すると夜目がききにくくなるのと同じ。食事をとれなくなったことで不足してしまった栄養素を補う必要がある。
「なーー」
「マメもおやつ食べるって?」
豆大福は、細長いチューブタイプのおやつがお気に入りだ。太らないように一日一本までと決めているけれど、もっと欲しいとねだるから困る。
「あらら、ごめんなさいね。チューチューは昨日なくなってしまったのよ。買ってくるのを忘れていたわ」
「うにゃーー」
おやつ抜きと言われてちょっと不満げだ。
「僕、買ってくるよ」
「大丈夫? 今日は起きていられる?」
「うん。今は大丈夫」
朝の九時くらいまではだるくて起き上がるのが辛いが、昼近くになればいくらか頭がスッキリして起きられる。
病気を知らない人が見たら、ただのサボり魔にしか見えないだろう。
スマホがピコンと音を立てて、メッセージの着信を告げる。
ポップアップで、ミオからだとわかる。
『海、きれいだよ』
たぶん七里ヶ浜の駅あたりで撮影したものだ。青い空に江ノ島が映える。
文字でのやり取りなら聴力は関係ないから、メッセージでのミオは直接話すよりも|饒舌《じょうぜつ》だ。
感動で泣く猫のスタンプを押す。
グッと親指を立てるスタンプが返ってくる。
こんなふうに意味もない他愛のないやり取りをする相手は、これまでいなかった。
学生時代は祖父母に遠慮して、部活に入らずまっすぐ帰宅していた。
友だちを家に呼ぶのも、気が引けてしたことがない。
友だちの家に行くと、自分に親がいないのを実感してしまうから、友だちの家を訪問するのも好きではなかった。
そうやって当たり障りなく、人と一定の距離を保っていたから、本当に友だと言える人は片手の指の数より少ない。
気まぐれに、膝に乗っている豆大福を撮って送る。
数分も待たずに、『かわいい!』というスタンプが連打された。
『豆大福だよ』
『ネコちゃんだよね?』
『名前が豆大福』
スマホの画面を遮るように、豆大福が手に乗ってきた。
「ふにゃ」
「マメ、見えないよ」
「携帯電話よりわたしを見てよー、って言ってるのよ」
「……じいちゃんも新聞読むの、じゃまされるもんね」
きょうだいのいないセンリにとっては年の離れた妹みたいなもので、豆大福はすっかり甘えん坊に育った。
昼を食べるときもずっとセンリにくっついている。
「きゅうりをできる限り小さめに切ったから、食べやすいと思うのだけど」
「ありがとう」
少しは塩気を感じるようになってきたから、だいぶ進歩した。
すりごまと細切りの大葉が入っていて、味覚が正常だったらすごく美味しいはずなのにななんて考えて|咀嚼《そしゃく》する。
少しだけ冷汁を飲んで、センリはショルダーバッグをかけてサンダルをつっかける。
耳にはイヤーマフと呼ばれる耳あてをつける。
センリは過敏性聴覚障害(かびんせいちょうかくしょうがい)というものになっていると、初田に言われた。
人が気にならないような音が神経にさわる症状だ。現代医学で治す方法はないため、対処法を学んでいくしかないという。
その話を聞いた利男が、職場の人に聞いて買ってきてくれた。
見た目はヘッドホンだが、大きな音を和らげてくれるアイテムだ。
警察などの射撃訓練で耳へのダメージを防ぐために使われることもあるらしい。
つけてみると確かに甲高い音が和らいで、それでいて日常会話や生活音はきちんと聞き取れる。
「それじゃあ行ってくる」
「無理だと思ったら途中で帰ってきていいからね」
「うん」
徒歩圏内にあるスーパーで、ネコのおやつ一つ買って帰るのもまともにできなくなったらいよいよ危うい。
商品名を忘れてしまわないように、メモに空き袋を貼り付けて持ってきた。
「あらセンリ君じゃない。大丈夫なの?」
声をかけてきたのは、公園前で井戸端会議に興じていた、近所のおばさん方だ。
みんな、センリが秤夫妻に引き取られた頃からこのあたりに住んでいるため、秤家の事情を知っている。
センリが病気療養で休職していることも、とっくに近所のおばさんたちは知っている。
「はい。今日は起きていられます」
「育ててくれたおばあちゃんたちに恩返しできるようにがんばりなさいね。センリ君はまだ若いんだから、すぐ良くなるわよ」
「そうよー、アタシもうつ病について調べたんだけどさ、海藻サラダとか、牛肉がいいんだって。食べてみなさいな」
おばさんたちに悪気や悪意がないのはわかる。善意で言ってくれているけれど、正直どう返答していいかわからない。
昨日は起きていられなくてずっと布団の中だったし、今日はたまたま具合がいいだけだ。
固形物を飲み込むのが辛いというのを言って理解してもらえるかわからない。
試したくても、喉を通らなければ吐き戻すだけ。食材の無駄だ。
治療は一進一退で、口で言うほど簡単じゃない。
おばさんたちが求める答えはきっと、「がんばってじいちゃんばあちゃんのために治すよ」ということなのだろう。
(あぁ、相手の望む言葉を答えるのって、しんどいな)
なんでこれまでそうやって生きていたのか、今となってはわからない。
近所付き合いはこれからも続くから、下手なことを言えない。
センリはあいまいに笑ってやり過ごす。
ずっとあいまいに、波風を立てないように、風見鶏のように生きてきたから、いまさら自分を強く持って本音を言うなんて、無理だった。
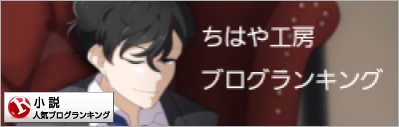
休みの延長が決定して、会社から連絡が入った。
休みの延長を許可しないという返事が来るのかと身構えたが、相手が人事課の蛇場見で安堵の息を吐いた。
休職後に事務課の誰からも連絡がなかったのは、個々が連絡しないようにと通達していたかららしい。
数名からバラバラに連絡が入ると一回一回返信しなければならないし、それは負担になる。だから連絡は蛇場見が責任を持って一手に引き受けることにしていた。
『秤の主治医の初田に確認をとって、そうしろと言われたんだ。あれでもちゃんと医者だな』
「……そう、だったんですね」
知らないところで先生や人事課長に守られていた事を知り、感謝と申し訳無さが同時に押し寄せる。
田井多はともかく、事務課には世話焼きなおばさんや専務もいるから、彼らのうち誰かしらが「早く戻ってね」「まだ治らないのか」と急かすような連絡をして来るものと思っていた。
『その後、体調はどうだ』
蛇場見の声音はセンリを労るもので、不覚にも泣きそうになる。
「すみません、まだ、起きているのが、やっとの日もあります」
『そうか。こちらは大丈夫だから、ゆっくり休め。復帰後の仕事も、体調が安定するまで勤務時間の短縮と別の部署に移動するようにと言っていたから、秤が嫌でないなら製造部に移るといい。そこなら障害者枠があるから、サポート体制が整っている』
「製造部、ですか」
センリの働く会社は製造、デザイン、マーケティングや事務、営業、販売など多様な部署で成り立っている。
あまり他の部署との交流はないため、製造部にどういう人がいるのかはわからない。
障害者枠もあるなら、そう負担の大きな仕事をふられるわけではないと思う。
「はい、それでお願いします」
『わかった。こちらで準備をしておく。詳しくはまた日が近くなってから話そう』
「ありがとうございます」
電話が切れて、肩の荷が下りた。
少なくとも、復帰してすぐまた八時間フルタイム勤務ということはない。
初田も言っていた。
うつ病に限らず、休職があけたあと多くの人は復帰してしばらくは三、四時間の軽い業務から慣らしていくものらしい。
「なーぅ」
豆大福がネズミのおもちゃをくわえて持ってきた。センリの膝に乗って、遊んでほしいとせがんでいる。
センリが家にいる時間が増えたから、いつも上機嫌だ。
喉の下に触れると、ゴロゴロと喉を鳴らしてセンリにすり寄る。
「センリ、電話終わったの?」
「ばあちゃん。うん。人事課長が、部署移動させてくれるって」
「それは良かったわ。事務だとセンリは残業ばかりで、いつも疲れた顔をしていたもの。次の部署は負担の少ないところだといいわねぇ」
チヨの言葉に、センリは心から頷く。
「お昼ごはん、食べられそう? 今日は暑いから冷汁にしてみたんだけど」
「少しなら、たぶん」
治療前よりは、固形物を食べられるようになってきた。味覚がすぐに戻るわけではないから、味のないガムを食べるような違和感はまだ残っている。
食事とサプリメントで補うことで、時間をかけて改善されると初田は言っていた。
ビタミンAが不足すると夜目がききにくくなるのと同じ。食事をとれなくなったことで不足してしまった栄養素を補う必要がある。
「なーー」
「マメもおやつ食べるって?」
豆大福は、細長いチューブタイプのおやつがお気に入りだ。太らないように一日一本までと決めているけれど、もっと欲しいとねだるから困る。
「あらら、ごめんなさいね。チューチューは昨日なくなってしまったのよ。買ってくるのを忘れていたわ」
「うにゃーー」
おやつ抜きと言われてちょっと不満げだ。
「僕、買ってくるよ」
「大丈夫? 今日は起きていられる?」
「うん。今は大丈夫」
朝の九時くらいまではだるくて起き上がるのが辛いが、昼近くになればいくらか頭がスッキリして起きられる。
病気を知らない人が見たら、ただのサボり魔にしか見えないだろう。
スマホがピコンと音を立てて、メッセージの着信を告げる。
ポップアップで、ミオからだとわかる。
『海、きれいだよ』
たぶん七里ヶ浜の駅あたりで撮影したものだ。青い空に江ノ島が映える。
文字でのやり取りなら聴力は関係ないから、メッセージでのミオは直接話すよりも|饒舌《じょうぜつ》だ。
感動で泣く猫のスタンプを押す。
グッと親指を立てるスタンプが返ってくる。
こんなふうに意味もない他愛のないやり取りをする相手は、これまでいなかった。
学生時代は祖父母に遠慮して、部活に入らずまっすぐ帰宅していた。
友だちを家に呼ぶのも、気が引けてしたことがない。
友だちの家に行くと、自分に親がいないのを実感してしまうから、友だちの家を訪問するのも好きではなかった。
そうやって当たり障りなく、人と一定の距離を保っていたから、本当に友だと言える人は片手の指の数より少ない。
気まぐれに、膝に乗っている豆大福を撮って送る。
数分も待たずに、『かわいい!』というスタンプが連打された。
『豆大福だよ』
『ネコちゃんだよね?』
『名前が豆大福』
スマホの画面を遮るように、豆大福が手に乗ってきた。
「ふにゃ」
「マメ、見えないよ」
「携帯電話よりわたしを見てよー、って言ってるのよ」
「……じいちゃんも新聞読むの、じゃまされるもんね」
きょうだいのいないセンリにとっては年の離れた妹みたいなもので、豆大福はすっかり甘えん坊に育った。
昼を食べるときもずっとセンリにくっついている。
「きゅうりをできる限り小さめに切ったから、食べやすいと思うのだけど」
「ありがとう」
少しは塩気を感じるようになってきたから、だいぶ進歩した。
すりごまと細切りの大葉が入っていて、味覚が正常だったらすごく美味しいはずなのにななんて考えて|咀嚼《そしゃく》する。
少しだけ冷汁を飲んで、センリはショルダーバッグをかけてサンダルをつっかける。
耳にはイヤーマフと呼ばれる耳あてをつける。
センリは過敏性聴覚障害(かびんせいちょうかくしょうがい)というものになっていると、初田に言われた。
人が気にならないような音が神経にさわる症状だ。現代医学で治す方法はないため、対処法を学んでいくしかないという。
その話を聞いた利男が、職場の人に聞いて買ってきてくれた。
見た目はヘッドホンだが、大きな音を和らげてくれるアイテムだ。
警察などの射撃訓練で耳へのダメージを防ぐために使われることもあるらしい。
つけてみると確かに甲高い音が和らいで、それでいて日常会話や生活音はきちんと聞き取れる。
「それじゃあ行ってくる」
「無理だと思ったら途中で帰ってきていいからね」
「うん」
徒歩圏内にあるスーパーで、ネコのおやつ一つ買って帰るのもまともにできなくなったらいよいよ危うい。
商品名を忘れてしまわないように、メモに空き袋を貼り付けて持ってきた。
「あらセンリ君じゃない。大丈夫なの?」
声をかけてきたのは、公園前で井戸端会議に興じていた、近所のおばさん方だ。
みんな、センリが秤夫妻に引き取られた頃からこのあたりに住んでいるため、秤家の事情を知っている。
センリが病気療養で休職していることも、とっくに近所のおばさんたちは知っている。
「はい。今日は起きていられます」
「育ててくれたおばあちゃんたちに恩返しできるようにがんばりなさいね。センリ君はまだ若いんだから、すぐ良くなるわよ」
「そうよー、アタシもうつ病について調べたんだけどさ、海藻サラダとか、牛肉がいいんだって。食べてみなさいな」
おばさんたちに悪気や悪意がないのはわかる。善意で言ってくれているけれど、正直どう返答していいかわからない。
昨日は起きていられなくてずっと布団の中だったし、今日はたまたま具合がいいだけだ。
固形物を飲み込むのが辛いというのを言って理解してもらえるかわからない。
試したくても、喉を通らなければ吐き戻すだけ。食材の無駄だ。
治療は一進一退で、口で言うほど簡単じゃない。
おばさんたちが求める答えはきっと、「がんばってじいちゃんばあちゃんのために治すよ」ということなのだろう。
(あぁ、相手の望む言葉を答えるのって、しんどいな)
なんでこれまでそうやって生きていたのか、今となってはわからない。
近所付き合いはこれからも続くから、下手なことを言えない。
センリはあいまいに笑ってやり過ごす。
ずっとあいまいに、波風を立てないように、風見鶏のように生きてきたから、いまさら自分を強く持って本音を言うなんて、無理だった。
