夢で満ちたら
店を出たミチルとユメ。
ミチルは、まず近くの店の前にいる優しそうな雰囲気のおじいさんに声をかけた。
おじいさんは小柄な背を丸め、水タバコをふかしている。
紙巻きタバコのような嫌な煙たさはなく、タバコとは思えないような甘い香りがしている。
「おじいさん。あの、ご迷惑でなかったら、小さい頃の夢と今のお仕事を聞いてもいいですか?」
「おお、どうしたんだねお嬢さん。道に迷ったのかね」
「え、いえ。道には迷っていません」
「お前さん、人生の岐路で迷ったような顔をしておる。もう成人しているのに、親を見失った幼児のような」
顔を見ただけでわかるのは、年の功というものだろうか。
おじいさんが言うことは当たっていた。
ミチルは自分の価値が見出だせず、この先どんな仕事についたらいいかわからず、迷っている。
「あの、ワンダーウォーカーの店長に言われたゲームなんです。三十人に、小さい頃の夢と今の仕事を聞いてきなさいって」
「……わしの小さい頃の夢は、早く戦争が終わってたらふくうまいもんを食べることだったの。まだ十にも満たない子どもで、食えるものは一日一食、芋のツルしかないくらいに、食うに困っていた。今は亡くなった嫁さんの実家である、このペットショップを継いで営んでおる」
おじいさんの後ろには、小さなペットショップがある。開いている扉の向こうには、犬猫などの動物でなく、小鳥や金魚などの省スペースで飼えるペットが見える。
「そう、なんですね。お話してくださって、ありがとうございます」
「食べ物に困らないし、争いもない。いくらでも道がある。お嬢さんたちはいい時代に生まれて幸せだな」
戦乱の時代をのりこえてきた人に言われると、胸にくる。
おじいさんは夢を見ることすらできず、生きるだけで精一杯だった人。悩み事が「なりたい仕事がわからない」だなんて、きっとおじいさんから見たら贅沢なことなのだ。
ユメは真剣な顔をして、おじいさんの話をノートに書いた。
おじいさんにもう一度お礼を言って、次の人を探す。
「ミチルちゃん、ついでにこの商店街でおつかい済ませちゃおうよ」
「おつかい忘れてなかったんだね」
「もちろんだよー。あ、そこで野菜買えるよ」
青果店の前に、威勢の良い声を張り上げるおじさんとおばさんが立っている。
頼まれたレタスとトマトを買いつつ、ユメはおばさんに声を質問する。
「ねえねえおばちゃん。あのね、小さい頃の夢と今のお仕事教えて。ワンダーウォーカーで言われてね、いろんな人に聞いてくるゲームをしている最中なの」
「あらま、それは変わったゲームだねえ。小さい頃はアイドルに憧れていたわね。聖子ちゃんが大好きで、親におねだりしてカセットテープを買ってもらって、擦り切れるまで聞いたよ」
「お前はアイドルって柄じゃあねえよなあ」
旦那さんがケラケラ笑って野菜を買い物袋に詰めてくれて、その脇腹におばさんの肘鉄がクリーンヒットした。
「悪かったねえ柄じゃないアイドルなんか夢見て。今は見ての通り八百屋さ。旦那の実家だからこうして手伝うようになったけれど、お客さんと話すのが楽しくて、意外と自分に合っている気がするわねえ。テレビで歌えないけど、商店街のアイドルも悪くないってね。この人、あたしがいないとすーぐサボるんだから」
「へーへー。商店街のアイドルを嫁にできて幸せだなあ俺ぁ」
軽口を叩きながらも、二人ともこの仕事が好きでやっていると言うのが見ていて伝わってくる。
「お話、ありがとうございました」
青果店で深く頭を下げ、店を離れた。
近くにあるカフェのテラス席でお茶をしている親子に声をかける。幼い女の子を連れたお母さんだ。
「ねえねえ、小さい頃の夢と今のお仕事教えて。そういうゲームをしているの」
「面白いゲームね。私、小さい頃はケーキ屋さんになりたかったの。ショートケーキが大好きでね。ケーキに囲まれて過ごしたいなあって」
「わかるわかる。ケーキ美味しいから、あたしも好き」
ユメの反応に、お母さんも楽しそうに頷く。
「それで高校を出た後は調理師の専門学校に行ったんだけど、そこでパン作りの授業をしたらパンの歴史と奥深さにハマっちゃってね。バターや塩の配合一つで全く違うものができるのが楽しくて。目標が途中で変わって、それで今ではパン屋さんよ。いつか自分の店を持つために、そこのベーカリーで修行しているの」
「ママのパン、おいしーにょ」
女の子は、まるで自分のことのように誇らしげだ。
「あなたは大きくなったら何になるの?」
ミチルが聞くと、女の子は胸を張ってVサインを出す。
「まーたん、ぷいきゅあになゆの」
「そっか、なれるといいね」
「ん! なったら、おねーたんたすけてあげゆね」
まーたんがなりたいのは、人気アニメの魔法少女。
したったらずな口調で、可愛い約束をしてくれる。自分にもこんな頃があったな、なんて微笑ましくなる。
この子もいつか、魔法少女になれるわけがないとわかって悲しむ日が来るんだろうか。そんな日が来てほしくないなと思う。
まーたんにバイバイをして、また別の人の夢を聞きに行く。
精肉店で買い物をしていた女性。ミチルの母より少しだけ若いその人も、質問に丁寧に答えてくれる。
「子どもの私に、夢はなかったわ。片親でお金がないから、進学を望めなかったし。高校を卒業してすぐ結婚して、二年前に離婚したわ。今の私に夢があるとしたら、息子の夢を応援すること。そのために、スーパーで品出しをしているの」
女性の生い立ちを聞き、ミチルは後ろめたさ……罪悪感を覚えた。
父は大学卒業までの学費を出してくれたから、奨学金を借りることもなかった。
お金がなくて進学を諦める人はきっと多い。
その人達から見たら、大学に行きたくなかったと言うミチルは、身の程知らずでわがままな人間だろう。
ノートには少しずつ、いろんな人に聞いた話が集まっていく。
幼い頃の夢を叶えた人はゼロに近い。
ほとんどの人は、夢見ていたものとは違う仕事に就いている。
伴侶の家の仕事を継ぐこともある。それが天職という人もいる。
夢をみず、生活費のためになんとなくで適当に選んだバイトをする人もいる。
みんなの話を聞くにつれてわかってくるのは、ミチルとユメが狭い井戸《セカイ》しか知らない甘ちゃんだったということ。
歩に「糖蜜の井戸の中にいるオタマジャクシだ」と例えられたが、その通りだと自覚した。
何も見えていなかった。
父は歩を馬鹿だと言っていたけれど、きっと、本当に馬鹿なのはミチルだ。
親に与えられたレールを言われるまま歩くだけの馬鹿。
指示に従ったのは自分なのに、レールを歩かせた父に不満を抱く馬鹿。
このゲームはきっと、ミチルとユメに気づかせるためのものだった。
あと一人で三十人。
最後に話しかけたのは、竹ボウキを持って掃除をしていた男性だ。
「ねーねー。子供の頃の夢と、今なにをしているか教えて」
英国紳士のようなスーツに中折れ帽をかぶっている。高身長で、顔はモデル顔負けに整っている。
男性はのんびりした口調で答える。
「マッドハッターに答えのないなぞなぞを出すなんて、粋《いき》ですね」
「マッドハッター?」
「病院の先輩や同僚につけられたあだ名です。変人だから、マッドハッター」
「マッドハッターさんはなにをしている人?」
「さっきまでは玄関の掃除をしていました。今はあなたとお話ししています」
「それはそうだけど、そうじゃなくて、ええっと、うーんと、……小さい頃つきたかった職業と、今のお仕事を教えて欲しいんだよ」
のらりくらりした発言に、ユメが珍しく翻弄されている。
わざと斜め上のことを言っているのか、本当にずれているのか。男性はひとしきり笑ってから答えてくれる。
「七才の頃から精神科医を目指していました。今は独立してクリニックを営んでいます。わたしにとっては最良の道です」
男性は自分の背後を手のひらで示す。
道を挟んでワンダーウォーカーの真向かいにある建物の扉には、初田《はった》ハートクリニックと書かれた札がついていた。
「これはわたしにとっての最良であり、あなた方にとっての正解ではありません」
「どゆこと?」
首をかしげるユメに、男性は答える。
「たとえば君のお父さんが内科の開業医で、新しく精神科を設立したいから精神科医になりなさいとお父さん言われたら、なりますか? 精神科医独立の資格を得るには医大を出た後、精神科のある病院で五年実習をしないといけません。その頃あなたは三十五才になっています」
「えー、やだよ! あたし大学いけるほど頭良くないし、医者になりたいなんて思ったことないもん」
「そうでしょう。わたしと同じ医者であったとしても、個人病院を持ちたい医師から見たら、独立は羨む道。大病院で大成したい医師から見れば、愚かな道。わたしの正解は他人の不正解。白か黒かの二択では答えられない。だからあなた達の問いは、正しい答えのないなぞなぞなんです」
「そっか。じゃあ、あたしの正解の道ってなんだろう」
「それはわたしにもわかりません。道は、前にありません。自分が歩いた後ろにできるものですから。振り返ってから初めて、あの時ああしていればよかった、この道を選んでよかったと、思うものです」
言われて、ミチルもユメも自分の後ろを振り返る。
そこにはごく普通の商店街がある。
「世界は夢でできているんですよ」
「……あの、ここは夢じゃなくて、現実ですよね?」
不思議なことを言い出す男性。ミチルが聞き返すと、ポケットからいちご飴を二つ出してミチルとユメの手に一つずつ乗せる。
「これは夢の結晶です。この飴が君の手に届くまでに、どれだけの夢が集まっているか、わかりますか」
「飴が夢? ねえマッドハッター。それはなぞなぞなの?」
「いいえ。まず、製菓会社の企画部が企画立案します。製造部の人が試作を繰り返します。そしてコレだと思う味のものができたら、デザイン部がパッケージを作ります。作るだけでは売れないので、営業部の人があちこちに出向き、宣伝部の人がCMやチラシを作ります。販売決定したら工場で作り、配送の人が店に運ぶ。ここに来る過程の人、誰が欠けてもこのいちご飴はここに存在しません。この仕事に就きたくて、消費者に届けたくて頑張った人がいるから、いちご飴はここにあるのです」
飴一つについて、そこまで壮大なスケールで語られるとは思っていなかった。
というか、そこまで深く考えて飴を食べたことがない。
ミチルだけでなく、ユメも目をパチクリさせている。
「これを食べて、自分もこんなお菓子を作りたいと思う子がいたら、パティシエが生まれます。こんなパッケージを作りたいと思う子がいたら、デザイナーが生まれます。夢は夢を繋いでいきます。あなた達が歩く道もいつか、誰かの夢になるんです」
ミチルがこんなに悩んで泣きながら歩いた道でも。
男性が言うように、いつか誰かの夢に繋がるんだろうか。
「わたしは初田初斗《はったはつと》。あなた達のことは歩から聞いていました。ミチルさん、ユメさん。ふたりの未来が、夢で満ちることを願っています」
初田はにっこりと微笑んで、ミチルとユメの背を押した。
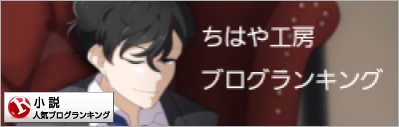
ミチルは、まず近くの店の前にいる優しそうな雰囲気のおじいさんに声をかけた。
おじいさんは小柄な背を丸め、水タバコをふかしている。
紙巻きタバコのような嫌な煙たさはなく、タバコとは思えないような甘い香りがしている。
「おじいさん。あの、ご迷惑でなかったら、小さい頃の夢と今のお仕事を聞いてもいいですか?」
「おお、どうしたんだねお嬢さん。道に迷ったのかね」
「え、いえ。道には迷っていません」
「お前さん、人生の岐路で迷ったような顔をしておる。もう成人しているのに、親を見失った幼児のような」
顔を見ただけでわかるのは、年の功というものだろうか。
おじいさんが言うことは当たっていた。
ミチルは自分の価値が見出だせず、この先どんな仕事についたらいいかわからず、迷っている。
「あの、ワンダーウォーカーの店長に言われたゲームなんです。三十人に、小さい頃の夢と今の仕事を聞いてきなさいって」
「……わしの小さい頃の夢は、早く戦争が終わってたらふくうまいもんを食べることだったの。まだ十にも満たない子どもで、食えるものは一日一食、芋のツルしかないくらいに、食うに困っていた。今は亡くなった嫁さんの実家である、このペットショップを継いで営んでおる」
おじいさんの後ろには、小さなペットショップがある。開いている扉の向こうには、犬猫などの動物でなく、小鳥や金魚などの省スペースで飼えるペットが見える。
「そう、なんですね。お話してくださって、ありがとうございます」
「食べ物に困らないし、争いもない。いくらでも道がある。お嬢さんたちはいい時代に生まれて幸せだな」
戦乱の時代をのりこえてきた人に言われると、胸にくる。
おじいさんは夢を見ることすらできず、生きるだけで精一杯だった人。悩み事が「なりたい仕事がわからない」だなんて、きっとおじいさんから見たら贅沢なことなのだ。
ユメは真剣な顔をして、おじいさんの話をノートに書いた。
おじいさんにもう一度お礼を言って、次の人を探す。
「ミチルちゃん、ついでにこの商店街でおつかい済ませちゃおうよ」
「おつかい忘れてなかったんだね」
「もちろんだよー。あ、そこで野菜買えるよ」
青果店の前に、威勢の良い声を張り上げるおじさんとおばさんが立っている。
頼まれたレタスとトマトを買いつつ、ユメはおばさんに声を質問する。
「ねえねえおばちゃん。あのね、小さい頃の夢と今のお仕事教えて。ワンダーウォーカーで言われてね、いろんな人に聞いてくるゲームをしている最中なの」
「あらま、それは変わったゲームだねえ。小さい頃はアイドルに憧れていたわね。聖子ちゃんが大好きで、親におねだりしてカセットテープを買ってもらって、擦り切れるまで聞いたよ」
「お前はアイドルって柄じゃあねえよなあ」
旦那さんがケラケラ笑って野菜を買い物袋に詰めてくれて、その脇腹におばさんの肘鉄がクリーンヒットした。
「悪かったねえ柄じゃないアイドルなんか夢見て。今は見ての通り八百屋さ。旦那の実家だからこうして手伝うようになったけれど、お客さんと話すのが楽しくて、意外と自分に合っている気がするわねえ。テレビで歌えないけど、商店街のアイドルも悪くないってね。この人、あたしがいないとすーぐサボるんだから」
「へーへー。商店街のアイドルを嫁にできて幸せだなあ俺ぁ」
軽口を叩きながらも、二人ともこの仕事が好きでやっていると言うのが見ていて伝わってくる。
「お話、ありがとうございました」
青果店で深く頭を下げ、店を離れた。
近くにあるカフェのテラス席でお茶をしている親子に声をかける。幼い女の子を連れたお母さんだ。
「ねえねえ、小さい頃の夢と今のお仕事教えて。そういうゲームをしているの」
「面白いゲームね。私、小さい頃はケーキ屋さんになりたかったの。ショートケーキが大好きでね。ケーキに囲まれて過ごしたいなあって」
「わかるわかる。ケーキ美味しいから、あたしも好き」
ユメの反応に、お母さんも楽しそうに頷く。
「それで高校を出た後は調理師の専門学校に行ったんだけど、そこでパン作りの授業をしたらパンの歴史と奥深さにハマっちゃってね。バターや塩の配合一つで全く違うものができるのが楽しくて。目標が途中で変わって、それで今ではパン屋さんよ。いつか自分の店を持つために、そこのベーカリーで修行しているの」
「ママのパン、おいしーにょ」
女の子は、まるで自分のことのように誇らしげだ。
「あなたは大きくなったら何になるの?」
ミチルが聞くと、女の子は胸を張ってVサインを出す。
「まーたん、ぷいきゅあになゆの」
「そっか、なれるといいね」
「ん! なったら、おねーたんたすけてあげゆね」
まーたんがなりたいのは、人気アニメの魔法少女。
したったらずな口調で、可愛い約束をしてくれる。自分にもこんな頃があったな、なんて微笑ましくなる。
この子もいつか、魔法少女になれるわけがないとわかって悲しむ日が来るんだろうか。そんな日が来てほしくないなと思う。
まーたんにバイバイをして、また別の人の夢を聞きに行く。
精肉店で買い物をしていた女性。ミチルの母より少しだけ若いその人も、質問に丁寧に答えてくれる。
「子どもの私に、夢はなかったわ。片親でお金がないから、進学を望めなかったし。高校を卒業してすぐ結婚して、二年前に離婚したわ。今の私に夢があるとしたら、息子の夢を応援すること。そのために、スーパーで品出しをしているの」
女性の生い立ちを聞き、ミチルは後ろめたさ……罪悪感を覚えた。
父は大学卒業までの学費を出してくれたから、奨学金を借りることもなかった。
お金がなくて進学を諦める人はきっと多い。
その人達から見たら、大学に行きたくなかったと言うミチルは、身の程知らずでわがままな人間だろう。
ノートには少しずつ、いろんな人に聞いた話が集まっていく。
幼い頃の夢を叶えた人はゼロに近い。
ほとんどの人は、夢見ていたものとは違う仕事に就いている。
伴侶の家の仕事を継ぐこともある。それが天職という人もいる。
夢をみず、生活費のためになんとなくで適当に選んだバイトをする人もいる。
みんなの話を聞くにつれてわかってくるのは、ミチルとユメが狭い井戸《セカイ》しか知らない甘ちゃんだったということ。
歩に「糖蜜の井戸の中にいるオタマジャクシだ」と例えられたが、その通りだと自覚した。
何も見えていなかった。
父は歩を馬鹿だと言っていたけれど、きっと、本当に馬鹿なのはミチルだ。
親に与えられたレールを言われるまま歩くだけの馬鹿。
指示に従ったのは自分なのに、レールを歩かせた父に不満を抱く馬鹿。
このゲームはきっと、ミチルとユメに気づかせるためのものだった。
あと一人で三十人。
最後に話しかけたのは、竹ボウキを持って掃除をしていた男性だ。
「ねーねー。子供の頃の夢と、今なにをしているか教えて」
英国紳士のようなスーツに中折れ帽をかぶっている。高身長で、顔はモデル顔負けに整っている。
男性はのんびりした口調で答える。
「マッドハッターに答えのないなぞなぞを出すなんて、粋《いき》ですね」
「マッドハッター?」
「病院の先輩や同僚につけられたあだ名です。変人だから、マッドハッター」
「マッドハッターさんはなにをしている人?」
「さっきまでは玄関の掃除をしていました。今はあなたとお話ししています」
「それはそうだけど、そうじゃなくて、ええっと、うーんと、……小さい頃つきたかった職業と、今のお仕事を教えて欲しいんだよ」
のらりくらりした発言に、ユメが珍しく翻弄されている。
わざと斜め上のことを言っているのか、本当にずれているのか。男性はひとしきり笑ってから答えてくれる。
「七才の頃から精神科医を目指していました。今は独立してクリニックを営んでいます。わたしにとっては最良の道です」
男性は自分の背後を手のひらで示す。
道を挟んでワンダーウォーカーの真向かいにある建物の扉には、初田《はった》ハートクリニックと書かれた札がついていた。
「これはわたしにとっての最良であり、あなた方にとっての正解ではありません」
「どゆこと?」
首をかしげるユメに、男性は答える。
「たとえば君のお父さんが内科の開業医で、新しく精神科を設立したいから精神科医になりなさいとお父さん言われたら、なりますか? 精神科医独立の資格を得るには医大を出た後、精神科のある病院で五年実習をしないといけません。その頃あなたは三十五才になっています」
「えー、やだよ! あたし大学いけるほど頭良くないし、医者になりたいなんて思ったことないもん」
「そうでしょう。わたしと同じ医者であったとしても、個人病院を持ちたい医師から見たら、独立は羨む道。大病院で大成したい医師から見れば、愚かな道。わたしの正解は他人の不正解。白か黒かの二択では答えられない。だからあなた達の問いは、正しい答えのないなぞなぞなんです」
「そっか。じゃあ、あたしの正解の道ってなんだろう」
「それはわたしにもわかりません。道は、前にありません。自分が歩いた後ろにできるものですから。振り返ってから初めて、あの時ああしていればよかった、この道を選んでよかったと、思うものです」
言われて、ミチルもユメも自分の後ろを振り返る。
そこにはごく普通の商店街がある。
「世界は夢でできているんですよ」
「……あの、ここは夢じゃなくて、現実ですよね?」
不思議なことを言い出す男性。ミチルが聞き返すと、ポケットからいちご飴を二つ出してミチルとユメの手に一つずつ乗せる。
「これは夢の結晶です。この飴が君の手に届くまでに、どれだけの夢が集まっているか、わかりますか」
「飴が夢? ねえマッドハッター。それはなぞなぞなの?」
「いいえ。まず、製菓会社の企画部が企画立案します。製造部の人が試作を繰り返します。そしてコレだと思う味のものができたら、デザイン部がパッケージを作ります。作るだけでは売れないので、営業部の人があちこちに出向き、宣伝部の人がCMやチラシを作ります。販売決定したら工場で作り、配送の人が店に運ぶ。ここに来る過程の人、誰が欠けてもこのいちご飴はここに存在しません。この仕事に就きたくて、消費者に届けたくて頑張った人がいるから、いちご飴はここにあるのです」
飴一つについて、そこまで壮大なスケールで語られるとは思っていなかった。
というか、そこまで深く考えて飴を食べたことがない。
ミチルだけでなく、ユメも目をパチクリさせている。
「これを食べて、自分もこんなお菓子を作りたいと思う子がいたら、パティシエが生まれます。こんなパッケージを作りたいと思う子がいたら、デザイナーが生まれます。夢は夢を繋いでいきます。あなた達が歩く道もいつか、誰かの夢になるんです」
ミチルがこんなに悩んで泣きながら歩いた道でも。
男性が言うように、いつか誰かの夢に繋がるんだろうか。
「わたしは初田初斗《はったはつと》。あなた達のことは歩から聞いていました。ミチルさん、ユメさん。ふたりの未来が、夢で満ちることを願っています」
初田はにっこりと微笑んで、ミチルとユメの背を押した。
