夢で満ちたら
翌朝、ユメが目を覚ますと、ミチルはまだ寝ていた。ちゃんと手を握ったままでいてくれて、なんだか嬉しい。
幼い頃、正月やお盆で祖父母の家に行くと、ユメが迷子にならないよう、いつもミチルが手を引いていてくれた。
ユメは気が向くとどこにでも走っていってしまうから、年が近いミチルが面倒を見る役になるのは必然だったのかもしれない。
(ミチルちゃんは、あの頃と同じで優しいな)
対価をもらうために嫌々付き合っているわけじゃなくて、ミチルの意思でユメの力になろうとしてくれている。
バカでもそれくらいは感じ取れる。
そして、昨日ばったり出くわしたクラスメートのような人の悪意もまた感じ取れる。
なんで嗤われるのか理由はわからない。
でも、ユメを見下しているのは伝わる。
子どもの頃は、世界がキレイなものでいっぱいだと思っていられたのに。
成長して見える世界は……人の心は、醜いものとキレイなものが入り乱れている。
人から向けられる悪意がわからないくらい鈍感になれたら幸せだろうか。
でも、そうなると身近な人が向けてくれる愛情にも気づけなくなる。
そんなのは嫌だ。
ユメは自分を大切にしてくれる人の気持ちに、ちゃんと応えられる人でありたいと願う。
バカでも、バカにされても。
ミチルが小さく身じろぎして、瞳を開いた。
「うー……もう起きたの、ユメ」
「うん。いま起きた。おはよう、ミチルちゃん」
「おはよ。ふぁ……」
二度寝してしまわないよう布団をたたんで、買ってきたばかりのスポーツウェアに袖を通す。
店でランニング向きですよ、とオススメされた可愛いカラーでかっこいいデザインのやつだ。
「早く走ろ! 今日もまた海に行く? それともこのあたりを走る?」
「北鎌倉駅の反対側に出て、円覚寺の方に行ってみようか。あのへんは長閑《のどか》で車通りも少ないから危なくないし」
「うん!」
海もいいけど緑もいい。
ミチルの言うとおり静かなところで、海に比べて観光客は少ない。
朝だからか、犬の散歩をしているおじいちゃんとかおばあちゃんが通るくらい。
手を振ったら手を振り返してくれる。
緑が多くて、森の中を走っているみたいな気分になる。
昨日は飛ばしすぎてすぐに疲れたから、今日はミチルの歩調にあわせてゆっくり走る。
空を見上げれば飛行機雲。視界の端をスズメが飛んでいく。
「いいなぁ。あたしも空飛んでみたいなぁ」
「昔も言ってたね、それ。飛行機に乗れば飛べるんじゃないかな」
「がいこく?」
「もちろん海外も行けるけど、国内線もあるよ。沖縄とか北海道とか大阪とか」
昔より少しだけ詳しくなったガイド。
学校の人たちみたいに“生身の人間が空を飛ぶなんて無理に決まってるだろ”なんて笑ったりしない。
真面目に答えてくれる。
「あたし修学旅行以外で神奈川を出たことない。日光、京都。どっちもバスか新幹線。高校は学校行事自体ほとんどなかった」
「なら、ユメが高校を卒業したら、お祝いで飛行機に乗って北海道に行こうか」
「ほんと!? あたしラベンダー畑見てみたい!」
「そうなると七月頃の富良野だなぁ」
ミチルがとても素敵な提案をしてくれた。
高校で行われる定期テストは、後期の中間と期末の二回。
それされ終われば飛行機に乗って北海道。
がぜんやる気が出てきた。
「そうと決まったら、私は来月から仕事探しがんばんないとね」
「カテキョか個別指導塾講師!」
「家のパソコンで調べてみたら、どこも大卒以上必須だったな」
「ミチルちゃん大卒だからいけるじゃん! マッドハッターが言ってた地盤だよ」
ミチルは家庭教師になろうと思って大学を出たわけではない。
父に言われたから大学に行っただけ。
不本意だったとしても、それが役に立つなら利用すればいいと思う。
「まだ応募するとは言ってないよ」
「でもさー、でもさー、やってみて合わないと思ったらシヨウキカン? でやめたらいいんじゃない。商店街の人に聞いたみたいに、世の中お仕事はたくさんあるんだからさ」
「そうだね。人生長いし、もしかしたら天職かもしれないし、就活の選択肢に入れとくよ」
再会したばかりのときはこの世の終わりみたいな顔をしていたけれど、今日のミチルは明るい笑みを浮かべている。
「ユメが来て、ここ数日いろんな人と話して……私、自分からインコの鳥かごの中に閉じこもっているだけだったんだなって判った」
「ミチルちゃん……」
「だからありがとう、ユメ。叔父さんに会えたのもユメのおかげだよ」
「えへへ」
ミチルの言葉はいつもまっすぐだ。
スッとユメの心に入ってくる。
ミチルは再会してから一度もユメのこと馬鹿にしていない。
ADHDだということを話していないから、クラスメートのようにおかしな行動を取る変な子だって言ってもおかしくないのに。
明るくて優しくて、やればできる子だよと言って手を引いてくれる。
(ミチルちゃんが教えてくれた分、結果、出したいな)
並走していたミチルが生け垣の隅を見ながらユメの肩に触れる。
「ほら見てユメ。猫がいるよ。三毛かな。かわいいね」
「わ、ほんとだ。猫もこの時間気持ちいいんだね」
ふっくら体型の猫が、生け垣と地面の間の、三十センチほどの隙間の影でぐでんとお腹を出して寝ている。
気持ちよさそうに寝る姿は愛くるしい。
「いいなぁ、あたし、猫になりたい」
「たしかに。こんなに緑が豊かなとこでお日様を浴びて寝たら、いい夢見れそうだもんね」
「でしょー? 昔、おじいちゃんちの縁側で、お昼寝用のお布団かけて寝たもんね」
「あれは猫になった気分だったよ」
ごろごろ寝ている猫に手を振ってまた走る。
ランニングを終えて家に帰って、朝ごはんのあとまた勉強する。
数学は見るだけで頭がバーンとなるからすごく苦手。
ミチルが過去問からユメの苦手な部分を導き出して、ノートに書き出す。
「数学は公式だけ覚えて、二つくらい練習問題を解けばいいよ。テストに出るのは数字が違うだけで同じ式を使うやつだから」
「ならがんばる」
身につくように問題百問解けって言われたらやる気がゼロになるところだった。
休憩時間になって伯母が麦茶とおせんべいを持ってきてくれる。
「ミチル、夏の間に携帯電話を契約しておいたほうがいいわよ。お仕事をはじめるなら、家の固定電話だけだと、会社と連絡を取りにくいでしょう。嫌な思い出があるのはわかっているけど、ね?」
ミチルは顔をしかめて、麦茶に伸ばしかけた手を止めた。
「…………そうだね」
伯母から、ミチルは退職時に会社からかなり圧力をかけられたということだけ聞いている。五分おきにかかってくる電話で着信音が怖くなったと。
スマホを持っていないことが就職活動で不採用につながるとは思わないけれど、怖いのを少しでも和らげられたらいい。
「ねえ、ミチルちゃん。買うならあたしのスマホと色違いにしようよ。そんで、着音これにするの!」
ユメは自分のスマホをタップして、着信音の視聴を起動する。
〈にゃ〜お、にゃ〜お、にゃ〜お〉
リビングに響く猫の鳴き声。
ミチルと伯母の目が点になって、笑い出す。
「あはははっ。なにこれ可愛い」
「ね、ね、可愛いでしょ!? 動物鳴き声アプリでね、着信音をワンコやカッコウ、牛にできるの」
「あらカッコウなんてあるの? 面白そうね。わたしにも教えて。入れてみたいわ」
「これだよー」
アプリの画面を見せると伯母もすぐに自分のスマホにダウンロードした。
伯母のスマホがコケーッココココ! と鳴き出して、ミチルが笑う。
「あははは。たしかにこれなら笑っちゃうから、怖くないね。ありがとう、これ、スマホ買ったら入れてみるよ」
こうして、午後はスマホショップ行きが決定した。
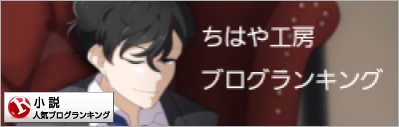
幼い頃、正月やお盆で祖父母の家に行くと、ユメが迷子にならないよう、いつもミチルが手を引いていてくれた。
ユメは気が向くとどこにでも走っていってしまうから、年が近いミチルが面倒を見る役になるのは必然だったのかもしれない。
(ミチルちゃんは、あの頃と同じで優しいな)
対価をもらうために嫌々付き合っているわけじゃなくて、ミチルの意思でユメの力になろうとしてくれている。
バカでもそれくらいは感じ取れる。
そして、昨日ばったり出くわしたクラスメートのような人の悪意もまた感じ取れる。
なんで嗤われるのか理由はわからない。
でも、ユメを見下しているのは伝わる。
子どもの頃は、世界がキレイなものでいっぱいだと思っていられたのに。
成長して見える世界は……人の心は、醜いものとキレイなものが入り乱れている。
人から向けられる悪意がわからないくらい鈍感になれたら幸せだろうか。
でも、そうなると身近な人が向けてくれる愛情にも気づけなくなる。
そんなのは嫌だ。
ユメは自分を大切にしてくれる人の気持ちに、ちゃんと応えられる人でありたいと願う。
バカでも、バカにされても。
ミチルが小さく身じろぎして、瞳を開いた。
「うー……もう起きたの、ユメ」
「うん。いま起きた。おはよう、ミチルちゃん」
「おはよ。ふぁ……」
二度寝してしまわないよう布団をたたんで、買ってきたばかりのスポーツウェアに袖を通す。
店でランニング向きですよ、とオススメされた可愛いカラーでかっこいいデザインのやつだ。
「早く走ろ! 今日もまた海に行く? それともこのあたりを走る?」
「北鎌倉駅の反対側に出て、円覚寺の方に行ってみようか。あのへんは長閑《のどか》で車通りも少ないから危なくないし」
「うん!」
海もいいけど緑もいい。
ミチルの言うとおり静かなところで、海に比べて観光客は少ない。
朝だからか、犬の散歩をしているおじいちゃんとかおばあちゃんが通るくらい。
手を振ったら手を振り返してくれる。
緑が多くて、森の中を走っているみたいな気分になる。
昨日は飛ばしすぎてすぐに疲れたから、今日はミチルの歩調にあわせてゆっくり走る。
空を見上げれば飛行機雲。視界の端をスズメが飛んでいく。
「いいなぁ。あたしも空飛んでみたいなぁ」
「昔も言ってたね、それ。飛行機に乗れば飛べるんじゃないかな」
「がいこく?」
「もちろん海外も行けるけど、国内線もあるよ。沖縄とか北海道とか大阪とか」
昔より少しだけ詳しくなったガイド。
学校の人たちみたいに“生身の人間が空を飛ぶなんて無理に決まってるだろ”なんて笑ったりしない。
真面目に答えてくれる。
「あたし修学旅行以外で神奈川を出たことない。日光、京都。どっちもバスか新幹線。高校は学校行事自体ほとんどなかった」
「なら、ユメが高校を卒業したら、お祝いで飛行機に乗って北海道に行こうか」
「ほんと!? あたしラベンダー畑見てみたい!」
「そうなると七月頃の富良野だなぁ」
ミチルがとても素敵な提案をしてくれた。
高校で行われる定期テストは、後期の中間と期末の二回。
それされ終われば飛行機に乗って北海道。
がぜんやる気が出てきた。
「そうと決まったら、私は来月から仕事探しがんばんないとね」
「カテキョか個別指導塾講師!」
「家のパソコンで調べてみたら、どこも大卒以上必須だったな」
「ミチルちゃん大卒だからいけるじゃん! マッドハッターが言ってた地盤だよ」
ミチルは家庭教師になろうと思って大学を出たわけではない。
父に言われたから大学に行っただけ。
不本意だったとしても、それが役に立つなら利用すればいいと思う。
「まだ応募するとは言ってないよ」
「でもさー、でもさー、やってみて合わないと思ったらシヨウキカン? でやめたらいいんじゃない。商店街の人に聞いたみたいに、世の中お仕事はたくさんあるんだからさ」
「そうだね。人生長いし、もしかしたら天職かもしれないし、就活の選択肢に入れとくよ」
再会したばかりのときはこの世の終わりみたいな顔をしていたけれど、今日のミチルは明るい笑みを浮かべている。
「ユメが来て、ここ数日いろんな人と話して……私、自分からインコの鳥かごの中に閉じこもっているだけだったんだなって判った」
「ミチルちゃん……」
「だからありがとう、ユメ。叔父さんに会えたのもユメのおかげだよ」
「えへへ」
ミチルの言葉はいつもまっすぐだ。
スッとユメの心に入ってくる。
ミチルは再会してから一度もユメのこと馬鹿にしていない。
ADHDだということを話していないから、クラスメートのようにおかしな行動を取る変な子だって言ってもおかしくないのに。
明るくて優しくて、やればできる子だよと言って手を引いてくれる。
(ミチルちゃんが教えてくれた分、結果、出したいな)
並走していたミチルが生け垣の隅を見ながらユメの肩に触れる。
「ほら見てユメ。猫がいるよ。三毛かな。かわいいね」
「わ、ほんとだ。猫もこの時間気持ちいいんだね」
ふっくら体型の猫が、生け垣と地面の間の、三十センチほどの隙間の影でぐでんとお腹を出して寝ている。
気持ちよさそうに寝る姿は愛くるしい。
「いいなぁ、あたし、猫になりたい」
「たしかに。こんなに緑が豊かなとこでお日様を浴びて寝たら、いい夢見れそうだもんね」
「でしょー? 昔、おじいちゃんちの縁側で、お昼寝用のお布団かけて寝たもんね」
「あれは猫になった気分だったよ」
ごろごろ寝ている猫に手を振ってまた走る。
ランニングを終えて家に帰って、朝ごはんのあとまた勉強する。
数学は見るだけで頭がバーンとなるからすごく苦手。
ミチルが過去問からユメの苦手な部分を導き出して、ノートに書き出す。
「数学は公式だけ覚えて、二つくらい練習問題を解けばいいよ。テストに出るのは数字が違うだけで同じ式を使うやつだから」
「ならがんばる」
身につくように問題百問解けって言われたらやる気がゼロになるところだった。
休憩時間になって伯母が麦茶とおせんべいを持ってきてくれる。
「ミチル、夏の間に携帯電話を契約しておいたほうがいいわよ。お仕事をはじめるなら、家の固定電話だけだと、会社と連絡を取りにくいでしょう。嫌な思い出があるのはわかっているけど、ね?」
ミチルは顔をしかめて、麦茶に伸ばしかけた手を止めた。
「…………そうだね」
伯母から、ミチルは退職時に会社からかなり圧力をかけられたということだけ聞いている。五分おきにかかってくる電話で着信音が怖くなったと。
スマホを持っていないことが就職活動で不採用につながるとは思わないけれど、怖いのを少しでも和らげられたらいい。
「ねえ、ミチルちゃん。買うならあたしのスマホと色違いにしようよ。そんで、着音これにするの!」
ユメは自分のスマホをタップして、着信音の視聴を起動する。
〈にゃ〜お、にゃ〜お、にゃ〜お〉
リビングに響く猫の鳴き声。
ミチルと伯母の目が点になって、笑い出す。
「あはははっ。なにこれ可愛い」
「ね、ね、可愛いでしょ!? 動物鳴き声アプリでね、着信音をワンコやカッコウ、牛にできるの」
「あらカッコウなんてあるの? 面白そうね。わたしにも教えて。入れてみたいわ」
「これだよー」
アプリの画面を見せると伯母もすぐに自分のスマホにダウンロードした。
伯母のスマホがコケーッココココ! と鳴き出して、ミチルが笑う。
「あははは。たしかにこれなら笑っちゃうから、怖くないね。ありがとう、これ、スマホ買ったら入れてみるよ」
こうして、午後はスマホショップ行きが決定した。
