一章 セツカと時の鎖
「……懐かしい夢を見たなぁ」
今朝見た夢のことを考えながら、庭園の白薔薇に水やりをする。
貴族のアーノルド・マーズさんに引き取られてから十五年。
今年の春ノーゼンハイムという国の首都、ノーゼンハイムの学校を卒業した。
今の俺はマーズ家の庭師として庭園の管理を一手に担っている。
貴族というのは魔法を使う血族の呼称だ。
神の御技、魔法を使える貴き血族だから、貴族。
拾われる前の記憶は戻らないまま、俺の記憶はこの薔薇と同じようにまっさらだ。
花に触れる俺の手は、薔薇に負けないくらい白い。
うつむいて目元にかかる髪は銀色。
瞳は冬空のような灰色。
こんな色だから、学生時代のあだ名は歩く雪人形。
上級生に石を包んだ雪玉を投げつけられたことも一度や二度じゃない。
北風に吹かれて、薔薇の葉がひらりと揺れる。なんとなく、慰めてくれているように感じた。
「ありがとう。君たちは優しいね」
ふと、ひとつの枝が目に止まった。
毎日手入れしているのに、この一枝だけ異様に長く伸びている。一日二日で伸びる長さじゃない。
「……俺をよく思わないやつに何かイタズラされた? いや、でも花の成長を変化させる魔法なんて存在しないはず」
ひとりごちていると後ろから肩を叩かれた。
振り返ると漆黒の騎士制服に身を包んだアーノルドさんがいた。
アーノルドさんは空色の瞳をやわらかく細める。栗色の癖毛がふわりと揺れる。
「おはようセツカ。まーた花に話しかけてんのか?」
「おはようございます、ご主人様。本日は早番なのですね。行ってらっしゃーーあいたっ!!」
言い終える前にチョップが降ってきた。
「敬語禁止」
「ですが、執事長からも主に敬意を払えと」
「堅苦しいのは嫌いなんだ。普通にしろ普通に」
二投目のチョップが降り注ぐ。
かしずかれるのが嫌いな貴族なんて、アーノルドさんとその娘リーンくらいじゃなかろうか。
この近辺に住んでいる貴族は使用人を家畜同然に扱う人が多い。
アーノルドさんは楽しげに笑い、目を細める。
「そうやって毎日花に話しかけてるの、アスターみたいだなホント」
「なんだかこの子達を見ていると話しかけたくなるんですよ。ほら、おばあちゃんがペットに話しかけるようなものです」
「そういうもんか。アスターが生きていたら、絶対セツカと気が合うんだろうな〜」
アスターというのは、二十年前戦死したアーノルドさんの親友。ちょくちょくアーノルドさんの思い出話に登場するから、一度も会ったことがないのに詳しくなってしまった。
「それで、イタズラがどうこう言っていたが、どうした?」
主であるアーノルドさんには伝えておくべきか。
「それが、見てくださいこの枝。この株は昨日剪定したばかりなのに、この枝だけこんなに長く伸びているんです。あとで原因を調べてみます」
「……そう、か。もう十五年だもんな。時が来てしまったのか」
アーノルドさんは先程と打って変わって、顔を曇らせた。
「時が来た?」
「いーや。なんでもない。それより、今日はセツカの誕生日だろ。帰ってきたらリーンと誕生日祝いやるから俺の部屋に来てくれ。で、いつものもヨロシク」
アーノルドさんが深刻な表情を見せたのもほんの一瞬で、ポケットからクシャクシャになったメモを出して俺の手に持たせる。
買ってくるものリストと題されていて、お菓子の名前がズラリ。……甘党なんだよな。
「出会った日を誕生日にしましょう!」と決めたのはアーノルドさんの娘アイリーン。色々と父親に似ている。
「いってらっしゃい、アーノルドさん」
出勤するアーノルドさんを見送り、思う。
記憶を失う前の俺にも、こんなふうに祝ってくれる家族はいたんだろうか。
どんな人たちだったんだろう。
叶うなら帰りたい。
失ってしまった過去を知りたい。
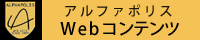

今朝見た夢のことを考えながら、庭園の白薔薇に水やりをする。
貴族のアーノルド・マーズさんに引き取られてから十五年。
今年の春ノーゼンハイムという国の首都、ノーゼンハイムの学校を卒業した。
今の俺はマーズ家の庭師として庭園の管理を一手に担っている。
貴族というのは魔法を使う血族の呼称だ。
神の御技、魔法を使える貴き血族だから、貴族。
拾われる前の記憶は戻らないまま、俺の記憶はこの薔薇と同じようにまっさらだ。
花に触れる俺の手は、薔薇に負けないくらい白い。
うつむいて目元にかかる髪は銀色。
瞳は冬空のような灰色。
こんな色だから、学生時代のあだ名は歩く雪人形。
上級生に石を包んだ雪玉を投げつけられたことも一度や二度じゃない。
北風に吹かれて、薔薇の葉がひらりと揺れる。なんとなく、慰めてくれているように感じた。
「ありがとう。君たちは優しいね」
ふと、ひとつの枝が目に止まった。
毎日手入れしているのに、この一枝だけ異様に長く伸びている。一日二日で伸びる長さじゃない。
「……俺をよく思わないやつに何かイタズラされた? いや、でも花の成長を変化させる魔法なんて存在しないはず」
ひとりごちていると後ろから肩を叩かれた。
振り返ると漆黒の騎士制服に身を包んだアーノルドさんがいた。
アーノルドさんは空色の瞳をやわらかく細める。栗色の癖毛がふわりと揺れる。
「おはようセツカ。まーた花に話しかけてんのか?」
「おはようございます、ご主人様。本日は早番なのですね。行ってらっしゃーーあいたっ!!」
言い終える前にチョップが降ってきた。
「敬語禁止」
「ですが、執事長からも主に敬意を払えと」
「堅苦しいのは嫌いなんだ。普通にしろ普通に」
二投目のチョップが降り注ぐ。
かしずかれるのが嫌いな貴族なんて、アーノルドさんとその娘リーンくらいじゃなかろうか。
この近辺に住んでいる貴族は使用人を家畜同然に扱う人が多い。
アーノルドさんは楽しげに笑い、目を細める。
「そうやって毎日花に話しかけてるの、アスターみたいだなホント」
「なんだかこの子達を見ていると話しかけたくなるんですよ。ほら、おばあちゃんがペットに話しかけるようなものです」
「そういうもんか。アスターが生きていたら、絶対セツカと気が合うんだろうな〜」
アスターというのは、二十年前戦死したアーノルドさんの親友。ちょくちょくアーノルドさんの思い出話に登場するから、一度も会ったことがないのに詳しくなってしまった。
「それで、イタズラがどうこう言っていたが、どうした?」
主であるアーノルドさんには伝えておくべきか。
「それが、見てくださいこの枝。この株は昨日剪定したばかりなのに、この枝だけこんなに長く伸びているんです。あとで原因を調べてみます」
「……そう、か。もう十五年だもんな。時が来てしまったのか」
アーノルドさんは先程と打って変わって、顔を曇らせた。
「時が来た?」
「いーや。なんでもない。それより、今日はセツカの誕生日だろ。帰ってきたらリーンと誕生日祝いやるから俺の部屋に来てくれ。で、いつものもヨロシク」
アーノルドさんが深刻な表情を見せたのもほんの一瞬で、ポケットからクシャクシャになったメモを出して俺の手に持たせる。
買ってくるものリストと題されていて、お菓子の名前がズラリ。……甘党なんだよな。
「出会った日を誕生日にしましょう!」と決めたのはアーノルドさんの娘アイリーン。色々と父親に似ている。
「いってらっしゃい、アーノルドさん」
出勤するアーノルドさんを見送り、思う。
記憶を失う前の俺にも、こんなふうに祝ってくれる家族はいたんだろうか。
どんな人たちだったんだろう。
叶うなら帰りたい。
失ってしまった過去を知りたい。
