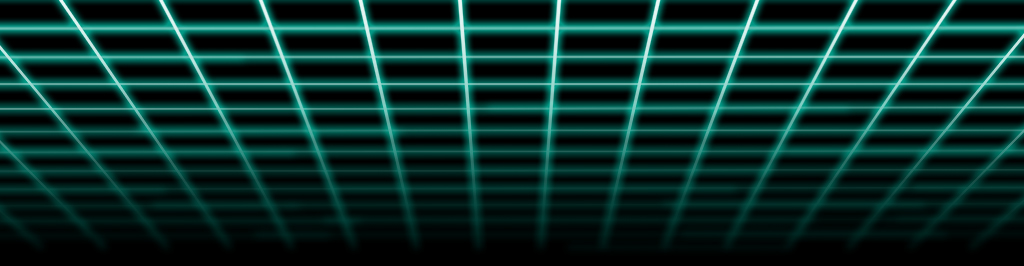#11 パンドラの箱
夢小説設定
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
『おかえりなさーい。』
一拍間を置いて「ああ」と返事をしてくれた狡噛さんの隣で、何故か驚いたような顔をしている宜野座さんに、瞬く。
半分無意識に征陸さんの肩から手を離すと、「有難う」とお礼を言われた。
「どうだった。」
「今晩の客は俺達だけ。従業員は全員アリバイあり…勘違いの線が濃厚だな。」
『ええっ!……じゃ、外から忍び込んだ…とか……』
「そんな痕跡もないと、さっき風呂場で言ったろ。」
『でも…』となおも食い下がろうとして、息を吐く。
『わ、かりました。お手数おかけしてすみません、宜野座さんも。』
「いや」と座卓に腰を下ろすのを見て、膝を伸ばす。
用意された4人分のお茶セットに使われている急須は、控えめに可愛らしい色をしていて、愛らしい。
「しかしアレだな。客、俺達だけだって?いっくら平日とはいえ、景気の悪い話じゃあないか。」
「…こんな山奥にわざわざ好き好んでやってくるヤツがいると思うか?」
「いるからあるんだろ、旅館が。」
リズムの良いような悪いような、父親と息子達と言った風な会話に笑いを誘われながら『どうぞ』とお茶を差し出す。
「おっ、有難う。」
「ああ、悪い。」
例によってややぎこちない狡噛さんのお礼の表現に知らず頬を緩めて、宜野座さんの分のお茶に手を伸ばそうとした時だった。
「そういや買ってなかったな、土産。」
「……土産?」と眉を寄せて視線を上げた宜野座さんが、片腕一本で無理矢理立たされる。
「――な、おい!!」
「じゃ、ちょっと言ってくらぁ。」