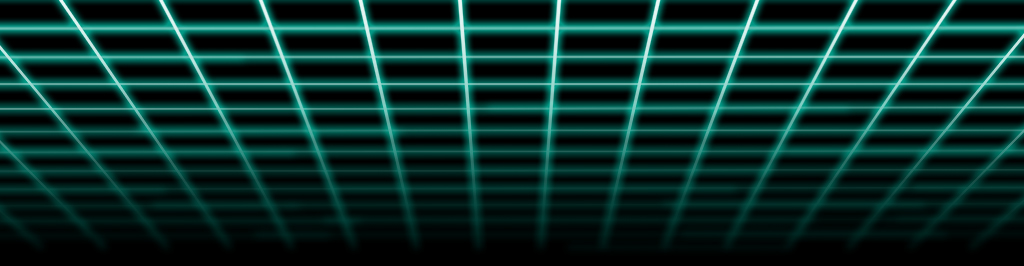第五章
夢小説設定
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
二
――――――――――――――――――
「…確かに。」
そう言って小さく顎を引いた雑賀教授が、手に持った紙の束を軽く叩いた。
「相変わらずらしい。」
口元を緩め、控えめに室内を見渡した視線を戻す。
「うん、まあ俺も人のことは言えないんだけど。」
『私もです。電子書籍は…味気ない。』
濃厚な香りを醸すコーヒーに口をつけた教授が、はははと声を上げて笑う。
「それはちょっと偏執的傾向だな。」
『紙をめくる時の感覚と、あとは…匂いもかな。好きで。』
「今は、何を読んでいるんだい?」
『"スワン家の方へ"、を。ここまでくる間に、第二部まで読みました。』
車の助手席に置きっぱなしになっている本のことを思い出し、ああと内心で肩を下げる。
こんなことならもう一冊持ってくれば良かった。
きっと青柳さんの家に帰り着く頃には、読み終わってしまう。
「その歳で"スワン"か。さすがあいつの研究室に出入りしているだけのことはあるね。」
答えに窮していると、鋭利な知性を宿した黒い瞳が優しく細められる。
自分がまだティーンエイジャーに過ぎないのだという自覚。
感じさせられるのは、久し振りだ。
「高等教育過程では社会学専攻なんだろう?進学してもやっぱりその道に進むかい?」
『はい、そのつもりです。社会心理学科では一回生でも教授の講義を受けられるので。』
実の父よりも、余程自分の世話を焼いてくれている恩師。
そういえば日本文化好きな彼に、何かお土産のひとつも買って帰ってあげようか。
と、気を緩めた途端に漂いだした思考を慌てて引き戻す。
『でも臨床心理…犯罪心理学にもかなり興味があって。教授もそれを知って今回、私に声をかけて下さったんです。』
「…ほう…?あっちじゃまだ需要があんのかい?今の日本じゃその分野に関する研究は廃れて久しい…時代遅れの無用な知識だよ。」
肩をすくめてカップに口をつける教授に無意識に右手を、握りこむ。
シビュラの管理下ではそもそも犯罪など起こる筈がなく、起こったとしたならそれはその環境に欠陥があり、それを改善すべきだという思考方。
社会全体がそうであれば、その論理はまかり通る。
例えそれの通用しないことが起きたとしても、それはただのイレギュラーでしかない。
『…ですが……』
しかもそれを完全に取り去る必要はおろか、隠す必要すらない。
[無かったこと]にするのはシステムではないく、私たち自身だからだ。
そしてそれを、望むのもまた。
私は
『善悪の選り分けを行うのがシステムであっても実行するのはシステムではない。…社会を形作っているのは…ここに在るのは、私達――人間です。』
私は、違う。
――――――――――――――――――