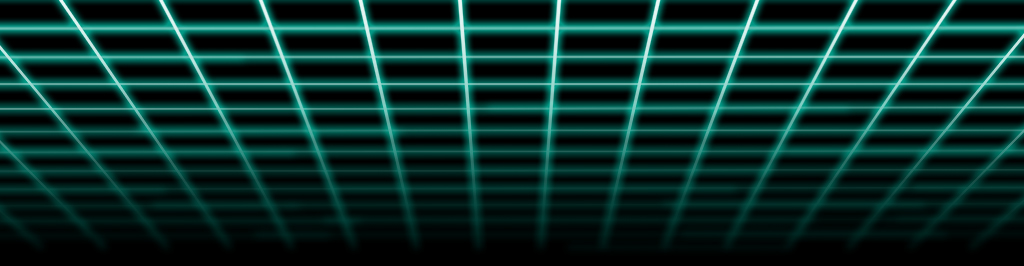第三章
夢小説設定
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
二
――――――――――――――――――
「もうびっくりしちゃったわよー。」
込み合う店内で忙しく立ち動いているのは給仕用ドローンではなく、人間。
この都市では非常に、珍しい光景だ。
機械工学技術の飛躍的な進歩と、人口の激減に伴い市場は次第にオートメーション化され人の手を、どこまでも不要としていった。
飲食店などはその、最たるものだ。
がしかしそんな時代になっても、いやそんな時代だからこそと言うべきか。
人は、同じ人の手で苦労をかけて生み出されるものを好み、そこに価値を見出す。
…まあ単純に数少ないもの=貴重ってだけだろうけど。
と思いながら、この店の名物である"こってりドロドロ豚骨"をすする佐々山。
そして彼の横では青柳が同じものを、彼よりも早いペースで、着々と消化している。
「適当に出前でも取ろっかなーなんて思って帰ったらさ、完全に出来上がってて。」
「……あ、卵ももらおっかな。」
湯気で向こう側の見えないカウンターに、替え玉を要求すべく手を上げる。
「はいよ!」とスープが跳ねるのにも構わずぶち込まれる、麺と卵。
これはちょっともう少し、なんとかならないもんだろうか。
「クッキングマシンじゃないちゃんとしたご飯なんてあたし…ここ数ヶ月は食べてなかったったんじゃないかなー。」
女子としてそれはどうなんだと、麺をすする。
勿論口には出さない、思うだけだ。
「しかも『おかえりなさい』なんて言ってくれてーなんか癒されたわぁ。」
「へー……」
「でもさ」
くすりという笑みに、顔を横向ける。
「朝、駄目なのねきっと。声かけたら結構間あいてなんかよく意味分かんない英語返ってきて…笑っちゃったわ。時差ボケって言うより多分低血圧ね、アレは。」
「………」
何故かは分からない。
なんとなくこそばゆいような感覚はひどく、居心地が悪くて。
腕のバングルが告げた着信に、いくらか救われたような思いで応える。
ホロ表示された名前を見る前から浮かんでいた、その顔。
「へーい、こちら佐々<何をしてんだお前、佐々山!!>
折角の渋さを台無しにするヒステリックな声を聞きながら、チャーシューを口に運ぶ。
執行官の位置は、監視官の携帯端末を使えばすぐに知れる。
がしかし奴は不思議なことにその便利な機能をあまり、積極的に使おうとはしない。
何と言うかどこまでも、"優等生"という言葉の似合う男なのだ。
「ラーメン食ってまーす。」
<っ…まーすじゃない!この――>
ブツッと切れた直後、隣の青柳が箸を唇にあてて腕を上げる。
リングに表示されたホロ画面が見えないのを良いことに、食事を続ける。
「あったりー!さっすが狡噛くん…いやただ休憩被ったから……あはは、ラーメン食べてんのはホントよ。来る?」
さすが、察しの良いことだ。
――――――――――――――――――