ミリアッドカラーズ
「な、に、してるの……?」
ようやく絞り出した声に、当事者達の目線がばっと振り向く。
ルートヴィッヒが何でもない風に装う傍ら、ルシャントは酷く動揺していた。剣を持つ手が意思関係なくかたかたと震えては揺れる。
顕現を解除したルシャントは青い蝶の残影を残してその場から離脱。残されたのは鼻に突く鉄の匂いと、首筋からとめどなく血を流すルートヴィッヒ。
はっとしたリアムは止血すべく駆け寄る。
「大丈夫⁉︎」
「少々切っただけだ」
「少しじゃないよ! とりあえず止血しないと」
血で穢れるのも厭わず、シャツ越しに傷口を押さえつけたリアムの隣で、ふわりと彼の
不思議に思う彼らの眼差しを浴びつつ、ひとりでにページが捲られていく。やがてピタリと停止したかと思えば、桃色の魔法円を発動。光粒から放たれた柔らかな光雨が、ルートヴィッヒの体に降り注ぐ。
「……痛くない」
「え?」
呟かれた言葉を訝しみながら、リアムは恐る恐るシャツから手を離し首筋付近を捲る。
すると、べっとりと血痕は残りつつも、傷口らしきものは傷跡も残らず消えていた。どうやら、《アンティフォン》が自らの意思で治癒を施したらしい。
(凄い……)
覚醒した《アンティフォン》に感嘆したリアムは、「ありがとう」と空き手で我が子に接するかのように優しく表紙をなぞる。たちまち光が消え失せ、《アンティフォン》は沈黙。
「君まで汚れてしまったな」
血に塗れたリアムの手を取るルートヴィッヒに、多少の不信感を抱く。びくりと肩を震わせた少年の心情を知ってか知らずか、男は笑みを讃える。
「……どうして、あんなことを?」
反応を固唾を呑んで見守るリアムに、ふっと嘲笑。
「君には到底理解出来ないさ」
いつの間に取り出した布で、少年の手に付着した血液の大半を拭ったルートヴィッヒは仮面に手を添える。
「さあ、早く行きたまえ。私は自室に一旦戻る」
「う、うん……わかったよ」
これ以上は『
記者としての勘から、底なし沼の如く狂気を察した少年は、逃げるようにその場から立ち去る。
ひとりその場に残された男の背中を、鳴り止まぬ雷鳴が煌々と照らした。
まるで、光が強くなればなるほど、影が濃くなるように。
目を開けるとそこは異世界でした──
なんてフレーズがリアムの脳内を過ぎる。目の前の光景を言い換えるならば、『戻ってくるとそこは大波乱でした』だろうか。
キッチンへと踵を返したリアムと、料理をしていたはずのアステルのぎこちない視線が交差する。彼の隣には、平然と佇むミュティスの姿も。
そして問題のキッチンは荒れに荒れていた。何をどうすればこんなに汚せるのかを寧ろ教えて欲しいレベル。ところどころに転がるキッチン用品、食材(だったもの)が机だけでなく壁や天井までに付着している。
「こ、これはそのー……あはは……」
首筋を手で撫でるアステルと口を半開きにするリアム。
そこに、「おやおや」とルートヴィッヒが──さるも先程の出来事をなかったごとく身支度を整え──顔を覗かせた。
「素晴らしい! どのようにすればこのような奇跡が起きるのか?」
「や、やめてくれよ! 失敗したんだから!」
芸術の一端として捉えるルートヴィッヒに、アステルは眉を釣り上げる。
「すまないすまない」
「……で、材料は?」
「……ほとんど使いきっちまった」
空になった冷蔵庫を見せつけられたリアムは再び唖然。
萎縮するアステルの肩を、ぽんと叩いたのはルートヴィッヒだった。
「心配無用だ。まだ昨日仕込んだビーフシチューがある」
「あ、それ聞こうとしていたやつ」
「奇跡的に無事だ。今晩はこれにしよう」
「……悪いな」
「失敗は誰にだってあるさ。気にしないでくれ。さて、皆のもの。片付けるのを手伝っておくれ」
一同は分担してキッチンの清掃に取り掛かり、元の清潔な姿へと戻す。
夕食であるビーフシチューで卓を囲んだのは、その後の話。
応接間と同じ居住地帯にあるダイニングルームに招待されたリアム、アステル、ミュティスの三人は、皿に盛り付けられたトロリと滴る芳醇な香りが鼻腔をくすぐるビーフシチューを受け取る。
リアムとアステルがごくりと喉を鳴らす中、席についたルートヴィッヒはどうぞと手を差し向けた。
「「いただきます!」」
「……」
食らいついたリアムとアステルは途端に目を見開き、う〜んと感激。黙々と口に運ぶミュティスも表情には出さないものの、気に入った様子。
にこやかに見守りながら、ルートヴィッヒもまたスプーンで口に運ぶ。
「「美味しい!」」
「それは良かった。こちらとしても嬉しい限りだ」
「これがビーフシチューか……いいな!」
「お肉も口の中にいれた瞬間溶けていくし……プロ並みだよ!」
リアムと笑い合うアステルは不意に俯き気味に呟く。
「……ルシャントも食べればいいのにな」
事情を知る少年は「そうだね」と誤魔化すか如く頬張り、「そんな日もあるさ」と男はなだめる。
「また作ってくれるか? オレ、アイツにも食べてほしいんだ」
「もちろん。君達の為なら喜んで応えよう」
ほっと安堵したアステルは、彼特有の勢いでビーフシチューへと口付ける。
そんな少年を尻目にリアムは思う。
僕は、アステルは。ルシャントのことをどこまで知っているのだろうか。
何を僕は知らなくて、何を少年は知らなくて。
何を僕は知っていて、何を少年は知っているのか。
──さあ早く、私を殺して喰べてくれ。
ルートヴィッヒの台詞が頭にこびりついて離れない。
彼だっておかしい。初めて会ったはずのルシャントの『何か』を知っているみたいだ。
錆びついた血と似た色をしたスープを、一口啜る。
今の心情には似つかわしくない美の味がした。
蒼然とした空に
大嵐はすっかりと消え去り、嘘のように綺麗な夜空が広がっている。
屋敷の屋根上で佇むルシャントのローブが風にはためく。
見下げる
「ここにいたか“ルシャント”」
すっかり『現代語』の名前を使いこなすアステルは、よいしょと華麗に屋根上へと降り立つ。
「ご飯、食べなくてよかったのか?」
「必要ない」
「……そうだったな」
遠慮がちに距離を詰める彼に、ルシャントは何の前触れもなく振り向く。びくりと肩を震わせたアステルを意に止めず、月の光を背に口を開いた。
「聞きたいんだ、君のこと。いい?」
アステルは瞠目したのち、目を伏せる。
「どうして『生きているか』……だな」
沈黙という名の肯定。
ルシャントは聞き手の姿勢へと回り、アステルの言葉を待つ。
ややあってアステルはその場に腰を下ろし、ルシャントが知らぬ自身の末路を語る。
「オマエが世界を消滅させる前に、オレは病気が悪化して死んだんだ」
眉を顰める少年に、自身の手を見つめながら死んだ少年は経緯を口にする。
「この体は、オレが死んだあとにミュティスが作った『作りもん』さ。本当の肉体に近くはあるらしいけど」
「……どうして」
ルシャントの疑問を、ははっと力なく笑い飛ばす。
「オレの願いを叶えるためだってさ」
「……」
「オレが死んだあと、父さんや母さんがオマエを追い詰めたって知ったのは随分とあとだ。その事も……約束も守れなくてごめん」
話すにつれて声音が震えだすのを、ルシャントはただじっと見つめ、そして冷ややかに告げる。
「……別に恨んでないから許すも何もないよ。君の両親が僕に言った言葉は正しいさ」
はっとアステルが顔を上げたときにはもう、ルシャントはここではない何処か遠くを見据えていて。
「僕が災いを呼ぶ蝶なのは間違いない。世界を消滅させる為に沢山の人間を喰ったのも、後悔なんてしてない。……僕は大罪人だ。今までも、これからも」
言外に自分のせいではないと言われても、素直に喜べはしなかった。
目の前の少年は自分が知るその人ではないと、はっきり分からされたから。
蝶の如くその場を飛び去る友人の手に、伸ばすことすらできず胸の前で握りしめた。
次の日の朝。天候は快晴。
森を歩くには申し分ない天気に心持ちも晴れやかとなる。
「では参ろうか」
図書館の両開き扉を押し開けたルートヴィッヒの顔が朝日に照らされる。
身支度を整えたリアム、アステル、ミュティス──と、姿をくらましていたルシャントも男の後に続き、森の更に奥深くへ。
リアムはルシャントが姿を現したことに、内心安堵していた。その一方で、アステルとの距離感が不自然なのは気にかかるが。目下、優先すべきはこの先にあるという《リトルクリスタル》の保護。
鞄から『精霊王辞典』を取り出したリアムは、先導するルートヴィッヒに尋ねた。
「ねえ、ルーイ。この先にある《リトルクリスタル》ってなんの加護なの?」
「詳しい事情は私にも分からぬが、『言霊』を司るらしい」
言霊、と聞き辞典を捲るも。どの項目にもその記述はない。
「おかしいなぁ最新のはずなのに……」
小首をかしげるリアムに、「それもそうね」とミュティスが突っかかる。
「【言霊の精霊王】はつい最近誕生した【精霊王】……通常の人間が発見出来るほどの力はまだないわ」
「それって……」
リアムは前方を進む──聞いて見ぬふりをしている──ルートヴィッヒの背中を見つめた。
彼も自分達と同じ、普通の人間ではないのだろうか。
そう問いかけるにはまだ、彼と自分の関係値は浅い気がした。
「さあ、着いたぞ」
鬱蒼と絡み合う草木をかき分けた先、開けた空間に辿り着いた一同を迎えたのは一欠片の水晶。
ほんのりと光を発するその様子はやはり《リトルクリスタル》とは異なり、例えるならまるで……まだこの世に生を受けたばかりの赤ん坊のように儚い雰囲気だった。
「紹介しよう。この子が【言霊の精霊王】だ」
歩み寄るルートヴィッヒに倣い、リアム達も《リトルクリスタル》へと距離を詰める。
「は、初めまして。リアムです」
困惑しながらも名を名乗れば、呼応するかの如く光が明滅する。
「ははっ、この子も嬉しそうだ」
優しく《リトルクリスタル》を撫でるその仕草は子供をあやすようにも似ていて。なんだか、心の奥が暖かい気持ちで満たされる。
この世界にはこうして、【精霊王】を友として向き合っている人間がいると思うと嬉しく感じた。
これまでにはなかった感情の変化に、リアムは若干戸惑う。
「にしても……『ルスト』はいないな」
周囲を警戒していたアステルの言葉が、リアムを現実へと引き戻す。
「たしかに気配もないね」
「情報が間違っていたんじゃないのか?」
「うーん……ピーターさんが間違えるとは思えないけど……」
念の為調べてみようと意見が合致した、その時。
「「……!」」
ミュティスとルシャントが、同時に上空を見遣る。
なんだなんだと不思議に思う中釣られて顔を上げれば──気配を感じさせることもなくただただ無言で浮遊する『男』がいた。
こちらを見下すような目線に背中がぞわりと震える。
黄金色の長髪、金色の瞳。白きローブに映し出されしは果てしない銀河の光景。風は吹けど、首元の光輪は微動だにしない。
男が発するオーラに、誰しもが息を呑んだ。小鳥囀るはずの森も沈黙を保つ。
あのミュティスでさえも、困惑を露わにしていた。
「どうしてあなたが……」
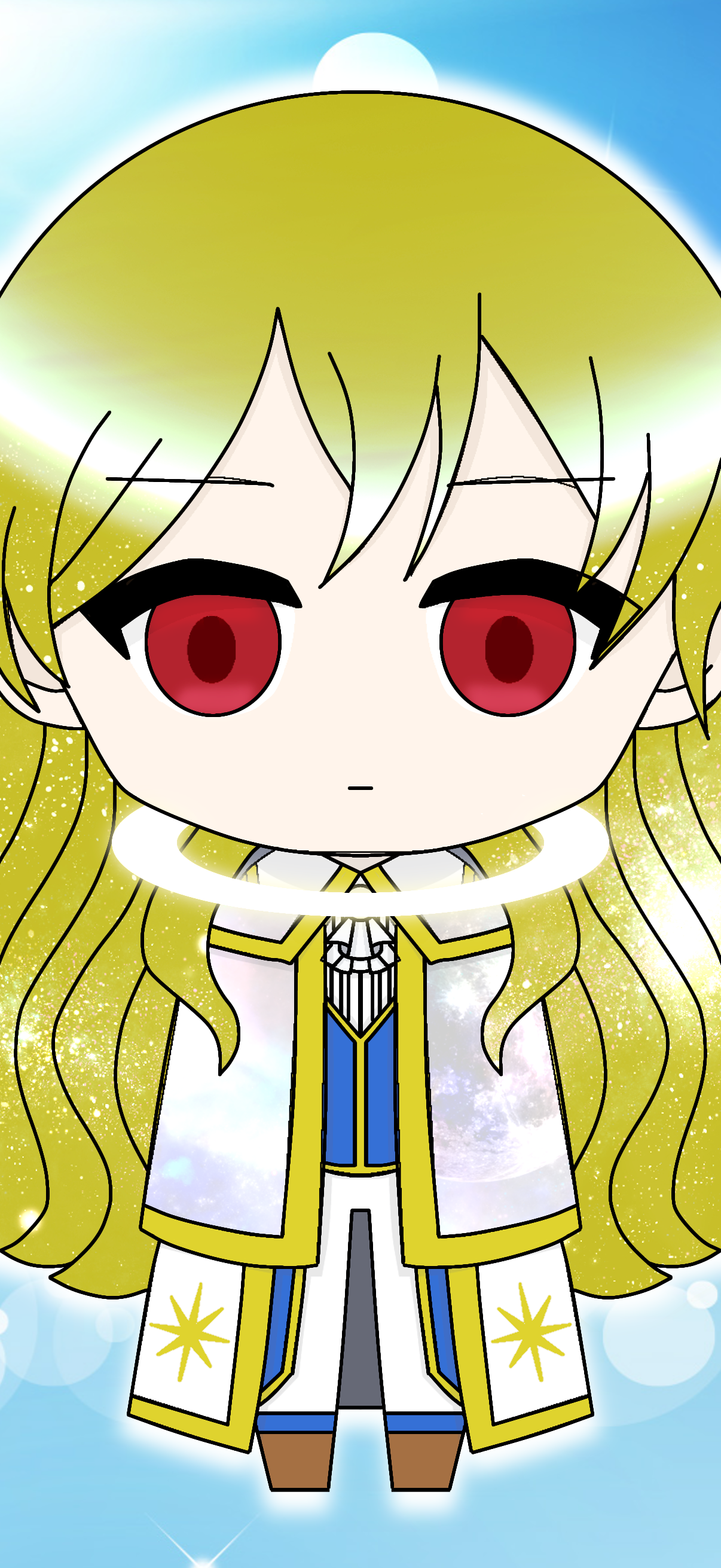
『……』
問いかけに答える気はないらしい。
ただじっとこちらを見据える男に、痺れを切らしたのはルシャントだった。
青い剣を顕現し、蝶の翅で羽ばたいたルシャントは一気に肉薄する。
「アストルムっ……‼︎‼︎」
《星神アストルム》。
この世界を想像した唯一の神。
迫り来る蝶の斬撃にぴくりともせず、そっと手を翳した。
「ぐうっっっ⁉︎」
ただそれだけだった。
目に見えぬ圧に抑えつけられたルシャントは瞬く間に地上へと堕とされ、地面に窪みを作るほど押しつぶされる。
抵抗しようと力を振り絞るも圧力は増し、まともな呻き声すら上げられないまま血反吐を吐き捨てた。
「ルシャント!」
「ダメ、アステル君っ‼︎」
助けようと飛び出したアステルを背後から抱きついて制止する。テリトリーに入ったところで二の舞だ。抗う術はない。
トドメを刺そうと手を動かしたアストルム。
一瞬の思考の先、アストルムとルシャントの間に滑り込んだリアムは聞こえるように叫んだ。
「お待ちくださいアストルム様!」
『……』
「リアム……?」
一体何をするつもりなのかとアステル達三人が訝しむ視線を受けつつ、リアムは食指をアストルムに『突き立てた』。
「僕は貴方が作り出した女神アストレアを知っています!」
アストレア──それは、密かに生み出されたアストルムの分身とも呼べる女神。
噂ですらないその存在の在りかを、リアムはあろうことか『脅し』として利用したのだ。
「貴方にほんの少しの愛情があるのなら、彼女の幸せを願う気持ちがあるのなら、今すぐ攻撃をやめてください! さもなければ真実を世界中に広めることになりますよ!」
携帯端末をチラつかせながら訴えるリアムの心臓はこれまでにないほど波打っている。
人様でなく神様を脅してしまうとは。これは地獄落ち決定だなと微かに思いながら。
そんな訴えが通じたのか、ルシャントは圧力から解放された。ルシャントは立つことすらままならなかったが、どうにか無事なようだ。
良かったと安堵するも一転。「うわっ⁉︎」とアステルの悲鳴が轟く。そちらを見遣れば、アステルの体が宙に浮きアストルムのもとへ。
「かっ、……」
「アステル君!」
意識を奪ったアストルムは、最後と言わんばかりに──ルートヴィッヒを見つめる。
『……『リーヴ』を探し出せ。ヤツの息子よ』
「!」
『……それまで預かっておく』
「ま、……て……!」
ふらつきながらも立ち上がるルシャントに見向きもせず、アストルムはアステルとともにその場から消え去ってしまう。
アストルムの登場。アステルの誘拐。そして『リーヴ』という名の人物。
「なにがどうなってるの……?」
ルシャントを介抱するリアムは眉を顰めるばかりであった。
