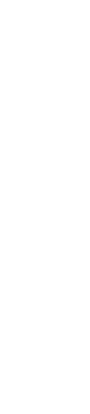夜蝶の灯火Ⅰ
夢小説設定
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
初めて一歩外に出れば、あまり人気がないスラム街のような光景。そして後ろを振り返れば、ネオンの配管で模った"Devil May Cry"という文字が目に入りそれを見上げた。
"Devil May Cry"......
《分かりやすい看板ですね》
スマホの画面をトリッシュに見せると、最初、不思議そうな驚いた表情を見せるが小さく笑みを浮かべて同じく看板を見上げる。
「そう......そういう事ね。今までその機械でダンテと話してたのね」
《これ、日本語を英語に変換してくれるのでこれで会話ができるんです。でも簡単な単語は調べられてすぐに意味は分かるんですけど、ネイティブだとどうしても早くて聞き取れなくて、何を話しているのか分からないんです》
「すごい機能をもった機械なのね」
《トリッシュさんは持ってないんですか?スマホ.....》
「スマホ......?」
「あっ、スマートフォン!」
正式名称で伝わるかと思い千尋がトリッシュに伝えるが、当の本人は苦笑いを浮かべるながら「分からない」という仕草をした。それに違和感を感じて、スマホを操作して恐る恐るトリッシュに向ける。
《今、何年の何月ですか?》
「えーと、今は19ーーー...」
「!?」
"19ーーー"からの単語に事務所に引き返してドアを開ける。
「千尋!?」
トリッシュが声を掛けるがお構いなしに入って行き、その音でソファーに寝ていたダンテが目を開いて千尋を横目に見た。
「どうした?トリッシュと買い物に行ったんじゃないのか?」
「.........」
ダンテの声にも答えずに千尋がテーブルにあった新聞を手に取り何かを確認すると、そのままダンテの向かいのソファーに力なく座り込む。身体を起こしたダンテが入り口の壁に寄りかかるトリッシュに問う。
「何が起きた?」
「よく私も分からないんだけど、千尋が年月日を聞いた瞬間、驚いた顔してーーー...」
それを聞いて、ふとダンテの中で先程免許証を見せてもらった事を思い出す。そこには確か、千尋の生年月日が19ーーから始まるもので、普通に考えてみれば、もちろんこの年には生まれていないことになるのだ。
「そういう事か...」
「私にも分かる様に説明してくれる?」
「要は千尋はこの世に存在してないってことだよ」
頭を抱えて俯く千尋を横目にダンテが預かっていた免許証を懐から取り出し、スッとトリッシュへと投げてそれを見事に受け取り、ダンテの言った通り生年月日に目を通す。それは紛れもなく今のいる時代と違っていた。
「千尋は...未来から来たって事かしら?」
「何とも信じがたい事実だな」
「あら。ダンテも知らなかった口ぶりね」
「免許証を見た時点で気づくべきだったぜ」
不意に千尋の肩が震え出し、鼻をすする音と同時に掠れた声を出すーーー。
『私、帰りたいっ......なんでここに連れて来られたのっ......どうしてっ......』
次の瞬間、ダンテが千尋と同じ高さになるようにしゃがみ込み、その大きな手を頭の上に乗せる。その行動にトリッシュが「ワオ!」と驚く仕草をして、それに構わずダンテが千尋に声を掛けた。
「無事に帰してやる。だから泣くな」
"泣くな"。その言葉の意味だけが千尋には分かり、ダンテが優しい言葉をかけてくれていると分かっていても、どうしても不安と現状を呑み込めずに涙が溢れでて止まらない。千尋が落ち着くまで待とうとダンテがトリッシュに声を掛ける。
「トリッシュ、話がある」
「OK」
千尋の座るソファから少し離れ、入り口付近で千尋を横目で見るダンテにトリッシュが口を開くーーー。
「何か他に気になる事でもあるの?」
「あぁ。悪魔が現れた時、もちろん千尋は悪魔に怯えていたが、それよりも俺の銃と銃声に酷く怯えてた」
「なら、当分の間はあなたの相棒はお休みね」
「それは約束できねーな。俺を廃業にする気か?」
「あら。あなたの相棒は銃だけじゃないでしょう?」
「笑わせるな。コイツを使わねーと、エボリーもアイボリーも寂しがるだろ」
確かにトリッシュの言う通り、千尋がエボリーとアイボリーに敏感に怯えているのなら極力控えた方が得策だが、ダンテからしたらそういう訳にもいかないのも確かで。ふとソファを見据えれば、いつの間にか泣き疲れたのか寝息をたてて眠る千尋の姿が目に入った。
「泣き疲れちゃったみたいね。年上と言っても、幼く見えるわね」
「悪いが買い物はまた今度にしてくれ」
仕方がないと言った表情のトリッシュに手を挙げて事務所の中に入りドアを閉める。カバンを持って眠る千尋を横抱きに抱きかかえ、二階の階段を上る。部屋に入り千尋をベッドに横たわらせると軽くシーツをかけた。
"Devil May Cry"......
《分かりやすい看板ですね》
スマホの画面をトリッシュに見せると、最初、不思議そうな驚いた表情を見せるが小さく笑みを浮かべて同じく看板を見上げる。
「そう......そういう事ね。今までその機械でダンテと話してたのね」
《これ、日本語を英語に変換してくれるのでこれで会話ができるんです。でも簡単な単語は調べられてすぐに意味は分かるんですけど、ネイティブだとどうしても早くて聞き取れなくて、何を話しているのか分からないんです》
「すごい機能をもった機械なのね」
《トリッシュさんは持ってないんですか?スマホ.....》
「スマホ......?」
「あっ、スマートフォン!」
正式名称で伝わるかと思い千尋がトリッシュに伝えるが、当の本人は苦笑いを浮かべるながら「分からない」という仕草をした。それに違和感を感じて、スマホを操作して恐る恐るトリッシュに向ける。
《今、何年の何月ですか?》
「えーと、今は19ーーー...」
「!?」
"19ーーー"からの単語に事務所に引き返してドアを開ける。
「千尋!?」
トリッシュが声を掛けるがお構いなしに入って行き、その音でソファーに寝ていたダンテが目を開いて千尋を横目に見た。
「どうした?トリッシュと買い物に行ったんじゃないのか?」
「.........」
ダンテの声にも答えずに千尋がテーブルにあった新聞を手に取り何かを確認すると、そのままダンテの向かいのソファーに力なく座り込む。身体を起こしたダンテが入り口の壁に寄りかかるトリッシュに問う。
「何が起きた?」
「よく私も分からないんだけど、千尋が年月日を聞いた瞬間、驚いた顔してーーー...」
それを聞いて、ふとダンテの中で先程免許証を見せてもらった事を思い出す。そこには確か、千尋の生年月日が19ーーから始まるもので、普通に考えてみれば、もちろんこの年には生まれていないことになるのだ。
「そういう事か...」
「私にも分かる様に説明してくれる?」
「要は千尋はこの世に存在してないってことだよ」
頭を抱えて俯く千尋を横目にダンテが預かっていた免許証を懐から取り出し、スッとトリッシュへと投げてそれを見事に受け取り、ダンテの言った通り生年月日に目を通す。それは紛れもなく今のいる時代と違っていた。
「千尋は...未来から来たって事かしら?」
「何とも信じがたい事実だな」
「あら。ダンテも知らなかった口ぶりね」
「免許証を見た時点で気づくべきだったぜ」
不意に千尋の肩が震え出し、鼻をすする音と同時に掠れた声を出すーーー。
『私、帰りたいっ......なんでここに連れて来られたのっ......どうしてっ......』
次の瞬間、ダンテが千尋と同じ高さになるようにしゃがみ込み、その大きな手を頭の上に乗せる。その行動にトリッシュが「ワオ!」と驚く仕草をして、それに構わずダンテが千尋に声を掛けた。
「無事に帰してやる。だから泣くな」
"泣くな"。その言葉の意味だけが千尋には分かり、ダンテが優しい言葉をかけてくれていると分かっていても、どうしても不安と現状を呑み込めずに涙が溢れでて止まらない。千尋が落ち着くまで待とうとダンテがトリッシュに声を掛ける。
「トリッシュ、話がある」
「OK」
千尋の座るソファから少し離れ、入り口付近で千尋を横目で見るダンテにトリッシュが口を開くーーー。
「何か他に気になる事でもあるの?」
「あぁ。悪魔が現れた時、もちろん千尋は悪魔に怯えていたが、それよりも俺の銃と銃声に酷く怯えてた」
「なら、当分の間はあなたの相棒はお休みね」
「それは約束できねーな。俺を廃業にする気か?」
「あら。あなたの相棒は銃だけじゃないでしょう?」
「笑わせるな。コイツを使わねーと、エボリーもアイボリーも寂しがるだろ」
確かにトリッシュの言う通り、千尋がエボリーとアイボリーに敏感に怯えているのなら極力控えた方が得策だが、ダンテからしたらそういう訳にもいかないのも確かで。ふとソファを見据えれば、いつの間にか泣き疲れたのか寝息をたてて眠る千尋の姿が目に入った。
「泣き疲れちゃったみたいね。年上と言っても、幼く見えるわね」
「悪いが買い物はまた今度にしてくれ」
仕方がないと言った表情のトリッシュに手を挙げて事務所の中に入りドアを閉める。カバンを持って眠る千尋を横抱きに抱きかかえ、二階の階段を上る。部屋に入り千尋をベッドに横たわらせると軽くシーツをかけた。