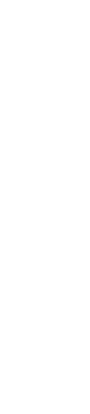夜蝶の灯火Ⅰ
夢小説設定
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
事務所にある古い階段を上り、ある部屋の前で足を止める。ダンテは思った以上に高身長で、身体つきもガッシリした体型だとこの時、千尋は気づく。
「俺の部屋だが...とりあえず今はここ使え」
《でも、ダンテさんは?》
「仕方ねーだろ。なんならフカフカのベッドよりソファで寝るか?」
「私、ソファ大丈夫」
機械を使わずに片言の英語を繋ぎ合わせて言う千尋だが、なぜかダンテは深い溜息を吐いて不意に千尋からカバンを奪い、ベッドの方に放り投げて千尋を部屋の中に押し込む。
『ちょっ...!』
「いいから使えよ。休んどけ」
バタンとドアが閉まりダンテの姿が見えなくなり、千尋は数秒だけ唖然とドアを見つめるしか出来ずーーー。
改めて部屋を見渡せば、殺風景な内装にサイドテーブルとベッドがあるだけで。
『も、もしかして.........怒らせちゃった......?』
その時、不覚にも千尋の腹の虫が騒ぎ出し音を立てそっとお腹に手を置く。家を出てから何も食べていない事に気づくが、ダンテに遠慮することもあって、その日は部屋から出ることはできなかった。
ーーーーーーーーーーー
一切れのピザを口に運ぼうとして、その手を止めた。その傍らには好物のストロベリーサンデー。
部屋に入れたのはいいが、腹が減っているかもしれないと思い大袈裟だが罪悪感が湧き、重い腰を上げて二階へと足を進める。ノックをしても反応はなく、躊躇なく部屋のドアを開ける。
「......あ、...えと......ごめんなさい」
ボーっとしていたのか窓の外からダンテに目線を戻して申し訳なさそうに俯くが、何に対しての「ごめん」なのか分からずダンテが言葉を続けた。
「腹、減ってねーか?」
「あー、..........」
千尋は少し考えてから控えめに首を振り、相変わらず顔を上げない千尋にダンテが壁に寄り掛かった時だったーーー。
「.......!」
それは一瞬のこと。ベッドに座る千尋の背後の窓から黒い何かが風になびいて千尋を包み込もうとする。咄嗟に腰から二丁のエボニーとアイボリーを構えて、その黒い何かに銃弾を撃つーーー。その弾は千尋の横を掠めて黒い何かに命中し、紺色の蝶に変化したあともう一発打ち込み、その場に屍骸として落ちていく。
が、その瞬間には銃声と二丁の拳銃を見た千尋がベッドから素早く降りて、酷く怯えた様子で背中を丸め、部屋の端で身体を震わせていたから。
『ゃっ.......殺さないで!!お願いっ!......助けて......!!』
ダンテには叫んでいる日本語の意味は分からないが、悪魔に怯えているというよりもエボニーとアイボリーと、そしてその銃声に怯えているといった方が当てはまる。二丁の銃を仕舞い込み、屍骸に目を向ければ周りに銀の粉が撒かれ、蝶というよりは蛾のような見た目。それを横目に背中を丸くする千尋の背後にしゃがみ声をかけた。
「もう大丈夫だ。落ち着け」
『っ.......ゃだっ.......撃たないでっ.......!』
ぎゅっと耳を塞ぐ千尋の手をダンテが両手で両手首を掴んで無理やりと言っていいほどの力で引き離し、グイっと身体を反転させた。小刻みに震えるその身体から、地面には無数の涙のシミが浮き出て床を濡らしている。
「誰もお前を撃ちやしねーよ」
「...........!」
何かに弾かれたように顔を上げて千尋が目を見開いたままダンテのブルーアイの瞳を見据える。日本語が飛び出してくると思いきや、片言のそして震えた声がダンテの耳に響く。
「......私を、......殺す、の......?」
「殺さない。お前を殺す意味は俺にはないからな」
最初の"殺さない"という単語を理解したのか、ようやく強張っていた身体の力を抜いてその場にへたり込む。千尋の目線を辿れば、ダンテの背後にある蝶の屍骸を目にして壁に背中を押し付けながら指を差す。
「蝶っ........知ってる.....夢、見たっ......」
「夢?」
小さく頷く千尋からダンテが同じく蝶の屍骸に目を向ける。
「銃.......あなたのーーー.....」
眉を潜めて何か考えるように言葉を詰まらせる千尋を見て、ダンテは何となく言いたいことを察さして屍骸から目線を千尋に向けた。
「無理して話すことはねーよ」
『話すーーー.....あぁ......そうか......』
日本語を呟き、ひとり納得する仕草を見せたかと思えば顔を上げてダンテに向かい少しだけ口元を緩ませるーーー。
「......ありがとう......」
「!」
初めて千尋の笑った笑顔を見て、ダンテは一瞬驚いた表情を浮かべるがすぐに同じように薄く口元を上げた。
「ーーー誰も居ないみたいね......」
そして何事もなかったように立ち上がったのと同時に、事務所のドアが開くのが聞こえ、女性の声が部屋まで聞こえる。ダンテはウンザリしたような表情を見せて千尋にも声をかける。
「来い」
千尋が頷いて立ち上がれば階段を下りるダンテについて行き、事務所に入ればそこにはスタイルのいい髪の長い金髪の女性がビリヤード台の端に座り、黒い8ボールを指で弄んでいる。少し露出の激しい服装に女の千尋でも目のやり場に困り、最後の階段を下りたところで足を止めた。
ダンテはそんなのお構いなしにいつもの定位置である椅子に腰を下ろしてテーブルに足を投げ出し呟く。
「何の用だ?」
「相変わらず冷たいわね。......その子が例の子?」
金髪の女性が立ち上がり、階段の前に立つ千尋に紅い唇で微笑み顔を覗かせると、千尋が咄嗟に目を逸らして俯く。
「千尋、よね?私はトリッシュ。ダンテの元相棒」
「何喋っても英語が通じねーぞ」
「それを早く言ってちょうだい」
トリッシュは千尋の肩に軽く手を置いて微笑み、改めてダンテに向き直った。
「早く用件を言え」
「その子の蝶の痣、......いえ。その前にどうしてここから悪魔の気配が微かにするのかしら?」
「ついさっきまで悪魔がお出ましになったからな」
「やっぱり来て正解だったわ。あの子の痣、.....あれが悪魔の目印になってるの。それに吸い寄せられて悪魔がここに現れた」
「他の行方不明になったっていう奴らもか?」
「いいえ。その行方不明者は痣以外は無傷で帰ってくるけど、まるで前より人が変わったって家族が口々に話してるのよ」
その言葉にダンテが少し顔を上げてチラリと千尋を見れば不安げな表情の裏に、恐らく悪魔や蝶という単語で何の話をしているのか察しがついたようだ。いつの間にか階段に腰を下ろしていた千尋にダンテが軽く手招きをすると、おずおずと空いているソファーに腰を下ろす。その様子からして何か考え込んでいる様にも見えなくもない。
『.......ダンテさん』
語尾は日本語だが名前を呼ばれてダンテが千尋に目を向け、話していたトリッシュも同じく目線を向けて次の言葉を待つ。
『あ、......えーと、.......何て言うんだっけ......』
「......私、英語、勉強ーーー......勉強がしたい、英語の」
「英語の勉強?」
言葉が通じた安堵からか先ほどより大きく首を立てに振る千尋にトリッシュが関心と言わんばかりに同じく頷く。
勉強、か。
チラシの裏に書かなくても済むなら楽になるかもな。
「関心ね。言葉が分からないとこの子から話も聞けないし、ある程度の単語は把握してるみたいだから教えてあげたら?」
「レディといいお前といい、なんで俺に押し付ける?」
「この子のご指名なんだから仕方がないんじゃない?」
「.......報酬はないにしろ、教える価値はあるかもな」
「えぇ、それはもちろん。分かってるじゃない.....巷の悪魔の話もそうだけど、私、この子に用があったのよ」
「千尋にか?」
ダンテが千尋の名前を口にした時、ダンテの方を見据えて首を傾げる仕草をした。
「気分転換に買い物でも行きましょうか」
「買い物.......?」
「そう。いつまで居るかわからいもの。洋服が必要でしょう?」
「あー.....私と、あなた、買い物......?」
千尋は自分を指差してトリッシュに疑問を投げかければ、トリッシュは軽く頷いて笑顔を見せた。すると千尋が眉を下げて心配そうにダンテの方を見て言葉を求めるーーー。
それにダンテが薄く笑い、軽く頷けばまたしても千尋が一瞬だけ微笑み笑顔を見せていた。
「俺の部屋だが...とりあえず今はここ使え」
《でも、ダンテさんは?》
「仕方ねーだろ。なんならフカフカのベッドよりソファで寝るか?」
「私、ソファ大丈夫」
機械を使わずに片言の英語を繋ぎ合わせて言う千尋だが、なぜかダンテは深い溜息を吐いて不意に千尋からカバンを奪い、ベッドの方に放り投げて千尋を部屋の中に押し込む。
『ちょっ...!』
「いいから使えよ。休んどけ」
バタンとドアが閉まりダンテの姿が見えなくなり、千尋は数秒だけ唖然とドアを見つめるしか出来ずーーー。
改めて部屋を見渡せば、殺風景な内装にサイドテーブルとベッドがあるだけで。
『も、もしかして.........怒らせちゃった......?』
その時、不覚にも千尋の腹の虫が騒ぎ出し音を立てそっとお腹に手を置く。家を出てから何も食べていない事に気づくが、ダンテに遠慮することもあって、その日は部屋から出ることはできなかった。
ーーーーーーーーーーー
一切れのピザを口に運ぼうとして、その手を止めた。その傍らには好物のストロベリーサンデー。
部屋に入れたのはいいが、腹が減っているかもしれないと思い大袈裟だが罪悪感が湧き、重い腰を上げて二階へと足を進める。ノックをしても反応はなく、躊躇なく部屋のドアを開ける。
「......あ、...えと......ごめんなさい」
ボーっとしていたのか窓の外からダンテに目線を戻して申し訳なさそうに俯くが、何に対しての「ごめん」なのか分からずダンテが言葉を続けた。
「腹、減ってねーか?」
「あー、..........」
千尋は少し考えてから控えめに首を振り、相変わらず顔を上げない千尋にダンテが壁に寄り掛かった時だったーーー。
「.......!」
それは一瞬のこと。ベッドに座る千尋の背後の窓から黒い何かが風になびいて千尋を包み込もうとする。咄嗟に腰から二丁のエボニーとアイボリーを構えて、その黒い何かに銃弾を撃つーーー。その弾は千尋の横を掠めて黒い何かに命中し、紺色の蝶に変化したあともう一発打ち込み、その場に屍骸として落ちていく。
が、その瞬間には銃声と二丁の拳銃を見た千尋がベッドから素早く降りて、酷く怯えた様子で背中を丸め、部屋の端で身体を震わせていたから。
『ゃっ.......殺さないで!!お願いっ!......助けて......!!』
ダンテには叫んでいる日本語の意味は分からないが、悪魔に怯えているというよりもエボニーとアイボリーと、そしてその銃声に怯えているといった方が当てはまる。二丁の銃を仕舞い込み、屍骸に目を向ければ周りに銀の粉が撒かれ、蝶というよりは蛾のような見た目。それを横目に背中を丸くする千尋の背後にしゃがみ声をかけた。
「もう大丈夫だ。落ち着け」
『っ.......ゃだっ.......撃たないでっ.......!』
ぎゅっと耳を塞ぐ千尋の手をダンテが両手で両手首を掴んで無理やりと言っていいほどの力で引き離し、グイっと身体を反転させた。小刻みに震えるその身体から、地面には無数の涙のシミが浮き出て床を濡らしている。
「誰もお前を撃ちやしねーよ」
「...........!」
何かに弾かれたように顔を上げて千尋が目を見開いたままダンテのブルーアイの瞳を見据える。日本語が飛び出してくると思いきや、片言のそして震えた声がダンテの耳に響く。
「......私を、......殺す、の......?」
「殺さない。お前を殺す意味は俺にはないからな」
最初の"殺さない"という単語を理解したのか、ようやく強張っていた身体の力を抜いてその場にへたり込む。千尋の目線を辿れば、ダンテの背後にある蝶の屍骸を目にして壁に背中を押し付けながら指を差す。
「蝶っ........知ってる.....夢、見たっ......」
「夢?」
小さく頷く千尋からダンテが同じく蝶の屍骸に目を向ける。
「銃.......あなたのーーー.....」
眉を潜めて何か考えるように言葉を詰まらせる千尋を見て、ダンテは何となく言いたいことを察さして屍骸から目線を千尋に向けた。
「無理して話すことはねーよ」
『話すーーー.....あぁ......そうか......』
日本語を呟き、ひとり納得する仕草を見せたかと思えば顔を上げてダンテに向かい少しだけ口元を緩ませるーーー。
「......ありがとう......」
「!」
初めて千尋の笑った笑顔を見て、ダンテは一瞬驚いた表情を浮かべるがすぐに同じように薄く口元を上げた。
「ーーー誰も居ないみたいね......」
そして何事もなかったように立ち上がったのと同時に、事務所のドアが開くのが聞こえ、女性の声が部屋まで聞こえる。ダンテはウンザリしたような表情を見せて千尋にも声をかける。
「来い」
千尋が頷いて立ち上がれば階段を下りるダンテについて行き、事務所に入ればそこにはスタイルのいい髪の長い金髪の女性がビリヤード台の端に座り、黒い8ボールを指で弄んでいる。少し露出の激しい服装に女の千尋でも目のやり場に困り、最後の階段を下りたところで足を止めた。
ダンテはそんなのお構いなしにいつもの定位置である椅子に腰を下ろしてテーブルに足を投げ出し呟く。
「何の用だ?」
「相変わらず冷たいわね。......その子が例の子?」
金髪の女性が立ち上がり、階段の前に立つ千尋に紅い唇で微笑み顔を覗かせると、千尋が咄嗟に目を逸らして俯く。
「千尋、よね?私はトリッシュ。ダンテの元相棒」
「何喋っても英語が通じねーぞ」
「それを早く言ってちょうだい」
トリッシュは千尋の肩に軽く手を置いて微笑み、改めてダンテに向き直った。
「早く用件を言え」
「その子の蝶の痣、......いえ。その前にどうしてここから悪魔の気配が微かにするのかしら?」
「ついさっきまで悪魔がお出ましになったからな」
「やっぱり来て正解だったわ。あの子の痣、.....あれが悪魔の目印になってるの。それに吸い寄せられて悪魔がここに現れた」
「他の行方不明になったっていう奴らもか?」
「いいえ。その行方不明者は痣以外は無傷で帰ってくるけど、まるで前より人が変わったって家族が口々に話してるのよ」
その言葉にダンテが少し顔を上げてチラリと千尋を見れば不安げな表情の裏に、恐らく悪魔や蝶という単語で何の話をしているのか察しがついたようだ。いつの間にか階段に腰を下ろしていた千尋にダンテが軽く手招きをすると、おずおずと空いているソファーに腰を下ろす。その様子からして何か考え込んでいる様にも見えなくもない。
『.......ダンテさん』
語尾は日本語だが名前を呼ばれてダンテが千尋に目を向け、話していたトリッシュも同じく目線を向けて次の言葉を待つ。
『あ、......えーと、.......何て言うんだっけ......』
「......私、英語、勉強ーーー......勉強がしたい、英語の」
「英語の勉強?」
言葉が通じた安堵からか先ほどより大きく首を立てに振る千尋にトリッシュが関心と言わんばかりに同じく頷く。
勉強、か。
チラシの裏に書かなくても済むなら楽になるかもな。
「関心ね。言葉が分からないとこの子から話も聞けないし、ある程度の単語は把握してるみたいだから教えてあげたら?」
「レディといいお前といい、なんで俺に押し付ける?」
「この子のご指名なんだから仕方がないんじゃない?」
「.......報酬はないにしろ、教える価値はあるかもな」
「えぇ、それはもちろん。分かってるじゃない.....巷の悪魔の話もそうだけど、私、この子に用があったのよ」
「千尋にか?」
ダンテが千尋の名前を口にした時、ダンテの方を見据えて首を傾げる仕草をした。
「気分転換に買い物でも行きましょうか」
「買い物.......?」
「そう。いつまで居るかわからいもの。洋服が必要でしょう?」
「あー.....私と、あなた、買い物......?」
千尋は自分を指差してトリッシュに疑問を投げかければ、トリッシュは軽く頷いて笑顔を見せた。すると千尋が眉を下げて心配そうにダンテの方を見て言葉を求めるーーー。
それにダンテが薄く笑い、軽く頷けばまたしても千尋が一瞬だけ微笑み笑顔を見せていた。