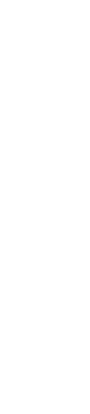夜蝶の灯火Ⅰ
夢小説設定
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
蝶の夢を見た。
キラキラ光る紺色の蝶。
その無数の蝶はキラキラした粉を振りまいては周りを飛び、
それは眩しささえ覚えた。
「ーーーっ......」
「.....ーーー起きたみいよ、お嬢ちゃん」
優しい女性の声が微かに耳に響き、薄っすらと目を開ければ顔を覗き込むショートカットの女性と目が合う。
それはほんの数秒の出来事で、脳内が覚醒し始めたときには眠っていたソファーから起き上がり、ガタっと音を立ててそばの壁へと後ずさりしていた。
「あら.....ごめんなさい。ビックリさせちゃったわね」
『えっ.......え.......?』
「怖がらせてどうすんだよ」
男の声がすると思い千尋がそこに目を向ければ、椅子に座り足を投げ出す姿と雑誌で顔を窺い知ることができずより一層不安を掻き立てられるーーー。
「そりゃ、突然知らないこんなボロイ家にいれば怖がるのは当たり前じゃない」
「こんなボロイ家に連れて来たのはどこのどいつだよ」
そう言って雑誌の裏から顔を出した男性は、珍しいくらいの銀髪でその銀髪の間からは綺麗なブルーアイの瞳が見え、思わず吸い込まれそうになる。二人が何を話しているのかさっぱり分からないが、ここはどこなのか、この人たちは何者なのかより、不思議な雰囲気に言葉を詰まらせた。
すると女性が少しずつ近づき、安心させるかのように千尋の顔を覗き込み笑みを浮かべる。
「あなた、名前は?」
「ぁ........千尋、白石.....です」
「東洋人?.....名前からして日本人かしら」
簡単な英会話、単語はわかるものの、それで理解をして自分の名前を英語で口にすれば「日本」という言葉に反応して控えめに頷く。
「少なからず、英語は通じるみたいね」
「......え、英語、少しだけ......」
「そう.....あなた、近くの路地裏で倒れてたのよ。覚えてる?」
「..............?」
首を傾げる千尋の様子を見れば、伝わっていないのは明白で女性が眉を下げて一歩だけ距離をとる。すると何を思い立ったのか、千尋が肩に掛けていたカバンをあさり始めて何か小さい薄っぺらい機械を取り出して操作し始めた。
「.......なんだ、その変な機械」
「さぁ......」
二人が不思議そうに見つめる中、千尋が操作していた手を止めて、画面を女性に見せた。そこには英文で《ここはどこですか?あなた達は誰ですか?》と。二人は顔を見合わせて驚いた表情を見せた。
「ここは"Devil May Cry"っていうあそこにいるダンテがやってる便利屋さんよ。そして、私はレディ。まぁ、私もダンテと同じ家業ってとこかしら」
千尋は相変わらずその小さな機械を見て何かを読む仕草をすると、機械から顔を上げて頷き再びその機械を見せる。ダンテも気になったのか、椅子から腰を上げて向かいのソファーに再び腰を下ろして機械を覗き込んだ。
《便利屋なのはわかりました。でもここは日本じゃないんですか?》
「まさか、このちっこい機械で言葉がわかるのか」
「そうみたいね。......ここは少なくとも日本じゃないわ。どうやってここまで来たか、覚えてる?」
《自分でも分からないんです。なんでここにいるのか......日本に居たはずなのに......》
「瞬間移動でもして来たってのか?」
「観光旅行にしては、荷物もこのカバンだけだし......」
レディが考え込む仕草をして不意に千尋の二の腕に目を向けた時、蝶の痣 を発見して咄嗟にその腕を取る。
「........っ!」
「ダンテ!これ見て」
「蝶......?」
二の腕の痣をダンテに見せれば微かに渋い表情を見せ、それは千尋にも安易に伝わり自分の二の腕に目を向けた。その痣は千尋にも見に覚えがないらしく、その痣を見て身体の動きを止めていた。
「この蝶の痣......聞いたことがあるわ。最近、ここあたりで行方不明者が続出していて、見つかった行方不明者にはこの蝶の痣があるらしいの。でも、この子の痣は黒.....。その行方不明者の痣は赤色だそうよ」
「悪魔絡みか。厄介なお嬢ちゃんを連れ込んだもんだぜ」
「悪魔絡みなら本業でしょう?」
"悪魔"という単語に千尋が酷く反応を見せ、掴んでいたレディの手を振り払い少しだけ距離をとる。
この人たち、......"悪魔"とか言ってるけど何なの?
「報酬は、......見込めなそうだな」
「結構いい仕事だとは思うけど。私がここに連れて来たのはその仕事を任せるためだもの」
「は?」
「依頼者は最初にこの子を介抱していた近所のおばあさん。そのおばあさん、なんでも腰が悪いみたいでこの子を預けれる人を捜してたのよ」
「で、俺を勝手に紹介したって訳か」
「そういうこと」
溜息混じりにダンテが背もたれに身体を預ければ、レディが千尋の近くの肘掛に軽く腰を下ろす。しかし警戒しているのか、身体を縮こませていた。
「安心して。千尋がなぜここに来たのか、私の方でも調べてみるわ。その間はここで過ごすといいわ」
「おい、勝手に決め付けんな」
「だって仕方がないでしょう?もう引き受けちゃったんだし」
何だか言い争いをしている二人に千尋が機械を操作してそれを控えめに二人へとかざす。
《あの、どこかホテルを紹介してもらえればそこでしばらく過ごすので》
「ここら辺は治安が悪いの。千尋が一人でいるには危険過ぎるわ。特に夜はね」
《さっきの悪魔、のこと.....?》
「そうよ。夜は悪魔が活発になるから、ダンテと一緒にいた方が得策ね」
《悪魔って......本当にいるんですね......》
「あら。案外、冷静なのね」
「俺は一言もOKなんて言ってないけど」
「もう決定事項なの。私もたまに様子見に来るけど、あとはよろしくね」
そう言ってレディが千尋の頭を軽く撫でて立ち上がり、ダンテに手を振り出て行く。二人の会話が早すぎるのか呑み込めないといった表情を浮かべてから、心配そうに遅れてダンテに目を向けた。
「......勝手に話して出て行きやがった」
「.........」
「ま、とりあえずレディがそう言ってんだ。治安が悪いのに放っぽりだせねーしな」
「......?」
「あー、もう。クソっ!」
ポカンとした表情のまま見つめる千尋にダンテが一瞬眉を潜め立ち上がり、テーブルから紙とペンを引っ張り出す。どこかのチラシ裏を使い、ペンで殴り書きをして千尋に見せた。それを見た千尋がまた小さい機械で操作を始める。
《私のこと、信じてくれるんですか?》
「なんか身分分かるもの持ってるか?」
千尋にも分かるようにゆっくりとした発音で発すれば、機械を覗き込んだあと持っていたカバンの中から財布だろか、それを取り出して中から一枚のカードを取り出す。当然そのカードは日本語で書かれており、分かるのは顔写真だけ。生年月日を見れば、ダンテより少しばかり歳上だった。
《運転免許証です》
「家の連絡先は?」
「......家族、いない。私一人.....」
両親がいないのか。
じゃ、連絡の取り用がねーな。
ふと影を作る千尋の表情に、とりあえずダンテが顎で「付いて来い」という仕草をする。千尋は不思議そうというか、少し警戒しつつもそのダンテの後ろをついて行ったーーー。
キラキラ光る紺色の蝶。
その無数の蝶はキラキラした粉を振りまいては周りを飛び、
それは眩しささえ覚えた。
「ーーーっ......」
「.....ーーー起きたみいよ、お嬢ちゃん」
優しい女性の声が微かに耳に響き、薄っすらと目を開ければ顔を覗き込むショートカットの女性と目が合う。
それはほんの数秒の出来事で、脳内が覚醒し始めたときには眠っていたソファーから起き上がり、ガタっと音を立ててそばの壁へと後ずさりしていた。
「あら.....ごめんなさい。ビックリさせちゃったわね」
『えっ.......え.......?』
「怖がらせてどうすんだよ」
男の声がすると思い千尋がそこに目を向ければ、椅子に座り足を投げ出す姿と雑誌で顔を窺い知ることができずより一層不安を掻き立てられるーーー。
「そりゃ、突然知らないこんなボロイ家にいれば怖がるのは当たり前じゃない」
「こんなボロイ家に連れて来たのはどこのどいつだよ」
そう言って雑誌の裏から顔を出した男性は、珍しいくらいの銀髪でその銀髪の間からは綺麗なブルーアイの瞳が見え、思わず吸い込まれそうになる。二人が何を話しているのかさっぱり分からないが、ここはどこなのか、この人たちは何者なのかより、不思議な雰囲気に言葉を詰まらせた。
すると女性が少しずつ近づき、安心させるかのように千尋の顔を覗き込み笑みを浮かべる。
「あなた、名前は?」
「ぁ........千尋、白石.....です」
「東洋人?.....名前からして日本人かしら」
簡単な英会話、単語はわかるものの、それで理解をして自分の名前を英語で口にすれば「日本」という言葉に反応して控えめに頷く。
「少なからず、英語は通じるみたいね」
「......え、英語、少しだけ......」
「そう.....あなた、近くの路地裏で倒れてたのよ。覚えてる?」
「..............?」
首を傾げる千尋の様子を見れば、伝わっていないのは明白で女性が眉を下げて一歩だけ距離をとる。すると何を思い立ったのか、千尋が肩に掛けていたカバンをあさり始めて何か小さい薄っぺらい機械を取り出して操作し始めた。
「.......なんだ、その変な機械」
「さぁ......」
二人が不思議そうに見つめる中、千尋が操作していた手を止めて、画面を女性に見せた。そこには英文で《ここはどこですか?あなた達は誰ですか?》と。二人は顔を見合わせて驚いた表情を見せた。
「ここは"Devil May Cry"っていうあそこにいるダンテがやってる便利屋さんよ。そして、私はレディ。まぁ、私もダンテと同じ家業ってとこかしら」
千尋は相変わらずその小さな機械を見て何かを読む仕草をすると、機械から顔を上げて頷き再びその機械を見せる。ダンテも気になったのか、椅子から腰を上げて向かいのソファーに再び腰を下ろして機械を覗き込んだ。
《便利屋なのはわかりました。でもここは日本じゃないんですか?》
「まさか、このちっこい機械で言葉がわかるのか」
「そうみたいね。......ここは少なくとも日本じゃないわ。どうやってここまで来たか、覚えてる?」
《自分でも分からないんです。なんでここにいるのか......日本に居たはずなのに......》
「瞬間移動でもして来たってのか?」
「観光旅行にしては、荷物もこのカバンだけだし......」
レディが考え込む仕草をして不意に千尋の二の腕に目を向けた時、蝶の
「........っ!」
「ダンテ!これ見て」
「蝶......?」
二の腕の痣をダンテに見せれば微かに渋い表情を見せ、それは千尋にも安易に伝わり自分の二の腕に目を向けた。その痣は千尋にも見に覚えがないらしく、その痣を見て身体の動きを止めていた。
「この蝶の痣......聞いたことがあるわ。最近、ここあたりで行方不明者が続出していて、見つかった行方不明者にはこの蝶の痣があるらしいの。でも、この子の痣は黒.....。その行方不明者の痣は赤色だそうよ」
「悪魔絡みか。厄介なお嬢ちゃんを連れ込んだもんだぜ」
「悪魔絡みなら本業でしょう?」
"悪魔"という単語に千尋が酷く反応を見せ、掴んでいたレディの手を振り払い少しだけ距離をとる。
この人たち、......"悪魔"とか言ってるけど何なの?
「報酬は、......見込めなそうだな」
「結構いい仕事だとは思うけど。私がここに連れて来たのはその仕事を任せるためだもの」
「は?」
「依頼者は最初にこの子を介抱していた近所のおばあさん。そのおばあさん、なんでも腰が悪いみたいでこの子を預けれる人を捜してたのよ」
「で、俺を勝手に紹介したって訳か」
「そういうこと」
溜息混じりにダンテが背もたれに身体を預ければ、レディが千尋の近くの肘掛に軽く腰を下ろす。しかし警戒しているのか、身体を縮こませていた。
「安心して。千尋がなぜここに来たのか、私の方でも調べてみるわ。その間はここで過ごすといいわ」
「おい、勝手に決め付けんな」
「だって仕方がないでしょう?もう引き受けちゃったんだし」
何だか言い争いをしている二人に千尋が機械を操作してそれを控えめに二人へとかざす。
《あの、どこかホテルを紹介してもらえればそこでしばらく過ごすので》
「ここら辺は治安が悪いの。千尋が一人でいるには危険過ぎるわ。特に夜はね」
《さっきの悪魔、のこと.....?》
「そうよ。夜は悪魔が活発になるから、ダンテと一緒にいた方が得策ね」
《悪魔って......本当にいるんですね......》
「あら。案外、冷静なのね」
「俺は一言もOKなんて言ってないけど」
「もう決定事項なの。私もたまに様子見に来るけど、あとはよろしくね」
そう言ってレディが千尋の頭を軽く撫でて立ち上がり、ダンテに手を振り出て行く。二人の会話が早すぎるのか呑み込めないといった表情を浮かべてから、心配そうに遅れてダンテに目を向けた。
「......勝手に話して出て行きやがった」
「.........」
「ま、とりあえずレディがそう言ってんだ。治安が悪いのに放っぽりだせねーしな」
「......?」
「あー、もう。クソっ!」
ポカンとした表情のまま見つめる千尋にダンテが一瞬眉を潜め立ち上がり、テーブルから紙とペンを引っ張り出す。どこかのチラシ裏を使い、ペンで殴り書きをして千尋に見せた。それを見た千尋がまた小さい機械で操作を始める。
《私のこと、信じてくれるんですか?》
「なんか身分分かるもの持ってるか?」
千尋にも分かるようにゆっくりとした発音で発すれば、機械を覗き込んだあと持っていたカバンの中から財布だろか、それを取り出して中から一枚のカードを取り出す。当然そのカードは日本語で書かれており、分かるのは顔写真だけ。生年月日を見れば、ダンテより少しばかり歳上だった。
《運転免許証です》
「家の連絡先は?」
「......家族、いない。私一人.....」
両親がいないのか。
じゃ、連絡の取り用がねーな。
ふと影を作る千尋の表情に、とりあえずダンテが顎で「付いて来い」という仕草をする。千尋は不思議そうというか、少し警戒しつつもそのダンテの後ろをついて行ったーーー。
1/4ページ