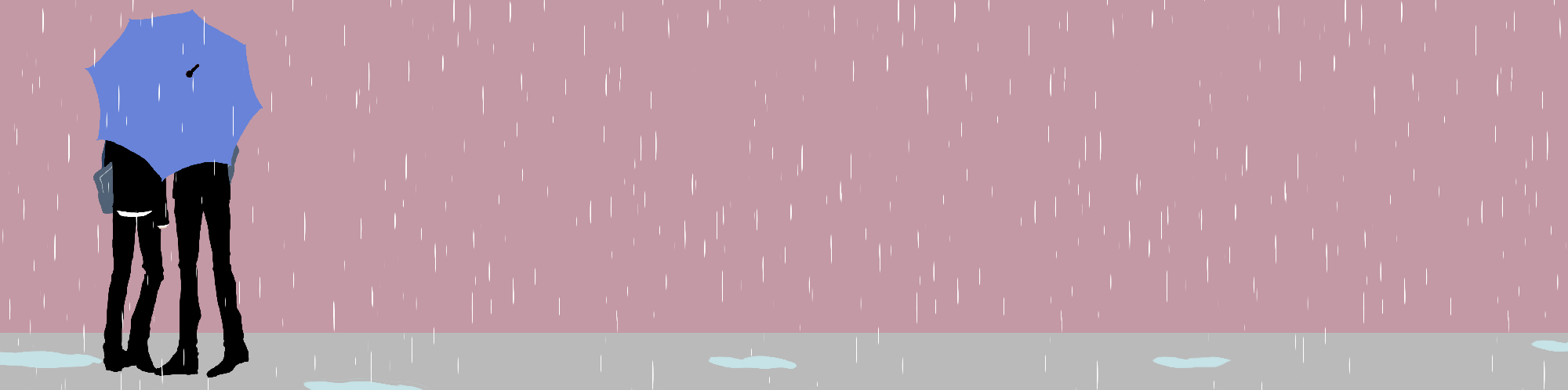姫は王子のもの。
姫野と野島が座る2人掛けのテーブル席は、入店する客の注目を密かに集めていた。
「なんか……僕たち見られてるね」
「そう?」
姫野は目の前のドーナツに夢中だった。春の新作が7種類もあり、結局4つも買ってしまった。
「なんでかな……」
「さあ。俺がドーナツ4つも食べてるから?どうでもいいよ」
姫野と野島は、自分たちの容姿が注目を集めているとは思ってもみない。愛らしい顔をした男子高校生2人組が向かい合ってドーナツを頬張る図が、女子高生やごく一部の男子高生を釘付けにしていたのだ。
「野島、食細いね」
「えー、2つって少なくはないような」
「それおいしい?」
姫野は、野島のプレートに乗っている、自分が買わなかった新作のドーナツを指差した。
「うん。少し食べる?」
「じゃあこれあげる」
野島は自分の手が触れた部分を食べさせることが忍びなく、姫野はただ千切るのが面倒で、お互いに相手の伸ばした手から一口かじった。
店内が低くざわめき、小さく歓声をあげる者もいた。
「やっぱそれも買えばよかった」
「おみやげに買って帰ったら?この後本城くんと会わないの?」
姫野は野島にまだ何も説明していない。昨日、自分と本城のせいで野島が嫌な思いをしたのではないかと案じているのに、それを口にできないでいた。
「会わない。今日は野島と遊ぶ」
「そっか……あの、本城くんと……仲直りした?」
逆にそのことに触れられて言葉につまる。
「ん……まぁ……」
「あ、そうなんだ、よかった」
「昨日……野島……」
笑顔になった野島に、一言謝ろうと切り出す。
「僕?あ、聞いた?土屋くんから」
「土屋?」
土屋の名前が出てくる意味がわからない。
「土屋くんが誘ってくれて、アイス食べに行って、ビリヤード教えてもらって、ダーツやって」
「2人で?」
「うん。カラオケも誘ってくれたんだけど僕は歌わないから土屋くんが歌うならって言って、そしたら土屋くんがそれじゃ野島がつまんないだろって言ってね、僕は全然よかったんだけど、結局少しお茶してから帰ったよ」
土屋。
土屋はまったりお茶なんかするようなやつじゃない。野島に合わせたな。
「……バスケの試合観に来いって言われなかった?」
「言われた言われた!今度観に行こうかと思ってる」
野島はニコニコしながらドーナツをかじった。
土屋は野島さえその気になれば落ちる気がするが、野島の気持ちについては全くわからなかった。今だって、嬉しそうにしているのは友達と楽しく遊べたからなのかもしれない。
土屋のことをどう見ているのか。本当にノンケなのか。
野島に初めて会った時のことを思い出した。
野島は本城と姫野にこう言ったのだった。
『僕は男の子好きにならないから。邪魔はしないから』
「野島は前の学校に彼女とかいなかったわけ」
野島は一瞬視線を落とした。
「……好きな人はいたよ」
「片想いだったの?」
「多分。多分、僕だけだった」
野島は確かめるように言う。叶わない恋だったのだろうか。
「ふぅん」
「ねぇ、姫野くんたちはどうやって付き合うことになったの?」
「忘れた」
「嘘!ねぇどうやって?」
「絶対教えない」
「いいなぁ。僕も新しく好きな人、欲しいなぁ」
男でチャラくてバスケ部でいいなら近くにまあまあな物件がある、と言いかけてやめる。
本人たちが決めればいいことだ。他人が入るとややこしくなる。
「まあ、できるんじゃない、そのうち」
「そうだね。そしたら姫野くん、相談に乗ってくれる?」
ん、と返事をすると、野島は少し下を向いて笑った。なんとなく、野島には想う人がいるような気がした。
この、他人のことばかり考えているお人好しが、大事な人を手に入れられる日が果たして来るのだろうか。
唐突に本城の顔が思い浮かんで、姫野はカップに残っていたカフェオレを飲み干す。
「……やっぱりおみやげドーナツ買おう」
「じゃあ僕も」
プレートを空にした2人は、トレーを下げてから再びカウンターの列に並んだ。
*
はぁ。
本城は、テンション高くマイクを握る友人たちの歌をぼんやり聞きながら、もう何度目かのため息をつく。
どうしても野島と2人で遊ぶと言って譲らなかった姫野に負けて、今日は一日放置されている本城だった。たまたまクラスメイトに誘われて、気分転換にと来たカラオケ。
本城は釈然としない。本城にヤキモチを妬かせたいということはわかっている。わかっていて了承したのに。
やっぱりあまりいいものじゃないな。
明日は2人で何をしよう。本城はグラスを取ってウーロン茶をごくりと飲んだ。
皆でカラオケ店を出たところで、同じ高校の制服を着た生徒が1人、近づいて来るのが目に入った。
また、あいつだ。
本城は内心身構える。
「本城先輩」
笑顔で本城を呼ぶその生徒の髪は銀色で、ほんの少し吊りぎみの目と身軽そうな身のこなしが猫を連想させる。
「カラオケですか。先輩も歌ったりするんだ。いいな、今度俺も連れてって下さいよ」
人懐こそうな笑顔を浮かべて本城を見上げ、一緒にいた本城の友人たちにも愛想を振りまいている。
友人の1人が本城の耳元で「姫の前でこれやられたら厄介だな」と囁く。苦笑でそれに応えながら、本城は思う。
こいつの狙いは俺ではない。だから厄介なんだ。俺だったらどうにでもなったのに。
「あれ?姫野先輩は今日、一緒じゃないんですね」
一同を見回して銀髪の猫が言う。本城はみぞおちのあたりに不快感を覚えた。
「姫は今日は別だよな」
「野島といるんだっけ?」
「本城このあと合流しねぇの?」
何も知らない友人たちが彼にどんどん情報を与えてしまうので、本城は口を開く。
「名前は?」
初対面ではないものの、本城が彼に言葉をかけるのはこれが初めてだった。
自分の名前を聞かれたのだと悟った彼は、嬉しそうに笑った。
「タツキです」
苗字が?それとも名前?まぁどっちでもいい。
野島と平和に過ごしているであろう恋人の顔を思い浮かべて、本城は密かに歯噛みする。
こいつには触れさせない。
初めに声をかけてきた時も、タツキは人懐こそうな笑顔を浮かべていた。
「本城先輩」
先輩、と呼ばれたことで、相手が1年生だと知る。その銀髪に見覚えはなかった。
「近くで見ると、ほんと背高いですね。しかもきれいな金髪。かっこいい」
そう言う相手も背が高い。170代後半くらいか。
初対面にしては馴れ馴れしいと思った。
「目もグレーだ。カラコンじゃないし。……これは落ちますよね。男でも」
本城はまじまじと相手の顔を見た。彼はもう笑っていなかった。かと言って喧嘩を売るような顔でもない。穏やかな無表情に見えた。
しかし本城には相手の目的がうっすら透けて見えた気がした。
はっきり言え。
無言で問うと、人好きのする笑顔に戻ってタツキは言った。
「本城先輩、友達になって下さい」
「イチ!」
本城が記憶の中でしかめ面をしたところで、あらぬ方向から大声が聞こえた。
遠くから猫を呼んだのは、体格のいい短髪。彼も同じ高校の制服を着ている。
「イチ、先に行くぞー」
どうやらタツキを呼んでいるらしいが、タツキは短髪を無視して本城に微笑みかける。
イチとタツキ、どっちが何だ。
「本城、顔怖ぇよ?大丈夫?」
「本城なんで男にモテんの」
「姫もらっていい?」
「本城!浮気か!だめだぞ!」
「そうだぞ、姫に言うぞ」
「言わないから姫ちょうだい?」
友人たちがふざけて口々に言う。それに笑顔で答えられないくらいタツキに苛立っていることを、本城は自覚する。
「イチー!」
短髪がまた呼ぶ。猫の飼い主ってとこか。
「今度、姫野先輩と遊ぶ時に交ぜて下さいね」
タツキは去り際、首を傾げて爽やかに笑って言い、本城は無言で応えた。
言葉すら交わしたくない。交わしたら最後、感情のコントロールができなくなりそうな気がした。
猫と飼い主の後ろ姿をちらりと見遣って、本城は友人の輪に戻る。
無性に姫野に会いたくなった。
夜でもいいから会いたいとメールをしようとして本城が携帯を取り出すと、ちょうど着信していて、表示されている名前に本城の胸は愛しさで満たされる。
「もしもし、姫野?」
うお、このタイミングで本妻から電話、という友人の声は無視することにする。
『ドーナツ食べたい?』
本城はその唐突な提案に微笑んだ。
「食べたい」
姫野の家のリビング。テーブルにはドーナツが7つ。どれも見たことのないもので、姫野は春の新作だと自慢気だ。
買ってきたペットボトルから無糖の紅茶を注ぐ姫野の隣に座り、本城は椅子をさらに姫野の方へ寄せた。
「……何」
「別に?」
「なんか今日、変。気持ち悪い」
「そうかな」
本城はテーブルに横向きに突っ伏して、姫野を見上げた。
大きな目が真剣にドーナツを選んでいる。姫野を迎えに行ったドーナツ店の前で野島から、姫野くんはドーナツを4つも食べたんだよ、と報告を受けたのを思い出す。
「姫野、猫好き?」
本城は冗談半分で、それでも半分は祈るような気持ちで聞いた。
「全然好きじゃない。猫アレルギーだし」
ばっさりと切り捨てた姫野の返事に、本城は声を上げて笑った。
「何?ほんと、変」
口を尖らせる姫野を横から抱きしめた。さっきまで荒みに荒んでいた心が嘘のように凪いだ。
「姫野、知らない猫にはついて行っちゃダメだよ?」
こめかみにキスをすると、は?意味わかんない、と、姫野のいつもの声が聞こえた。
-end-
「なんか……僕たち見られてるね」
「そう?」
姫野は目の前のドーナツに夢中だった。春の新作が7種類もあり、結局4つも買ってしまった。
「なんでかな……」
「さあ。俺がドーナツ4つも食べてるから?どうでもいいよ」
姫野と野島は、自分たちの容姿が注目を集めているとは思ってもみない。愛らしい顔をした男子高校生2人組が向かい合ってドーナツを頬張る図が、女子高生やごく一部の男子高生を釘付けにしていたのだ。
「野島、食細いね」
「えー、2つって少なくはないような」
「それおいしい?」
姫野は、野島のプレートに乗っている、自分が買わなかった新作のドーナツを指差した。
「うん。少し食べる?」
「じゃあこれあげる」
野島は自分の手が触れた部分を食べさせることが忍びなく、姫野はただ千切るのが面倒で、お互いに相手の伸ばした手から一口かじった。
店内が低くざわめき、小さく歓声をあげる者もいた。
「やっぱそれも買えばよかった」
「おみやげに買って帰ったら?この後本城くんと会わないの?」
姫野は野島にまだ何も説明していない。昨日、自分と本城のせいで野島が嫌な思いをしたのではないかと案じているのに、それを口にできないでいた。
「会わない。今日は野島と遊ぶ」
「そっか……あの、本城くんと……仲直りした?」
逆にそのことに触れられて言葉につまる。
「ん……まぁ……」
「あ、そうなんだ、よかった」
「昨日……野島……」
笑顔になった野島に、一言謝ろうと切り出す。
「僕?あ、聞いた?土屋くんから」
「土屋?」
土屋の名前が出てくる意味がわからない。
「土屋くんが誘ってくれて、アイス食べに行って、ビリヤード教えてもらって、ダーツやって」
「2人で?」
「うん。カラオケも誘ってくれたんだけど僕は歌わないから土屋くんが歌うならって言って、そしたら土屋くんがそれじゃ野島がつまんないだろって言ってね、僕は全然よかったんだけど、結局少しお茶してから帰ったよ」
土屋。
土屋はまったりお茶なんかするようなやつじゃない。野島に合わせたな。
「……バスケの試合観に来いって言われなかった?」
「言われた言われた!今度観に行こうかと思ってる」
野島はニコニコしながらドーナツをかじった。
土屋は野島さえその気になれば落ちる気がするが、野島の気持ちについては全くわからなかった。今だって、嬉しそうにしているのは友達と楽しく遊べたからなのかもしれない。
土屋のことをどう見ているのか。本当にノンケなのか。
野島に初めて会った時のことを思い出した。
野島は本城と姫野にこう言ったのだった。
『僕は男の子好きにならないから。邪魔はしないから』
「野島は前の学校に彼女とかいなかったわけ」
野島は一瞬視線を落とした。
「……好きな人はいたよ」
「片想いだったの?」
「多分。多分、僕だけだった」
野島は確かめるように言う。叶わない恋だったのだろうか。
「ふぅん」
「ねぇ、姫野くんたちはどうやって付き合うことになったの?」
「忘れた」
「嘘!ねぇどうやって?」
「絶対教えない」
「いいなぁ。僕も新しく好きな人、欲しいなぁ」
男でチャラくてバスケ部でいいなら近くにまあまあな物件がある、と言いかけてやめる。
本人たちが決めればいいことだ。他人が入るとややこしくなる。
「まあ、できるんじゃない、そのうち」
「そうだね。そしたら姫野くん、相談に乗ってくれる?」
ん、と返事をすると、野島は少し下を向いて笑った。なんとなく、野島には想う人がいるような気がした。
この、他人のことばかり考えているお人好しが、大事な人を手に入れられる日が果たして来るのだろうか。
唐突に本城の顔が思い浮かんで、姫野はカップに残っていたカフェオレを飲み干す。
「……やっぱりおみやげドーナツ買おう」
「じゃあ僕も」
プレートを空にした2人は、トレーを下げてから再びカウンターの列に並んだ。
*
はぁ。
本城は、テンション高くマイクを握る友人たちの歌をぼんやり聞きながら、もう何度目かのため息をつく。
どうしても野島と2人で遊ぶと言って譲らなかった姫野に負けて、今日は一日放置されている本城だった。たまたまクラスメイトに誘われて、気分転換にと来たカラオケ。
本城は釈然としない。本城にヤキモチを妬かせたいということはわかっている。わかっていて了承したのに。
やっぱりあまりいいものじゃないな。
明日は2人で何をしよう。本城はグラスを取ってウーロン茶をごくりと飲んだ。
皆でカラオケ店を出たところで、同じ高校の制服を着た生徒が1人、近づいて来るのが目に入った。
また、あいつだ。
本城は内心身構える。
「本城先輩」
笑顔で本城を呼ぶその生徒の髪は銀色で、ほんの少し吊りぎみの目と身軽そうな身のこなしが猫を連想させる。
「カラオケですか。先輩も歌ったりするんだ。いいな、今度俺も連れてって下さいよ」
人懐こそうな笑顔を浮かべて本城を見上げ、一緒にいた本城の友人たちにも愛想を振りまいている。
友人の1人が本城の耳元で「姫の前でこれやられたら厄介だな」と囁く。苦笑でそれに応えながら、本城は思う。
こいつの狙いは俺ではない。だから厄介なんだ。俺だったらどうにでもなったのに。
「あれ?姫野先輩は今日、一緒じゃないんですね」
一同を見回して銀髪の猫が言う。本城はみぞおちのあたりに不快感を覚えた。
「姫は今日は別だよな」
「野島といるんだっけ?」
「本城このあと合流しねぇの?」
何も知らない友人たちが彼にどんどん情報を与えてしまうので、本城は口を開く。
「名前は?」
初対面ではないものの、本城が彼に言葉をかけるのはこれが初めてだった。
自分の名前を聞かれたのだと悟った彼は、嬉しそうに笑った。
「タツキです」
苗字が?それとも名前?まぁどっちでもいい。
野島と平和に過ごしているであろう恋人の顔を思い浮かべて、本城は密かに歯噛みする。
こいつには触れさせない。
初めに声をかけてきた時も、タツキは人懐こそうな笑顔を浮かべていた。
「本城先輩」
先輩、と呼ばれたことで、相手が1年生だと知る。その銀髪に見覚えはなかった。
「近くで見ると、ほんと背高いですね。しかもきれいな金髪。かっこいい」
そう言う相手も背が高い。170代後半くらいか。
初対面にしては馴れ馴れしいと思った。
「目もグレーだ。カラコンじゃないし。……これは落ちますよね。男でも」
本城はまじまじと相手の顔を見た。彼はもう笑っていなかった。かと言って喧嘩を売るような顔でもない。穏やかな無表情に見えた。
しかし本城には相手の目的がうっすら透けて見えた気がした。
はっきり言え。
無言で問うと、人好きのする笑顔に戻ってタツキは言った。
「本城先輩、友達になって下さい」
「イチ!」
本城が記憶の中でしかめ面をしたところで、あらぬ方向から大声が聞こえた。
遠くから猫を呼んだのは、体格のいい短髪。彼も同じ高校の制服を着ている。
「イチ、先に行くぞー」
どうやらタツキを呼んでいるらしいが、タツキは短髪を無視して本城に微笑みかける。
イチとタツキ、どっちが何だ。
「本城、顔怖ぇよ?大丈夫?」
「本城なんで男にモテんの」
「姫もらっていい?」
「本城!浮気か!だめだぞ!」
「そうだぞ、姫に言うぞ」
「言わないから姫ちょうだい?」
友人たちがふざけて口々に言う。それに笑顔で答えられないくらいタツキに苛立っていることを、本城は自覚する。
「イチー!」
短髪がまた呼ぶ。猫の飼い主ってとこか。
「今度、姫野先輩と遊ぶ時に交ぜて下さいね」
タツキは去り際、首を傾げて爽やかに笑って言い、本城は無言で応えた。
言葉すら交わしたくない。交わしたら最後、感情のコントロールができなくなりそうな気がした。
猫と飼い主の後ろ姿をちらりと見遣って、本城は友人の輪に戻る。
無性に姫野に会いたくなった。
夜でもいいから会いたいとメールをしようとして本城が携帯を取り出すと、ちょうど着信していて、表示されている名前に本城の胸は愛しさで満たされる。
「もしもし、姫野?」
うお、このタイミングで本妻から電話、という友人の声は無視することにする。
『ドーナツ食べたい?』
本城はその唐突な提案に微笑んだ。
「食べたい」
姫野の家のリビング。テーブルにはドーナツが7つ。どれも見たことのないもので、姫野は春の新作だと自慢気だ。
買ってきたペットボトルから無糖の紅茶を注ぐ姫野の隣に座り、本城は椅子をさらに姫野の方へ寄せた。
「……何」
「別に?」
「なんか今日、変。気持ち悪い」
「そうかな」
本城はテーブルに横向きに突っ伏して、姫野を見上げた。
大きな目が真剣にドーナツを選んでいる。姫野を迎えに行ったドーナツ店の前で野島から、姫野くんはドーナツを4つも食べたんだよ、と報告を受けたのを思い出す。
「姫野、猫好き?」
本城は冗談半分で、それでも半分は祈るような気持ちで聞いた。
「全然好きじゃない。猫アレルギーだし」
ばっさりと切り捨てた姫野の返事に、本城は声を上げて笑った。
「何?ほんと、変」
口を尖らせる姫野を横から抱きしめた。さっきまで荒みに荒んでいた心が嘘のように凪いだ。
「姫野、知らない猫にはついて行っちゃダメだよ?」
こめかみにキスをすると、は?意味わかんない、と、姫野のいつもの声が聞こえた。
-end-