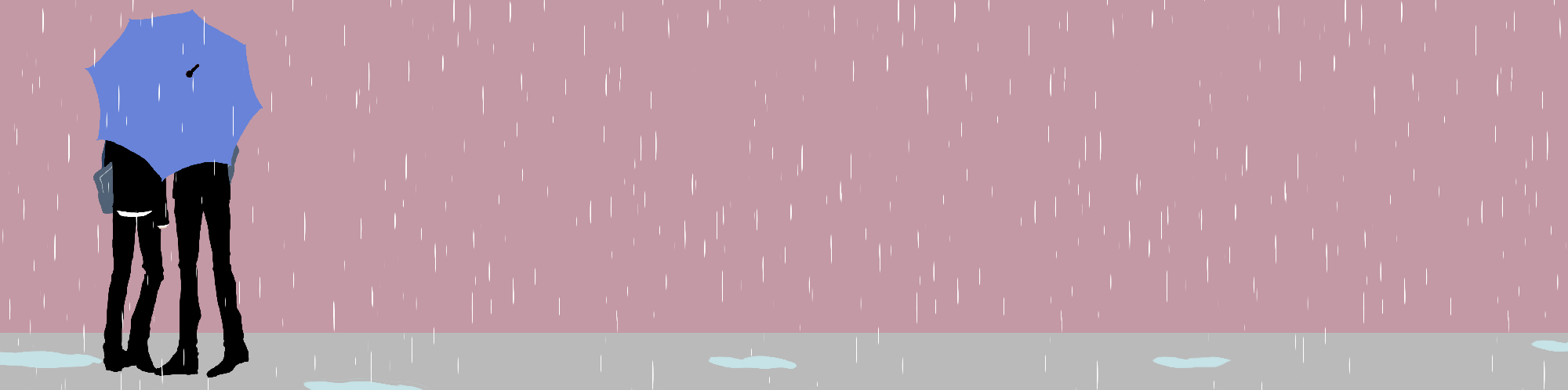姫は王子のもの。
「もしもし、姫野?」
『ん』
「寝てた?」
『……起きてた』
姫野は今日、風邪で学校を休んだ。
熱があるとはメールで聞いていた。だから、寝込んでいるかもしれないし、1日くらい我慢しようと思ったのだが、結局本城は今、姫野の声を聞いている。
「熱下がった?」
『さっき寝てて、汗かいたら少し下がった』
姫野がいつもより力の無い鼻声で話すのを聞いて、今すぐ家まで行ってベッドに潜り込んで抱き締めてキスしてぐちゃぐちゃにしてしまいたい衝動に駆られる。
「食欲は?なんか食べた?」
『あんまり』
グス、と鼻をすする音が聞こえる。
「ダメだよ、食べなきゃ。たくさん食べてたくさん寝て、早く学校おいでよ」
『……』
「明日も休みだったら、帰りにお見舞いに行ってもいい?」
『……』
あれ、寝ちゃったかな、と本城が考えた時。
『……今、会いたい』
拗ねた子どもみたいな言い方がかわいくて、本城は深く息を吐いた。そうしなければ気持ちを落ち着けられなかったのだ。
姫野はそれをため息ととったのか、だって、と呟いた。
だって、なんなのか。本城は今着ている部屋着から何に着替えようか、目でクローゼットを探しながら、姫野に聞く。
「だって?」
『……寒いし』
「寒いし?」
『……食欲ないし』
「ないし?」
本城は堪えきれなくなって、軽く笑った。
『……寂しいんだもん。会いたい』
だもん、という語尾に、本城は表情に出さずにしばし悶えた。
「今から行くから待ってて」
電話を切ると、着替えて部屋を飛び出した。
チャリを飛ばして10分。いつもなら15分は絶対にかかる距離。しかも今日は途中コンビニに寄ったにも関わらずだ。
夜分にすみません、心配で、などと言って家の人に部屋へ通してもらう。
部屋に入ると、ベッドの上で深々と布団にくるまった姫野が顔を出した。熱で潤んだ瞳が見開かれる。
「早かった……ね」
本城は床に膝をついて姫野の顔を覗きこんだ。
「あんなかわいいこと言うから」
「かわいいことなんか言ってない」
「言ったよ、寂しいんだもん、って」
姫野の目が一瞬だけ泳ぐ。
「寂しいんだもん、会いたい、って」
「言ってない」
「言ったよ、俺一生忘れない。録音した」
「うそ!」
姫野が起き上がりかけて、本城はその肩を支えた。
「嘘だけど、忘れない」
そのまま抱き寄せてぷっくりした唇に口づける。照れたのか、仏頂面の姫野の頬を人差し指でつんつんとつつく。
「どうしてこんなにすべすべなの?」
指先で優しく撫でる。姫野はされるがままになっていた。
「プリン買ってきたよ。食べる?」
「…うぅ…」
「食べようよ、姫野が前おいしいって言った『超絶うますぎる悶絶プリン』のミルクキャラメルバター味が出てたよ」
「食べる」
蓋を開けてプラスチックのスプーンですくって差し出す。
「あーん、は?」
姫野は口をへの字にして微動だにしない。
「食べないの?早くしないととろけちゃうよ」
「自分で…食べられる」
「お願い。食べさせたい。どうしても」
「…なんで」
「かわいいから。ほら、いいから早く」
ほとんど無理やりスプーンを口に近付けると、姫野は渋々その口を開いた。
いい顔。犯したい。
本城は獣のような欲望を瞬時に笑顔の下に隠した。
結局全部を食べさせられて、姫野はまた布団に潜り込んだ。まだ熱が下がりきっていないからか、頬はいつもより熱く、ふうふうという呼吸が苦しそうだった。
かわいそうに。
そうだ。
「ねぇ姫野、熱出たら腰とか関節痛くならない?」
「なった。さっき」
「揉んであげよっか」
姫野は本城から逃げるように体をずらして壁側に寄った。
「え、い、いい」
「いいからほら、うつ伏せになって」
「いいってば!あっやめろ!ふ、くく、ははは!やめ、ふはは!」
本城が布団を捲って少し腰に触っただけで、姫野はくすぐったがって笑い出した。のたうち回って逃げようとする体に毛布をかけて跨がり、押さえつける。熱のせいで全然力が入っていない。
「大丈夫だから、ほら、毛布の上からならくすぐったくないでしょ?寒くないし」
「ふ、ふふ、…はぁ、疲れた…」
「ごめんね」
大人しくなった姫野の背中から腰にかけてを、優しく親指で圧す。細い腰を後ろから掴むことで変な想像をしそうになるのを、本城は堪えた。
背骨に沿って指圧しながら上に上がっていくと、姫野がまた体をよじった。
「ふ、ちょっと、う゛、背中やめっあはは」
「姫野は感じやすいね」
「は?それ関係ないし」
口を尖らせる姫野に、感じやすいのは否定しないのか、と本城はニヤニヤしてしまった。
「もういい」
「えー、もう少し揉むよ」
「いいから」
姫野はうつ伏せの姿勢で後ろに手を伸ばし、本城の手首を掴んだ。
「……一緒に寝る」
「今日は甘えんぼさんだね」
「うるっさいな。じゃあもう帰れば?」
「かわいいね」
「意味わかんない」
本城はベッドから降りて姫野に布団をかけ直した。それから改めて姫野の横に潜り込もうと思っていたのに、姫野はそれより前に不安げな顔で本城を見上げた。
「ほんとに帰るの?」
本城は思った。
崩壊する。理性が崩壊する。危ない。相手は病人だ。落ち着け。
でも悪いのは姫野だ。ツンとデレのスイッチ切り替えがスムーズ過ぎてついていけない。
本城は少し意地悪をしたくなった。
「具合悪いんだから、ちゃんと寝た方がいいよ」
「……大丈夫」
「大丈夫じゃないでしょ?俺がいると邪魔だから」
「邪魔じゃない」
「じゃあどうしてほしいの、ちゃんと言って」
姫野のしてほしいことなんてわかってる。だってさっき言ってたし。でもちゃんとおねだりされたい。
「い、っしょに……寝よ、少し、だけ」
本城は激しく揺さぶられた気持ちを表に出すことなく、にっこり笑った。
ベッドに入り、姫野を後ろから抱きしめる。姫野は早くも微睡んでいて、ふう、ふう、と息をすると同時に脇腹が上下して、本城の腕に伝わる。
「姫野の体、あったかい」
「ほんじょう、も…あったかい」
眠そうな声でほとんど無意識に呟かれたその言葉を最後に、姫野は本城の腕の中で眠りについたようだった。
姫野の黒い髪に鼻をうずめて、深く息を吸い込む。姫野の匂いがした。
自分の体にすっぽりと包まれて眠る姫野の体温を感じながら、本城も少し眠くなった。しかし眠るわけにはいかない。今は夜で、いつものようにゆっくりしてはいられないからだ。
今度は姫野の首筋に口を付けた。すると姫野が身じろぎして微かに声をあげた。
「ん…んん……」
それを聞いて、本城は自分の欲望に火がついてしまったのを感じた。
だめだ。姫野は熱があるんだから。我慢しなきゃ。
それでもむくむくと頭をもたげ始めた自身が、密着した姫野の柔らかな双丘に当たって熱が集まっていく。姫野の匂いがそれに拍車をかけた。
だめだ。少しだけ。
本城はそこに腰を押し付けて自身を刺激する。布越しに擦れる刺激で完全に勃起していた。
「はぁ……っ、あぁ」
姫野を起こさないように静かに腰を動かしながら、眠る姫野を使って自慰をしている状況に興奮して息が上がってゆく。
そのうち、姫野の呼吸がおかしいことに気付いた。さっきより呼吸が早い。具合が悪いのかと心配になり、頭を持ち上げて顔を見ると、姫野の目は開いていた。
「起きてたの?」
「っ、ちが、寝てたし、」
姫野の顔が赤いのは、熱のせいだけではなさそうだ。
「あーあ、バレちゃった。ごめんね、起こして」
「え、ぃ、な、にが?」
しどろもどろの度が過ぎる。本城は、あくまでしらを切るつもりの姫野に、ちゃんと教えてあげよう、と思った。
「姫野のお尻でオナニーしてた」
「あ、あ、そぅ、なんだ…」
「ふふ、斬新だねその反応。知ってたんでしょ?俺の喘ぎ声も聞いてた?」
耳元に唇を寄せて囁くと、姫野がふるっと震えた。
「ここが当たってるのも知ってたんだよね?感じた?」
さっきまでしていたように、自身を擦り付けるように腰を動かした。
「ぁ、ふ、」
「かわいいな。姫野はほんとにかわいいよ…すぐ抱きたくなっちゃう」
言いながら首筋にキスをする。
「でも我慢する。風邪だし、おうちの人いるし、ね」
「やぁっ…ずるい…」
「俺、そろそろ帰るね」
「待って」
「明日また来るから」
ベッドから出ようとしてみると、姫野が振り返った。
「ぃや、まだ行かないで」
ほんとにほんとにかわいい。
もう本城にもあまり焦らしている余裕はなく、でも今日は本当に無理はさせたくなかった。布団を姫野と自分にかけなおして、さっきまでのように後ろからぎゅっと抱く。
「じゃあ、今日は挿れないでしようね。触ってあげるから」
後ろからパジャマのズボンの中に手を突っ込んで太ももを撫でる。一瞬何気なく下着に触れると、姫野のそこも固くなっていた。
「勃っちゃったの?」
「ぁ、だって、ゆき、が」
「俺が?」
「…俺の、おしり…」
熱でとろとろした話し方になっているのがたまらなくかわいかった。
「姫野のおしり?」
下着の上から後ろを撫でる。
「あんっ、おしり使ってた、から」
「興奮したの?」
「ん、したの…」
したの、だって。
もう少し焦らそうと思っていた本城は、一気に下着をずらして姫野の自身を握った。
「ああぁっ!」
姫野が声をあげたので、もう片方の手で口をふさぐ。
「だめだってば、聞こえちゃうよ?」
姫野自身を扱き上げながら、腰を激しく動かして自分のそれを姫野の後ろに擦る。口をふさいでいる手の指を姫野の口に突っ込んだ。
「すごい、いろんなとこがべちゃべちゃだ」
「ん、んふ、っん、ん」
「姫野のここ、熱い」
いつもより熱を持ったそこが、どんどん張り詰めていく。先端を人差し指と親指でくちゅくちゅと扱きながら、残りの指を使って下の方を強く握り込む。
「んぐ!う!」
「痛い?…姫野」
びくっと跳ねた姫野の体に興奮が高まり、手を使わないでもイってしまいそうだった。
「う、う、」
「もっと痛くしてあげるね」
本城は扱く指に力を込めながら腰をふり、目の前にある姫野の耳たぶをギリっと噛んだ。
「う゛ぐぅ!」
姫野は抑えた声で悲鳴を上げて、本城の手に吐精した。
「あーあ、はは、やっぱり姫野は変態だ」
本城の言葉に反応してビクビクと跳ねる姫野の自身を、搾り取るように扱いて手を離した。
手についた姫野の精液を塗り込めるように自身を握り、本城もラストスパートをかけた。
「っは、イく…」
呟くと、姫野が手を伸ばして本城のそこを撫でた。
「…じゃあちょっと手貸して」
本城は姫野の手ごと自身を扱いた。
「ん、ゆき、あ、おっきぃ、」
「あぁ、出そう」
姫野を見ると、姫野も本城を見ていた。手の動きがどんどん激しくなっていく。
「あ、ぁ、」
触ってもいないのに姫野が喘ぎ、本城は限界を迎えた。
「っ、出る」
あっという間にイってしまい、ぐったりと目を閉じた。
「大丈夫?」
姫野の声がして目を開けると、半分閉じかけたような潤んだ目で見つめられていた。
「ごめんね、姫野、疲れたよね?」
「う…」
姫野は今にも寝てしまいそうだ。
半分意識がないように見えるその口から、絞り出された今日最後の言葉。
「ありがと…来てくれて」
朦朧としていて、きっと照れも意地も何もない場所から届いたその言葉を、本城は大事に胸にしまいこんでから、そっとベッドを抜け出た。
布団をかけなおして、その額にキスをする。
姫野のためならなんだってできるよ。いつでも呼んで。ね。
でも俺はなるべくなら、姫野が何も言わなくても、してほしいことをわかっていたい。
俺が先回りして先回りして、どこからどうがんばったって俺の腕から逃げられなくて、真っ赤になる姫野が好きだから。
ほんとだよ、なんだってする。姫野の気持ち、もっとちゃんとわかるようになる。
だから、俺以外にはこんな顔、絶対に見せないで。
安心しきったような顔で眠る姫野の唇にキスを落としてから、少しパジャマをずらして鎖骨の下に強く吸い付いて痕を残した。自分が帰ったことを知らない姫野が、起きた時に寂しい思いをしないで済みますように、と願いながら。
後ろ髪を引かれつつ、本城は姫野の家を後にした。
まだ少し肌寒い夜の空気をたっぷり纏いながら、本城は自転車をこぐ。胸が痛くなるほど姫野のことを想った。
季節はもうすぐ春。
本城にとってそれは、外でアイスが食べたいと、姫野が言い出す季節。
-end-
『ん』
「寝てた?」
『……起きてた』
姫野は今日、風邪で学校を休んだ。
熱があるとはメールで聞いていた。だから、寝込んでいるかもしれないし、1日くらい我慢しようと思ったのだが、結局本城は今、姫野の声を聞いている。
「熱下がった?」
『さっき寝てて、汗かいたら少し下がった』
姫野がいつもより力の無い鼻声で話すのを聞いて、今すぐ家まで行ってベッドに潜り込んで抱き締めてキスしてぐちゃぐちゃにしてしまいたい衝動に駆られる。
「食欲は?なんか食べた?」
『あんまり』
グス、と鼻をすする音が聞こえる。
「ダメだよ、食べなきゃ。たくさん食べてたくさん寝て、早く学校おいでよ」
『……』
「明日も休みだったら、帰りにお見舞いに行ってもいい?」
『……』
あれ、寝ちゃったかな、と本城が考えた時。
『……今、会いたい』
拗ねた子どもみたいな言い方がかわいくて、本城は深く息を吐いた。そうしなければ気持ちを落ち着けられなかったのだ。
姫野はそれをため息ととったのか、だって、と呟いた。
だって、なんなのか。本城は今着ている部屋着から何に着替えようか、目でクローゼットを探しながら、姫野に聞く。
「だって?」
『……寒いし』
「寒いし?」
『……食欲ないし』
「ないし?」
本城は堪えきれなくなって、軽く笑った。
『……寂しいんだもん。会いたい』
だもん、という語尾に、本城は表情に出さずにしばし悶えた。
「今から行くから待ってて」
電話を切ると、着替えて部屋を飛び出した。
チャリを飛ばして10分。いつもなら15分は絶対にかかる距離。しかも今日は途中コンビニに寄ったにも関わらずだ。
夜分にすみません、心配で、などと言って家の人に部屋へ通してもらう。
部屋に入ると、ベッドの上で深々と布団にくるまった姫野が顔を出した。熱で潤んだ瞳が見開かれる。
「早かった……ね」
本城は床に膝をついて姫野の顔を覗きこんだ。
「あんなかわいいこと言うから」
「かわいいことなんか言ってない」
「言ったよ、寂しいんだもん、って」
姫野の目が一瞬だけ泳ぐ。
「寂しいんだもん、会いたい、って」
「言ってない」
「言ったよ、俺一生忘れない。録音した」
「うそ!」
姫野が起き上がりかけて、本城はその肩を支えた。
「嘘だけど、忘れない」
そのまま抱き寄せてぷっくりした唇に口づける。照れたのか、仏頂面の姫野の頬を人差し指でつんつんとつつく。
「どうしてこんなにすべすべなの?」
指先で優しく撫でる。姫野はされるがままになっていた。
「プリン買ってきたよ。食べる?」
「…うぅ…」
「食べようよ、姫野が前おいしいって言った『超絶うますぎる悶絶プリン』のミルクキャラメルバター味が出てたよ」
「食べる」
蓋を開けてプラスチックのスプーンですくって差し出す。
「あーん、は?」
姫野は口をへの字にして微動だにしない。
「食べないの?早くしないととろけちゃうよ」
「自分で…食べられる」
「お願い。食べさせたい。どうしても」
「…なんで」
「かわいいから。ほら、いいから早く」
ほとんど無理やりスプーンを口に近付けると、姫野は渋々その口を開いた。
いい顔。犯したい。
本城は獣のような欲望を瞬時に笑顔の下に隠した。
結局全部を食べさせられて、姫野はまた布団に潜り込んだ。まだ熱が下がりきっていないからか、頬はいつもより熱く、ふうふうという呼吸が苦しそうだった。
かわいそうに。
そうだ。
「ねぇ姫野、熱出たら腰とか関節痛くならない?」
「なった。さっき」
「揉んであげよっか」
姫野は本城から逃げるように体をずらして壁側に寄った。
「え、い、いい」
「いいからほら、うつ伏せになって」
「いいってば!あっやめろ!ふ、くく、ははは!やめ、ふはは!」
本城が布団を捲って少し腰に触っただけで、姫野はくすぐったがって笑い出した。のたうち回って逃げようとする体に毛布をかけて跨がり、押さえつける。熱のせいで全然力が入っていない。
「大丈夫だから、ほら、毛布の上からならくすぐったくないでしょ?寒くないし」
「ふ、ふふ、…はぁ、疲れた…」
「ごめんね」
大人しくなった姫野の背中から腰にかけてを、優しく親指で圧す。細い腰を後ろから掴むことで変な想像をしそうになるのを、本城は堪えた。
背骨に沿って指圧しながら上に上がっていくと、姫野がまた体をよじった。
「ふ、ちょっと、う゛、背中やめっあはは」
「姫野は感じやすいね」
「は?それ関係ないし」
口を尖らせる姫野に、感じやすいのは否定しないのか、と本城はニヤニヤしてしまった。
「もういい」
「えー、もう少し揉むよ」
「いいから」
姫野はうつ伏せの姿勢で後ろに手を伸ばし、本城の手首を掴んだ。
「……一緒に寝る」
「今日は甘えんぼさんだね」
「うるっさいな。じゃあもう帰れば?」
「かわいいね」
「意味わかんない」
本城はベッドから降りて姫野に布団をかけ直した。それから改めて姫野の横に潜り込もうと思っていたのに、姫野はそれより前に不安げな顔で本城を見上げた。
「ほんとに帰るの?」
本城は思った。
崩壊する。理性が崩壊する。危ない。相手は病人だ。落ち着け。
でも悪いのは姫野だ。ツンとデレのスイッチ切り替えがスムーズ過ぎてついていけない。
本城は少し意地悪をしたくなった。
「具合悪いんだから、ちゃんと寝た方がいいよ」
「……大丈夫」
「大丈夫じゃないでしょ?俺がいると邪魔だから」
「邪魔じゃない」
「じゃあどうしてほしいの、ちゃんと言って」
姫野のしてほしいことなんてわかってる。だってさっき言ってたし。でもちゃんとおねだりされたい。
「い、っしょに……寝よ、少し、だけ」
本城は激しく揺さぶられた気持ちを表に出すことなく、にっこり笑った。
ベッドに入り、姫野を後ろから抱きしめる。姫野は早くも微睡んでいて、ふう、ふう、と息をすると同時に脇腹が上下して、本城の腕に伝わる。
「姫野の体、あったかい」
「ほんじょう、も…あったかい」
眠そうな声でほとんど無意識に呟かれたその言葉を最後に、姫野は本城の腕の中で眠りについたようだった。
姫野の黒い髪に鼻をうずめて、深く息を吸い込む。姫野の匂いがした。
自分の体にすっぽりと包まれて眠る姫野の体温を感じながら、本城も少し眠くなった。しかし眠るわけにはいかない。今は夜で、いつものようにゆっくりしてはいられないからだ。
今度は姫野の首筋に口を付けた。すると姫野が身じろぎして微かに声をあげた。
「ん…んん……」
それを聞いて、本城は自分の欲望に火がついてしまったのを感じた。
だめだ。姫野は熱があるんだから。我慢しなきゃ。
それでもむくむくと頭をもたげ始めた自身が、密着した姫野の柔らかな双丘に当たって熱が集まっていく。姫野の匂いがそれに拍車をかけた。
だめだ。少しだけ。
本城はそこに腰を押し付けて自身を刺激する。布越しに擦れる刺激で完全に勃起していた。
「はぁ……っ、あぁ」
姫野を起こさないように静かに腰を動かしながら、眠る姫野を使って自慰をしている状況に興奮して息が上がってゆく。
そのうち、姫野の呼吸がおかしいことに気付いた。さっきより呼吸が早い。具合が悪いのかと心配になり、頭を持ち上げて顔を見ると、姫野の目は開いていた。
「起きてたの?」
「っ、ちが、寝てたし、」
姫野の顔が赤いのは、熱のせいだけではなさそうだ。
「あーあ、バレちゃった。ごめんね、起こして」
「え、ぃ、な、にが?」
しどろもどろの度が過ぎる。本城は、あくまでしらを切るつもりの姫野に、ちゃんと教えてあげよう、と思った。
「姫野のお尻でオナニーしてた」
「あ、あ、そぅ、なんだ…」
「ふふ、斬新だねその反応。知ってたんでしょ?俺の喘ぎ声も聞いてた?」
耳元に唇を寄せて囁くと、姫野がふるっと震えた。
「ここが当たってるのも知ってたんだよね?感じた?」
さっきまでしていたように、自身を擦り付けるように腰を動かした。
「ぁ、ふ、」
「かわいいな。姫野はほんとにかわいいよ…すぐ抱きたくなっちゃう」
言いながら首筋にキスをする。
「でも我慢する。風邪だし、おうちの人いるし、ね」
「やぁっ…ずるい…」
「俺、そろそろ帰るね」
「待って」
「明日また来るから」
ベッドから出ようとしてみると、姫野が振り返った。
「ぃや、まだ行かないで」
ほんとにほんとにかわいい。
もう本城にもあまり焦らしている余裕はなく、でも今日は本当に無理はさせたくなかった。布団を姫野と自分にかけなおして、さっきまでのように後ろからぎゅっと抱く。
「じゃあ、今日は挿れないでしようね。触ってあげるから」
後ろからパジャマのズボンの中に手を突っ込んで太ももを撫でる。一瞬何気なく下着に触れると、姫野のそこも固くなっていた。
「勃っちゃったの?」
「ぁ、だって、ゆき、が」
「俺が?」
「…俺の、おしり…」
熱でとろとろした話し方になっているのがたまらなくかわいかった。
「姫野のおしり?」
下着の上から後ろを撫でる。
「あんっ、おしり使ってた、から」
「興奮したの?」
「ん、したの…」
したの、だって。
もう少し焦らそうと思っていた本城は、一気に下着をずらして姫野の自身を握った。
「ああぁっ!」
姫野が声をあげたので、もう片方の手で口をふさぐ。
「だめだってば、聞こえちゃうよ?」
姫野自身を扱き上げながら、腰を激しく動かして自分のそれを姫野の後ろに擦る。口をふさいでいる手の指を姫野の口に突っ込んだ。
「すごい、いろんなとこがべちゃべちゃだ」
「ん、んふ、っん、ん」
「姫野のここ、熱い」
いつもより熱を持ったそこが、どんどん張り詰めていく。先端を人差し指と親指でくちゅくちゅと扱きながら、残りの指を使って下の方を強く握り込む。
「んぐ!う!」
「痛い?…姫野」
びくっと跳ねた姫野の体に興奮が高まり、手を使わないでもイってしまいそうだった。
「う、う、」
「もっと痛くしてあげるね」
本城は扱く指に力を込めながら腰をふり、目の前にある姫野の耳たぶをギリっと噛んだ。
「う゛ぐぅ!」
姫野は抑えた声で悲鳴を上げて、本城の手に吐精した。
「あーあ、はは、やっぱり姫野は変態だ」
本城の言葉に反応してビクビクと跳ねる姫野の自身を、搾り取るように扱いて手を離した。
手についた姫野の精液を塗り込めるように自身を握り、本城もラストスパートをかけた。
「っは、イく…」
呟くと、姫野が手を伸ばして本城のそこを撫でた。
「…じゃあちょっと手貸して」
本城は姫野の手ごと自身を扱いた。
「ん、ゆき、あ、おっきぃ、」
「あぁ、出そう」
姫野を見ると、姫野も本城を見ていた。手の動きがどんどん激しくなっていく。
「あ、ぁ、」
触ってもいないのに姫野が喘ぎ、本城は限界を迎えた。
「っ、出る」
あっという間にイってしまい、ぐったりと目を閉じた。
「大丈夫?」
姫野の声がして目を開けると、半分閉じかけたような潤んだ目で見つめられていた。
「ごめんね、姫野、疲れたよね?」
「う…」
姫野は今にも寝てしまいそうだ。
半分意識がないように見えるその口から、絞り出された今日最後の言葉。
「ありがと…来てくれて」
朦朧としていて、きっと照れも意地も何もない場所から届いたその言葉を、本城は大事に胸にしまいこんでから、そっとベッドを抜け出た。
布団をかけなおして、その額にキスをする。
姫野のためならなんだってできるよ。いつでも呼んで。ね。
でも俺はなるべくなら、姫野が何も言わなくても、してほしいことをわかっていたい。
俺が先回りして先回りして、どこからどうがんばったって俺の腕から逃げられなくて、真っ赤になる姫野が好きだから。
ほんとだよ、なんだってする。姫野の気持ち、もっとちゃんとわかるようになる。
だから、俺以外にはこんな顔、絶対に見せないで。
安心しきったような顔で眠る姫野の唇にキスを落としてから、少しパジャマをずらして鎖骨の下に強く吸い付いて痕を残した。自分が帰ったことを知らない姫野が、起きた時に寂しい思いをしないで済みますように、と願いながら。
後ろ髪を引かれつつ、本城は姫野の家を後にした。
まだ少し肌寒い夜の空気をたっぷり纏いながら、本城は自転車をこぐ。胸が痛くなるほど姫野のことを想った。
季節はもうすぐ春。
本城にとってそれは、外でアイスが食べたいと、姫野が言い出す季節。
-end-