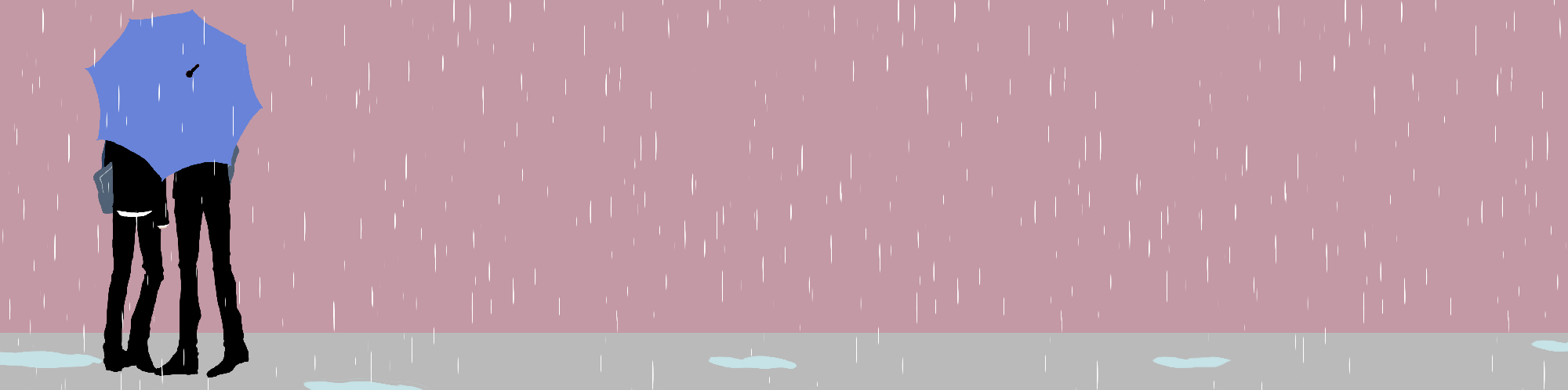姫は王子のもの。
朝から雨が降っていた。
外でサッカーをする予定だった体育も体育館内でのマット運動へ変更され、クラスの皆はやる気のない放漫な動作で体を動かしている。
湿気を帯びた床が、靴の底のゴムでキュッキュと鳴った。
姫野は何してるかな。
本城は壁際であぐらをかき、野島がマットの上でくるりと回るのを見ながら考えた。
ぼんやりと窓の外を見ているだろうか。
真剣に板書しているだろうか。
眠気を抑えるために教科書を読んでいるだろうか。
自分のことを、思い出すことはあるだろうか。
野島は、腹の上までめくれてしまったTシャツを急いで直し、本城の横で小さく体育座りをした。
「できなかった……」
「そう?できてたよ」
「苦手なの、マット運動」
「足、大丈夫?無理しないでね」
「このくらいなら平気。ありがとう」
恥ずかしそうにする野島の腹が色白ですべらかだったことを思う。
姫野とどっちが白いかな。ぼんやり考える本城の目の前で、他のクラスメイトが宙返りをする。
「うわぁ!すごい!」
感嘆の声をあげて拍手をした野島にそのクラスメイトが寄ってきて、ハイタッチを要求した。
どさくさに紛れて手を握られている。
最近、本城のクラスでは野島の人気が高まりつつある。可愛らしい容姿と、優しくて明るく素直な気質。
姫野とは違う。全然違う。
別に野島のことを嫌うわけではないし、むしろ友達としては本当に付き合いやすいタイプだった。
でも自分は姫野がいいし、姫野しかいらない。何があってもそれだけは揺るがない。
本城は、手を握られ困惑して照れ笑いをする野島を微笑ましく見守りながら、延々と姫野のことを考えていた。
「すごいね」
昇降口から外を見ると、授業中より降り方が酷くなっていた。
本城はガラス戸を出て自分のビニール傘を広げ、姫野を振り仰いだ。
「こっちで一緒に帰ろう」
姫野は少し戸惑い気味に、自分の傘を閉じたまま本城の傘の下に入った。本城は手を差し出し、姫野の傘も持ってやる。綺麗に畳んで細く巻かれた、紺色の傘。
少し歩みを進めただけで、足元がべちゃべちゃに濡れた。雨粒が傘を叩く音が、バツバツと聞こえる。
「もっとこっち来ないと濡れちゃうよ」
「いいの」
「駄目だってば。風邪引くよ」
「大丈夫だし」
「今日ね、体育、マットになったよ」
「ふぅん」
「野島もやったんだよ。ころって前転して」
「野島だって前転くらいできるでしょ」
「俺ね、ずっと、姫野のこと考えてた」
土砂降りの中、一本の傘の下で続ける会話は、世界中の誰にも邪魔されないような気がして心地が良かった。
「ずっと、姫野のこと考えてるよ。いつも」
怖いくらいだ。どうしてこんなに、姫野じゃなきゃ駄目なんだろう。
姫野がいなくなったら、きっと自分は、ぱっと消えて無くなるに違いない。
「変。最近、本城、変」
口を尖らせて自分を見上げる姫野を、抱きしめたくて仕方がなくなる。
「聞いてるの?ちょっと、本城」
「ああ、うん。聞いてる」
「ぼーっとしてるし、迎えに来るの遅いし、金髪が前より金色になった感じするし、野島とすごい仲いいし、でも野島のことはいいけど、なんか変」
「へえ。そうかな」
姫野の言うことの半分くらいは意味がよくわからなかった。
「髪がなんだって?」
「だから、前より金色だって」
「えー、何それ」
「知らないよ」
「姫野が言ったんでしょ」
「だってそうなんだもん」
永遠にこうやって話していたい。
「ねえ姫野。姫野は、俺のこと考えたりする?」
自分と同じくらいじゃなくてもいい。
胸が苦しくなったり、なんで本城じゃなきゃいけないんだろうとか、考えたりする?
姫野は無言だ。
その時、雨の音が一段と大きくなった。風はないのに、雨の勢いだけで傘が壊れそうだった。
「どっか寄って雨宿りしてこっか」
本城が言うと、姫野は尖った声で「いいよ」と言った。
公園にある大きな遊具の中に、2人で入った。土砂降りなので、公園には当然誰もいない。
真っ赤で大きな球体のその遊具は、中が空洞で、下の部分に幾つか穴があいており、そこから中へ入って、壁をよじ登ったり寄りかかったりする以外にどうやって遊ぶのかがよくわからない。
薄暗いその空間は、外の雨の音すら遮断してしまった。
「……お父さん、帰って来た?」
「ああ、いや。まだ。来週か、その次の週かな」
姫野には、父が帰って来るという話だけしていた。
本城がどんな話をするつもりなのか、その結果が本城家にどんな影響を与え得るか、そういうことは一切伏せたまま。
「もしよかったら、またうちに来て。それで、父さんにも会って」
「いいけど」
「姫野」
畳んだ傘を2本、遊具の内側に立てかけ、横に立った姫野の肩を抱く。髪を撫でる。
「姫野と一緒に住めるなら、俺、ここでもいいなぁ」
遊具の天井を見上げる。
薄暗く、湿った空気が滞留していて、声が少し響いて聞こえる、がらんどうのようなここでも。
「嫌だよ、こんなとこ」
姫野が、にべもなく否定する。
「どうして?」
「だって座れないじゃん」
「敷物を持ってくるんだよ。家から」
「それで?」
「あと、ベッドを置く」
「2こ?」
「1こ」
「…ベッド1こ…」
「一緒に寝るからいいでしょ」
「あとは?」
「冷蔵庫もいるかなぁ。姫野のケーキとかアイスとか入れておかないと」
「電源がないじゃん」
「そうだね…その都度買えばいいか」
「暗いの嫌だ」
「怖がり」
「違うし!」
「電池で点くランプとか置けばよくない?」
「テレビもない」
「ケータイで我慢してよ」
「…ハムスター飼いたい」
「いいよ。飼おう」
話に乗ってきた姫野のことを、苦しいくらいに、好きだと感じる。
離れるのが、本当に苦痛だ。一体いつになったら、自分は姫野と離れずに暮らせるようになるのだろう。そのために、一体いくつの壁を越えなければならないのだろう。
そういうことを考えるたび、本城は少しだけ怖くなる。そばにいる小さな体を思い切り抱きしめずにはいられなくなる。
「姫野」
姫野の制服は少し湿っている。姫野の香りがする。
「大好きだよ」
いつも、言葉になって出るのはその想いだけだ。
「ゆき」
小さな声が返って来て、本城は顔を近づけ、キスをした。
体を離そうとすると、姫野が腕を本城の首に絡めて、ほとんどぶら下がるような格好で抱きついてきた。
「…どうしたの。本城、変」
たまらなくなってまた抱き返す。
姫野はたまに、本城の心の動きに恐ろしく敏感だ。
自分の些細な不安でも、伝われば姫野が不安になることは本城にもわかる。自分が安定していなければ、姫野は安心してツンツンしていられないのだ。
かわいいな。俺が全て、みたいで。
ぎゅうと抱きしめたまま、首筋や耳にキスをしながら、姫野に聞く。
「姫野、ハムスター好きなの?」
「…好きっていうか、まあ、飼ってみたいだけ」
「かわいいもんね。姫野みたいで」
「は?意味がわかんない」
「姫野、似てるよ。ハムスターに」
「似てない」
「似てる」
「似てないってば」
「似てるよ」
「しつこい」
「ごめん」
本城から離れ、壁に寄りかかって、姫野は口を尖らせた。
「姫野って、どんな子どもだったの?」
姫野は顔を上げて本城を見上げた。険しい眼差しに、思わず笑みがこぼれる。
「どんなって何」
「引っ込み思案で泣き虫だった?」
「…そんなことないし」
図星だな。
「ママっ子だったでしょ」
「違う」
「恥ずかしくなるとお母さんの影に隠れちゃった?」
「…覚えてない、そんなこと」
姫野の顔が少し赤くなる。
「本城だって、かわいい水着着てたくせに」
「まだ言う?それ」
「雨、止んできた」
耳を澄ましても、雨の音はほとんど聞こえなくなっていた。
「送るね」
「…ゆき…あのね……」
姫野が何か言いづらそうにしている。
「うん。どうしたの」
「やっ、ぱ、いい」
姫野は自分の傘を持って遊具を出た。本城も続く。
「靴、汚れた」
「姫野の家に着いたら拭いてあげる」
姫野は紺色の傘を開かなかった。本城は自分の傘の下に、姫野を引き寄せる。
弱く小雨が、降り続いている。
玄関先で、本城は姫野の靴を拭いてやった。こげ茶色の、姫野の足に馴染んだ小さなローファーに、ハンカチを滑らせる。
「ハンカチ汚れるよ」
「大丈夫」
「雑巾あるってば」
「いいよ、はい、もう終わり。綺麗になったね」
姫野に微笑みかけてから、本城はハンカチをポケットにしまう。
「寄っていい?」
姫野が頷いたので本城は靴を脱いだ。
姫野の家は、薄暗くしんと静まり返っている。共働きの両親はまだ帰っていないようだった。
ゲームをするのを見ていると、姫野が小さくあくびをした。
「眠いの?」
「昨日ゲームしすぎた」
「寝てもいいよ」
「寝ないし」
「おばさん、帰って来ないね」
立って窓に寄り、外を覗きながら言う。街灯の灯りがくっきり見えるほど暗くなっていた。姫野の母親はいつもならもうとっくに帰っている時間のはずだ。
姫野が何も言わないので振り返ると、ぱちりと目が合った。
「ん?」
「なっ、何」
「何って?何が?」
「……今日…」
姫野が何か言いかける。
「今日?」
「…今日は…」
姫野はゲームを床に置くと、立ち上がって下を向いたまま本城に近づき、ぽすっと抱きついた。
「今日……、お母さんもお父さんも、帰ってこない」
心臓がとくりと音を立てる。
姫野は本城の胸に顔をうずめたまま黙った。
「…旅行かなにか?」
姫野は頷き、本城の制服の背中をきゅっと握った。
それは。それって。
本城はドキドキしながら考える。
泊まってもいいのかな。明日も学校だけど、このまま行けるし、ない教科書は隣に見せてもらうことにして。うちには後で連絡を入れればいいし。
しがみついたままの姫野の顔を覗き込む。
「泊まってもいい?」
目を合わせてくれない姫野は「いいけど」と言ってまた黙った。
何をしよう。何を話そう。
「なんかご飯買いに行く?」
「なんか…カレーがあるとか…言ってたけどね」
ちょっと見てくる、と言って離れた姫野の後に続いて部屋を出る。
「俺も行く」
キッチンにはカレーのどっさり入った鍋があった。炊飯器にはご飯もセットされている。
「おばさん優しいね」
「別に」
「お腹すいた?」
「うん」
「いただく?」
「うん」
手分けをして、2人とも慣れない手つきでカレーを取り分ける。
「おいしそう。俺もお腹減っちゃった」
「…いただきます」
「いただきます」
一口食べて、自分の家で姫野とご飯を食べた時もメニューがカレーだったことを思い出す。
姫野の家のカレーは、少し甘くて、キノコが入っていた。
「キノコだ」
「いつも入ってる」
「へえ」
ニンジンの形も、ジャガイモの大きさも、本城の家のものとは違っていた。
気がつけば姫野のことをじっと見つめていて、視線を感じたのか姫野が睨み返してきた。
「見ないでよ」
「なんで?」
「知らない」
「だってかわいいから」
「意味わかんない」
「ハムスターみたいだし」
「うるさい。しつこい」
「ねえ姫野。俺と姫野が結婚したら、いつもこんなふうに一緒にいられるね」
その言葉は滑るように本城の口から出てきて、自分でもうろたえるほどだった。
姫野は口に運ぼうとしていたスプーンを止めた。
「……結婚……?」
「ああ、ごめんね。何でもない。気にしないで」
自分は何をそんなに焦っているのだろう。こんなことを言うはずではなかった。
それでも、姫野の反応がどうなのか、照れるか、全否定されるか、平静な顔で無視されるか。
本城は自分の動揺をよそに、姫野の動向の行方に胸を高鳴らせた。
「できるの?」
姫野は向かいに座る本城を見上げた。その目は少しだけ見開かれている。
「ん?」
「ゆきと結婚、できるの?男でも?どうやるの?」
そのあどけない口元に目をやる。
珍しく素直な、少し幼げなその反応を見て、本城は顔に出さずにただただ考える。
姫野は、どうしてそんなにかわいいの。
どうしてそんなに、俺の心臓を放してくれないの。
「俺と結婚したい?」
そう言ってにこりと笑うと、姫野は途端に顔を強張らせた。
「別に、どうするのかって聞いただけだし」
姫野はぷすっとして、カレーを食べ始める。
「できるよ。できる。俺がなんとかするからね」
だから何も心配しないで。
「ねえ姫野。ご飯食べたら、一緒にお風呂に入らない?」
途端に顔を赤くした姫野を、本城は笑顔で見つめた。
静かで幸せな食事を終え、少し惜しいような思いをしながら2人で食器を下げ、並んで皿洗いをした。
「カレーってなかなか落ちないね」
「油がすごい」
「スポンジ汚れるね」
「……明日の朝も、カレーだけど」
「いいね。姫野の家のカレー、好きだ」
隣で洗剤のあわを洗い流す姫野の横顔は、いつもより少しだけ子どもっぽく見える。
姫野の家のキッチンは、本城の家のそれの半分くらいの広さで、でも道具類がすっきりと使いやすくまとめられ、好ましく思えた。
姫野へと視線を戻し、本城は唐突に強い衝動に駆られた。
触りたい。姫野と自分しかいない姫野の家の、あらゆる場所で姫野を犯したい。
「姫野」
すすぎ終わってタオルで手を拭く姫野がちらりと本城を見上げる。
「お風呂、入る?」
「……うん」
「お湯ためなきゃね」
「知ってる」
むすっとしてバスルームへ向かう姫野の後について行く。
姫野は風呂用のピンクのスリッパを履いて、浴槽のゴム栓をはめようと屈んだ。
スリッパは姫野には少し大きい。
抱きたいなあ。
「姫野、やっぱお風呂あとにする?」
「は?」
振り返った姫野は不機嫌な顔。
「なんで」
「なんか」
「意味わかんない。入る。お風呂」
姫野は容赦なく湯張りスイッチを押した。じゃーっと音がして、湯気が立つ。
「姫野はいつも、お風呂一人で入るの?」
「あったりまえでしょ」
「じゃあ今日は特別なんだ。俺とお風呂、入るんだから」
浴室の壁に姫野を押し付け、顔をぐいっと近づける。
姫野は動揺したのか目を泳がせながら少し抵抗した。
背中がぞわりと鳥肌をたてる。早く。早く。
「姫野、もうこのまま一回ヤらせて」
「い、いやだ…」
「なんで?好きだよ姫野」
形のいい耳に舌をつっこむと、姫野は体をふるりと震わせた。
「体…洗ってからじゃないと……」
「いつもはそんなこと気にしないくせに」
姫野を追い詰めるために耳元でぼそぼそと囁く。
「いいでしょ…?」
「…だめ……」
そんな言い方、ダメに聞こえない。
肩をおさえて、顔を背けようとする姫野の唇を奪う。
「制服は脱ごうね。濡れるといけないから」
体を硬くして抵抗する姫野のブレザーに手をかけ、柔らかな手つきで、有無を言わさず、脱がせていく。
風呂場の蒸気で少し湿ったそれを脱衣所の方へ落として、下着姿で体を隠そうとする姫野をゆっくり眺めた。
時間はたくさんある。なにをしよう。どんな顔を見られるだろう。
「……寒い」
「嘘。寒いわけないよ」
ほかほかと上がる湯気は、十分に浴室を温めている。
「見られるのが恥ずかしいの?それとも、」
白い肌に指を這わせる。それは少しだけ紅潮して。ゆっくり。ゆっくり。
「早く触ってほしくて、それを、その期待を知られるのが、恥ずかしいのかな」
「…っ、」
姫野。
黒く艶めく髪の毛を撫でると、姫野が体を震わせてから、首をすくませた。腹の底で加虐心が頭をもたげる。
「だってね、別に、俺に今日ご両親がいないって言う必要は無かったよね?1人でゲームして夜更かししてのんびりしてもよかったんだよね?けど姫野は俺に、誰もいないって言った。それって、俺とたくさんセックスができるって思ったからだ。泊まって、夜通し、俺とセックスしたいって思ったからだ。違う?」
焦ったような表情。
「ち、ちがう!」
「そうだろ」
衝動的に、首元に噛みついてしまった。
「あっ、いたい」
逃げようとする体を壁に押さえつけて、噛んだ跡を舐めた。
痛がる顔がかわいくてかわいくて、抱きしめて優しいキスがしたくなる。
でもそれは、あとの楽しみに取っておこう。
「やらしいね、姫野」
「ちがう…」
「セックスしたい?」
「したく…ない…」
「俺はしたい。姫野とセックスがしたい。たくさん触りたい。中に突っ込んでぐちゅぐちゅにして奥の方たくさん突いて、わけのわからなくなった姫野の中に、たくさん中出ししたい。何回も、何回も、中に、俺のを、」
言いながら興奮が抑えられなくなってきて、本城はまた恋人の体を噛んだ。
今度は肩口を。
「いやっ」
「駄目だ。我慢できなくなってきたよ」
息を飲む姫野の顔を至近距離で見つめる。
「下着、脱いで。見せて」
「や…」
「見せて」
「やだ…」
「勃ってるから?わかるよ、こっちからでも。ここ…」
「あ、やっ、い…」
前に触れるとそこはもう存在を主張していて、姫野は体をよじって逃げようとする。
「見せてよ。お願い。姫野」
やだ、やだ、と小声で拒否を続ける姫野に、少し本気で虐めてみたいという気持ちが芽生える。
楽しくて、興奮して、笑みを抑えられない。
無言でシャワーヘッドを掴み、大きな目で見上げる姫野に向かって思い切り蛇口を捻った。
「あ、やだ、パンツ…濡れる…」
かわいい。かわいい。かわいい。髪の間からのぞく耳に唇を寄せた。
「もう濡れてるんじゃないの?」
囁きながら、シャワーを後頭部へ伸ばす。髪も濡れていく。姫野の匂いが立つ。
「姫野」
「んん…」
「されるままでいいの?抵抗しないんだ?早くパンツ脱いで」
湯で濡れることでくっきりと浮かび上がったそこを、本城は意識的にまじまじと見た。
つられて視線を落とし、はっとしたように見上げ、姫野は本城の顔に手を伸ばした。
「見ないで…」
本城は恋人の手で覆われた目を軽く見開く。血が逆流し始める。
両極端な自分の感情に引き裂かれそうな感覚を覚えた。
「俺に逆らうな」
自分の喉から出た低い声に、姫野が伸ばした手を下ろしかける。
その手を取り、壁に固定し、頭のてっぺんからシャワーを浴びせた。
湯が勢いよく顔を流れ、苦しそうに顔を背ける姫野に、また興奮が高まった。
かは、うう、と姫野が溺れている様を、本城は息荒く見つめる。
「愛してるよ。愛してる。姫野」
シャワーヘッドを湯船へ投げ込んで、そうすると水音が籠った。そこで初めて、自分が制服を着たままで、それがべちゃべちゃに濡れていることに気づく。
ポケットの携帯も財布も濡れてしまった。まあいい。そんなことはどうだって。
「姫野。俺の服、脱がせて」
手近にあったタオルで顔を拭ってやると、姫野は伏し目がちにそっと、本城の体に触れた。
身長差があるので姫野はとてもやりにくそうだ。上着を脱がそうとするのに手間取っているのを見下ろしながら、気がおかしくなりそうだと思った。
背伸びをして手を伸ばしてくるのが、どうしてこんなにかわいく見えるのだろう。
姫野は本城の制服を、静かに脱衣所の床へ置いた。
お互い下着だけの姿になり、本城はそれが濡れるのにも構わず湯船に入り、姫野の手を引いた。
向かい合わせに本城の膝に跨る形になった姫野は、本城の明け透けな視線を受け止めきれないと言うように体を寄せてきた。
満水に近くなった湯船に、2人。
「姫野」
綺麗な形の後頭部に手をやり、唇を覆うようにキスをする。姫野の舌を引っ張り出し、噛み、吸った。姫野の反応がいつもよりも濃い。
本城は嬉しくなって少し笑った。
「家だから、興奮する?」
返事はない。肯定か。ただ、更に深いキスをねだられて本城は腕に力を込めた。
もっともっと近くに行きたい。
色々な水音をたてながら片手で姫野の下着に触れると、下半身を押し付けられる。
「どうしたの。いやらしい」
だって、と呟く姫野の唇。赤く濡れて。
空いている方の手を頬にやり、その唇の奥に親指を突っ込んだ。
横に引かれる形になった姫野の唇は、それでも形よく艶めいて見えた。
「う」
「舐めて」
「ん…」
ちゅぷ。ちゅ。
「もっと。れろってして」
ちゅ。れろ…。
「姫野の舌、見たい」
親指で顎を押し下げると、赤い唇の中に、濡れた舌が見えた。
「動かして」
少し首を傾げる姫野。
「れろれろしてるの見せて」
「ん…?」
戸惑いながらゆっくり舌を出し、持ち上げ、横へずらし、また首を傾げる。
従順だ。
「いい子」
下着をずらし、奥へ指を滑らす。
「んっ」
「このまま挿れていい?いいよね」
だってもう待てない。待たない。
自分の下着からペニスを出す。水面が大きく揺れて湯が零れていく。
姫野の腰を持ち上げ、ずらした下着の隙間から挿入した。
「あんっ!」
「あー…入っちゃうね」
「やぁ…ゆきぃ…」
上気した姫野の顔が上を向き、うっとりと目を閉じる。濡れた髪が一筋頬にかかっているのを、本城は優しい手つきで耳にかけてやった。
「気持ちいいの?」
「…ん…」
「中、すっごい動いてる」
絞るように伸縮して、奥に誘っているみたいだ。
「ああんっ、あ、う、」
「家だよ、姫野。いつもお父さんやお母さんも使ってる、姫野んちのお風呂だよ。ほら。目、開けて」
姫野は途端に下を向いて本城の肩をぎゅっと掴んだ。
「帰って来たらどうする?」
下から突き上げる。
「あっ!だめ!」
「声、聞かれたら、入って来ちゃうかも」
ふるふると首を横に振る表情が苦しげで、本城は「好きだ」と呟いた。
好きだ。好きなんだ。どうしたらいいのかわからない。この気持ちの行き場が。
腰の動きを速くすると、湯が動いてばしゃばしゃと波が立つ。
「ひっ、いや!だめ、だめぇ!あぁん!」
「っ、いつもより、声が大きい」
「ちがう!…ああっ」
何が違うものか。ああ。やっぱり、いつもと違う場所はいい。
「気持ちいいんだね…かわいいよ…」
「もうだめ…出る…うぅ、ん」
「一回イく?」
姫野の顔が赤い。のぼせて体調を崩してはかわいそうだと、本城は挿入したまま体を抱き上げた。
バスタブの縁に腰掛け、抱きつく姫野のペニスを握る。
「あぁ…ゆき」
「好きだよ姫野」
かわいい。
背中を支えてやりながら強めに握って上下に動かすと、姫野は声を漏らしながら懸命に本城の唇をしゃぶってきた。
「んっ、ふ、んん、んっ、んっ、」
姫野の腰が動き、中の本城を締め付ける。
「んぐ、イくっ…」
呆気なく精を吐き、しなだれかかる姫野を見守りながら、本城は腹に力を入れて、射精したいという欲望に耐えた。
まだ全然許してあげられそうもない。
くたくたしてしまった姫野を脱衣所の床に座らせ、タオルで体を拭いてやった。
白い肌が全体的に赤みを帯び、とても性的に見えた。
「姫野。大丈夫?」
聞きながら何度かキスをする。
「うん……水飲みたい」
水ね。
「おいで」
くったりとした姫野を裸のまま抱き上げて運び、目的の場所へとゆっくり下ろす。
廊下の先。玄関だ。
「姫野、舐めて」
「こんな、ところで、やだ」
「いいから。早く」
まただ。怯えたような顔をする。
逃げられないくせに。逃げたくもないくせに。俺にひどいことをされるのが好きなくせに。
床に尻をついたまま後ずさった姫野を追う。頭を押さえて口に無理矢理突っ込むと、途端に大人しくなって本城の勃起したものをしゃぶり始めた。
「うまくできたら、水、飲ませてあげるよ」
姫野は両手を丁寧に根元に添えて、先端をちゅぷちゅぷとしゃぶっている。
姫野の家の玄関には、フラワーリースがかかっている。母親が作ったものらしい。父親がちょっと外に出る時に履くのであろう男物のサンダルがあり、女物のスリッパがある。
そんな場所で、息子が彼氏のペニスを丁寧にしゃぶっている。
興奮で意識が飛びそうになった。
「姫野」
髪を撫で、後頭部を押さえて何度か喉奥を突き、姫野が嘔吐きそうになったところで解放してやる。涙目の姫野は、それでも再度咥えようと口を開いた。
「姫野。かわいいよ。愛してる。ねぇ……」
俺は、可哀想な姫野がかわいいんだ、どこかおかしいのかな。
口に出さずに、胸に思いを秘めて、それから少し笑ってしまった。
ちらりと見上げたその瞳は、少し充血して潤んでいる。髪や頬や耳や首筋を、優しく優しく撫でながら、ペニスをしゃぶる姫野に話しかけた。
「俺の精液、姫野の口に出して、姫野がそれを飲み込んで、胃か、腸のあたりからそれを吸収して、俺の一部が姫野の一部になっちゃうのかな……そしたら、ずっと一緒だ。姫野と、俺、ずっと一緒だね」
言いながらどんどん興奮して、本城は喉の奥までペニスを突っ込んだ。
姫野が苦しそうにする。
「俺の精液が、姫野のこのへんの細胞になればいいな」
乳首を触ってやると、姫野の体がひくりと反応する。
「そしたらもっともっと敏感になって、ここからミルクが出ちゃって、俺がそれを吸って、飲んで、そしたらまた、ずっと一緒だ」
「んっ……」
こりこりと指で弾くと、姫野の乳首は簡単に固くなっていく。
「自分ちの玄関でフェラするの、どんな気持ち?」
本城に言われてしばらくぶりに場所を思い出したのか、姫野はぎゅっと目をつむった。同時に口の中も狭くなる。粘膜がペニスを包み、あたたかくてひどく気持ちがいい。
「一回出すね……姫野……愛してるよ、ほんとに」
ぐっと奥まで突っ込んでしばらくそのままにすると、姫野が苦しさに悶え始めた。唇の端から涎が垂れて、大きな瞳から涙が零れる。
ああ。興奮する。興奮する。興奮する。助けて。姫野。俺を助けて。
「っ、飲んでね、全部」
ずっと我慢していた分勢いが増した射精は、ひどく長く続いたように思う。満足してペニスを口内から引きずり出すと、姫野は思い切りむせた。
「ゲホッ、かはっ」
「大丈夫? お水持ってくるから待ってて」
くったりと座り込んで動かなくなった姫野を一度抱きしめてから、本城は一人キッチンへ向かった。
適当なグラスに水を注いで戻ると、玄関は無人で、代わりに二階から物音が聞こえた。
「……姫野?」
「ゆき」
階段を上り、姫野の部屋へ行く途中、廊下の左側の部屋を覗くと、中には大きなダブルベッドが据えられていた。
「何してるの」
素肌に薄手のカーディガンを羽織って部屋から出てきた姫野に、グラスを手渡す。
「ここ、ご両親の寝室?」
ごくごくと喉を鳴らしながら水を飲み、姫野は本城を見上げた。
「そうだけど」
「ここでしよっか」
言葉を失った姫野からグラスを取り上げ、その体を抱き上げるのは簡単だった。
「や! 降ろして! やだ!」
「いいでしょ。汚さなければバレないよ」
「そういう問題じゃないっ!」
暴れる姫野の手が頬を叩くのにも構わず、本城はダブルベッドに姫野を押し倒した。上から押さえつけて無理矢理キスをする。
「んっ! やだっ! んっ、う」
「暴れないで。ねえ姫野、ここで、すっごくいやらしいセックスしよう」
つづく
2019.9.29
外でサッカーをする予定だった体育も体育館内でのマット運動へ変更され、クラスの皆はやる気のない放漫な動作で体を動かしている。
湿気を帯びた床が、靴の底のゴムでキュッキュと鳴った。
姫野は何してるかな。
本城は壁際であぐらをかき、野島がマットの上でくるりと回るのを見ながら考えた。
ぼんやりと窓の外を見ているだろうか。
真剣に板書しているだろうか。
眠気を抑えるために教科書を読んでいるだろうか。
自分のことを、思い出すことはあるだろうか。
野島は、腹の上までめくれてしまったTシャツを急いで直し、本城の横で小さく体育座りをした。
「できなかった……」
「そう?できてたよ」
「苦手なの、マット運動」
「足、大丈夫?無理しないでね」
「このくらいなら平気。ありがとう」
恥ずかしそうにする野島の腹が色白ですべらかだったことを思う。
姫野とどっちが白いかな。ぼんやり考える本城の目の前で、他のクラスメイトが宙返りをする。
「うわぁ!すごい!」
感嘆の声をあげて拍手をした野島にそのクラスメイトが寄ってきて、ハイタッチを要求した。
どさくさに紛れて手を握られている。
最近、本城のクラスでは野島の人気が高まりつつある。可愛らしい容姿と、優しくて明るく素直な気質。
姫野とは違う。全然違う。
別に野島のことを嫌うわけではないし、むしろ友達としては本当に付き合いやすいタイプだった。
でも自分は姫野がいいし、姫野しかいらない。何があってもそれだけは揺るがない。
本城は、手を握られ困惑して照れ笑いをする野島を微笑ましく見守りながら、延々と姫野のことを考えていた。
「すごいね」
昇降口から外を見ると、授業中より降り方が酷くなっていた。
本城はガラス戸を出て自分のビニール傘を広げ、姫野を振り仰いだ。
「こっちで一緒に帰ろう」
姫野は少し戸惑い気味に、自分の傘を閉じたまま本城の傘の下に入った。本城は手を差し出し、姫野の傘も持ってやる。綺麗に畳んで細く巻かれた、紺色の傘。
少し歩みを進めただけで、足元がべちゃべちゃに濡れた。雨粒が傘を叩く音が、バツバツと聞こえる。
「もっとこっち来ないと濡れちゃうよ」
「いいの」
「駄目だってば。風邪引くよ」
「大丈夫だし」
「今日ね、体育、マットになったよ」
「ふぅん」
「野島もやったんだよ。ころって前転して」
「野島だって前転くらいできるでしょ」
「俺ね、ずっと、姫野のこと考えてた」
土砂降りの中、一本の傘の下で続ける会話は、世界中の誰にも邪魔されないような気がして心地が良かった。
「ずっと、姫野のこと考えてるよ。いつも」
怖いくらいだ。どうしてこんなに、姫野じゃなきゃ駄目なんだろう。
姫野がいなくなったら、きっと自分は、ぱっと消えて無くなるに違いない。
「変。最近、本城、変」
口を尖らせて自分を見上げる姫野を、抱きしめたくて仕方がなくなる。
「聞いてるの?ちょっと、本城」
「ああ、うん。聞いてる」
「ぼーっとしてるし、迎えに来るの遅いし、金髪が前より金色になった感じするし、野島とすごい仲いいし、でも野島のことはいいけど、なんか変」
「へえ。そうかな」
姫野の言うことの半分くらいは意味がよくわからなかった。
「髪がなんだって?」
「だから、前より金色だって」
「えー、何それ」
「知らないよ」
「姫野が言ったんでしょ」
「だってそうなんだもん」
永遠にこうやって話していたい。
「ねえ姫野。姫野は、俺のこと考えたりする?」
自分と同じくらいじゃなくてもいい。
胸が苦しくなったり、なんで本城じゃなきゃいけないんだろうとか、考えたりする?
姫野は無言だ。
その時、雨の音が一段と大きくなった。風はないのに、雨の勢いだけで傘が壊れそうだった。
「どっか寄って雨宿りしてこっか」
本城が言うと、姫野は尖った声で「いいよ」と言った。
公園にある大きな遊具の中に、2人で入った。土砂降りなので、公園には当然誰もいない。
真っ赤で大きな球体のその遊具は、中が空洞で、下の部分に幾つか穴があいており、そこから中へ入って、壁をよじ登ったり寄りかかったりする以外にどうやって遊ぶのかがよくわからない。
薄暗いその空間は、外の雨の音すら遮断してしまった。
「……お父さん、帰って来た?」
「ああ、いや。まだ。来週か、その次の週かな」
姫野には、父が帰って来るという話だけしていた。
本城がどんな話をするつもりなのか、その結果が本城家にどんな影響を与え得るか、そういうことは一切伏せたまま。
「もしよかったら、またうちに来て。それで、父さんにも会って」
「いいけど」
「姫野」
畳んだ傘を2本、遊具の内側に立てかけ、横に立った姫野の肩を抱く。髪を撫でる。
「姫野と一緒に住めるなら、俺、ここでもいいなぁ」
遊具の天井を見上げる。
薄暗く、湿った空気が滞留していて、声が少し響いて聞こえる、がらんどうのようなここでも。
「嫌だよ、こんなとこ」
姫野が、にべもなく否定する。
「どうして?」
「だって座れないじゃん」
「敷物を持ってくるんだよ。家から」
「それで?」
「あと、ベッドを置く」
「2こ?」
「1こ」
「…ベッド1こ…」
「一緒に寝るからいいでしょ」
「あとは?」
「冷蔵庫もいるかなぁ。姫野のケーキとかアイスとか入れておかないと」
「電源がないじゃん」
「そうだね…その都度買えばいいか」
「暗いの嫌だ」
「怖がり」
「違うし!」
「電池で点くランプとか置けばよくない?」
「テレビもない」
「ケータイで我慢してよ」
「…ハムスター飼いたい」
「いいよ。飼おう」
話に乗ってきた姫野のことを、苦しいくらいに、好きだと感じる。
離れるのが、本当に苦痛だ。一体いつになったら、自分は姫野と離れずに暮らせるようになるのだろう。そのために、一体いくつの壁を越えなければならないのだろう。
そういうことを考えるたび、本城は少しだけ怖くなる。そばにいる小さな体を思い切り抱きしめずにはいられなくなる。
「姫野」
姫野の制服は少し湿っている。姫野の香りがする。
「大好きだよ」
いつも、言葉になって出るのはその想いだけだ。
「ゆき」
小さな声が返って来て、本城は顔を近づけ、キスをした。
体を離そうとすると、姫野が腕を本城の首に絡めて、ほとんどぶら下がるような格好で抱きついてきた。
「…どうしたの。本城、変」
たまらなくなってまた抱き返す。
姫野はたまに、本城の心の動きに恐ろしく敏感だ。
自分の些細な不安でも、伝われば姫野が不安になることは本城にもわかる。自分が安定していなければ、姫野は安心してツンツンしていられないのだ。
かわいいな。俺が全て、みたいで。
ぎゅうと抱きしめたまま、首筋や耳にキスをしながら、姫野に聞く。
「姫野、ハムスター好きなの?」
「…好きっていうか、まあ、飼ってみたいだけ」
「かわいいもんね。姫野みたいで」
「は?意味がわかんない」
「姫野、似てるよ。ハムスターに」
「似てない」
「似てる」
「似てないってば」
「似てるよ」
「しつこい」
「ごめん」
本城から離れ、壁に寄りかかって、姫野は口を尖らせた。
「姫野って、どんな子どもだったの?」
姫野は顔を上げて本城を見上げた。険しい眼差しに、思わず笑みがこぼれる。
「どんなって何」
「引っ込み思案で泣き虫だった?」
「…そんなことないし」
図星だな。
「ママっ子だったでしょ」
「違う」
「恥ずかしくなるとお母さんの影に隠れちゃった?」
「…覚えてない、そんなこと」
姫野の顔が少し赤くなる。
「本城だって、かわいい水着着てたくせに」
「まだ言う?それ」
「雨、止んできた」
耳を澄ましても、雨の音はほとんど聞こえなくなっていた。
「送るね」
「…ゆき…あのね……」
姫野が何か言いづらそうにしている。
「うん。どうしたの」
「やっ、ぱ、いい」
姫野は自分の傘を持って遊具を出た。本城も続く。
「靴、汚れた」
「姫野の家に着いたら拭いてあげる」
姫野は紺色の傘を開かなかった。本城は自分の傘の下に、姫野を引き寄せる。
弱く小雨が、降り続いている。
玄関先で、本城は姫野の靴を拭いてやった。こげ茶色の、姫野の足に馴染んだ小さなローファーに、ハンカチを滑らせる。
「ハンカチ汚れるよ」
「大丈夫」
「雑巾あるってば」
「いいよ、はい、もう終わり。綺麗になったね」
姫野に微笑みかけてから、本城はハンカチをポケットにしまう。
「寄っていい?」
姫野が頷いたので本城は靴を脱いだ。
姫野の家は、薄暗くしんと静まり返っている。共働きの両親はまだ帰っていないようだった。
ゲームをするのを見ていると、姫野が小さくあくびをした。
「眠いの?」
「昨日ゲームしすぎた」
「寝てもいいよ」
「寝ないし」
「おばさん、帰って来ないね」
立って窓に寄り、外を覗きながら言う。街灯の灯りがくっきり見えるほど暗くなっていた。姫野の母親はいつもならもうとっくに帰っている時間のはずだ。
姫野が何も言わないので振り返ると、ぱちりと目が合った。
「ん?」
「なっ、何」
「何って?何が?」
「……今日…」
姫野が何か言いかける。
「今日?」
「…今日は…」
姫野はゲームを床に置くと、立ち上がって下を向いたまま本城に近づき、ぽすっと抱きついた。
「今日……、お母さんもお父さんも、帰ってこない」
心臓がとくりと音を立てる。
姫野は本城の胸に顔をうずめたまま黙った。
「…旅行かなにか?」
姫野は頷き、本城の制服の背中をきゅっと握った。
それは。それって。
本城はドキドキしながら考える。
泊まってもいいのかな。明日も学校だけど、このまま行けるし、ない教科書は隣に見せてもらうことにして。うちには後で連絡を入れればいいし。
しがみついたままの姫野の顔を覗き込む。
「泊まってもいい?」
目を合わせてくれない姫野は「いいけど」と言ってまた黙った。
何をしよう。何を話そう。
「なんかご飯買いに行く?」
「なんか…カレーがあるとか…言ってたけどね」
ちょっと見てくる、と言って離れた姫野の後に続いて部屋を出る。
「俺も行く」
キッチンにはカレーのどっさり入った鍋があった。炊飯器にはご飯もセットされている。
「おばさん優しいね」
「別に」
「お腹すいた?」
「うん」
「いただく?」
「うん」
手分けをして、2人とも慣れない手つきでカレーを取り分ける。
「おいしそう。俺もお腹減っちゃった」
「…いただきます」
「いただきます」
一口食べて、自分の家で姫野とご飯を食べた時もメニューがカレーだったことを思い出す。
姫野の家のカレーは、少し甘くて、キノコが入っていた。
「キノコだ」
「いつも入ってる」
「へえ」
ニンジンの形も、ジャガイモの大きさも、本城の家のものとは違っていた。
気がつけば姫野のことをじっと見つめていて、視線を感じたのか姫野が睨み返してきた。
「見ないでよ」
「なんで?」
「知らない」
「だってかわいいから」
「意味わかんない」
「ハムスターみたいだし」
「うるさい。しつこい」
「ねえ姫野。俺と姫野が結婚したら、いつもこんなふうに一緒にいられるね」
その言葉は滑るように本城の口から出てきて、自分でもうろたえるほどだった。
姫野は口に運ぼうとしていたスプーンを止めた。
「……結婚……?」
「ああ、ごめんね。何でもない。気にしないで」
自分は何をそんなに焦っているのだろう。こんなことを言うはずではなかった。
それでも、姫野の反応がどうなのか、照れるか、全否定されるか、平静な顔で無視されるか。
本城は自分の動揺をよそに、姫野の動向の行方に胸を高鳴らせた。
「できるの?」
姫野は向かいに座る本城を見上げた。その目は少しだけ見開かれている。
「ん?」
「ゆきと結婚、できるの?男でも?どうやるの?」
そのあどけない口元に目をやる。
珍しく素直な、少し幼げなその反応を見て、本城は顔に出さずにただただ考える。
姫野は、どうしてそんなにかわいいの。
どうしてそんなに、俺の心臓を放してくれないの。
「俺と結婚したい?」
そう言ってにこりと笑うと、姫野は途端に顔を強張らせた。
「別に、どうするのかって聞いただけだし」
姫野はぷすっとして、カレーを食べ始める。
「できるよ。できる。俺がなんとかするからね」
だから何も心配しないで。
「ねえ姫野。ご飯食べたら、一緒にお風呂に入らない?」
途端に顔を赤くした姫野を、本城は笑顔で見つめた。
静かで幸せな食事を終え、少し惜しいような思いをしながら2人で食器を下げ、並んで皿洗いをした。
「カレーってなかなか落ちないね」
「油がすごい」
「スポンジ汚れるね」
「……明日の朝も、カレーだけど」
「いいね。姫野の家のカレー、好きだ」
隣で洗剤のあわを洗い流す姫野の横顔は、いつもより少しだけ子どもっぽく見える。
姫野の家のキッチンは、本城の家のそれの半分くらいの広さで、でも道具類がすっきりと使いやすくまとめられ、好ましく思えた。
姫野へと視線を戻し、本城は唐突に強い衝動に駆られた。
触りたい。姫野と自分しかいない姫野の家の、あらゆる場所で姫野を犯したい。
「姫野」
すすぎ終わってタオルで手を拭く姫野がちらりと本城を見上げる。
「お風呂、入る?」
「……うん」
「お湯ためなきゃね」
「知ってる」
むすっとしてバスルームへ向かう姫野の後について行く。
姫野は風呂用のピンクのスリッパを履いて、浴槽のゴム栓をはめようと屈んだ。
スリッパは姫野には少し大きい。
抱きたいなあ。
「姫野、やっぱお風呂あとにする?」
「は?」
振り返った姫野は不機嫌な顔。
「なんで」
「なんか」
「意味わかんない。入る。お風呂」
姫野は容赦なく湯張りスイッチを押した。じゃーっと音がして、湯気が立つ。
「姫野はいつも、お風呂一人で入るの?」
「あったりまえでしょ」
「じゃあ今日は特別なんだ。俺とお風呂、入るんだから」
浴室の壁に姫野を押し付け、顔をぐいっと近づける。
姫野は動揺したのか目を泳がせながら少し抵抗した。
背中がぞわりと鳥肌をたてる。早く。早く。
「姫野、もうこのまま一回ヤらせて」
「い、いやだ…」
「なんで?好きだよ姫野」
形のいい耳に舌をつっこむと、姫野は体をふるりと震わせた。
「体…洗ってからじゃないと……」
「いつもはそんなこと気にしないくせに」
姫野を追い詰めるために耳元でぼそぼそと囁く。
「いいでしょ…?」
「…だめ……」
そんな言い方、ダメに聞こえない。
肩をおさえて、顔を背けようとする姫野の唇を奪う。
「制服は脱ごうね。濡れるといけないから」
体を硬くして抵抗する姫野のブレザーに手をかけ、柔らかな手つきで、有無を言わさず、脱がせていく。
風呂場の蒸気で少し湿ったそれを脱衣所の方へ落として、下着姿で体を隠そうとする姫野をゆっくり眺めた。
時間はたくさんある。なにをしよう。どんな顔を見られるだろう。
「……寒い」
「嘘。寒いわけないよ」
ほかほかと上がる湯気は、十分に浴室を温めている。
「見られるのが恥ずかしいの?それとも、」
白い肌に指を這わせる。それは少しだけ紅潮して。ゆっくり。ゆっくり。
「早く触ってほしくて、それを、その期待を知られるのが、恥ずかしいのかな」
「…っ、」
姫野。
黒く艶めく髪の毛を撫でると、姫野が体を震わせてから、首をすくませた。腹の底で加虐心が頭をもたげる。
「だってね、別に、俺に今日ご両親がいないって言う必要は無かったよね?1人でゲームして夜更かししてのんびりしてもよかったんだよね?けど姫野は俺に、誰もいないって言った。それって、俺とたくさんセックスができるって思ったからだ。泊まって、夜通し、俺とセックスしたいって思ったからだ。違う?」
焦ったような表情。
「ち、ちがう!」
「そうだろ」
衝動的に、首元に噛みついてしまった。
「あっ、いたい」
逃げようとする体を壁に押さえつけて、噛んだ跡を舐めた。
痛がる顔がかわいくてかわいくて、抱きしめて優しいキスがしたくなる。
でもそれは、あとの楽しみに取っておこう。
「やらしいね、姫野」
「ちがう…」
「セックスしたい?」
「したく…ない…」
「俺はしたい。姫野とセックスがしたい。たくさん触りたい。中に突っ込んでぐちゅぐちゅにして奥の方たくさん突いて、わけのわからなくなった姫野の中に、たくさん中出ししたい。何回も、何回も、中に、俺のを、」
言いながら興奮が抑えられなくなってきて、本城はまた恋人の体を噛んだ。
今度は肩口を。
「いやっ」
「駄目だ。我慢できなくなってきたよ」
息を飲む姫野の顔を至近距離で見つめる。
「下着、脱いで。見せて」
「や…」
「見せて」
「やだ…」
「勃ってるから?わかるよ、こっちからでも。ここ…」
「あ、やっ、い…」
前に触れるとそこはもう存在を主張していて、姫野は体をよじって逃げようとする。
「見せてよ。お願い。姫野」
やだ、やだ、と小声で拒否を続ける姫野に、少し本気で虐めてみたいという気持ちが芽生える。
楽しくて、興奮して、笑みを抑えられない。
無言でシャワーヘッドを掴み、大きな目で見上げる姫野に向かって思い切り蛇口を捻った。
「あ、やだ、パンツ…濡れる…」
かわいい。かわいい。かわいい。髪の間からのぞく耳に唇を寄せた。
「もう濡れてるんじゃないの?」
囁きながら、シャワーを後頭部へ伸ばす。髪も濡れていく。姫野の匂いが立つ。
「姫野」
「んん…」
「されるままでいいの?抵抗しないんだ?早くパンツ脱いで」
湯で濡れることでくっきりと浮かび上がったそこを、本城は意識的にまじまじと見た。
つられて視線を落とし、はっとしたように見上げ、姫野は本城の顔に手を伸ばした。
「見ないで…」
本城は恋人の手で覆われた目を軽く見開く。血が逆流し始める。
両極端な自分の感情に引き裂かれそうな感覚を覚えた。
「俺に逆らうな」
自分の喉から出た低い声に、姫野が伸ばした手を下ろしかける。
その手を取り、壁に固定し、頭のてっぺんからシャワーを浴びせた。
湯が勢いよく顔を流れ、苦しそうに顔を背ける姫野に、また興奮が高まった。
かは、うう、と姫野が溺れている様を、本城は息荒く見つめる。
「愛してるよ。愛してる。姫野」
シャワーヘッドを湯船へ投げ込んで、そうすると水音が籠った。そこで初めて、自分が制服を着たままで、それがべちゃべちゃに濡れていることに気づく。
ポケットの携帯も財布も濡れてしまった。まあいい。そんなことはどうだって。
「姫野。俺の服、脱がせて」
手近にあったタオルで顔を拭ってやると、姫野は伏し目がちにそっと、本城の体に触れた。
身長差があるので姫野はとてもやりにくそうだ。上着を脱がそうとするのに手間取っているのを見下ろしながら、気がおかしくなりそうだと思った。
背伸びをして手を伸ばしてくるのが、どうしてこんなにかわいく見えるのだろう。
姫野は本城の制服を、静かに脱衣所の床へ置いた。
お互い下着だけの姿になり、本城はそれが濡れるのにも構わず湯船に入り、姫野の手を引いた。
向かい合わせに本城の膝に跨る形になった姫野は、本城の明け透けな視線を受け止めきれないと言うように体を寄せてきた。
満水に近くなった湯船に、2人。
「姫野」
綺麗な形の後頭部に手をやり、唇を覆うようにキスをする。姫野の舌を引っ張り出し、噛み、吸った。姫野の反応がいつもよりも濃い。
本城は嬉しくなって少し笑った。
「家だから、興奮する?」
返事はない。肯定か。ただ、更に深いキスをねだられて本城は腕に力を込めた。
もっともっと近くに行きたい。
色々な水音をたてながら片手で姫野の下着に触れると、下半身を押し付けられる。
「どうしたの。いやらしい」
だって、と呟く姫野の唇。赤く濡れて。
空いている方の手を頬にやり、その唇の奥に親指を突っ込んだ。
横に引かれる形になった姫野の唇は、それでも形よく艶めいて見えた。
「う」
「舐めて」
「ん…」
ちゅぷ。ちゅ。
「もっと。れろってして」
ちゅ。れろ…。
「姫野の舌、見たい」
親指で顎を押し下げると、赤い唇の中に、濡れた舌が見えた。
「動かして」
少し首を傾げる姫野。
「れろれろしてるの見せて」
「ん…?」
戸惑いながらゆっくり舌を出し、持ち上げ、横へずらし、また首を傾げる。
従順だ。
「いい子」
下着をずらし、奥へ指を滑らす。
「んっ」
「このまま挿れていい?いいよね」
だってもう待てない。待たない。
自分の下着からペニスを出す。水面が大きく揺れて湯が零れていく。
姫野の腰を持ち上げ、ずらした下着の隙間から挿入した。
「あんっ!」
「あー…入っちゃうね」
「やぁ…ゆきぃ…」
上気した姫野の顔が上を向き、うっとりと目を閉じる。濡れた髪が一筋頬にかかっているのを、本城は優しい手つきで耳にかけてやった。
「気持ちいいの?」
「…ん…」
「中、すっごい動いてる」
絞るように伸縮して、奥に誘っているみたいだ。
「ああんっ、あ、う、」
「家だよ、姫野。いつもお父さんやお母さんも使ってる、姫野んちのお風呂だよ。ほら。目、開けて」
姫野は途端に下を向いて本城の肩をぎゅっと掴んだ。
「帰って来たらどうする?」
下から突き上げる。
「あっ!だめ!」
「声、聞かれたら、入って来ちゃうかも」
ふるふると首を横に振る表情が苦しげで、本城は「好きだ」と呟いた。
好きだ。好きなんだ。どうしたらいいのかわからない。この気持ちの行き場が。
腰の動きを速くすると、湯が動いてばしゃばしゃと波が立つ。
「ひっ、いや!だめ、だめぇ!あぁん!」
「っ、いつもより、声が大きい」
「ちがう!…ああっ」
何が違うものか。ああ。やっぱり、いつもと違う場所はいい。
「気持ちいいんだね…かわいいよ…」
「もうだめ…出る…うぅ、ん」
「一回イく?」
姫野の顔が赤い。のぼせて体調を崩してはかわいそうだと、本城は挿入したまま体を抱き上げた。
バスタブの縁に腰掛け、抱きつく姫野のペニスを握る。
「あぁ…ゆき」
「好きだよ姫野」
かわいい。
背中を支えてやりながら強めに握って上下に動かすと、姫野は声を漏らしながら懸命に本城の唇をしゃぶってきた。
「んっ、ふ、んん、んっ、んっ、」
姫野の腰が動き、中の本城を締め付ける。
「んぐ、イくっ…」
呆気なく精を吐き、しなだれかかる姫野を見守りながら、本城は腹に力を入れて、射精したいという欲望に耐えた。
まだ全然許してあげられそうもない。
くたくたしてしまった姫野を脱衣所の床に座らせ、タオルで体を拭いてやった。
白い肌が全体的に赤みを帯び、とても性的に見えた。
「姫野。大丈夫?」
聞きながら何度かキスをする。
「うん……水飲みたい」
水ね。
「おいで」
くったりとした姫野を裸のまま抱き上げて運び、目的の場所へとゆっくり下ろす。
廊下の先。玄関だ。
「姫野、舐めて」
「こんな、ところで、やだ」
「いいから。早く」
まただ。怯えたような顔をする。
逃げられないくせに。逃げたくもないくせに。俺にひどいことをされるのが好きなくせに。
床に尻をついたまま後ずさった姫野を追う。頭を押さえて口に無理矢理突っ込むと、途端に大人しくなって本城の勃起したものをしゃぶり始めた。
「うまくできたら、水、飲ませてあげるよ」
姫野は両手を丁寧に根元に添えて、先端をちゅぷちゅぷとしゃぶっている。
姫野の家の玄関には、フラワーリースがかかっている。母親が作ったものらしい。父親がちょっと外に出る時に履くのであろう男物のサンダルがあり、女物のスリッパがある。
そんな場所で、息子が彼氏のペニスを丁寧にしゃぶっている。
興奮で意識が飛びそうになった。
「姫野」
髪を撫で、後頭部を押さえて何度か喉奥を突き、姫野が嘔吐きそうになったところで解放してやる。涙目の姫野は、それでも再度咥えようと口を開いた。
「姫野。かわいいよ。愛してる。ねぇ……」
俺は、可哀想な姫野がかわいいんだ、どこかおかしいのかな。
口に出さずに、胸に思いを秘めて、それから少し笑ってしまった。
ちらりと見上げたその瞳は、少し充血して潤んでいる。髪や頬や耳や首筋を、優しく優しく撫でながら、ペニスをしゃぶる姫野に話しかけた。
「俺の精液、姫野の口に出して、姫野がそれを飲み込んで、胃か、腸のあたりからそれを吸収して、俺の一部が姫野の一部になっちゃうのかな……そしたら、ずっと一緒だ。姫野と、俺、ずっと一緒だね」
言いながらどんどん興奮して、本城は喉の奥までペニスを突っ込んだ。
姫野が苦しそうにする。
「俺の精液が、姫野のこのへんの細胞になればいいな」
乳首を触ってやると、姫野の体がひくりと反応する。
「そしたらもっともっと敏感になって、ここからミルクが出ちゃって、俺がそれを吸って、飲んで、そしたらまた、ずっと一緒だ」
「んっ……」
こりこりと指で弾くと、姫野の乳首は簡単に固くなっていく。
「自分ちの玄関でフェラするの、どんな気持ち?」
本城に言われてしばらくぶりに場所を思い出したのか、姫野はぎゅっと目をつむった。同時に口の中も狭くなる。粘膜がペニスを包み、あたたかくてひどく気持ちがいい。
「一回出すね……姫野……愛してるよ、ほんとに」
ぐっと奥まで突っ込んでしばらくそのままにすると、姫野が苦しさに悶え始めた。唇の端から涎が垂れて、大きな瞳から涙が零れる。
ああ。興奮する。興奮する。興奮する。助けて。姫野。俺を助けて。
「っ、飲んでね、全部」
ずっと我慢していた分勢いが増した射精は、ひどく長く続いたように思う。満足してペニスを口内から引きずり出すと、姫野は思い切りむせた。
「ゲホッ、かはっ」
「大丈夫? お水持ってくるから待ってて」
くったりと座り込んで動かなくなった姫野を一度抱きしめてから、本城は一人キッチンへ向かった。
適当なグラスに水を注いで戻ると、玄関は無人で、代わりに二階から物音が聞こえた。
「……姫野?」
「ゆき」
階段を上り、姫野の部屋へ行く途中、廊下の左側の部屋を覗くと、中には大きなダブルベッドが据えられていた。
「何してるの」
素肌に薄手のカーディガンを羽織って部屋から出てきた姫野に、グラスを手渡す。
「ここ、ご両親の寝室?」
ごくごくと喉を鳴らしながら水を飲み、姫野は本城を見上げた。
「そうだけど」
「ここでしよっか」
言葉を失った姫野からグラスを取り上げ、その体を抱き上げるのは簡単だった。
「や! 降ろして! やだ!」
「いいでしょ。汚さなければバレないよ」
「そういう問題じゃないっ!」
暴れる姫野の手が頬を叩くのにも構わず、本城はダブルベッドに姫野を押し倒した。上から押さえつけて無理矢理キスをする。
「んっ! やだっ! んっ、う」
「暴れないで。ねえ姫野、ここで、すっごくいやらしいセックスしよう」
つづく
2019.9.29