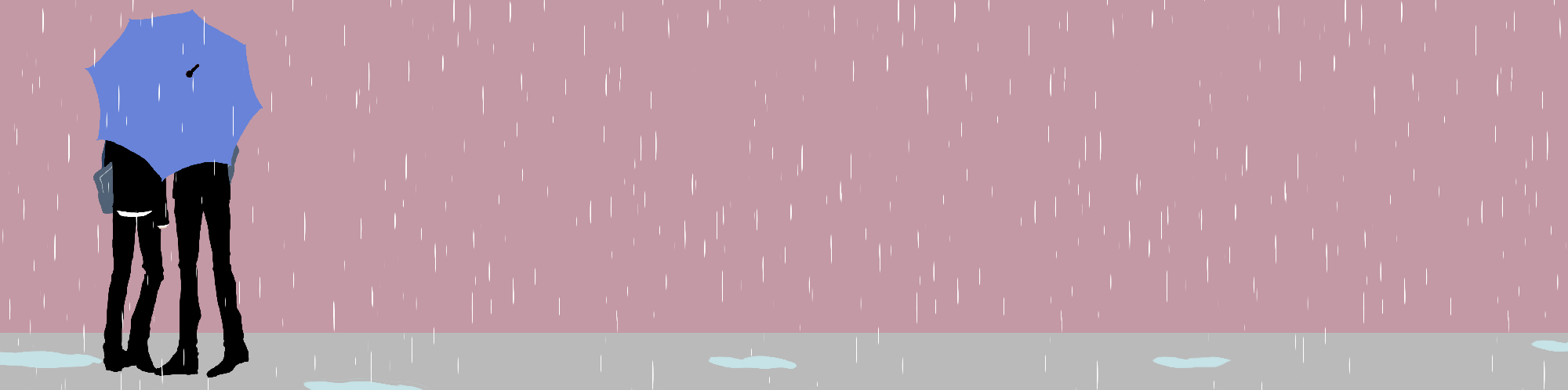姫は王子のもの。
暑い。
姫野はしかめ面で手を引かれていた。
5月とは思えない日差しの強さが、汗をかきづらい体質の姫野から体力を奪いつつあった。
「遠い」
「ごめんね。もうすぐだよ」
本城が振り返り、笑った。
2人は本城の家の敷地内を歩いていた。
広いと言っても門を入ってから玄関までは少し距離がある程度だ。それでも炎天下を自宅から歩いてきた姫野にとってはその距離でさえひどく遠い。
本城はそんな事情も全てわかっているように謝る。
「何しようね、うちで。アイスとかケーキとか、適当に頼んでおいたから、まずはおやつにしようか」
「おやつ」
姫野の機嫌が少し上向き、本城はそれを感じたのか嬉しそうな顔をした。
「本城の家、大きすぎ」
「そうかな。住んでるとよくわからない」
王子様みたい。金髪を見上げ、姫野は思った。
広いリビングに入り、姫野は息を飲んだ。
本城とどこか似ている女性が3人と、小柄な女性が1人、姫野を見てパッと表情を明るくした。
「あら」
「姫野くんね?」
「まあ」
「いらっしゃい」
口々に言われ、姫野はやっと「姫野です。お邪魔します」と言った。
「姫野。こっちの3人が姉、あと彼女が家のことをいろいろしてくれる坂田さんだよ」
本城が言うと、女性たちが代わる代わる笑顔で名乗った。
聞いてない。お姉ちゃんが3人もいるなんて。しかもお手伝いさんまで。
姫野は若干の気後れを感じた。
「部屋に行こっか」
家族の前でも臆することなく自分の手を握った本城に姫野が驚いていると、女性たちが口を開いた。
「ゆきちゃん。私たちもう少し姫野くんとお話がしたいわ」
「そうよ、独り占めなんてずるいわ」
「ねえ未琴くん。ゆきちゃんの小さな頃のアルバムがあるのよ」
本城のアルバム。見たい。
姫野は強く興味を惹かれ、桜のそばに座った。桜からはふんわりと上品な香りが漂った。
「用意してたんですか」
本城が困り顔で隣に座り、姫野は差し出された厚いアルバムを手に取った。
*
いつまで笑っているつもりだろう。
本城は少し呆れつつも、やわらかい気持ちで隣の姫野を見つめていた。
発端は、アルバムに飾られていた、本城が3歳頃の写真だった。
夏真っ盛りで暑かったのだろう。庭にビニールプールを出してもらい、幼少の本城はご機嫌な様子で水浴びをしている。満面の笑みをたたえた金髪の幼児は、なぜか姉のお古のピンクのビキニを着せられていた。
それを見た姫野は本城の隣で盛大に吹き出した。それから他の写真を見る間もずっと、クスクスと笑っていた。
「ほらほら、これは幼稚園の制服ね」
「この子と仲良しだったけど、よくケンカもしたのよね」
「雪ちゃんがこの子を引っかいて、母が謝りに行ったりもしたのよ」
姉たちはアルバムをめくりながら、嬉々として姫野に本城の小さな失敗を暴露していく。
「この電車のおもちゃが大好きだったわよね」
「そう!ベッドに入れて一緒に寝ていたわ」
「壊れてしまった時は泣いたり癇癪を起こしたり大変で、父が修理に持って行ったの」
姫野は姉たちの話に耳を傾けながら、時折小さく笑い声を上げた。
「これは」
夏実が指差した写真には、家族6人全員が写っていた。自宅を背景に撮ったもので、皆が少し改まったような顔で整列していた。
本城はその写真を撮った時のことをよく覚えていた。
「母がフランスに発つ日に撮った写真なの」
懐かしさが滲む夏実の声を聞いた姫野が、つと顔をこちらに向けて言った。
「本城、まだ小さい」
眉尻を下げた姫野の表情だけで、言いたいことが伝わった。
本当に優しい。
「もう結構いろんなことをわかってた頃だけどね」
「でもまだ小さい」
そう言って姫野はまた写真に視線を落とした。
10歳。小学校中学年。手放しで泣くには、少し大きくなりすぎていた。
「未琴くんは優しいのね」
桜が微笑む。
「本当に」
「雪ちゃん、素敵な人に出会ったわね」
桃香と夏実も口々に言う。
本城は「意味がわかんない」と言いたげに唇を尖らせて俯く姫野の肩に軽く触れた。
「雪哉くん。おやつを運びましょうか」
キッチンから出てきた坂田に言われ、そろそろ2人になりたいと思っていた本城は立ち上がった。
「写真の続きはまた今度にしたら」
姫野の手からアルバムを優しく取り上げ、テーブルに置く。
「未琴くん。雪ちゃんと一緒にいてくれてありがとう」
「私たちは、2人の味方ですからね」
「ゆっくりして行ってね」
姉たちの言葉に若干居たたまれないような気持ちがして姫野を見ると、その顔に愛らしい照れ笑いを浮かべ3人に向かって頷いたので、もう少しでキスしてしまうところだった。
「坂田さん、おやつって何?」
「とりあえずケーキを盛り付けたけど、アイスと、プリンもあるよ。モリヤの」
「モリヤのプリン」
姫野が思わずといった感じで呟いてから顔を赤くしたので、みんなで笑った。
プリンも運びますねと言って戻りかけた坂田の背中に「和室にお願い」と声をかけ、本城は姫野の手を取ってリビングを出た。
2階に上がって、いくつもあるドアのうちの1つを開ける。
「入って。ここが俺の部屋」
「……広すぎ」
部屋は洋間で、20畳ほどの広さがある。
「ベッド、あり得ない」
「俺もそう思う」
キングサイズのベッドが右の壁に沿うように、でん、と置かれている。
その他に、本棚と作り付けの大きなクローゼット、4人掛けのテーブルセットがあった。
どの家具も、深い色の木製で、重厚な造りだ。
「なんか、何もない」
「そう。何もないね」
「生活感がない」
「よくわかるね。俺、ここで生活してないんだ」
それを聞いて姫野は首を傾げた。
「本城の部屋なんでしょ」
「そう。母が用意した、俺の部屋。おいで姫野」
本城はその部屋を出て、向かい側の引き戸を開けた。
「こっちが俺の部屋。俺が好きで使ってる部屋」
それは和室で、8畳ほどしかない。マットレスを直接置いた寝具と、小さなローテーブルと、その他細々としたものが雑然と置いてある。
「本城の部屋」
満足したように自分を見上げる姫野の頭を撫でる。サラサラした髪の手触りが心地よい。
「基本的にはこっちを使ってるんだ」
こくんと頷いた姫野を促し、マットレスを背に座る。
姫野はキョロキョロと辺りを見回し落ち着かない。
「ごめんね。おもしろいものは無いよ」
「ゲームとか漫画とか、無い」
「うん。無いね」
「本城、家で何してるの」
「音楽聞いたり。姫野のこと考えたり」
言いながら姫野を横から抱きしめる。
バカじゃないの、と言われてかわいくて堪らなくなり、押し倒そうとしたその時、引き戸がトントンと音をたて、姫野が慌てて離れていった。
「雪哉くん。おやつどうぞ」
坂田の声がして、本城は立ち上がり、戸を開けてケーキとプリンと飲み物を受け取った。
「ありがとう」
「夕飯はどうする?」
「夕飯、ね」
姫野は帰ると言うだろうか。
「ねえ姫野」
振り返ると、姫野はカラーボックスの引き出しをこっそり開けようとしているところだった。
「何してるの、姫野さん」
「……なにも」
ごまかそうとしてツンとする姫野に笑みが溢れる。
「夜ご飯、一緒に食べて帰る?」
「うん」
「じゃあ。坂田さん、お願い」
「うん。姫野くん、カレー好き?」
聞かれてコクコク頷く姫野に微笑みを返し、坂田は下がって行った。
ケーキやプリンが山のように盛られた盆をテーブルに置き、カラーボックスから離れて棚の方を見ている姫野の隣に座る。
「見てもいいよ」
「何を?」
「引き出し」
「いい。別に」
「かわいいなぁ」
「本城はお母さんと仲悪いの?」
単刀直入に聞かれて、本城は首を横に振った。
「悪くないよ。離れて暮らしてるけど、電話が来れば普通に話すし。ただ」
ポケットに入れていた携帯や財布を無造作に棚の上に置く。
「離れてる時間が多すぎて、お互いのことがよくわかんない」
母は本当に家族想いだと思う。ただ、方向性がずれたまま突っ走る傾向にあるだけだ。
そういうところに、自分がついて行けないだけだ。
「あの部屋も、特にベッドなんか、姉から俺の背が伸びたって聞いていきなり送ってきたんだ。俺はこれで足りてるのに」
マットレスをフカフカと押してみせる。
「お母さん、本城が和室使ってるって知らないの?」
「どうだろう。俺は言ってないけど」
「言えばいいのに」
「うーん。いいよ。面倒」
「ゆき」
姫野が手に触れて、遠慮がちに撫でた。
「ちっちゃい頃、寂しかった?」
寂しかったかと言われても本城にはよくわからなかった。姉がいたし、坂田たちもいた。よく面倒を見てもらって、自分は独りではなかった。
「母がいないと思うことはたまにあったけど、寂しいとはあんまり思わなかった。俺が寂しいのは、姫野に会えない時くらいだよ」
手を伸ばしてぷっくりした唇を親指で撫でる。
「だから本城は寂しがりやなんだ」
姫野が言った言葉の意味を、瞬時に理解できなかった。
「寂しがり屋?俺が?」
「そうでしょ、だっていっつもいっつも俺にくっついてばっかりいるし」
「そうか。だからか」
少し違うような気もしたが、本城は敢えて正さなかった。姫野がそう思っていてくれるならそれでいい。
「姫野」
横から抱き締めて、頭の上に顎を乗せる。
「姫野が、俺の部屋にいるね」
「……ん」
「変な感じだけど、すっごく嬉しい」
「……ふぅん」
「姫野は?姫野は俺の部屋に来てどう思った?」
「お姉ちゃんが3人もいてびっくりしたんだけど。聞いてないし」
そういうことを聞いたんじゃないんだけど。
「ごめんね」
本城は笑ってしまう。
「姫野はかわいいね。ほんと、俺の癒しだ」
ぎゅうぎゅうと抱きながらその髪に頬を擦り付けた。
「いい匂い」
「変態」
「ねえ、姫野」
押し倒す。畳に押し付けるように素早く。
「しよう」
「だめ、本城」
「お願い。我慢できない」
「だめ、ケーキ、ケーキ!」
姫野がいつもより激しく暴れるので、本城は驚いて退いてしまった。
おもむろに起き上がった姫野は本城を見て、ばつが悪そうな顔で言った。
「……ケーキとか、食べたらね」
ありがとうと言ってから、姫野の柔らかい唇に3回キスをした。
「姫野、早くケーキ食べて」
「無茶言わないで」
「早く早く」
「落ち着けば。本城は食べないの?」
「ケーキより姫野の方がおいしそうだし」
「バッカじゃないの」
心底軽蔑するという表情で睨まれて、本城は微笑んだ。
姫野はこちらに構わずチョコレートモンブランを食べ始めた。
「おいしい?」
「本城も食べて」
「じゃあプリンだけ食べる」
プリンを食べながら姫野の小動物のような咀嚼を眺めて、本城は畳に寝転がった。
姫野は次々にケーキを平らげていく。小さい体のどこに、こんなにたくさん入るんだろう。
そんな姫野の表情が一瞬ぴくりと動いた。そのまま少しの間固まっている。
「どうしたの?」
頭を起こして聞くと、ケーキをフォークに一口分乗せて本城の口元に差し出してきた。
「食べていいの?」
神妙にうなずく姫野に従い口を開ける。
「おいしいの。これ」
姫野のその言い方は、あまりに素直な感動で包まれていて、本城の胸はキュンと縮まってしまった。
「もう、無理なんだけど」
素早くフォークを取り上げてテーブルに置き、甘い匂いのする体を掻き抱く。
「ケーキ…」
「ケーキはまた後にしなよ。俺にも構ってよ」
「ん……」
「抱いていい?」
敢えてはっきり口にすると、姫野は視線をさまよわせた。
「ねえ姫野。抱いていい?」
「知らない」
「知らないじゃないでしょ、姫野の気持ちはどうなの、俺に抱かれたい?」
少し赤くなりつつも口をへの字に結ぶ姫野のことが、本城はかわいくてたまらない。
「それとも抱かれたくない?ケーキ食べる?」
「なんでっ、そんなこと聞くの」
「聞いちゃだめなの?」
「だめに決まってるでしょ」
「どうして?」
むすりとしたまま、姫野は答えない。
「悲しい」
本城はわざと、ゆっくり姫野を抱いた腕を離した。
「姫野は俺のこと、好きじゃないんだ」
「何言ってんの、バカじゃないの」
いつもより少し焦ったような声で言い、姫野は離れた分だけ間をつめてきた。
これは。かわいい。犯したい。
「そうだね、バカなのかも」
「なに?」
「姫野は俺のこと好きなんて全然言ってくれないし。俺だって自信なくなるよ」
心にもないことを言いながら布団に横になり、顔を覆う。
「…ゆき……?」
弱々しく呼びながらそっと、姫野が本城の頭に触れた。
「…ゆき…ちゃん……」
何て言った?ゆきちゃん?姫野が俺のことを?
このままでは自分の心臓がもたないと危機感を抱く。
尚もじっとして、時折鼻をすすってみせたりしていると、姫野は顔を覆った手に触れた。
「起きて、ねえ……」
「…起きられない…元気出ないもん……」
「ゆき。ねえ」
ゆるゆると体を揺すられて、それでも本城は頑張った。
すると。
「うぅ、もう!」
唸った姫野に、鳩尾のあたりを平手で殴られた。
「いて」
「いい加減にしてよ!ワガママばっかり言わないで!」
「ワガママ…」
「ゆきのことどう思ってるかなんて知ってるくせに!」
姫様がお怒りだ。
「だって、姫野が俺に冷たいからわからなくなったって言ってるんだよ」
「嘘ばっかり!」
「姫野、ちょっと落ち着いてよ」
「好きに決まってるでしょ!バカみたい!」
「……そう?」
顔を上げるとキッと睨まれて、本城は首をすくませた。
「もう二度と言わないから。ケーキ食べる」
姫野はつと本城から離れ、またテーブルに戻ってしまった。
思ってた流れと違う。第一、抱かれたいかどうかを聞けてない。
「ねえ姫野、怒ったの?」
姫野はモンブランを食べている。
「ごめん、許して。好きだよ姫野。ちょっと甘えたくなっちゃって。ね、こっち来て、姫野」
姫野は動かない。
「ケーキ、余ったの全部持って帰れるように、坂田さんに箱に入れてもらうから」
姫野が一瞬本城を見た。
くそ。ケーキめ。
本城はちろりと嫉妬をする。
「俺が悪かったから。来て。ね?」
両腕を広げると、姫野がゆっくり近づいて、本城の胸に収まった。
「ああ、待った。ほんと。いただきます」
本城が呟いた言葉の意味を考えているらしい姫野を、ぎゅっと抱き締める。
いつか、「ゆき、お願い、抱いて」って言ってくれないかなぁ。
「ニヤニヤして。気持ち悪い」
「ごめん。……抱いていい?」
腕の中の姫野に聞くと、唇を尖らせてこくりと頷いた。
本城は、想像していたよりもずっと、かわいい姫野が自分の部屋にいることを嬉しく思っていた。
それを感じれば感じるほどに、本城の胸は押し潰されそうになる。
苦しくて切なくて、姫野を抱く腕に力が入った。
「いっ、いたい…」
「っ、ごめん」
姫野の肩が畳に擦れている。後ろから姫野を犯しながら、その細い肩や首にキスをする。腕はすべすべした腰を支えて、時折姫野のものをまさぐった。
「んんっ…やぁ……」
「姫野」
優しくしたい。
それなのに、自分の中に渦巻くどす黒い欲求は静まることを知らず、赤くなった姫野の肩にもっと畳が食い込めばいいと思わずにいられない。
俺の部屋のあらゆるものが、消えない跡を姫野に刻めばいいのに。
「姫野」
「あっ、やぁんっ、おっき、ぃ」
「姫野、好きだよ……大好きだ」
夕方になり、西を向いた窓からは濃い夕陽の色が射し込んでいる。
姫野の白い肌もオレンジ色に染まっていた。
黒い髪の下、感じる度に伸ばされる首の筋を、本城は腰を前後に振りながら食い入るように見つめた。
姫野の、首。
後ろから両手で力いっぱい絞めれば、きっと姫野は抵抗できないだろう。
そんなことは絶対にしないけれど、
でも、もし姫野が。
「ねえ姫野」
「ん、ふ、ぅ」
「俺が、姫野を帰したくないってワガママ言って、泣き出したらどうする?」
姫野は、頬を畳につけて顔を横にし、はあはあと息をしながら、視線だけで後ろを向こうとした。
「ゆきが…?泣く……?っん」
「泣いたとしたら」
「あぁっ、う」
本城は遠慮なく奥を突く。
「よしよしって、してあげる」
姫野は目を閉じて感じ、喘ぎながら、そう言った。
そうか。姫野は、俺が甘えたら、甘えさせてくれるんだ。
帰したくなくて苦しくて引き裂かれそうな気持ちを持て余すのは目に見えていて、それが姫野を自宅に呼ばなかった理由のひとつだけれど。
姫野が帰った後の部屋に1人残ることに耐えられるか不安だったけれど。
どうしても辛くなったら、そう姫野に言えばいいんだ。それで、よしよしって、してもらう。
本城の心はたちまち温かいもので充ちていく。
一度抜いて姫野を仰向けにし、脚を開いてまた貫く。
「あぁっん!」
「姫野……好きだ」
言葉にできないよ。本当に。
姫野が体を揺すられながらぼんやりと本城を見上げている。
「ねえ姫野」
ずっと一緒にいてよと、その一言はなぜか本城の喉に引っ掛かって出てこない。
「大好きだよ」
こんなに好きなこと、何度言えば伝わるんだろう。
「ゆき、髪、きれい」
何のことかと首を傾げる本城の頭に、姫野が手を伸ばす。
「金髪、オレンジに、光って、キラキラしてる」
喘ぎすぎて涙目になっている姫野に、何度も何度も触れるだけのキスをする。
どうして、俺たちには、別の家があるんだろう。
「カレー、ちょっと辛くなったかも。姫野くん、大丈夫かな」
坂田が気をきかせて夕飯を運んでくれた頃には、部屋の空気の入れ換えも済み、姫野は満足いくまでケーキを食べ終えていた。
カレーの匂いが立ち込める和室には、また2人だけになった。
「本城はいっつもここでご飯食べるの?」
「いつもは姉たちとみんなで下のダイニングで食べたり、自分だけの時は、坂田さんがいるキッチンで食べたりするよ」
ふん、と頷く姫野の表情は穏やかだ。
「カレー、おいしい」
「そう?後で坂田さんに言っておくね。喜ぶよ」
「本城んち、おっきいから、もっと変なご飯かと思った」
「変なご飯?」
「なんとかのなんとか包みみたいのとか」
本城は思わず吹き出した。
姫野はムッとしたのか黙っている。
「坂田さんの作るご飯はいつも、普通のご飯だよ。俺たちは結構、普通に育ててもらった」
特別扱いはされず育った。外に出てからも特別扱いされないように。
無力な自分が好きな人を守るのに必要なことは何だろう。姉や坂田を味方につけた今。まずは、本城家の父の説得だ。
「姫野は、大学受かったら、実家から通うつもり?」
「うん」
「どうして?」
「だって、ご飯作るとか無理だし」
料理は本城も自信のない分野だ。
「姫野のお父さんは、一人暮らししたいって言ったらさせてくれそう?」
「多分。心配はすると思うけど。お父さん、心配性だから」
心配性。
果たしてそれがどの程度のものなのかわからないけれど、後々のために留意すべきだろうと本城は思う。
「本城、一人暮らしするの?」
「二人暮らしがしたいんだけど」
「誰と?」
本城は黙った。
勘の悪い恋人に何からどう話そうと思案していると、姫野が「中川?」と言ったのでカレーを吹き出しそうになった。
「なんで中川」
「……仲いいから」
姫野には自分と中川がどう見えているのだろう。特に仲良くしている自覚はなかった。
そこで姫野はぴくりと顔を引きつらせた。
「……阿部?」
「ちょっと姫野、あんまりおもしろいこと言わないでよ」
阿部と同棲。噴飯ものだ。
「土屋なわけないし……」
「土屋はないね」
その点では2人の意見が合致した。
「野島には先生がいるし」
「先生?」
「あっ、な、なんでもない!」
急に焦りだした姫野を尻目に、同棲を申し込むのはまた今度にしようと本城は溜め息をついた。
姫野がそろそろ帰ると言い出して、2人で食器を下げ、坂田にごちそうさまを言い、姉たちにさようならを言って、そろって本城の家を出た。
本城の左手は、姫野の右手をしっかり握っている。右手には、お土産のケーキを提げて。
夜になり、気温が少し下がって、たまに吹く風が心地好かった。
「姫野、明日は何してる?」
「何も」
「会いに行っていい?」
「来れば」
「うん」
明日、また会える。明日まで、離ればなれ。
「姫野」
本城は思わず恋人の名前を呼んだ。
「うん」
本城には姫野の返事が、肯定に聞こえた。
姫野が自分と同じ気持ちでいてくれたら、どんなに幸せだろう。
こんなに離れたくない、こんなに。
それを姫野に言うのは簡単で、でも、とてもじゃないけれど全てを伝えきる自信がない。
「俺ね、たまに、姫野を監禁したくなっちゃうんだけど」
「は?」
「ずっと触ってたいし、誰にも取られたくないって思って」
「取られないし」
「姫野は、俺が誰かに取られないようにしまっちゃいたいって思うこと、ある?」
「ない、そんなの」
そっか、と言って本城は空を仰ぐ。
「しまわなくたって大丈夫だし」
「大丈夫かなあ」
「それに、離れてないと、電話とかできないから」
「電話?」
「電話……」
振り返ると、姫野が恥ずかしそうに目を逸らした。
「本城と、電話するの、結構、好きだし」
「ほんと?姫野、俺と電話するの、好きなんだ」
「電話したあとは、ドキドキする」
そうだね、俺もドキドキする。
「それで、明日も会えるって、思うし」
そうだ。そうだね。
「姫野はそれ、幸せ?」
「まあね」
「そっか。嬉しい。なんか。幸せ。俺も」
きゅっと手を握る。
「意味わかんない」
「そうかな」
姫野は、ふん、と言って下を向いた。
姫野はいつもそうだね。俺が不安になるとちゃんと答えをくれる。
「姫野が冷たいとか言って、ごめんね。姫野は優しいよね、半分くらいは」
「なにそれ」
「好きだよ、そういうとこも」
本城は、姫野の家に着くまで手を離さなかった。
家に戻ってすぐ、本城はリビングの電話を手にした。短縮ダイヤルで表示された携帯番号への発信。3回のコール音の後、相手が出る。
「お父さん」
『ああ、雪哉。久しぶりだな』
「はい」
『めずらしいな、お前が電話をくれるなんて』
「今、お昼休み?」
『ああ。そっちは夜だな』
「はい。お父さん、話があるんですけど」
『どうした』
口の中がカラカラで、本城はひとつ、息を飲んだ。
「僕、今、男の子と付き合っていて、大学はお母さんに言われてた宮大じゃなくてその子と同じ大学に行きます。それから、家を出てその子と同棲したいと思ってます。それから」
『待て、雪哉。情報を処理しきれないんだけど』
「僕、家を継ぎたくない」
父は黙った。
本城も黙っていた。
やがて、うん、と言った父の声にはため息が混じっていた。
『とにかくお前に意志があるってことはわかった。近々帰るからゆっくり話を聞かせてくれるかな』
「はい」
『ちなみに』
「桜ちゃんたちには、その子に会ってもらいました。応援するって、言ってくれました」
父は笑った。
『根回しが早いな』
坂田にも同じようなことを言われたと、本城は思い出す。
『お母さんには?』
「まだ」
『だろうな。……帰る日が決まったら連絡するよ』
「はい」
『雪哉、大人になったな』
父の声は優しい。それに比べて自分の声は固い。
大人になった?
違う。自分はまだ子どもなのだ。嫌になるくらいに。
大人になったなら、自分の大事なものくらい、一人で守れるようになるはずだ。
大事なものを守るのに、誰の許可もいらないはずだ。
電話を切った後、少し疲れて自室に戻り、今度は自分の携帯から電話をかける。
『……もしもし』
「姫野?」
-end-
2013.10.6
姫野はしかめ面で手を引かれていた。
5月とは思えない日差しの強さが、汗をかきづらい体質の姫野から体力を奪いつつあった。
「遠い」
「ごめんね。もうすぐだよ」
本城が振り返り、笑った。
2人は本城の家の敷地内を歩いていた。
広いと言っても門を入ってから玄関までは少し距離がある程度だ。それでも炎天下を自宅から歩いてきた姫野にとってはその距離でさえひどく遠い。
本城はそんな事情も全てわかっているように謝る。
「何しようね、うちで。アイスとかケーキとか、適当に頼んでおいたから、まずはおやつにしようか」
「おやつ」
姫野の機嫌が少し上向き、本城はそれを感じたのか嬉しそうな顔をした。
「本城の家、大きすぎ」
「そうかな。住んでるとよくわからない」
王子様みたい。金髪を見上げ、姫野は思った。
広いリビングに入り、姫野は息を飲んだ。
本城とどこか似ている女性が3人と、小柄な女性が1人、姫野を見てパッと表情を明るくした。
「あら」
「姫野くんね?」
「まあ」
「いらっしゃい」
口々に言われ、姫野はやっと「姫野です。お邪魔します」と言った。
「姫野。こっちの3人が姉、あと彼女が家のことをいろいろしてくれる坂田さんだよ」
本城が言うと、女性たちが代わる代わる笑顔で名乗った。
聞いてない。お姉ちゃんが3人もいるなんて。しかもお手伝いさんまで。
姫野は若干の気後れを感じた。
「部屋に行こっか」
家族の前でも臆することなく自分の手を握った本城に姫野が驚いていると、女性たちが口を開いた。
「ゆきちゃん。私たちもう少し姫野くんとお話がしたいわ」
「そうよ、独り占めなんてずるいわ」
「ねえ未琴くん。ゆきちゃんの小さな頃のアルバムがあるのよ」
本城のアルバム。見たい。
姫野は強く興味を惹かれ、桜のそばに座った。桜からはふんわりと上品な香りが漂った。
「用意してたんですか」
本城が困り顔で隣に座り、姫野は差し出された厚いアルバムを手に取った。
*
いつまで笑っているつもりだろう。
本城は少し呆れつつも、やわらかい気持ちで隣の姫野を見つめていた。
発端は、アルバムに飾られていた、本城が3歳頃の写真だった。
夏真っ盛りで暑かったのだろう。庭にビニールプールを出してもらい、幼少の本城はご機嫌な様子で水浴びをしている。満面の笑みをたたえた金髪の幼児は、なぜか姉のお古のピンクのビキニを着せられていた。
それを見た姫野は本城の隣で盛大に吹き出した。それから他の写真を見る間もずっと、クスクスと笑っていた。
「ほらほら、これは幼稚園の制服ね」
「この子と仲良しだったけど、よくケンカもしたのよね」
「雪ちゃんがこの子を引っかいて、母が謝りに行ったりもしたのよ」
姉たちはアルバムをめくりながら、嬉々として姫野に本城の小さな失敗を暴露していく。
「この電車のおもちゃが大好きだったわよね」
「そう!ベッドに入れて一緒に寝ていたわ」
「壊れてしまった時は泣いたり癇癪を起こしたり大変で、父が修理に持って行ったの」
姫野は姉たちの話に耳を傾けながら、時折小さく笑い声を上げた。
「これは」
夏実が指差した写真には、家族6人全員が写っていた。自宅を背景に撮ったもので、皆が少し改まったような顔で整列していた。
本城はその写真を撮った時のことをよく覚えていた。
「母がフランスに発つ日に撮った写真なの」
懐かしさが滲む夏実の声を聞いた姫野が、つと顔をこちらに向けて言った。
「本城、まだ小さい」
眉尻を下げた姫野の表情だけで、言いたいことが伝わった。
本当に優しい。
「もう結構いろんなことをわかってた頃だけどね」
「でもまだ小さい」
そう言って姫野はまた写真に視線を落とした。
10歳。小学校中学年。手放しで泣くには、少し大きくなりすぎていた。
「未琴くんは優しいのね」
桜が微笑む。
「本当に」
「雪ちゃん、素敵な人に出会ったわね」
桃香と夏実も口々に言う。
本城は「意味がわかんない」と言いたげに唇を尖らせて俯く姫野の肩に軽く触れた。
「雪哉くん。おやつを運びましょうか」
キッチンから出てきた坂田に言われ、そろそろ2人になりたいと思っていた本城は立ち上がった。
「写真の続きはまた今度にしたら」
姫野の手からアルバムを優しく取り上げ、テーブルに置く。
「未琴くん。雪ちゃんと一緒にいてくれてありがとう」
「私たちは、2人の味方ですからね」
「ゆっくりして行ってね」
姉たちの言葉に若干居たたまれないような気持ちがして姫野を見ると、その顔に愛らしい照れ笑いを浮かべ3人に向かって頷いたので、もう少しでキスしてしまうところだった。
「坂田さん、おやつって何?」
「とりあえずケーキを盛り付けたけど、アイスと、プリンもあるよ。モリヤの」
「モリヤのプリン」
姫野が思わずといった感じで呟いてから顔を赤くしたので、みんなで笑った。
プリンも運びますねと言って戻りかけた坂田の背中に「和室にお願い」と声をかけ、本城は姫野の手を取ってリビングを出た。
2階に上がって、いくつもあるドアのうちの1つを開ける。
「入って。ここが俺の部屋」
「……広すぎ」
部屋は洋間で、20畳ほどの広さがある。
「ベッド、あり得ない」
「俺もそう思う」
キングサイズのベッドが右の壁に沿うように、でん、と置かれている。
その他に、本棚と作り付けの大きなクローゼット、4人掛けのテーブルセットがあった。
どの家具も、深い色の木製で、重厚な造りだ。
「なんか、何もない」
「そう。何もないね」
「生活感がない」
「よくわかるね。俺、ここで生活してないんだ」
それを聞いて姫野は首を傾げた。
「本城の部屋なんでしょ」
「そう。母が用意した、俺の部屋。おいで姫野」
本城はその部屋を出て、向かい側の引き戸を開けた。
「こっちが俺の部屋。俺が好きで使ってる部屋」
それは和室で、8畳ほどしかない。マットレスを直接置いた寝具と、小さなローテーブルと、その他細々としたものが雑然と置いてある。
「本城の部屋」
満足したように自分を見上げる姫野の頭を撫でる。サラサラした髪の手触りが心地よい。
「基本的にはこっちを使ってるんだ」
こくんと頷いた姫野を促し、マットレスを背に座る。
姫野はキョロキョロと辺りを見回し落ち着かない。
「ごめんね。おもしろいものは無いよ」
「ゲームとか漫画とか、無い」
「うん。無いね」
「本城、家で何してるの」
「音楽聞いたり。姫野のこと考えたり」
言いながら姫野を横から抱きしめる。
バカじゃないの、と言われてかわいくて堪らなくなり、押し倒そうとしたその時、引き戸がトントンと音をたて、姫野が慌てて離れていった。
「雪哉くん。おやつどうぞ」
坂田の声がして、本城は立ち上がり、戸を開けてケーキとプリンと飲み物を受け取った。
「ありがとう」
「夕飯はどうする?」
「夕飯、ね」
姫野は帰ると言うだろうか。
「ねえ姫野」
振り返ると、姫野はカラーボックスの引き出しをこっそり開けようとしているところだった。
「何してるの、姫野さん」
「……なにも」
ごまかそうとしてツンとする姫野に笑みが溢れる。
「夜ご飯、一緒に食べて帰る?」
「うん」
「じゃあ。坂田さん、お願い」
「うん。姫野くん、カレー好き?」
聞かれてコクコク頷く姫野に微笑みを返し、坂田は下がって行った。
ケーキやプリンが山のように盛られた盆をテーブルに置き、カラーボックスから離れて棚の方を見ている姫野の隣に座る。
「見てもいいよ」
「何を?」
「引き出し」
「いい。別に」
「かわいいなぁ」
「本城はお母さんと仲悪いの?」
単刀直入に聞かれて、本城は首を横に振った。
「悪くないよ。離れて暮らしてるけど、電話が来れば普通に話すし。ただ」
ポケットに入れていた携帯や財布を無造作に棚の上に置く。
「離れてる時間が多すぎて、お互いのことがよくわかんない」
母は本当に家族想いだと思う。ただ、方向性がずれたまま突っ走る傾向にあるだけだ。
そういうところに、自分がついて行けないだけだ。
「あの部屋も、特にベッドなんか、姉から俺の背が伸びたって聞いていきなり送ってきたんだ。俺はこれで足りてるのに」
マットレスをフカフカと押してみせる。
「お母さん、本城が和室使ってるって知らないの?」
「どうだろう。俺は言ってないけど」
「言えばいいのに」
「うーん。いいよ。面倒」
「ゆき」
姫野が手に触れて、遠慮がちに撫でた。
「ちっちゃい頃、寂しかった?」
寂しかったかと言われても本城にはよくわからなかった。姉がいたし、坂田たちもいた。よく面倒を見てもらって、自分は独りではなかった。
「母がいないと思うことはたまにあったけど、寂しいとはあんまり思わなかった。俺が寂しいのは、姫野に会えない時くらいだよ」
手を伸ばしてぷっくりした唇を親指で撫でる。
「だから本城は寂しがりやなんだ」
姫野が言った言葉の意味を、瞬時に理解できなかった。
「寂しがり屋?俺が?」
「そうでしょ、だっていっつもいっつも俺にくっついてばっかりいるし」
「そうか。だからか」
少し違うような気もしたが、本城は敢えて正さなかった。姫野がそう思っていてくれるならそれでいい。
「姫野」
横から抱き締めて、頭の上に顎を乗せる。
「姫野が、俺の部屋にいるね」
「……ん」
「変な感じだけど、すっごく嬉しい」
「……ふぅん」
「姫野は?姫野は俺の部屋に来てどう思った?」
「お姉ちゃんが3人もいてびっくりしたんだけど。聞いてないし」
そういうことを聞いたんじゃないんだけど。
「ごめんね」
本城は笑ってしまう。
「姫野はかわいいね。ほんと、俺の癒しだ」
ぎゅうぎゅうと抱きながらその髪に頬を擦り付けた。
「いい匂い」
「変態」
「ねえ、姫野」
押し倒す。畳に押し付けるように素早く。
「しよう」
「だめ、本城」
「お願い。我慢できない」
「だめ、ケーキ、ケーキ!」
姫野がいつもより激しく暴れるので、本城は驚いて退いてしまった。
おもむろに起き上がった姫野は本城を見て、ばつが悪そうな顔で言った。
「……ケーキとか、食べたらね」
ありがとうと言ってから、姫野の柔らかい唇に3回キスをした。
「姫野、早くケーキ食べて」
「無茶言わないで」
「早く早く」
「落ち着けば。本城は食べないの?」
「ケーキより姫野の方がおいしそうだし」
「バッカじゃないの」
心底軽蔑するという表情で睨まれて、本城は微笑んだ。
姫野はこちらに構わずチョコレートモンブランを食べ始めた。
「おいしい?」
「本城も食べて」
「じゃあプリンだけ食べる」
プリンを食べながら姫野の小動物のような咀嚼を眺めて、本城は畳に寝転がった。
姫野は次々にケーキを平らげていく。小さい体のどこに、こんなにたくさん入るんだろう。
そんな姫野の表情が一瞬ぴくりと動いた。そのまま少しの間固まっている。
「どうしたの?」
頭を起こして聞くと、ケーキをフォークに一口分乗せて本城の口元に差し出してきた。
「食べていいの?」
神妙にうなずく姫野に従い口を開ける。
「おいしいの。これ」
姫野のその言い方は、あまりに素直な感動で包まれていて、本城の胸はキュンと縮まってしまった。
「もう、無理なんだけど」
素早くフォークを取り上げてテーブルに置き、甘い匂いのする体を掻き抱く。
「ケーキ…」
「ケーキはまた後にしなよ。俺にも構ってよ」
「ん……」
「抱いていい?」
敢えてはっきり口にすると、姫野は視線をさまよわせた。
「ねえ姫野。抱いていい?」
「知らない」
「知らないじゃないでしょ、姫野の気持ちはどうなの、俺に抱かれたい?」
少し赤くなりつつも口をへの字に結ぶ姫野のことが、本城はかわいくてたまらない。
「それとも抱かれたくない?ケーキ食べる?」
「なんでっ、そんなこと聞くの」
「聞いちゃだめなの?」
「だめに決まってるでしょ」
「どうして?」
むすりとしたまま、姫野は答えない。
「悲しい」
本城はわざと、ゆっくり姫野を抱いた腕を離した。
「姫野は俺のこと、好きじゃないんだ」
「何言ってんの、バカじゃないの」
いつもより少し焦ったような声で言い、姫野は離れた分だけ間をつめてきた。
これは。かわいい。犯したい。
「そうだね、バカなのかも」
「なに?」
「姫野は俺のこと好きなんて全然言ってくれないし。俺だって自信なくなるよ」
心にもないことを言いながら布団に横になり、顔を覆う。
「…ゆき……?」
弱々しく呼びながらそっと、姫野が本城の頭に触れた。
「…ゆき…ちゃん……」
何て言った?ゆきちゃん?姫野が俺のことを?
このままでは自分の心臓がもたないと危機感を抱く。
尚もじっとして、時折鼻をすすってみせたりしていると、姫野は顔を覆った手に触れた。
「起きて、ねえ……」
「…起きられない…元気出ないもん……」
「ゆき。ねえ」
ゆるゆると体を揺すられて、それでも本城は頑張った。
すると。
「うぅ、もう!」
唸った姫野に、鳩尾のあたりを平手で殴られた。
「いて」
「いい加減にしてよ!ワガママばっかり言わないで!」
「ワガママ…」
「ゆきのことどう思ってるかなんて知ってるくせに!」
姫様がお怒りだ。
「だって、姫野が俺に冷たいからわからなくなったって言ってるんだよ」
「嘘ばっかり!」
「姫野、ちょっと落ち着いてよ」
「好きに決まってるでしょ!バカみたい!」
「……そう?」
顔を上げるとキッと睨まれて、本城は首をすくませた。
「もう二度と言わないから。ケーキ食べる」
姫野はつと本城から離れ、またテーブルに戻ってしまった。
思ってた流れと違う。第一、抱かれたいかどうかを聞けてない。
「ねえ姫野、怒ったの?」
姫野はモンブランを食べている。
「ごめん、許して。好きだよ姫野。ちょっと甘えたくなっちゃって。ね、こっち来て、姫野」
姫野は動かない。
「ケーキ、余ったの全部持って帰れるように、坂田さんに箱に入れてもらうから」
姫野が一瞬本城を見た。
くそ。ケーキめ。
本城はちろりと嫉妬をする。
「俺が悪かったから。来て。ね?」
両腕を広げると、姫野がゆっくり近づいて、本城の胸に収まった。
「ああ、待った。ほんと。いただきます」
本城が呟いた言葉の意味を考えているらしい姫野を、ぎゅっと抱き締める。
いつか、「ゆき、お願い、抱いて」って言ってくれないかなぁ。
「ニヤニヤして。気持ち悪い」
「ごめん。……抱いていい?」
腕の中の姫野に聞くと、唇を尖らせてこくりと頷いた。
本城は、想像していたよりもずっと、かわいい姫野が自分の部屋にいることを嬉しく思っていた。
それを感じれば感じるほどに、本城の胸は押し潰されそうになる。
苦しくて切なくて、姫野を抱く腕に力が入った。
「いっ、いたい…」
「っ、ごめん」
姫野の肩が畳に擦れている。後ろから姫野を犯しながら、その細い肩や首にキスをする。腕はすべすべした腰を支えて、時折姫野のものをまさぐった。
「んんっ…やぁ……」
「姫野」
優しくしたい。
それなのに、自分の中に渦巻くどす黒い欲求は静まることを知らず、赤くなった姫野の肩にもっと畳が食い込めばいいと思わずにいられない。
俺の部屋のあらゆるものが、消えない跡を姫野に刻めばいいのに。
「姫野」
「あっ、やぁんっ、おっき、ぃ」
「姫野、好きだよ……大好きだ」
夕方になり、西を向いた窓からは濃い夕陽の色が射し込んでいる。
姫野の白い肌もオレンジ色に染まっていた。
黒い髪の下、感じる度に伸ばされる首の筋を、本城は腰を前後に振りながら食い入るように見つめた。
姫野の、首。
後ろから両手で力いっぱい絞めれば、きっと姫野は抵抗できないだろう。
そんなことは絶対にしないけれど、
でも、もし姫野が。
「ねえ姫野」
「ん、ふ、ぅ」
「俺が、姫野を帰したくないってワガママ言って、泣き出したらどうする?」
姫野は、頬を畳につけて顔を横にし、はあはあと息をしながら、視線だけで後ろを向こうとした。
「ゆきが…?泣く……?っん」
「泣いたとしたら」
「あぁっ、う」
本城は遠慮なく奥を突く。
「よしよしって、してあげる」
姫野は目を閉じて感じ、喘ぎながら、そう言った。
そうか。姫野は、俺が甘えたら、甘えさせてくれるんだ。
帰したくなくて苦しくて引き裂かれそうな気持ちを持て余すのは目に見えていて、それが姫野を自宅に呼ばなかった理由のひとつだけれど。
姫野が帰った後の部屋に1人残ることに耐えられるか不安だったけれど。
どうしても辛くなったら、そう姫野に言えばいいんだ。それで、よしよしって、してもらう。
本城の心はたちまち温かいもので充ちていく。
一度抜いて姫野を仰向けにし、脚を開いてまた貫く。
「あぁっん!」
「姫野……好きだ」
言葉にできないよ。本当に。
姫野が体を揺すられながらぼんやりと本城を見上げている。
「ねえ姫野」
ずっと一緒にいてよと、その一言はなぜか本城の喉に引っ掛かって出てこない。
「大好きだよ」
こんなに好きなこと、何度言えば伝わるんだろう。
「ゆき、髪、きれい」
何のことかと首を傾げる本城の頭に、姫野が手を伸ばす。
「金髪、オレンジに、光って、キラキラしてる」
喘ぎすぎて涙目になっている姫野に、何度も何度も触れるだけのキスをする。
どうして、俺たちには、別の家があるんだろう。
「カレー、ちょっと辛くなったかも。姫野くん、大丈夫かな」
坂田が気をきかせて夕飯を運んでくれた頃には、部屋の空気の入れ換えも済み、姫野は満足いくまでケーキを食べ終えていた。
カレーの匂いが立ち込める和室には、また2人だけになった。
「本城はいっつもここでご飯食べるの?」
「いつもは姉たちとみんなで下のダイニングで食べたり、自分だけの時は、坂田さんがいるキッチンで食べたりするよ」
ふん、と頷く姫野の表情は穏やかだ。
「カレー、おいしい」
「そう?後で坂田さんに言っておくね。喜ぶよ」
「本城んち、おっきいから、もっと変なご飯かと思った」
「変なご飯?」
「なんとかのなんとか包みみたいのとか」
本城は思わず吹き出した。
姫野はムッとしたのか黙っている。
「坂田さんの作るご飯はいつも、普通のご飯だよ。俺たちは結構、普通に育ててもらった」
特別扱いはされず育った。外に出てからも特別扱いされないように。
無力な自分が好きな人を守るのに必要なことは何だろう。姉や坂田を味方につけた今。まずは、本城家の父の説得だ。
「姫野は、大学受かったら、実家から通うつもり?」
「うん」
「どうして?」
「だって、ご飯作るとか無理だし」
料理は本城も自信のない分野だ。
「姫野のお父さんは、一人暮らししたいって言ったらさせてくれそう?」
「多分。心配はすると思うけど。お父さん、心配性だから」
心配性。
果たしてそれがどの程度のものなのかわからないけれど、後々のために留意すべきだろうと本城は思う。
「本城、一人暮らしするの?」
「二人暮らしがしたいんだけど」
「誰と?」
本城は黙った。
勘の悪い恋人に何からどう話そうと思案していると、姫野が「中川?」と言ったのでカレーを吹き出しそうになった。
「なんで中川」
「……仲いいから」
姫野には自分と中川がどう見えているのだろう。特に仲良くしている自覚はなかった。
そこで姫野はぴくりと顔を引きつらせた。
「……阿部?」
「ちょっと姫野、あんまりおもしろいこと言わないでよ」
阿部と同棲。噴飯ものだ。
「土屋なわけないし……」
「土屋はないね」
その点では2人の意見が合致した。
「野島には先生がいるし」
「先生?」
「あっ、な、なんでもない!」
急に焦りだした姫野を尻目に、同棲を申し込むのはまた今度にしようと本城は溜め息をついた。
姫野がそろそろ帰ると言い出して、2人で食器を下げ、坂田にごちそうさまを言い、姉たちにさようならを言って、そろって本城の家を出た。
本城の左手は、姫野の右手をしっかり握っている。右手には、お土産のケーキを提げて。
夜になり、気温が少し下がって、たまに吹く風が心地好かった。
「姫野、明日は何してる?」
「何も」
「会いに行っていい?」
「来れば」
「うん」
明日、また会える。明日まで、離ればなれ。
「姫野」
本城は思わず恋人の名前を呼んだ。
「うん」
本城には姫野の返事が、肯定に聞こえた。
姫野が自分と同じ気持ちでいてくれたら、どんなに幸せだろう。
こんなに離れたくない、こんなに。
それを姫野に言うのは簡単で、でも、とてもじゃないけれど全てを伝えきる自信がない。
「俺ね、たまに、姫野を監禁したくなっちゃうんだけど」
「は?」
「ずっと触ってたいし、誰にも取られたくないって思って」
「取られないし」
「姫野は、俺が誰かに取られないようにしまっちゃいたいって思うこと、ある?」
「ない、そんなの」
そっか、と言って本城は空を仰ぐ。
「しまわなくたって大丈夫だし」
「大丈夫かなあ」
「それに、離れてないと、電話とかできないから」
「電話?」
「電話……」
振り返ると、姫野が恥ずかしそうに目を逸らした。
「本城と、電話するの、結構、好きだし」
「ほんと?姫野、俺と電話するの、好きなんだ」
「電話したあとは、ドキドキする」
そうだね、俺もドキドキする。
「それで、明日も会えるって、思うし」
そうだ。そうだね。
「姫野はそれ、幸せ?」
「まあね」
「そっか。嬉しい。なんか。幸せ。俺も」
きゅっと手を握る。
「意味わかんない」
「そうかな」
姫野は、ふん、と言って下を向いた。
姫野はいつもそうだね。俺が不安になるとちゃんと答えをくれる。
「姫野が冷たいとか言って、ごめんね。姫野は優しいよね、半分くらいは」
「なにそれ」
「好きだよ、そういうとこも」
本城は、姫野の家に着くまで手を離さなかった。
家に戻ってすぐ、本城はリビングの電話を手にした。短縮ダイヤルで表示された携帯番号への発信。3回のコール音の後、相手が出る。
「お父さん」
『ああ、雪哉。久しぶりだな』
「はい」
『めずらしいな、お前が電話をくれるなんて』
「今、お昼休み?」
『ああ。そっちは夜だな』
「はい。お父さん、話があるんですけど」
『どうした』
口の中がカラカラで、本城はひとつ、息を飲んだ。
「僕、今、男の子と付き合っていて、大学はお母さんに言われてた宮大じゃなくてその子と同じ大学に行きます。それから、家を出てその子と同棲したいと思ってます。それから」
『待て、雪哉。情報を処理しきれないんだけど』
「僕、家を継ぎたくない」
父は黙った。
本城も黙っていた。
やがて、うん、と言った父の声にはため息が混じっていた。
『とにかくお前に意志があるってことはわかった。近々帰るからゆっくり話を聞かせてくれるかな』
「はい」
『ちなみに』
「桜ちゃんたちには、その子に会ってもらいました。応援するって、言ってくれました」
父は笑った。
『根回しが早いな』
坂田にも同じようなことを言われたと、本城は思い出す。
『お母さんには?』
「まだ」
『だろうな。……帰る日が決まったら連絡するよ』
「はい」
『雪哉、大人になったな』
父の声は優しい。それに比べて自分の声は固い。
大人になった?
違う。自分はまだ子どもなのだ。嫌になるくらいに。
大人になったなら、自分の大事なものくらい、一人で守れるようになるはずだ。
大事なものを守るのに、誰の許可もいらないはずだ。
電話を切った後、少し疲れて自室に戻り、今度は自分の携帯から電話をかける。
『……もしもし』
「姫野?」
-end-
2013.10.6