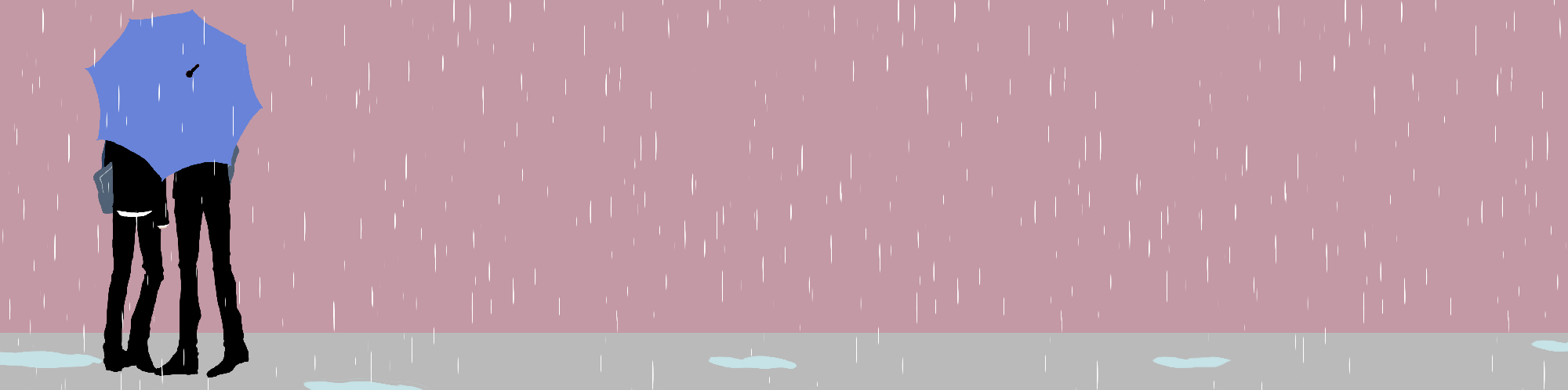姫は王子のもの。
平日の夕方。空は綺麗な夕焼け色。
いつものように姫野を送り、高級住宅地であるその辺りでもあまり見かけないような大きな屋敷の敷地へと入っていく長身の金髪。
「ただいま帰りました」
靴を脱ぎ、広いホールからリビングへと続く背の高いドアを開ける。
「お帰りなさい」
「雪ちゃん、あなたご飯は?」
「食べてません」
「坂田さんはキッチンじゃないかしらね」
大きな白いソファセットに集まっているのは3人の女性。
髪の色は様々だが、皆一様に彫りの深い顔立ちで、一目で純粋な日本人ではないことが知れる。
「桜ちゃんたちは食べたんですか」
「私たち、今日は外で頂いてきたの」
「そうですか」
本城は一旦リビングを出て、奥にあるキッチンへ向かう。
「坂田さん、ただいま」
「雪哉くん。お帰りなさい」
キッチンに居たのは30代半ばほどの小柄な女性で、ショートカットで小顔の彼女は純和風の面立ちだ。
「ご飯、何かある?」
「もちろん!今日は雪哉くんの好きな豚の角煮だよ」
「わあ。おいしそう」
鍋の蓋を開けて2人で中を覗く。
「明日の夜ごはんにも残るかなぁ」
「桜ちゃんたちが明日のお弁当に入れるって言ってたけど、雪哉くんの分だけよけておくね。そんなに喜んでもらえると作り甲斐がある」
女性はニコニコと笑いながら、味噌汁の鍋を火にかけた。
「坂田さん」
イスに掛けながら、その後ろ姿に声をかける。
キッチンに据えられた食卓テーブルは本来、坂田を始め家族以外の者が食事をするための場所だったが、本城は自分たちのためにある広いダイニングのばかでかいテーブルよりむしろこちらが落ち着くので、一人の食事はここで摂るようにしていた。
「ん?」
「俺ね、付き合ってる人がいるんだけど」
「そう。雪哉くんはモテそうだものね」
「今度、うちに連れて来るから」
「……珍しいね」
坂田は振り向いて本城を見た。
「うん。って言うより、初めてだよね」
「そうね。友達も連れて来ないものね」
「それでね、その人、男の子なんだよね。とってもかわいくて女の子みたいなんだけど」
坂田が内心動揺する様を、本城はじっと観察した。
「雪哉くん、それは、」
「自分が同性愛者かどうかはわかんない。その人のことがただ、本当に大好きなんだよ」
姫野のことをそんな風に人に話すのが新鮮で、本城は思わずニヤけた。
味噌汁の鍋が沸騰寸前の音をたて、坂田は慌てて振り返って火を止めた。
「桜ちゃんたちにもこれから話すんだけど、坂田さんに一番初めに話しておきたくて」
「……真剣なお付き合いなんだ」
「うん」
「真剣に、将来を考えてるってことね?」
「そう。まだ早いと思う?高校生の分際で先を見越しすぎ?いろいろ無謀すぎる?」
もう一度本城の顔を見た坂田さんの顔はもう普段の笑顔に戻っていた。
「少し驚いたけど、私は雪哉くんが幸せになることを祈ってるよ」
「坂田さんならそう言ってくれると思ってた」
「雪哉くん」
ご飯をよそった茶碗を本城の前に起きながら、坂田は言う。
「相変わらず、根回しの順番が上手ね」
「そうかな。僕も大人になったかな」
「うん。ま、昔からそういうところのある子ではあったけどね」
7年間、側で見守ってくれている人にそこを指摘されて、本城は苦笑した。
「いずれ戦争になるだろうから、味方は多い方がいいと思って。……正直、勝てるか不安だけど」
ぽつりと漏れた本城の本音に対して、坂田は何も言わなかった。
「その子、食べ物は何が好き?」
「甘いもの。女の子みたいにたくさん食べるよ」
「じゃあ、ケーキでも用意しておかないとね」
「夕飯も一緒に食べることになったら、また角煮作ってね」
「喜んで」
本城は少し安心して、いただきます、と言った。
本城には3人の姉がいる。
長女の桜、次女の夏実、三女の桃香。
金髪の末の男の子を、日本人の父も、イギリス人の母も、美人姉妹と言われ始めた姉たちも、皆が奪い合うようにして可愛がった。
それでも人間として立派に社会で生き抜くことのできるよう、愛情をかけながら躾はきちんと為され、本城は至極真っ当な幼少時代を送った。
忙しい両親がよくあそこまで、と感心するほどに、自分たち姉弟はきちんと目をかけられていたと本城は思っている。
そして本城が10歳の時、母はモデルの仕事を本格的に再開するために生まれ故郷であるヨーロッパへ戻った。
今はフランスにいるらしい。
父は仕事のためアメリカと日本を往復する日々だ。
ちなみに今はアメリカ。
そして、子どもたちだけになる家を心配して両親が雇ったのが、坂田たちだった。
坂田は家政婦ではない。民間の会社から派遣されている、訓練された警備員だった。
警護に加えて食事の支度を始めとした家事全般を、坂田たちが仕切っていた。
そこにかかる予算が月々どのくらいなのか、本城は知らない。
元々それは年頃の姉たちと幼かった本城のために交わされた契約で、現状にはそぐわないような気がしていたが、母は彼女らに家を守らせることを未だに頑として譲らない。
姉たちも社会人生活や学生生活を謳歌している。いずれ降りかかるであろう父の跡継ぎ問題を抱えた弟を、遠巻きに、それでも温かく見守ってきてくれた。
あとは自分次第。
本城は言い聞かせながら、リビングに戻り、姉たちと対峙した。
「まあ。大変なのね」
恋人が男の子です、と大発表した本城に、桜が全然大変ではなさそうに言った。
「あなた、やっぱり少し、そうね、わかる気がするわ」
夏実が頷く。
「雪ちゃんの恋人が男の子でも、あんまり違和感はないわね」
桃香が微笑む。
世間の価値観を気にしたことがなく、同じように他人に自分の価値観を押し付けないという点で、自分と姉たちはよく似ていると本城は思う。
「ただね、どんな子なのか気にならない?」
「なるわね」
「いつか私たちにも会わせてくれる?」
「できれば近々会ってほしいです」
本城が言うと3人は顔を見合わせ、それから揃って本城を見た。
「雪ちゃんそれは」
「それは、お母さんを敵に回すってことね?」
「もう決めてるってことよね、いろんなことを」
坂田といい姉たちといい、本城の性格と行動パターンを十分理解している。なにも言わなくても、俺が何を考えているか、この人たちはわかっている。本城の思考は、家族に限り筒抜けだ。
「今度、会ってください」
余計なことを挟まず頼むと、3人は表情を和らげた。
「楽しみだわ」
「本当にね」
「ねえ、その子のお名前は?」
「姫野未琴くん」
「随分かわいい名前ね」
「名前だけなら女の子に間違われるでしょうね」
「外見も女の子みたいですけどね」
姉たちに姫野のことを少しずつ説明しながら、かわいい恋人のことを想う。
大ごとになっちゃってごめんね。でもこうやって地盤を固めていかないと、俺は姫野を守れない。
姫野を傷つけるものは俺が取っ払うし、そのためならズルいことも汚いことも何だってできるよ。
何かや誰かのせいで姫野と離ればなれになるなんて、俺は絶対に嫌だから。
安心してね。俺の守備範囲からは絶対、出してあげないから。
「大丈夫よ雪ちゃん」
桜が本城に笑いかける。
「そんなに不安そうな顔をしないで」
夏実が身を乗り出して本城の肩を撫でた。
「私たちは雪ちゃんの味方よ。協力するわ」
桃香がくっきりと頷く。
自分は不安そうに見えたのかと思いながら、ありがとう、と小さく呟いた。
自分のことを誰よりわかっている3人に心から感謝をしながら、姫野をうちに呼んで何をしようかと、本城は気持ちを少し明るくした。
「それでね、今度の土曜日、来られないかと思って」
姫野の部屋のベッドの上で、制服を着たまま姫野を腕の中に閉じ込めている。
窓の外はもうほとんど真っ暗だ。
「家族の話とか、姫野にしたことあったっけ」
髪に鼻をくっつけながら聞くと、姫野が少し間をおいて答えた。
「お姉ちゃんがいるって、きいたけど」
「そう。姉がいる」
3人いるんだけど。
「土曜日ももしかしたらいるかも」
いや、絶対にいる。いてって頼んだのは俺。
姫野にそれを言うと緊張してかわいそうだから、偶然を装うつもりだけど。
「あと、父はアメリカにいる」
「アメリカ」
「うん。母はフランス」
「ふぅん」
本城は姫野を強く抱き締める。
「姫野」
本当はもう、一瞬だって離れていたくないと本城は思う。
高校を卒業したら。
最近頻繁に頭に浮かぶ未来のビジョンは、到達するのにやたら労力を使いそうで、今はそのための温存の時間だった。
「明日、学校さぼっちゃおうか。電車でケーキ屋さんに行かない?」
後ろから姫野の体を抱き込んで手を握る。
「明日現国のテストだからだめ」
「えー。行こうよ」
「嫌。1人で行って」
無下に断られて苦笑する。
「ケチ」
「うるさい」
「じゃあ放課後は?」
「理科室の掃除」
「それが終わってからは?」
「……別に」
「別に?」
「いいけど」
「よかった。ありがとう」
姫野。
「姫野は大学に行くんだよね」
姫野がこくりと頷く。
「俺も同じ大学に行く」
本城が言うと、姫野は驚いたようだった。向こうを向いたままの頭が少し動いた。
「同じ?」
「うん」
「……ふぅん」
「いいかな」
「いいんじゃない。別に」
いつもと変わらず素っ気ない姫野を物足りなく思い、本城は頭を上げて姫野の顔を覗き込んだ。
「……なんでそんなにかわいいの」
その顔が真っ赤になっているのを見て、やっぱり自分のお姫様はこの子以外に居ないと、本城は力いっぱい姫野を抱き締めた。
頭に浮かんだ母の顔をかき消すように、本城は姫野の首筋に赤い跡を付けた。
-end-
2013.6.10
いつものように姫野を送り、高級住宅地であるその辺りでもあまり見かけないような大きな屋敷の敷地へと入っていく長身の金髪。
「ただいま帰りました」
靴を脱ぎ、広いホールからリビングへと続く背の高いドアを開ける。
「お帰りなさい」
「雪ちゃん、あなたご飯は?」
「食べてません」
「坂田さんはキッチンじゃないかしらね」
大きな白いソファセットに集まっているのは3人の女性。
髪の色は様々だが、皆一様に彫りの深い顔立ちで、一目で純粋な日本人ではないことが知れる。
「桜ちゃんたちは食べたんですか」
「私たち、今日は外で頂いてきたの」
「そうですか」
本城は一旦リビングを出て、奥にあるキッチンへ向かう。
「坂田さん、ただいま」
「雪哉くん。お帰りなさい」
キッチンに居たのは30代半ばほどの小柄な女性で、ショートカットで小顔の彼女は純和風の面立ちだ。
「ご飯、何かある?」
「もちろん!今日は雪哉くんの好きな豚の角煮だよ」
「わあ。おいしそう」
鍋の蓋を開けて2人で中を覗く。
「明日の夜ごはんにも残るかなぁ」
「桜ちゃんたちが明日のお弁当に入れるって言ってたけど、雪哉くんの分だけよけておくね。そんなに喜んでもらえると作り甲斐がある」
女性はニコニコと笑いながら、味噌汁の鍋を火にかけた。
「坂田さん」
イスに掛けながら、その後ろ姿に声をかける。
キッチンに据えられた食卓テーブルは本来、坂田を始め家族以外の者が食事をするための場所だったが、本城は自分たちのためにある広いダイニングのばかでかいテーブルよりむしろこちらが落ち着くので、一人の食事はここで摂るようにしていた。
「ん?」
「俺ね、付き合ってる人がいるんだけど」
「そう。雪哉くんはモテそうだものね」
「今度、うちに連れて来るから」
「……珍しいね」
坂田は振り向いて本城を見た。
「うん。って言うより、初めてだよね」
「そうね。友達も連れて来ないものね」
「それでね、その人、男の子なんだよね。とってもかわいくて女の子みたいなんだけど」
坂田が内心動揺する様を、本城はじっと観察した。
「雪哉くん、それは、」
「自分が同性愛者かどうかはわかんない。その人のことがただ、本当に大好きなんだよ」
姫野のことをそんな風に人に話すのが新鮮で、本城は思わずニヤけた。
味噌汁の鍋が沸騰寸前の音をたて、坂田は慌てて振り返って火を止めた。
「桜ちゃんたちにもこれから話すんだけど、坂田さんに一番初めに話しておきたくて」
「……真剣なお付き合いなんだ」
「うん」
「真剣に、将来を考えてるってことね?」
「そう。まだ早いと思う?高校生の分際で先を見越しすぎ?いろいろ無謀すぎる?」
もう一度本城の顔を見た坂田さんの顔はもう普段の笑顔に戻っていた。
「少し驚いたけど、私は雪哉くんが幸せになることを祈ってるよ」
「坂田さんならそう言ってくれると思ってた」
「雪哉くん」
ご飯をよそった茶碗を本城の前に起きながら、坂田は言う。
「相変わらず、根回しの順番が上手ね」
「そうかな。僕も大人になったかな」
「うん。ま、昔からそういうところのある子ではあったけどね」
7年間、側で見守ってくれている人にそこを指摘されて、本城は苦笑した。
「いずれ戦争になるだろうから、味方は多い方がいいと思って。……正直、勝てるか不安だけど」
ぽつりと漏れた本城の本音に対して、坂田は何も言わなかった。
「その子、食べ物は何が好き?」
「甘いもの。女の子みたいにたくさん食べるよ」
「じゃあ、ケーキでも用意しておかないとね」
「夕飯も一緒に食べることになったら、また角煮作ってね」
「喜んで」
本城は少し安心して、いただきます、と言った。
本城には3人の姉がいる。
長女の桜、次女の夏実、三女の桃香。
金髪の末の男の子を、日本人の父も、イギリス人の母も、美人姉妹と言われ始めた姉たちも、皆が奪い合うようにして可愛がった。
それでも人間として立派に社会で生き抜くことのできるよう、愛情をかけながら躾はきちんと為され、本城は至極真っ当な幼少時代を送った。
忙しい両親がよくあそこまで、と感心するほどに、自分たち姉弟はきちんと目をかけられていたと本城は思っている。
そして本城が10歳の時、母はモデルの仕事を本格的に再開するために生まれ故郷であるヨーロッパへ戻った。
今はフランスにいるらしい。
父は仕事のためアメリカと日本を往復する日々だ。
ちなみに今はアメリカ。
そして、子どもたちだけになる家を心配して両親が雇ったのが、坂田たちだった。
坂田は家政婦ではない。民間の会社から派遣されている、訓練された警備員だった。
警護に加えて食事の支度を始めとした家事全般を、坂田たちが仕切っていた。
そこにかかる予算が月々どのくらいなのか、本城は知らない。
元々それは年頃の姉たちと幼かった本城のために交わされた契約で、現状にはそぐわないような気がしていたが、母は彼女らに家を守らせることを未だに頑として譲らない。
姉たちも社会人生活や学生生活を謳歌している。いずれ降りかかるであろう父の跡継ぎ問題を抱えた弟を、遠巻きに、それでも温かく見守ってきてくれた。
あとは自分次第。
本城は言い聞かせながら、リビングに戻り、姉たちと対峙した。
「まあ。大変なのね」
恋人が男の子です、と大発表した本城に、桜が全然大変ではなさそうに言った。
「あなた、やっぱり少し、そうね、わかる気がするわ」
夏実が頷く。
「雪ちゃんの恋人が男の子でも、あんまり違和感はないわね」
桃香が微笑む。
世間の価値観を気にしたことがなく、同じように他人に自分の価値観を押し付けないという点で、自分と姉たちはよく似ていると本城は思う。
「ただね、どんな子なのか気にならない?」
「なるわね」
「いつか私たちにも会わせてくれる?」
「できれば近々会ってほしいです」
本城が言うと3人は顔を見合わせ、それから揃って本城を見た。
「雪ちゃんそれは」
「それは、お母さんを敵に回すってことね?」
「もう決めてるってことよね、いろんなことを」
坂田といい姉たちといい、本城の性格と行動パターンを十分理解している。なにも言わなくても、俺が何を考えているか、この人たちはわかっている。本城の思考は、家族に限り筒抜けだ。
「今度、会ってください」
余計なことを挟まず頼むと、3人は表情を和らげた。
「楽しみだわ」
「本当にね」
「ねえ、その子のお名前は?」
「姫野未琴くん」
「随分かわいい名前ね」
「名前だけなら女の子に間違われるでしょうね」
「外見も女の子みたいですけどね」
姉たちに姫野のことを少しずつ説明しながら、かわいい恋人のことを想う。
大ごとになっちゃってごめんね。でもこうやって地盤を固めていかないと、俺は姫野を守れない。
姫野を傷つけるものは俺が取っ払うし、そのためならズルいことも汚いことも何だってできるよ。
何かや誰かのせいで姫野と離ればなれになるなんて、俺は絶対に嫌だから。
安心してね。俺の守備範囲からは絶対、出してあげないから。
「大丈夫よ雪ちゃん」
桜が本城に笑いかける。
「そんなに不安そうな顔をしないで」
夏実が身を乗り出して本城の肩を撫でた。
「私たちは雪ちゃんの味方よ。協力するわ」
桃香がくっきりと頷く。
自分は不安そうに見えたのかと思いながら、ありがとう、と小さく呟いた。
自分のことを誰よりわかっている3人に心から感謝をしながら、姫野をうちに呼んで何をしようかと、本城は気持ちを少し明るくした。
「それでね、今度の土曜日、来られないかと思って」
姫野の部屋のベッドの上で、制服を着たまま姫野を腕の中に閉じ込めている。
窓の外はもうほとんど真っ暗だ。
「家族の話とか、姫野にしたことあったっけ」
髪に鼻をくっつけながら聞くと、姫野が少し間をおいて答えた。
「お姉ちゃんがいるって、きいたけど」
「そう。姉がいる」
3人いるんだけど。
「土曜日ももしかしたらいるかも」
いや、絶対にいる。いてって頼んだのは俺。
姫野にそれを言うと緊張してかわいそうだから、偶然を装うつもりだけど。
「あと、父はアメリカにいる」
「アメリカ」
「うん。母はフランス」
「ふぅん」
本城は姫野を強く抱き締める。
「姫野」
本当はもう、一瞬だって離れていたくないと本城は思う。
高校を卒業したら。
最近頻繁に頭に浮かぶ未来のビジョンは、到達するのにやたら労力を使いそうで、今はそのための温存の時間だった。
「明日、学校さぼっちゃおうか。電車でケーキ屋さんに行かない?」
後ろから姫野の体を抱き込んで手を握る。
「明日現国のテストだからだめ」
「えー。行こうよ」
「嫌。1人で行って」
無下に断られて苦笑する。
「ケチ」
「うるさい」
「じゃあ放課後は?」
「理科室の掃除」
「それが終わってからは?」
「……別に」
「別に?」
「いいけど」
「よかった。ありがとう」
姫野。
「姫野は大学に行くんだよね」
姫野がこくりと頷く。
「俺も同じ大学に行く」
本城が言うと、姫野は驚いたようだった。向こうを向いたままの頭が少し動いた。
「同じ?」
「うん」
「……ふぅん」
「いいかな」
「いいんじゃない。別に」
いつもと変わらず素っ気ない姫野を物足りなく思い、本城は頭を上げて姫野の顔を覗き込んだ。
「……なんでそんなにかわいいの」
その顔が真っ赤になっているのを見て、やっぱり自分のお姫様はこの子以外に居ないと、本城は力いっぱい姫野を抱き締めた。
頭に浮かんだ母の顔をかき消すように、本城は姫野の首筋に赤い跡を付けた。
-end-
2013.6.10