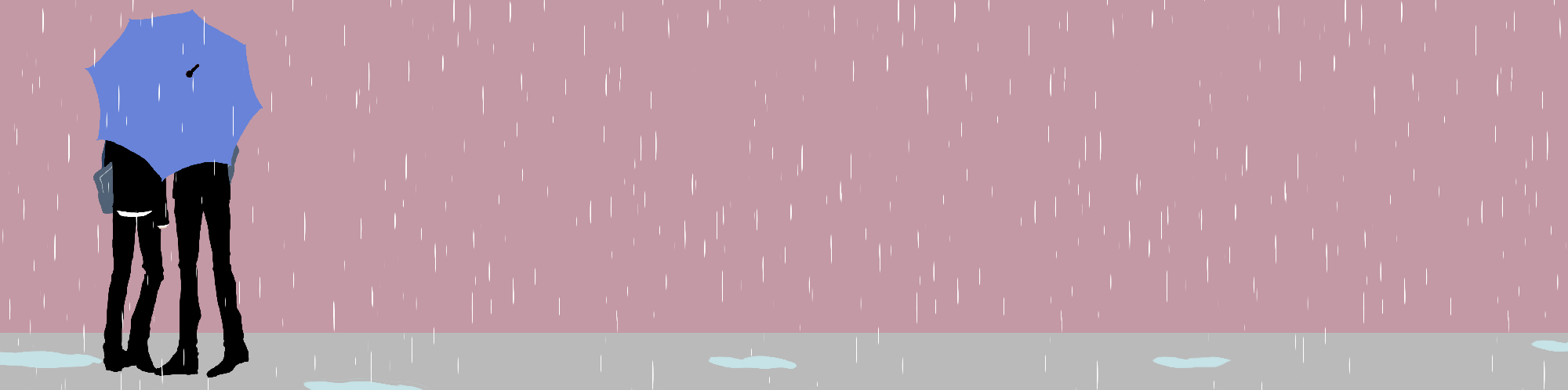姫は王子のもの。
「あれ、姫野は?」
月曜日、昼休みに姫野に会いに行ってみると、姫野だけがいなかった。先週の市井とのことが頭をよぎって冷や汗をかいた本城に、母親の手作りであろう弁当を掻き込みながら中川が応える。
「姫ならさっき野島と一緒に出てったよ」
「野島?」
「うん。野島の様子がなんか変でさ、姫野くん、ちょっといいかな、って言って。そしたら姫がしかめっ面して野島連れて出てった」
本城の腰にパンを持った阿部がまとわりつく。
「ほんじょー、今日は市井まだ来てないよ」
「お前はもう何も言うな」
明るく言う阿部に中川がつっこむ。
「野島、どうしたんだろうな」
阿部がお好み焼きパンをかじってもぐもぐしながら言う。
「そう言えば授業中も上の空だったよ」
「なんか頭にお花が咲いてたような、でもなんか切ないような、苦しげなような」
本城の言葉に、中川も応じた。
「目もうるうるしてたよな。肌もつるつるだし。ちっちゃいし、髪ふわっふわだし、かわいいし」
机に片肘をついてだらりとした体勢のままの土屋の言葉にだけ、他の皆とは違う感情が含まれている。それを感じ取って皆がさーっと引く気配がした。
「なんでだ。本城と姫野はよくて俺と野島がダメな理由は何だ」
ぼやいた土屋が、更に付け足す。
「つかさぁ、俺、わかっちゃった」
「何?」
中川が聞くと、土屋は飲んでいたパインジュースのストローをガシガシと噛んだ。
「土曜日さ、野島、バスケの試合見に来てくれてさ」
「うん」
「試合終わって片付け手伝ってくれてな」
「うん」
「次、バレー部の練習試合入ってたから、相手の高校が入って来てたんだけど」
「うん」
そこまで言って、土屋は、はぁ、とため息をついた。空になったジュースのパックを握りつぶすグシュ、という音がした。
「だめだ。俺ちょっと泣きそうだから帰るわ」
「はぁ?!気になるだろうが」
「中川、一緒に来いよ。公園で自主練付き合え」
「午後サボんの?嫌だよめんどくせえ」
「いいから。お前、大事な友達が失恋したんだぞ」
「失恋?」
「失恋?」
「失恋て言ったのか?」
どこにつっこんでいいかわからない。土曜日、野島に一体何が。
「だから来い。マジで。今日だけ」
「えー、うー」
中川は渋りながらもカバンを持って土屋と一緒に教室を出て行った。
「なんだぁ、みんないなくなった」
「だね」
「お好み焼きパンうまい。本城も食べる?」
「いや、いいよ。これあげる」
阿部が差し出したパンを断って、代わりに姫野にあげようと思っていたプリンを阿部に渡す。
「え!まじ?本城まじいいやつ!大好き!」
阿部を抱き止めながら、姫野と野島がどこに行って何を話しているのか、本城はぼんやり考えていた。
昼休みも半分過ぎた頃、携帯が鳴って、見ると姫野からの電話だった。
「もしもし姫野?」
『……本城。ちょっと来て』
「どうしたの?今どこ?」
『野島が全然泣き止まないんだけど』
本城は一呼吸置いてから言った。
「だめじゃない。いじめたら」
『いじめてない!早く来て!』
場所を聞き出す前に電話が切れた。
とりあえず教室を出る。
野島が泣いた?なぜ?
電話をかけ直す本城の頭に、先程の土屋の浮かない顔がちらりとよぎった。
*
前の学校で好きだった人と再会してしまった、と野島は言った。
人のあまり来ない廊下の端、階段を下りきったところで、姫野は野島と並んで壁に寄りかかっていた。
野島の顔は少し上気していて、視線はななめ下を向いている。
「それで?」
姫野が聞くと、野島は話し出した。
「好きな人、先生なんだ」
好きな人。
過去形じゃなくなった。
「バレー部の引率で来てて、偶然会って、僕のことたくさん心配してくれてて、僕はもうそれだけで嬉しくて死んじゃうかと思ったのに」
「なんか言われたの?」
「先生が帰ろうとした時、もう会えないかもしれないと思ったら寂しくなって、先生を呼び止めちゃって、そしたら……」
「そしたら?」
「話があるって言われて、それで、」
「好きって言われたの?」
野島はぶわっと顔を赤くした。
「良かったね」
「良くないよ」
野島はつっけんどんに言う。
「全然良くないの」
「何が」
「先生はとっても真面目な人で、僕と一緒にいたいから先生を辞めるって言った」
「いいじゃん、辞めてもらえば」
野島は目を見開いた。
「仕事を辞めるってことだよ?」
「だって先生なんでしょ?生徒のこと好きになって一緒にいたいならそうするしかないんじゃないの。野島はその先生と一緒にいたくないの?」
「いたいけど、でも、」
「辞めるかどうかは先生が決めることじゃん。それだけ野島と一緒にいたいってこと」
「でも僕は」
ああ、この目を知っている。野島のこの目を。
野島はこう見えて案外はっきりした性格で、譲れない何かがある時、こいつはこういう強い目をする。
姫野はもう、ただ決まった話を聞けばいいだけだと悟った。
「僕はね、その先生にたくさん助けてもらったんだ。先生だけが僕の味方でいてくれて、先生がいなかったら僕は学校に行けなかった。だからね、由井先生みたいな先生があの学校からいなくなったら、助けてほしいと思った人が、助けてもらえないかもしれない」
「でも、先生が先生を辞めたら野島が独り占めできるんだよ?」
「……独り占め、できなくてもいいよ。本当は、本当はしたいけど、でもそれより僕は、先生に先生を辞めてほしくない」
野島の目は真っ直ぐ前を見ている。意外と頑固。
「それ、先生に言った?」
「言った」
「なんか言われた?」
「笑ってた。野島くんはそう言うような気がしたって。野島くんがどうしても僕に教師を辞めてほしくないと言うなら辞めない、でももう一度考えてって。僕が教師を辞めなかったら、あと1年半、君が卒業するまでは会わないし、連絡もできないからって」
姫野はとつとつと語る野島の横顔をまじまじと見た。
「その先生、って、……男なの?」
野島ははっとした顔をした。それからうっすらと笑った。
「そう。男の人」
「なんだ。そうなんだ」
姫野はくすくす笑った。
野島は珍しいものを見るようにこちらを見ている。
「なんか、しっくり来る。わかんないけど」
「ふふ、なにそれ」
ひとしきり2人で笑ってから、姫野は聞いた。
「寂しくないの?1年半」
「寂しいけど、僕はずっと先生のこと好きな自信がある」
野島は口に手を当てて少しの間、目を閉じた。きれいな横顔だった。
その、ゆい先生とやらを思い浮かべてそんな顔をするのだとしたら。
土屋、気の毒だけど、これは何をどうがんばったってその先生には勝てないね。
姫野は重ねて聞く。
「先生しか味方がいなかったって、なんで?」
野島は首を傾げる。
「男の先生を好きだったからじゃないかな。わかんないけど」
「転校したのもそのせい?」
「でも多分僕が悪かったんだと思う。うじうじしちゃって」
その表情、笑顔の後ろに、何か張りつめたものを感じた。
「だからね、転校してからはいろいろ気をつけようと思ってた。なんとしても周りに合わせなきゃって。でも、そしたら」
野島は姫野を見た。
「初日から、本城くんが姫野くんを彼女だって言った。びっくりしちゃった」
姫野は恥ずかしくなって俯いた。
「でも本当にいいなって思ったんだよ。僕はまだ、男の人を好きにはなりませんってうそぶくのが精一杯だったから」
「……辛かった?前の学校の時」
「少し」
野島は笑う。
こんなにいいやつなのに、誰もそれをわからなかったなんて。
バカだ。
うちの学校ではこんなにうまくやってるし友達もいるし、中川たちにだって好かれてるんだから。
野島が悪かった訳がない。バカだ。そいつらは。
姫野はだんだん腹が立ってきて、口を尖らせた。
「そんな学校、転校して大正解だから。バカばっかりだったんじゃないの」
何も言わなくなった野島を見て、姫野は息を止めた。
*
両手で顔を覆っている野島の隣で、姫野は困りきった様子で佇んでいた。
姫野に事情を聞こうとすると、野島のプライベートだから理由は言えないと言う。
「いいからとにかく野島を泣き止ませてよ」
「えー、何も知らないのに無理だよ」
本城が言い返すと、ぐじゅぐじゅと鼻をすすりながら野島が顔を上げた。
「ごめんね、2人とも、困らせて」
「なんで泣くの。本当やめてよね」
「野島、大丈夫?」
野島は姫野に、ごめんね、と泣き笑いの顔を向けてから、本城に言った。
「姫野くんがすごく優しいこと言うから、いろいろ考えて、今が幸せで泣けたの」
はぁ?意味がわかんない。
と姫野がぶっきらぼうに言った。
姫野は野島に何を言ったんだろう。
それにしても野島はいろんな意味で愛されてるな。
まあとにかく、幸せの涙だったならいいか。
本城は、このかわいい2人の間にあっという間に築かれた不思議な友情に少しだけ嫉妬した。
今日帰ったら抱こう。
場違いなことを思いながら、それでも、野島のお陰で姫野の新しい一面がまた発見できたような気がした。
野島が転校してきてくれてよかった、と、本城は一瞬のうちに思った。
*
「全っ然入んないなー!」
大声で話しかけても土屋は無言のままシュートを打ち続ける。中川はそんな友人を木陰のベンチからずっと見ていた。
木陰にいても暑い。動かなくてもものすごい暑さだ。日向で動いている土屋は汗だくだった。
公園には2人の他には誰もいない。ただ、土屋のドリブルとシュートの音が響いている。
2年でレギュラー争いに食い込む実力のある土屋のシュートが、さっきから全然入らない。
「あっちい」
呟きながら、土屋の胸中を推し量る。
学校を出て公園に来る途中、土屋は野島の話を続けた。
「そのバレー部引率してた先生見たとたん野島がビクッてなって」
「うん」
「ビクッてなった野島もまじかわいいな、とか思ってたら」
「はいはい」
「そっから野島の体って敏感なのかなとか空想にふけってたら」
「はいはいはいはいもうわかったから先に進め」
「なんか、その先生が、すげぇ怪しくて」
「見た目が?」
「いーや、見た目はメガネで髪短くて真面目そうな、優男っつーの?なんかつまんなそうなやつだった。バレー部の引率だけあって背は高かったけど。なんでか野島が逃げて、そいつがそれを追ってってさ」
「うん」
「少しして2人で戻って来て、なんか野島と目合わせて笑い合って」
「……うん」
土屋はそこで小さくため息をついた。
「なんかさー、絶対怪しい。付き合ってるみたいに見えた」
「嘘だろ、先生でしょ?しかも男?」
「あり得なくはないんじゃね?変な時期に転校してきたのもその関係だったりして、とか思ったら全然寝られなかった」
中川は土屋の顔を見た。
「お前、野島のこと、本気だったの?」
土屋はゆっくり瞬きをした。
「わかんね」
「ふぅん」
住宅街を抜け、視界が一気に開けて、バスケットゴールのある公園が見えた。
「告んないの?」
「負け戦はしたくない」
「お前女の子にモテんだからわざわざ男狙うなよな」
「わざわざ狙ったわけじゃねえよ」
「まぁな……かわいいけどさ……」
「あーあ。次はドMの女狙おう」
「きゃー最低だわ土屋くん」
公園に入ると土屋はおもむろにボールを取り出し、練習を始めた。
それからもう1時間は経っていた。
ひたすらシュート練習ばかりして、流石に暑さに耐えられなくなったのか、土屋は中川の隣に来てどかりと座った。こめかみから首へ、汗が伝い落ちている。同性から見ても、モテる理由はわかりすぎるほどわかる。
「俺が女だったらお前のこと好きになってやるのにな」
中川の言葉に、土屋は声をあげて笑い、言う。
「ほんとだよ。横に居んのが女だったら、慰めろっつっていろいろ迫れるのによ」
「え、ここで?」
「燃えない?青姦」
「燃えない。大体女の子は嫌がるだろ」
「それがいいんじゃん。やめて恥ずかしいとか抵抗すんのをうるせえよっつって押さえつけて」
「……野島がそんな目に合わなくて本当によかったよ」
「野島にはしない。あいつだったら大事にする」
「嘘くさい」
「それがなんで横に居んのがお前なんだよ」
「お前が来いって言ったんだろ」
「言ったっけ?」
「はい、ありがとうの気持ちを形にして」
中川は手のひらを土屋に差し出す。
「仕方ねぇな、妹の友達を紹介してやる」
「嘘だよね」
「おう。なんでわかった」
「お前妹いないもんね」
「うん」
「くそおおおおおお!」
誰もいない公園に、中川の悲しい叫びがこだまする。
部活のバッグからタオルを出して汗を拭く土屋に、ジュースおごれ、2本な、と中川が言う。
土屋は中川を見てニヤ、と笑い、言った。
「でもお前が女だったらこんな仲良くなってねえな」
「まあね」
「だったらいいわ。今の方が」
髪をかき上げる土屋の耳で、ピアスが光った。
「そんな熱い言葉はいらない。飲み物買って来い」
「くそ、はぐらかそうと思ったのに」
「走れ、走って行け」
土屋が、細い道路を挟んだ向かい側に見える赤い自販機まで全速力で走って行った。
「はは。早っ。さすが」
中川は1人、ベンチで笑い転げた。
-end-
月曜日、昼休みに姫野に会いに行ってみると、姫野だけがいなかった。先週の市井とのことが頭をよぎって冷や汗をかいた本城に、母親の手作りであろう弁当を掻き込みながら中川が応える。
「姫ならさっき野島と一緒に出てったよ」
「野島?」
「うん。野島の様子がなんか変でさ、姫野くん、ちょっといいかな、って言って。そしたら姫がしかめっ面して野島連れて出てった」
本城の腰にパンを持った阿部がまとわりつく。
「ほんじょー、今日は市井まだ来てないよ」
「お前はもう何も言うな」
明るく言う阿部に中川がつっこむ。
「野島、どうしたんだろうな」
阿部がお好み焼きパンをかじってもぐもぐしながら言う。
「そう言えば授業中も上の空だったよ」
「なんか頭にお花が咲いてたような、でもなんか切ないような、苦しげなような」
本城の言葉に、中川も応じた。
「目もうるうるしてたよな。肌もつるつるだし。ちっちゃいし、髪ふわっふわだし、かわいいし」
机に片肘をついてだらりとした体勢のままの土屋の言葉にだけ、他の皆とは違う感情が含まれている。それを感じ取って皆がさーっと引く気配がした。
「なんでだ。本城と姫野はよくて俺と野島がダメな理由は何だ」
ぼやいた土屋が、更に付け足す。
「つかさぁ、俺、わかっちゃった」
「何?」
中川が聞くと、土屋は飲んでいたパインジュースのストローをガシガシと噛んだ。
「土曜日さ、野島、バスケの試合見に来てくれてさ」
「うん」
「試合終わって片付け手伝ってくれてな」
「うん」
「次、バレー部の練習試合入ってたから、相手の高校が入って来てたんだけど」
「うん」
そこまで言って、土屋は、はぁ、とため息をついた。空になったジュースのパックを握りつぶすグシュ、という音がした。
「だめだ。俺ちょっと泣きそうだから帰るわ」
「はぁ?!気になるだろうが」
「中川、一緒に来いよ。公園で自主練付き合え」
「午後サボんの?嫌だよめんどくせえ」
「いいから。お前、大事な友達が失恋したんだぞ」
「失恋?」
「失恋?」
「失恋て言ったのか?」
どこにつっこんでいいかわからない。土曜日、野島に一体何が。
「だから来い。マジで。今日だけ」
「えー、うー」
中川は渋りながらもカバンを持って土屋と一緒に教室を出て行った。
「なんだぁ、みんないなくなった」
「だね」
「お好み焼きパンうまい。本城も食べる?」
「いや、いいよ。これあげる」
阿部が差し出したパンを断って、代わりに姫野にあげようと思っていたプリンを阿部に渡す。
「え!まじ?本城まじいいやつ!大好き!」
阿部を抱き止めながら、姫野と野島がどこに行って何を話しているのか、本城はぼんやり考えていた。
昼休みも半分過ぎた頃、携帯が鳴って、見ると姫野からの電話だった。
「もしもし姫野?」
『……本城。ちょっと来て』
「どうしたの?今どこ?」
『野島が全然泣き止まないんだけど』
本城は一呼吸置いてから言った。
「だめじゃない。いじめたら」
『いじめてない!早く来て!』
場所を聞き出す前に電話が切れた。
とりあえず教室を出る。
野島が泣いた?なぜ?
電話をかけ直す本城の頭に、先程の土屋の浮かない顔がちらりとよぎった。
*
前の学校で好きだった人と再会してしまった、と野島は言った。
人のあまり来ない廊下の端、階段を下りきったところで、姫野は野島と並んで壁に寄りかかっていた。
野島の顔は少し上気していて、視線はななめ下を向いている。
「それで?」
姫野が聞くと、野島は話し出した。
「好きな人、先生なんだ」
好きな人。
過去形じゃなくなった。
「バレー部の引率で来てて、偶然会って、僕のことたくさん心配してくれてて、僕はもうそれだけで嬉しくて死んじゃうかと思ったのに」
「なんか言われたの?」
「先生が帰ろうとした時、もう会えないかもしれないと思ったら寂しくなって、先生を呼び止めちゃって、そしたら……」
「そしたら?」
「話があるって言われて、それで、」
「好きって言われたの?」
野島はぶわっと顔を赤くした。
「良かったね」
「良くないよ」
野島はつっけんどんに言う。
「全然良くないの」
「何が」
「先生はとっても真面目な人で、僕と一緒にいたいから先生を辞めるって言った」
「いいじゃん、辞めてもらえば」
野島は目を見開いた。
「仕事を辞めるってことだよ?」
「だって先生なんでしょ?生徒のこと好きになって一緒にいたいならそうするしかないんじゃないの。野島はその先生と一緒にいたくないの?」
「いたいけど、でも、」
「辞めるかどうかは先生が決めることじゃん。それだけ野島と一緒にいたいってこと」
「でも僕は」
ああ、この目を知っている。野島のこの目を。
野島はこう見えて案外はっきりした性格で、譲れない何かがある時、こいつはこういう強い目をする。
姫野はもう、ただ決まった話を聞けばいいだけだと悟った。
「僕はね、その先生にたくさん助けてもらったんだ。先生だけが僕の味方でいてくれて、先生がいなかったら僕は学校に行けなかった。だからね、由井先生みたいな先生があの学校からいなくなったら、助けてほしいと思った人が、助けてもらえないかもしれない」
「でも、先生が先生を辞めたら野島が独り占めできるんだよ?」
「……独り占め、できなくてもいいよ。本当は、本当はしたいけど、でもそれより僕は、先生に先生を辞めてほしくない」
野島の目は真っ直ぐ前を見ている。意外と頑固。
「それ、先生に言った?」
「言った」
「なんか言われた?」
「笑ってた。野島くんはそう言うような気がしたって。野島くんがどうしても僕に教師を辞めてほしくないと言うなら辞めない、でももう一度考えてって。僕が教師を辞めなかったら、あと1年半、君が卒業するまでは会わないし、連絡もできないからって」
姫野はとつとつと語る野島の横顔をまじまじと見た。
「その先生、って、……男なの?」
野島ははっとした顔をした。それからうっすらと笑った。
「そう。男の人」
「なんだ。そうなんだ」
姫野はくすくす笑った。
野島は珍しいものを見るようにこちらを見ている。
「なんか、しっくり来る。わかんないけど」
「ふふ、なにそれ」
ひとしきり2人で笑ってから、姫野は聞いた。
「寂しくないの?1年半」
「寂しいけど、僕はずっと先生のこと好きな自信がある」
野島は口に手を当てて少しの間、目を閉じた。きれいな横顔だった。
その、ゆい先生とやらを思い浮かべてそんな顔をするのだとしたら。
土屋、気の毒だけど、これは何をどうがんばったってその先生には勝てないね。
姫野は重ねて聞く。
「先生しか味方がいなかったって、なんで?」
野島は首を傾げる。
「男の先生を好きだったからじゃないかな。わかんないけど」
「転校したのもそのせい?」
「でも多分僕が悪かったんだと思う。うじうじしちゃって」
その表情、笑顔の後ろに、何か張りつめたものを感じた。
「だからね、転校してからはいろいろ気をつけようと思ってた。なんとしても周りに合わせなきゃって。でも、そしたら」
野島は姫野を見た。
「初日から、本城くんが姫野くんを彼女だって言った。びっくりしちゃった」
姫野は恥ずかしくなって俯いた。
「でも本当にいいなって思ったんだよ。僕はまだ、男の人を好きにはなりませんってうそぶくのが精一杯だったから」
「……辛かった?前の学校の時」
「少し」
野島は笑う。
こんなにいいやつなのに、誰もそれをわからなかったなんて。
バカだ。
うちの学校ではこんなにうまくやってるし友達もいるし、中川たちにだって好かれてるんだから。
野島が悪かった訳がない。バカだ。そいつらは。
姫野はだんだん腹が立ってきて、口を尖らせた。
「そんな学校、転校して大正解だから。バカばっかりだったんじゃないの」
何も言わなくなった野島を見て、姫野は息を止めた。
*
両手で顔を覆っている野島の隣で、姫野は困りきった様子で佇んでいた。
姫野に事情を聞こうとすると、野島のプライベートだから理由は言えないと言う。
「いいからとにかく野島を泣き止ませてよ」
「えー、何も知らないのに無理だよ」
本城が言い返すと、ぐじゅぐじゅと鼻をすすりながら野島が顔を上げた。
「ごめんね、2人とも、困らせて」
「なんで泣くの。本当やめてよね」
「野島、大丈夫?」
野島は姫野に、ごめんね、と泣き笑いの顔を向けてから、本城に言った。
「姫野くんがすごく優しいこと言うから、いろいろ考えて、今が幸せで泣けたの」
はぁ?意味がわかんない。
と姫野がぶっきらぼうに言った。
姫野は野島に何を言ったんだろう。
それにしても野島はいろんな意味で愛されてるな。
まあとにかく、幸せの涙だったならいいか。
本城は、このかわいい2人の間にあっという間に築かれた不思議な友情に少しだけ嫉妬した。
今日帰ったら抱こう。
場違いなことを思いながら、それでも、野島のお陰で姫野の新しい一面がまた発見できたような気がした。
野島が転校してきてくれてよかった、と、本城は一瞬のうちに思った。
*
「全っ然入んないなー!」
大声で話しかけても土屋は無言のままシュートを打ち続ける。中川はそんな友人を木陰のベンチからずっと見ていた。
木陰にいても暑い。動かなくてもものすごい暑さだ。日向で動いている土屋は汗だくだった。
公園には2人の他には誰もいない。ただ、土屋のドリブルとシュートの音が響いている。
2年でレギュラー争いに食い込む実力のある土屋のシュートが、さっきから全然入らない。
「あっちい」
呟きながら、土屋の胸中を推し量る。
学校を出て公園に来る途中、土屋は野島の話を続けた。
「そのバレー部引率してた先生見たとたん野島がビクッてなって」
「うん」
「ビクッてなった野島もまじかわいいな、とか思ってたら」
「はいはい」
「そっから野島の体って敏感なのかなとか空想にふけってたら」
「はいはいはいはいもうわかったから先に進め」
「なんか、その先生が、すげぇ怪しくて」
「見た目が?」
「いーや、見た目はメガネで髪短くて真面目そうな、優男っつーの?なんかつまんなそうなやつだった。バレー部の引率だけあって背は高かったけど。なんでか野島が逃げて、そいつがそれを追ってってさ」
「うん」
「少しして2人で戻って来て、なんか野島と目合わせて笑い合って」
「……うん」
土屋はそこで小さくため息をついた。
「なんかさー、絶対怪しい。付き合ってるみたいに見えた」
「嘘だろ、先生でしょ?しかも男?」
「あり得なくはないんじゃね?変な時期に転校してきたのもその関係だったりして、とか思ったら全然寝られなかった」
中川は土屋の顔を見た。
「お前、野島のこと、本気だったの?」
土屋はゆっくり瞬きをした。
「わかんね」
「ふぅん」
住宅街を抜け、視界が一気に開けて、バスケットゴールのある公園が見えた。
「告んないの?」
「負け戦はしたくない」
「お前女の子にモテんだからわざわざ男狙うなよな」
「わざわざ狙ったわけじゃねえよ」
「まぁな……かわいいけどさ……」
「あーあ。次はドMの女狙おう」
「きゃー最低だわ土屋くん」
公園に入ると土屋はおもむろにボールを取り出し、練習を始めた。
それからもう1時間は経っていた。
ひたすらシュート練習ばかりして、流石に暑さに耐えられなくなったのか、土屋は中川の隣に来てどかりと座った。こめかみから首へ、汗が伝い落ちている。同性から見ても、モテる理由はわかりすぎるほどわかる。
「俺が女だったらお前のこと好きになってやるのにな」
中川の言葉に、土屋は声をあげて笑い、言う。
「ほんとだよ。横に居んのが女だったら、慰めろっつっていろいろ迫れるのによ」
「え、ここで?」
「燃えない?青姦」
「燃えない。大体女の子は嫌がるだろ」
「それがいいんじゃん。やめて恥ずかしいとか抵抗すんのをうるせえよっつって押さえつけて」
「……野島がそんな目に合わなくて本当によかったよ」
「野島にはしない。あいつだったら大事にする」
「嘘くさい」
「それがなんで横に居んのがお前なんだよ」
「お前が来いって言ったんだろ」
「言ったっけ?」
「はい、ありがとうの気持ちを形にして」
中川は手のひらを土屋に差し出す。
「仕方ねぇな、妹の友達を紹介してやる」
「嘘だよね」
「おう。なんでわかった」
「お前妹いないもんね」
「うん」
「くそおおおおおお!」
誰もいない公園に、中川の悲しい叫びがこだまする。
部活のバッグからタオルを出して汗を拭く土屋に、ジュースおごれ、2本な、と中川が言う。
土屋は中川を見てニヤ、と笑い、言った。
「でもお前が女だったらこんな仲良くなってねえな」
「まあね」
「だったらいいわ。今の方が」
髪をかき上げる土屋の耳で、ピアスが光った。
「そんな熱い言葉はいらない。飲み物買って来い」
「くそ、はぐらかそうと思ったのに」
「走れ、走って行け」
土屋が、細い道路を挟んだ向かい側に見える赤い自販機まで全速力で走って行った。
「はは。早っ。さすが」
中川は1人、ベンチで笑い転げた。
-end-