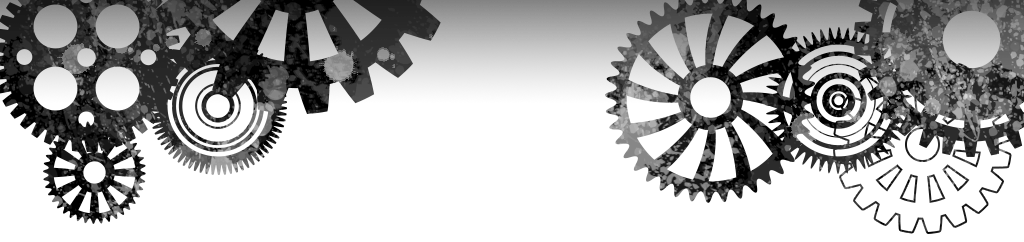焼けつくような夏
夜は過ごしやすい気温だし干し草をかぶれば十分寝られる。宿が見つかったのは幸運だった。
この先はこういうわけにゃいかねえからな。
そっとヒル魔は厩舎から忍び出た。すうすうと寝息を立てる連中を起こさないように、そっと。
暗闇。
風に乗って馬や牛の匂い。
目が闇に慣れると星明かり。
土を踏みしめて数歩ほど歩く。
遠目には黒々と樹木の影。
つい先ほどまでは部員たちと同じようによく眠っていた。その眠りの中で音を聞いた。
風を切る鋭い音。
キックの音だ。
あの男とは中学で知り合った。愛すべき巨漢としつこく誘って仲間に引き込んだ。3人でチームを始めた。
デビルバッツというチーム。目指すはクリマスボウル。
3人で同じ目標を目指すことに何の疑問も懸念もなかった。
あの男のキックは豪快だ。コントロールのあやふやな荒れ球、でも飛距離は誰にも負けない。
力強くぐんと伸びる球。
まるであいつそのものみたいだ。そう思ったことを覚えている。
すぐに惹かれた。
まっすぐなまなざし。日に焼けた頬。笑うと少し優しくなる目尻。
あの男と、巨漢と、3人で笑いあった日。毎日毎日のきついトレーニング、額に汗してでもちっとも苦でも何でもなかった。あの日々は自分の生き甲斐でもあったのだ。
けれど目を覚ますと隣にあの男はいない。
見上げると満天の星空。
静謐な。
──…………
今も鮮明によみがえる。耳の奥にあの男の声、肩に置かれる手。
どうしているだろう。
あの男もこの星を見ているだろうか。
遠くの空の下にいるあいつは。
考えても詮ないことだ、そう振り切ろうとした。それでも繰り返し押し寄せる。胸の中の思い。
目に映るのは満天の星。墨を流したような漆黒の空に輝く星々。
吸い込まれるような夜空。
ただ見上げる。
「ヒル魔」
控えめな声を背後に聞いた。
振り返らずとも分かる。巨漢の親友だ。
自分と同じように土を踏みしめる音。近づいてきた。
「どうしたんだい」
巨漢の声は穏やかだ。まるでこの夜のように。
「…………」
何と答えるべきか少し迷った。
すぐに気を取り直した。
「ケケ、考え事だ」
「考え事?」
「そうだ」
「どんなことだい」
「決まってンだろ、明日のトレーニング」
「ああ」
巨漢はヒル魔の背中に手を当てる。
「それもいいけど、まずは寝なくちゃ」
「…………」
「溝六先生だっているんだし。ヒル魔が一人で考えることないよ」
いたわるような声。
「……そうだな」
目を伏せてヒル魔は笑った。声を出さずに。
「戻ろう」
促されて踵を返す。
心優しい巨漢とともに。
巨漢の目。それはちらとヒル魔に当てられた。気がかりそうに。ヒル魔は気づかない。
──こっからだ
ヒル魔は思う。決然と。
これからが正念場なのだ。
静かに胸の中の影にささやく。心からの言葉。
二つの人影は厩舎へと消えた。
──テメーは戻る
馴染みの型枠大工は何か取りに行くと言ってこの場を離れた。すぐ戻るから、頑張ってな厳ちゃん、という言葉を残して。陽炎の立つ道路を車は走っていった。それを見送って、ムサシは再びスコップを握る。
小さな土間の修理。作業そのものは単純で、型枠のあとはコンクリートを流し込むだけだ。
平家建ての一軒家。その玄関先でトロ桶に向かう。今日も晴天で朝から気温は上がる一方だ。ランニングにニッカポッカ、頭にはタオル。タオルで止め切れない汗のしずくが顔を流れる。
セメントと砂を混ぜ終わったので砂利を入れた。全体が均一になるよう丁寧に混ぜていく。コンクリートはモルタルと違って砂利が入るため格段に重い。力を込めてスコップを入れる。力を込めてスコップを返す。地味な作業だが強度に関わるからおろそかになどできない。
息が切れるようなことはないしムサシの腕も腰も強靭だ。それに何と言ってもまだ若い。作業は別に苦にはならない。ただこの暑さはたまらねえな。
依頼された家と隣家の間には高木があり、そこから蝉の音が聞こえる。やかましいその声はまるで暑さを増幅させるようだ。
トロ桶の角まで丁寧にスコップを入れる。全体が馴染むまでひたすら混ぜて練ってを繰り返すのだ。こういう単純作業は別に嫌いではない。
顔から首をつたう汗。中腰のままムサシはスコップを離した。首のタオルで汗をこする。
ちくり。
──?
頭の片隅、痛みのようなもの。
こんなもの滅多に感じたことはない。何だろう。
暑気のせいかと軽く考えながら再びスコップを握る。
ザッ。
──それとも
ザッ。
──誰か噂でもしてやがるか
不意に胸にきた。
──…………
遠い笑い声。
不敵な悪魔笑いの声。
おのれの手が止まる。
思わずムサシは立ち尽くした。
俺は何を。そうは思う。何を急に思い出してる。
こんなところで立ち止まっている暇はない。目の前の仕事に集中するべきだ。なのに幻覚のようなかすかな笑い声が耳について離れない。
道路の方へ目をやった。誰もいない、当たり前だ。ただゆらゆらと陽炎の立つ道路。ひとっ子一人いはしない。
──戻れない
急激に胸を襲う思い。
もう戻れないんだろうか。
あの日に、自分は。
考えても詮ないことだ、そう振り切ろうとした。それでも繰り返し押し寄せる。胸の中の思い。
「厳ちゃん」
我に返った。振り向くとこの家の老女。工事中の玄関ではなく、反対側の庭先からこちらに回ってきたらしい。
「暑いでしょう。お茶をどうぞ」
お盆にはコップに麦茶。
少しぎこちなくムサシは笑った。
「ありがとう。おばさん」
スコップを置いてまた汗を拭った。
わずかな会話。だが声をかけられたことで何とか気を取り直した。
ありがたくもらおう。ぐっと飲んでそれからまた仕事だ。
そう思うと胸の痛みが少しまぎれるような気がした。
忘れることなどない。
胸の中の影。
暑くても日が暮れてからも。
まるで焼けつくような夏。
隣には誰もいない。
──焼けつくような夏。
この先はこういうわけにゃいかねえからな。
そっとヒル魔は厩舎から忍び出た。すうすうと寝息を立てる連中を起こさないように、そっと。
暗闇。
風に乗って馬や牛の匂い。
目が闇に慣れると星明かり。
土を踏みしめて数歩ほど歩く。
遠目には黒々と樹木の影。
つい先ほどまでは部員たちと同じようによく眠っていた。その眠りの中で音を聞いた。
風を切る鋭い音。
キックの音だ。
あの男とは中学で知り合った。愛すべき巨漢としつこく誘って仲間に引き込んだ。3人でチームを始めた。
デビルバッツというチーム。目指すはクリマスボウル。
3人で同じ目標を目指すことに何の疑問も懸念もなかった。
あの男のキックは豪快だ。コントロールのあやふやな荒れ球、でも飛距離は誰にも負けない。
力強くぐんと伸びる球。
まるであいつそのものみたいだ。そう思ったことを覚えている。
すぐに惹かれた。
まっすぐなまなざし。日に焼けた頬。笑うと少し優しくなる目尻。
あの男と、巨漢と、3人で笑いあった日。毎日毎日のきついトレーニング、額に汗してでもちっとも苦でも何でもなかった。あの日々は自分の生き甲斐でもあったのだ。
けれど目を覚ますと隣にあの男はいない。
見上げると満天の星空。
静謐な。
──…………
今も鮮明によみがえる。耳の奥にあの男の声、肩に置かれる手。
どうしているだろう。
あの男もこの星を見ているだろうか。
遠くの空の下にいるあいつは。
考えても詮ないことだ、そう振り切ろうとした。それでも繰り返し押し寄せる。胸の中の思い。
目に映るのは満天の星。墨を流したような漆黒の空に輝く星々。
吸い込まれるような夜空。
ただ見上げる。
「ヒル魔」
控えめな声を背後に聞いた。
振り返らずとも分かる。巨漢の親友だ。
自分と同じように土を踏みしめる音。近づいてきた。
「どうしたんだい」
巨漢の声は穏やかだ。まるでこの夜のように。
「…………」
何と答えるべきか少し迷った。
すぐに気を取り直した。
「ケケ、考え事だ」
「考え事?」
「そうだ」
「どんなことだい」
「決まってンだろ、明日のトレーニング」
「ああ」
巨漢はヒル魔の背中に手を当てる。
「それもいいけど、まずは寝なくちゃ」
「…………」
「溝六先生だっているんだし。ヒル魔が一人で考えることないよ」
いたわるような声。
「……そうだな」
目を伏せてヒル魔は笑った。声を出さずに。
「戻ろう」
促されて踵を返す。
心優しい巨漢とともに。
巨漢の目。それはちらとヒル魔に当てられた。気がかりそうに。ヒル魔は気づかない。
──こっからだ
ヒル魔は思う。決然と。
これからが正念場なのだ。
静かに胸の中の影にささやく。心からの言葉。
二つの人影は厩舎へと消えた。
──テメーは戻る
馴染みの型枠大工は何か取りに行くと言ってこの場を離れた。すぐ戻るから、頑張ってな厳ちゃん、という言葉を残して。陽炎の立つ道路を車は走っていった。それを見送って、ムサシは再びスコップを握る。
小さな土間の修理。作業そのものは単純で、型枠のあとはコンクリートを流し込むだけだ。
平家建ての一軒家。その玄関先でトロ桶に向かう。今日も晴天で朝から気温は上がる一方だ。ランニングにニッカポッカ、頭にはタオル。タオルで止め切れない汗のしずくが顔を流れる。
セメントと砂を混ぜ終わったので砂利を入れた。全体が均一になるよう丁寧に混ぜていく。コンクリートはモルタルと違って砂利が入るため格段に重い。力を込めてスコップを入れる。力を込めてスコップを返す。地味な作業だが強度に関わるからおろそかになどできない。
息が切れるようなことはないしムサシの腕も腰も強靭だ。それに何と言ってもまだ若い。作業は別に苦にはならない。ただこの暑さはたまらねえな。
依頼された家と隣家の間には高木があり、そこから蝉の音が聞こえる。やかましいその声はまるで暑さを増幅させるようだ。
トロ桶の角まで丁寧にスコップを入れる。全体が馴染むまでひたすら混ぜて練ってを繰り返すのだ。こういう単純作業は別に嫌いではない。
顔から首をつたう汗。中腰のままムサシはスコップを離した。首のタオルで汗をこする。
ちくり。
──?
頭の片隅、痛みのようなもの。
こんなもの滅多に感じたことはない。何だろう。
暑気のせいかと軽く考えながら再びスコップを握る。
ザッ。
──それとも
ザッ。
──誰か噂でもしてやがるか
不意に胸にきた。
──…………
遠い笑い声。
不敵な悪魔笑いの声。
おのれの手が止まる。
思わずムサシは立ち尽くした。
俺は何を。そうは思う。何を急に思い出してる。
こんなところで立ち止まっている暇はない。目の前の仕事に集中するべきだ。なのに幻覚のようなかすかな笑い声が耳について離れない。
道路の方へ目をやった。誰もいない、当たり前だ。ただゆらゆらと陽炎の立つ道路。ひとっ子一人いはしない。
──戻れない
急激に胸を襲う思い。
もう戻れないんだろうか。
あの日に、自分は。
考えても詮ないことだ、そう振り切ろうとした。それでも繰り返し押し寄せる。胸の中の思い。
「厳ちゃん」
我に返った。振り向くとこの家の老女。工事中の玄関ではなく、反対側の庭先からこちらに回ってきたらしい。
「暑いでしょう。お茶をどうぞ」
お盆にはコップに麦茶。
少しぎこちなくムサシは笑った。
「ありがとう。おばさん」
スコップを置いてまた汗を拭った。
わずかな会話。だが声をかけられたことで何とか気を取り直した。
ありがたくもらおう。ぐっと飲んでそれからまた仕事だ。
そう思うと胸の痛みが少しまぎれるような気がした。
忘れることなどない。
胸の中の影。
暑くても日が暮れてからも。
まるで焼けつくような夏。
隣には誰もいない。
──焼けつくような夏。
【END】
1/1ページ