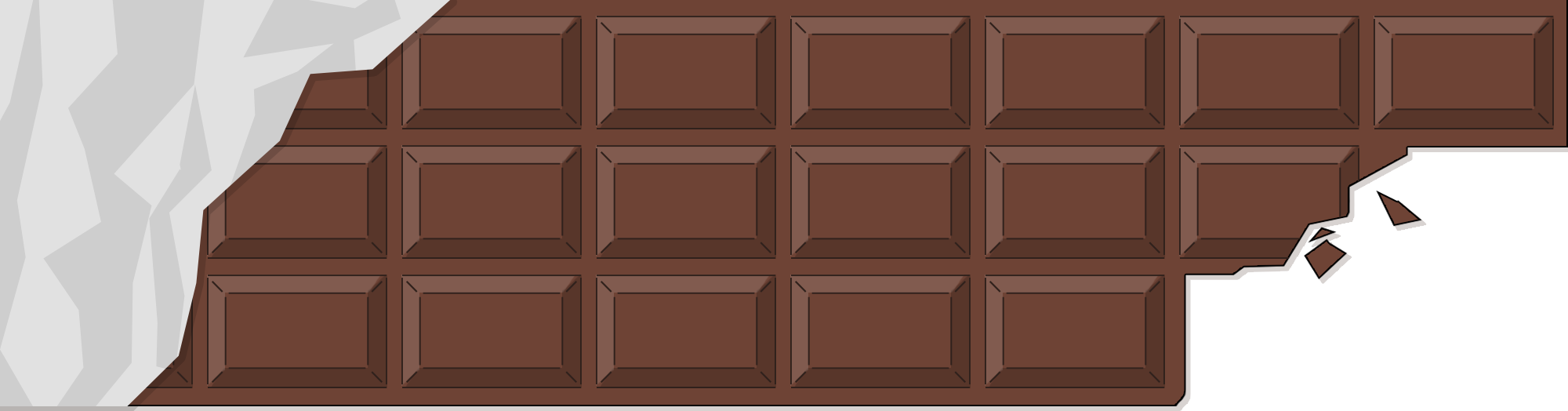バレンタインデイ・キッス
ノートパソコンを抱えてスタッフルームを出る。廊下を歩いている時からある気配を感じていたが、その気配は職員出口まで来るとますます濃厚になった。シューズロッカーから自分の靴を取り出して履き替える。そうしながら、ヒル魔は後ろに向かって声をかけた。
「おう、麻衣、カナ。何か用か」
くすくす、という声がきゃっと言う驚きに変わった。
「せんせー、後ろに目がついてんの?!」
「ケケ、お前らの気配なんか丸わかりだ」
物陰に隠れながら後をついて来ていたのは、やはりジュニアクラスの教え子たちだった。二人とも、徒競走の得意な活発な生徒だ。
「で? 俺ァ急いでるんでな、出すもの早く出しやがれ」
「えー、ひどーい!」
口を尖らせながらも女の子たちが差し出したのは、綺麗にリボンがかけられた小箱。
「義理だからね、義理! いつもお世話になってるし!」
満面の笑み、きらきらと輝く瞳。ヒル魔にさえまぶしい、愛しいと感じさせる若さ、可愛らしさ。女の子たちはヒル魔が受け取るなり、わっと駆け出して行ってしまった。
「じゃーねー、せんせー!」
ヒル魔は──苦笑などという表情を滅多に見せることのないこの男が──苦笑して玄関を出た。武藤麻衣、山下佳奈。最初はヒル魔を露骨に警戒していた二人である。まだ小5とはいえ、女の子の勘は鋭い。ヒル魔が独り身ではないことももう勘づいているらしい。だからこその”義理”チョコなのだが、素直に嬉しい。おそらく、さんざん二人で騒いで相談して、大騒ぎのあげく選んだものなのだろう。きゃっきゃと楽しそうなその場面を思い描いて、車に乗り込みながらまたヒル魔はふと笑んだ。
──?
その瞬間、まさに降って湧いた直感。二人の女生徒の行動から湧いた直感。あいつ、まさか。
実は今年はムサシとヒル魔が同棲を始めてちょうど10年目に当たる。そもそも、バレンタインとは男性が大切な人に贈り物をする日だったという説もある。そのため、今年は娯楽も兼ねてお互いにチョコレートを贈り合おうとふたりは以前から話していた。
話し合ってから間もなく、ヒル魔はこれなら良さそうだと思うものを決めて購入しておいた。職場の最寄駅の近くにあるショコラティエで、タブレット状の美しいチョコレートが一番人気の店だ。だがショーケースに並んださまざまな菓子を見てヒル魔が選んだのは、シンプルなチョコレートバーの詰め合わせだった。もともと、ムサシもヒル魔も甘いものを好むタイプではない。ただふたりとも家でのPC作業などが深夜にまで及ぶこともある。そうした時、コーヒーと共に少しの甘味をつまむこともあった。そのようなケースを考えて、ヒル魔は恋人への贈り物を決定した。一本ずつ丁寧に包装された、長方形のチョコレートバー。店頭で試食させてもらったそれはカカオの芳醇な香りと甘みがヒル魔の気に入った。さっそくそれをプレゼント用に包んでもらい、とっくにヒル魔は自室のある場所に保管していた。
だが一方、あいつはどうだろう。ハンドルを操りながらヒル魔は考える。あの糞ジジイ、一人で上手くチョコなど買えるだろうか。まさかこのところ様子がおかしかったのは、買い物──それも、ヒル魔への贈り物──で悩んでいたせいなのではないだろうか。
いや、とヒル魔は自分に思う。まさかそんなあまりにも型通りすぎることがあるだろうか。贈り物に悩んで挙動不審になるほどムサシも子供ではないだろう。第一、考えすぎたら禿げるぞ糞ジジイ。
とにかく、帰ろう。帰って飯を食って、チョコレートを贈り合う。その時にでも、真相は明かされるだろう。ヒル魔にはそんな気がした。
昨日は一日口を聞かなかったふたりだが、何事もなかったようにヒル魔は帰宅した。先に帰っていたムサシもそれは同様で、何事もなくおかえりのキスをする。それから普段より少し豪華な食事を済ませ、ムサシとヒル魔はそれぞれの贈り物を持って居間のソファに落ち着いた。
「こりゃ、美味そうだな」
ふたりで一緒に包みをほどきながら、蓋を開けたムサシが言う。開けた瞬間から立ちのぼる甘い芳香に顔をほころばせた。
「テメーのも美味そうだ」
ムサシがくれたのはシックなブラウンの薄い小箱。ブルーのリボンをほどいて蓋を開けると、いくつものキューブチョコが現れた。ふわりと華やかな洋酒の香り。
ありがとう。ああ、サンキューな。礼を言い合ってから、ヒル魔は軽い調子で言い出してみた。
「なあ、ムサシ」
「なんだ」
「テメーなんか困ってたんじゃねえか。変だったぞここんとこ」
ムサシの表情が変わった。笑顔から困惑したような顔へ。口はつぐんだままだ。
ヒル魔は穏やかに言葉を続けた。
「言いたくねえなら言わなくていい。けど俺たちはパートナーだろ。なんかあるなら隠さねえでほしい。俺はテメーを助けたい。ただもちろん、テメーが一人で」
「ヒル魔」
「? なんだ」
ムサシは明らかに逡巡した。それから、思い切ったように口を開いて、話し始めた。
ムサシの告白。要するに、ほぼヒル魔の直感通りだったのだ。もちろん、意外なこともあったのだけれど。
今月7日、バレンタインデーのちょうど一週間前。デザイン部の女性社員がムサシに持ちかけた話があった。得意先の家の娘が──以前、武蔵工務店がリフォームを手がけた家の小学生である──ムサシにチョコレートを渡したいと言っている。会ってやってほしい、と。バレンタイン当日はヒル魔とゆっくり過ごしたいと考えていたムサシは内心、困ったなと思った。だが大いに安心したことに、件の小学生は12日を指定してきたのである。次の日も、そのまた次の日も塾があるから、と。
それならということでムサシは承諾した。橋渡し役を務めてくれた女性社員には、よろしく頼むと伝えておいた。駅での待ち合わせはそういうことだったのである。ついでに、とムサシは考えた。チョコレートを受け取ったらそのあと駅ビルに立ち寄ろう。大切な恋人に贈る菓子をそこで手に入れることにしようと考えたのである。ところがそうはならなかった。
7日の夜、駅前に用事があったムサシはふとチョコレート売り場を見てみるかという気になった。
そうして駅ビルの一階、最も目立つ位置に設けられた売り場に出かけてみて、面食らってしまった。何しろ種類が豊富すぎるしどこもかしこも華やかにきらびやかすぎて、目がチカチカしてしまうような感覚を味わった。これではいけない。とにかく一旦退散し、その日からスマホと睨めっこする時間が増えた。形状、味、どの店のものが良いか。大切な恋人への、大切な贈り物である。一心不乱に考えているうち、ムサシの行動はおかしくなった。毎日、仕事からの帰りがけにあちこちのバレンタイン売り場を巡って歩く。まさかとは思うがヒル魔と鉢合わせなどすることのないよう、ヒル魔のスケジュールをしつこく尋ねた。いよいよこれと思うものを決めたのはバレンタインの前々日、やっと買いに行けるとほっとして思い出した。大事な待ち合わせがあるではないか。母親を同伴した、小6の女の子。一生懸命に手作りして、心を込めて包んだのであろう可愛らしい箱を手にして厚く礼を述べ、それからやっと自分の買い物を済ませてムサシは帰宅した。もらったことをヒル魔に話さなかったのは、なんだか気恥ずかしかったためである。一人でこっそり自室で開けた箱には綺麗に並んだ三つのトリュフ。口に入れながら、(女の子には申し訳ないが)ますますムサシはヒル魔への贈り物はどうだろう、これで良かっただろうかと悩んだ。
「俺に聞けばよかったじゃねえか。どんなんがいいんだ、とか」
率直にヒル魔はムサシに言った。全く、この男はどこまで朴訥にできているのだろう。
うーん……とムサシは妙な声を出した。
「それがな」
「?」
「俺はほら、その……すぐお前に頼りたくなるからな。こういうことは一人でするもんだ、と思ってな」
「…………」
ヒル魔がくれたチョコレート。その小箱を大切に抱えながら、なんだかムサシは気恥ずかしい。ヒル魔はその横顔をじっと見る。昨日一日抱えていた寂しさ、懸念が溶けていくのを感じながら。同時に何とも言えないおかしさ、そして愛しさがあらためて胸にせまるのを感じながら。
「ムサシ」
「?」
こちらを向いた恋人に、ヒル魔はキスをした。ここ一週間のうちでいちばん、いちばん甘いキスを贈ってやった。
「食わせてやるからそれよこせ」
「あ?」
ムサシの手から奪い取ったチョコレート。包みを剥がして、細長いそれをパキッと折って口にくわえた。
「ン」
「…………」
ムサシはヒル魔の意図を察した。黙って、ゆっくりと口で受け取る。ふたりの唇が触れ合った。
(もっと、だろ?)
恋人にぴったり体を寄せて、いたずらっぽくヒル魔は目で問いかける。
ムサシも目で応えた。ああ、もっとだな。
「…………」
「…………」
口にせずとも伝わる思い。大切な想い人への。チョコレートに乗せてふたりは語る。ヒル魔の口からムサシの口へ。
やがてムサシはヒル魔の肩を抱いて引き寄せた。恋人への贈り物。香り高いキューブチョコを口に入れ、恋人の唇へ。交互に、ふたりはたわむれを繰り返し始めた。
(なあ、ヒル魔)
(…………)
(気に入ったか? これ)
(たりめーだ。テメーが選んだモンだからな)
ヒル魔の思い。ムサシの想い。チョコレートとともにふたりの心も柔らかく溶けていく。
はずむ気持ち、しっとりと穏やかな時間。恋人たちの遊戯は続く。やがて艶めいた忍び笑い。
くす、くす。
くく、く。
くす、くす。
くく、く。
「おう、麻衣、カナ。何か用か」
くすくす、という声がきゃっと言う驚きに変わった。
「せんせー、後ろに目がついてんの?!」
「ケケ、お前らの気配なんか丸わかりだ」
物陰に隠れながら後をついて来ていたのは、やはりジュニアクラスの教え子たちだった。二人とも、徒競走の得意な活発な生徒だ。
「で? 俺ァ急いでるんでな、出すもの早く出しやがれ」
「えー、ひどーい!」
口を尖らせながらも女の子たちが差し出したのは、綺麗にリボンがかけられた小箱。
「義理だからね、義理! いつもお世話になってるし!」
満面の笑み、きらきらと輝く瞳。ヒル魔にさえまぶしい、愛しいと感じさせる若さ、可愛らしさ。女の子たちはヒル魔が受け取るなり、わっと駆け出して行ってしまった。
「じゃーねー、せんせー!」
ヒル魔は──苦笑などという表情を滅多に見せることのないこの男が──苦笑して玄関を出た。武藤麻衣、山下佳奈。最初はヒル魔を露骨に警戒していた二人である。まだ小5とはいえ、女の子の勘は鋭い。ヒル魔が独り身ではないことももう勘づいているらしい。だからこその”義理”チョコなのだが、素直に嬉しい。おそらく、さんざん二人で騒いで相談して、大騒ぎのあげく選んだものなのだろう。きゃっきゃと楽しそうなその場面を思い描いて、車に乗り込みながらまたヒル魔はふと笑んだ。
──?
その瞬間、まさに降って湧いた直感。二人の女生徒の行動から湧いた直感。あいつ、まさか。
実は今年はムサシとヒル魔が同棲を始めてちょうど10年目に当たる。そもそも、バレンタインとは男性が大切な人に贈り物をする日だったという説もある。そのため、今年は娯楽も兼ねてお互いにチョコレートを贈り合おうとふたりは以前から話していた。
話し合ってから間もなく、ヒル魔はこれなら良さそうだと思うものを決めて購入しておいた。職場の最寄駅の近くにあるショコラティエで、タブレット状の美しいチョコレートが一番人気の店だ。だがショーケースに並んださまざまな菓子を見てヒル魔が選んだのは、シンプルなチョコレートバーの詰め合わせだった。もともと、ムサシもヒル魔も甘いものを好むタイプではない。ただふたりとも家でのPC作業などが深夜にまで及ぶこともある。そうした時、コーヒーと共に少しの甘味をつまむこともあった。そのようなケースを考えて、ヒル魔は恋人への贈り物を決定した。一本ずつ丁寧に包装された、長方形のチョコレートバー。店頭で試食させてもらったそれはカカオの芳醇な香りと甘みがヒル魔の気に入った。さっそくそれをプレゼント用に包んでもらい、とっくにヒル魔は自室のある場所に保管していた。
だが一方、あいつはどうだろう。ハンドルを操りながらヒル魔は考える。あの糞ジジイ、一人で上手くチョコなど買えるだろうか。まさかこのところ様子がおかしかったのは、買い物──それも、ヒル魔への贈り物──で悩んでいたせいなのではないだろうか。
いや、とヒル魔は自分に思う。まさかそんなあまりにも型通りすぎることがあるだろうか。贈り物に悩んで挙動不審になるほどムサシも子供ではないだろう。第一、考えすぎたら禿げるぞ糞ジジイ。
とにかく、帰ろう。帰って飯を食って、チョコレートを贈り合う。その時にでも、真相は明かされるだろう。ヒル魔にはそんな気がした。
昨日は一日口を聞かなかったふたりだが、何事もなかったようにヒル魔は帰宅した。先に帰っていたムサシもそれは同様で、何事もなくおかえりのキスをする。それから普段より少し豪華な食事を済ませ、ムサシとヒル魔はそれぞれの贈り物を持って居間のソファに落ち着いた。
「こりゃ、美味そうだな」
ふたりで一緒に包みをほどきながら、蓋を開けたムサシが言う。開けた瞬間から立ちのぼる甘い芳香に顔をほころばせた。
「テメーのも美味そうだ」
ムサシがくれたのはシックなブラウンの薄い小箱。ブルーのリボンをほどいて蓋を開けると、いくつものキューブチョコが現れた。ふわりと華やかな洋酒の香り。
ありがとう。ああ、サンキューな。礼を言い合ってから、ヒル魔は軽い調子で言い出してみた。
「なあ、ムサシ」
「なんだ」
「テメーなんか困ってたんじゃねえか。変だったぞここんとこ」
ムサシの表情が変わった。笑顔から困惑したような顔へ。口はつぐんだままだ。
ヒル魔は穏やかに言葉を続けた。
「言いたくねえなら言わなくていい。けど俺たちはパートナーだろ。なんかあるなら隠さねえでほしい。俺はテメーを助けたい。ただもちろん、テメーが一人で」
「ヒル魔」
「? なんだ」
ムサシは明らかに逡巡した。それから、思い切ったように口を開いて、話し始めた。
ムサシの告白。要するに、ほぼヒル魔の直感通りだったのだ。もちろん、意外なこともあったのだけれど。
今月7日、バレンタインデーのちょうど一週間前。デザイン部の女性社員がムサシに持ちかけた話があった。得意先の家の娘が──以前、武蔵工務店がリフォームを手がけた家の小学生である──ムサシにチョコレートを渡したいと言っている。会ってやってほしい、と。バレンタイン当日はヒル魔とゆっくり過ごしたいと考えていたムサシは内心、困ったなと思った。だが大いに安心したことに、件の小学生は12日を指定してきたのである。次の日も、そのまた次の日も塾があるから、と。
それならということでムサシは承諾した。橋渡し役を務めてくれた女性社員には、よろしく頼むと伝えておいた。駅での待ち合わせはそういうことだったのである。ついでに、とムサシは考えた。チョコレートを受け取ったらそのあと駅ビルに立ち寄ろう。大切な恋人に贈る菓子をそこで手に入れることにしようと考えたのである。ところがそうはならなかった。
7日の夜、駅前に用事があったムサシはふとチョコレート売り場を見てみるかという気になった。
そうして駅ビルの一階、最も目立つ位置に設けられた売り場に出かけてみて、面食らってしまった。何しろ種類が豊富すぎるしどこもかしこも華やかにきらびやかすぎて、目がチカチカしてしまうような感覚を味わった。これではいけない。とにかく一旦退散し、その日からスマホと睨めっこする時間が増えた。形状、味、どの店のものが良いか。大切な恋人への、大切な贈り物である。一心不乱に考えているうち、ムサシの行動はおかしくなった。毎日、仕事からの帰りがけにあちこちのバレンタイン売り場を巡って歩く。まさかとは思うがヒル魔と鉢合わせなどすることのないよう、ヒル魔のスケジュールをしつこく尋ねた。いよいよこれと思うものを決めたのはバレンタインの前々日、やっと買いに行けるとほっとして思い出した。大事な待ち合わせがあるではないか。母親を同伴した、小6の女の子。一生懸命に手作りして、心を込めて包んだのであろう可愛らしい箱を手にして厚く礼を述べ、それからやっと自分の買い物を済ませてムサシは帰宅した。もらったことをヒル魔に話さなかったのは、なんだか気恥ずかしかったためである。一人でこっそり自室で開けた箱には綺麗に並んだ三つのトリュフ。口に入れながら、(女の子には申し訳ないが)ますますムサシはヒル魔への贈り物はどうだろう、これで良かっただろうかと悩んだ。
「俺に聞けばよかったじゃねえか。どんなんがいいんだ、とか」
率直にヒル魔はムサシに言った。全く、この男はどこまで朴訥にできているのだろう。
うーん……とムサシは妙な声を出した。
「それがな」
「?」
「俺はほら、その……すぐお前に頼りたくなるからな。こういうことは一人でするもんだ、と思ってな」
「…………」
ヒル魔がくれたチョコレート。その小箱を大切に抱えながら、なんだかムサシは気恥ずかしい。ヒル魔はその横顔をじっと見る。昨日一日抱えていた寂しさ、懸念が溶けていくのを感じながら。同時に何とも言えないおかしさ、そして愛しさがあらためて胸にせまるのを感じながら。
「ムサシ」
「?」
こちらを向いた恋人に、ヒル魔はキスをした。ここ一週間のうちでいちばん、いちばん甘いキスを贈ってやった。
「食わせてやるからそれよこせ」
「あ?」
ムサシの手から奪い取ったチョコレート。包みを剥がして、細長いそれをパキッと折って口にくわえた。
「ン」
「…………」
ムサシはヒル魔の意図を察した。黙って、ゆっくりと口で受け取る。ふたりの唇が触れ合った。
(もっと、だろ?)
恋人にぴったり体を寄せて、いたずらっぽくヒル魔は目で問いかける。
ムサシも目で応えた。ああ、もっとだな。
「…………」
「…………」
口にせずとも伝わる思い。大切な想い人への。チョコレートに乗せてふたりは語る。ヒル魔の口からムサシの口へ。
やがてムサシはヒル魔の肩を抱いて引き寄せた。恋人への贈り物。香り高いキューブチョコを口に入れ、恋人の唇へ。交互に、ふたりはたわむれを繰り返し始めた。
(なあ、ヒル魔)
(…………)
(気に入ったか? これ)
(たりめーだ。テメーが選んだモンだからな)
ヒル魔の思い。ムサシの想い。チョコレートとともにふたりの心も柔らかく溶けていく。
はずむ気持ち、しっとりと穏やかな時間。恋人たちの遊戯は続く。やがて艶めいた忍び笑い。
くす、くす。
くく、く。
くす、くす。
くく、く。
【END】
2/2ページ