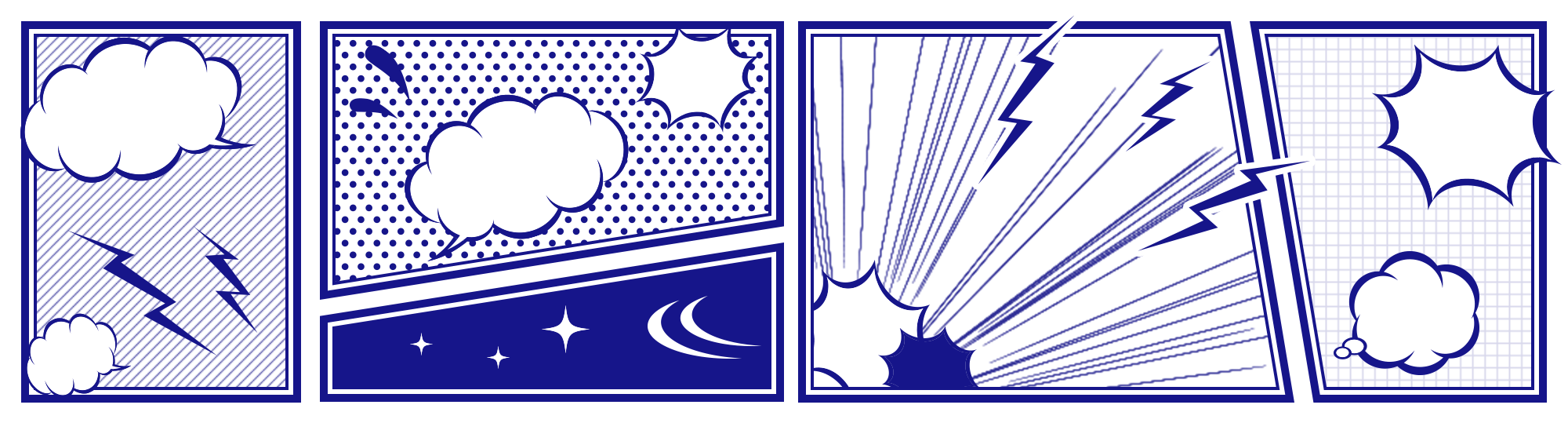杜王町編・第9話 ラット~ネズミ(虫食い)~
名前変換
この小説の夢小説設定ジョジョの奇妙な冒険連載夢小説です、第3部からのスタートです。
詳しくは『設定・注意書き』をお読みください。
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
「でも承太郎さん・・・日没までにって言いますけど、こんな広い田園地帯に逃げたちっこいネズミをどうやって追うつもりなんスか?」
「『シートン動物記』の著者であるE・T・シートンは『追跡不可能な動物はいない』と言っている。
走るのが早い動物よりも地形と風向き、動物の習性を研究している人間の方がちょっぴり有利というわけだ・・・いずれ追いつく。
ネズミという奴は相当に視力は弱く、臭いやヒゲの触覚で通り道を決める。
だから、縄張り内では自分の通り道は決まっていて、知らない道は通りたがらない。
つまり、やつの逃げるのは間違いなく例の用水路の通り道だ。
そしてネズミは常に何かを食っていないと10数時間で餓死する、食事量は実に体重の3分の1。
逃げながらもどこかで何かをかじっていないといけないというわけさ」
ネズミの被害を受けた農家から出て、用水路に向かう途中の畑を物色すると、ネズミのかじった跡が残されていた。
「茎の噛み口がまだ新しい・・・つい、今までここで食事中だったというわけだな」
「やったッ!こいつはスゲェッすッ!追いつめられるぜっ、野郎をよォ~~ッ!」
――――――――――――
用水路まで戻ってきた4人。
畑から下りたすぐ近くに足跡を見つけた、まだ新しい。
「日没まであと3時間、風は無し・・・住宅地まで1.5km。
自分の縄張りにいる者は人間だろうが同じネズミであろうが皆殺し・・・自分さえよけりゃあいいという・・・もはや、この地球上に生きていていい生物じゃあないな、こいつは・・・」
そして4人は仕掛けた罠のある奴の巣の排水溝へ・・・。
「仕掛けた罠には目もくれてない」
「素通りかよ」
「でもビデオには映っている」
承太郎がカメラの録画機能を切って巻き戻している。
戻ってきたネズミは罠を警戒して避けながら動いている。
「『用心深さ』の知恵はあるというわけか・・・録画は4分前だ。
たぶんヤツは、俺たちの200m先を進んでいる」
「特徴があるね、このネズミ・・・ほら、耳のところ」
言われてみるとネズミの耳が欠けている、ケンカか何かで噛み付かれて食われたのだろう。
「よし、今からコイツを『虫食い』と呼ぼう」
承太郎はポケットからあるものを取り出した。
「ライフルの実弾だ、念のために4発だけ持って来ておいた。
『虫食い』が用心深くなっているってことは、さっきと違って俺たちを20mなんて射程距離には寄せ付けないと予想できる。
ベアリングでは、空気抵抗のせいで20mを超す着弾が大きくブレる。
ライフルの弾丸なら50~70mまでなら、なんとかなる」
「それもスタンドで発射させるんスか?」
「そうだ」
「でも俺、20m以上のネズミなんてクレイジー・ダイヤモンドで狙う自信ねーっスよ」
「だろーな、やっぱり俺がやるしかねーか」
妙にあっさりしている承太郎、それに少しカチンとくる仗助。
「ちょっと待ってくださいよ、承太郎さん!
何スか?今の言い方・・・?結構カチーンときたんスけど・・・」
「『自信がねーんだろ』?」
「だからって!その言い方はねーんじゃあないスか!さっきだってネズミを仕留めたのは俺っスよ?完璧に命中はしませんでしたけどよォ~~、でも倒したことには変わらねーっスよ!」
「そうだな、じゃあ2発持て」
「え!?」
またもやあっさりと実弾を渡された。
承太郎はそのまま『虫食い』追跡に歩き出してしまう。
「ぷ・・プレッシャ~~・・・」
「フフフ、乗せるのが上手いね、承太郎」
「何のことかな?」
げんなりしている仗助を後目に歩いている里美と承太郎。
「父さん、私には?」
「危険すぎるからお前は母さんと一緒に後方支援をしてくれ」
「・・・わかった」
『虫食い』の足跡からはヤツの心理状態まで伝わってくる。
止まって様子をうかがっているようにも見え、落ち着きのないようにグルグルと歩き回っているようだ。
焦っているのだろう、逃げているはずなのに承太郎達が確実に自分に迫っていることをわかっている。
歩いていると道の途中に大きな水溜まりがある。足跡はその中に続いている。
「泳いだか・・・静亜、こっちにこい」
承太郎は静亜を抱き上げて水溜まりに入る、そして里美も続く。
「ええ・・・」
「どうしたの?仗助くん、置いていかれるよ?」
里美は微動だにしない仗助にそれだけ言うと先に進んでしまう。