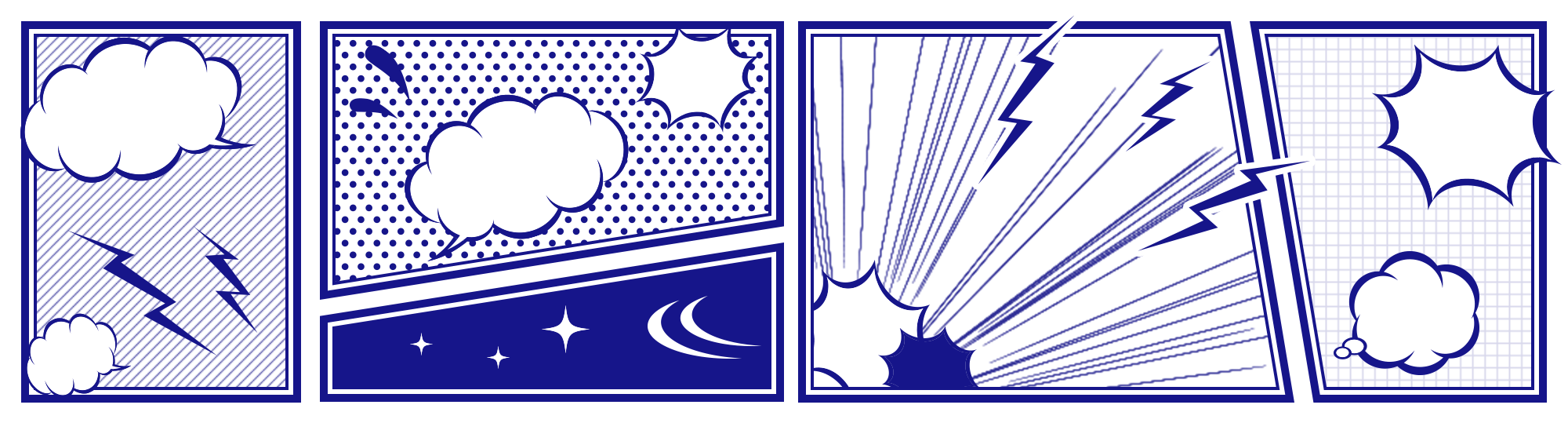第5話 癒しの樹~レスト・ウッド~
名前変換
この小説の夢小説設定ジョジョの奇妙な冒険連載夢小説です、第3部からのスタートです。
詳しくは『設定・注意書き』をお読みください。
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
「俺のスタンドは『戦車』のカードを持つ『銀の戦車(シルバー・チャリオッツ)』!
モハメド・アヴドゥル、始末してほしいのはきさまからのようだな。
そのテーブルに火時計を作った火が12時を燃やすまでにきさまを殺す!」
「恐るべき剣さばき、見事なものだが・・・・テーブルの炎が『12』を燃やすまでにこの私を倒すと?
ずいぶんと自惚れがすぎないか?」
そこでアヴドゥルは相手の名前を知らなかったっことに気づく。
「ああ――っと」
「ポルナレフ・・・名乗らせていただこう、ジャンピエール・ポルナレフ!」
「メルシーボークー(ありがとう)、自己紹介恐縮のいたり・・・しかし」
アヴドゥルが指を振ると火時計の下半分が燃えてしまった。
これでポルナレフの言ったことは実行できずに終わった。
「ムッシュ・ポルナレフ、私の炎が自然通り、常に上の方や風下へ燃えていくと考えないでいただきたい・・・。
炎を自在に扱えるからこそ『魔術師の赤(マジシャンズ・レッド)』と呼ばれている」
「・・・・フム、なるほど。
この世の始まりは炎に包まれていた、さすが『始まり』を暗示し、『始まり』である炎をあやつる『魔術師の赤(マジシャンズ・レッド)!
しかし、この俺を自惚れというのか?この俺の剣さばきを!!」
ポルナレフはコインを取り出すと空中へ放った、そして・・・・いともたやすくスタンドの剣に貫通させてしまった。
さらにはマジシャンズ・レッドの炎までコインとコインの間に取り込んでしまった。
「これでわかったか?私は自惚れているわけではない、私のスタンドは自由に炎をも切断できるということさ。
つまり、我がシルバー・チャリオッツの前ではきさまは無力ということだ」
するとそこへ店員や料理人たちが集まってきて騒がしくなってきた。
「さてここも騒がしくなってきたな、表に出るぞ、アヴドゥル。
俺も時間の惜しみなくお前と戦いたいが、あいにくDIOに送り届けなければならない人がいてね。
そのためにも早く終わらせたい」
「送り届けたい人・・・・っ!まさか!」
「ああ、高瀬里美。今、彼女の方にも1人スタンド使いが向かっている。
俺はここでお前たちを始末してそいつと合流する」
「なんだと!もう1人のスタンド使い!」
「まずい、早く高瀬さんを探さなければ!」
「承太郎、お前はアイスドールを連れて先に・・・」
動こうとした承太郎の前にシルバー・チャリオッツが立ちはだかる。
「誰1人として俺からは逃がさん、承太郎、お前のスター・プラチナが素早いのは知っている。だが、俺のシルバー・チャリオッツも速さでは劣らない。
お前たちは全員、俺が始末する。最初はアヴドゥル、お前だ。
俺のシルバー・チャリオッツは広いところでこそ、本来の力を発揮できる。それはアヴドゥル、お前もだろう?
花京院、空条承太郎、お前たちにも同じことが言える。ジョセフ・ジョースターは無関係な人間をスタンドの戦いには巻き込みたくないだろうしな。
お互い、表で思いきり、激しくやり合おうじゃあないか。その方が時間も早い」
――――――――
承太郎たちが敵と戦っているとは知らない里美はようやく見つけた電話ボックスで国際電話で祖母の入院する病院へ連絡を取った。
「はい、そうなんです。それで少しの間、日本を離れることになりまして・・・はい、はい・・・それについては大丈夫です。私の家に母方の祖母がきてくれているので、もし何かあれば私の家に電話をください、母方の祖母が対応してくれると思います。
祖母本人とも面識はありますし、アメリカに留学してからの親友という間柄なので・・・すいません、祖母をよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます、失礼します」
電話を切ると急いで承太郎たちのところへ戻ろうとアイスドールの気配を探る。
そこへ・・・・。
「待ちやがれ!このアマ!!」
「おとなしく捕まりやがれ!!」
後ろから男の声が聞こえたかと思い、振り向くと自分と同じくらいの女の子が男の2人組に追いかけらてていた。
「はあ・・はあ・・・っ」
女の子は息を切らせて苦し気に走ってきた、そして・・・。
「助けて!」
「え?」
「助けて、お願い!」
里美に助けを求めてきた。
女の子が後ろに隠れたすぐ後に男たちが息を切らせてやってきた。
「はあ・・・はあ・・・ようやく諦めたか」
「このガキ、てこずらせやがって・・」
男たちは女の子を睨んだ後、里美に視線を移した。
「何だ、この女?」
そして品定めをするように上から下、下から上へといやらしい目つきで見てくる。
「ねえちゃん、中国人じゃねえな。外国人・・・その堅苦しい制服を見ると日本からきたってところだな」
「ほお、結構上玉じゃねえか。なあ、こいつも連れて行っちまおうぜ」
「ああ、これだけの美人だ。きっといい値が付くぜ」
じりじりと男たちが詰め寄ってくる。
「・・・・・」
『アイス・フェアリー』
ツルッ!ツルッ!
「「!?」」
男たちがすっ転んだ。
「逃げるよ」
「え?」
「あ、こら!!待ちやがれ!!」
男たちが叫ぶが2人はそんなこと構わず、さっさと走り去った。