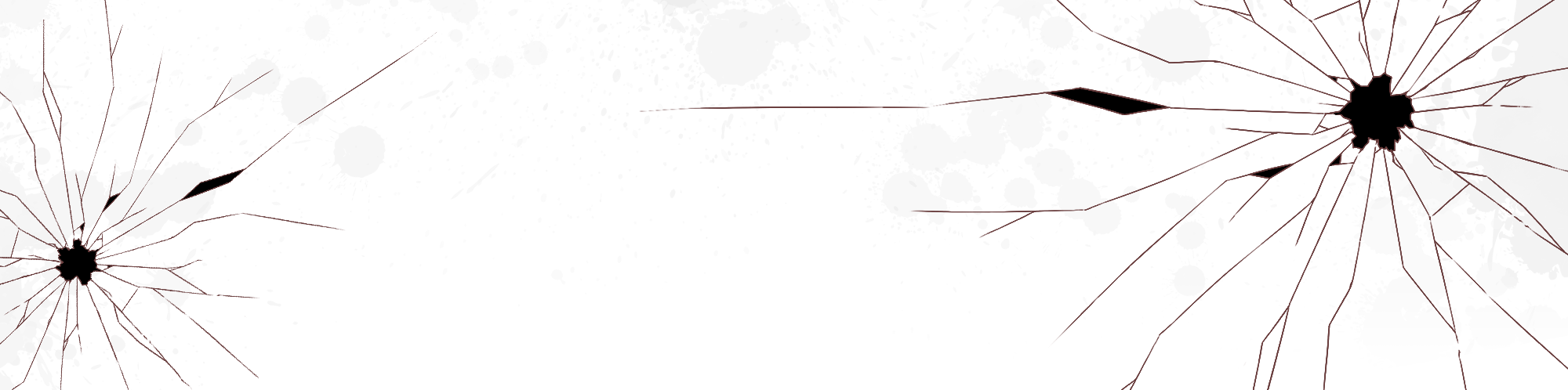第十一話 練習台
「この写真はお前にとって見慣れた写真だろう?」
「!!……それは……!」
その写真はエンリーケの故郷で、子供のころに撮影された写真だ。DV夫と離婚し、女手一つでエンリーケを育てた母と、年の離れた妹が写っている写真だ。妹はDV父が母に産ませた最後の子供で、母は妹を死なせまいとDV夫から必死に逃げ出した。エンリーケにとって命より大切な妹。遠く離れた故郷にあった写真だが、なぜこいつらがそれを持っている?
「お前が故郷に置いてきた母と妹。実は組織で預かっている」
「何!?」
「組織はお前の家族の生殺与奪の権利を握っている。お前は従うしかないだろう?」
エンリーケは狂ったように笑い出した。そんなバカな。エンリーケが組織に入った時にはすでに遠く離れた地域に住んでいた家族だ。今どこで暮らしているか、エンリーケですら把握していないのに、組織に分かるわけがない。
「ハッタリだろ?俺だって家族が今どこに住んでるか知らないんだぜ?俺の荷物に紛れていた写真見せて、ビビらそうとしてるんだろ?」
「撮ったばかりの新しい写真もあるぞ?」
するとファビオは新しい写真もエンリーケに突き付けた。そこには顔かたちは変わったが、確かに面影のある女性が二人写っていた。
「マジなのか……てめえら……」
「マジに決まっているだろう?どうだ、ファティマとヴィクトールを殺すか、俺にこの場で家族もろとも殺されるか、選べ」
「う……うわああああああああああ!!!」
新しい街に逃れてきたヴィクトールとファティマは、借りた宿の一室で何をするでもなく沈黙に包まれていた。
ヴィクトールは何度もエンリーケのスマートフォンに連絡を入れてみた。だが、電源が切られていて通じない。焦燥感と後悔で身も千切れんばかりに苦しんでいた。
落ち込むヴィクトールを見て、ファティマも気が気ではない。エンリーケの脱落は、いよいよ組織の魔手が身近に迫ってきた証拠だ。次は逃げきれないかもしれない。楽しかった逃亡生活の突然の終焉に、ファティマも焦りを感じていた。
「ヴィク、ター……」
「なんだ?」
「これからどうする?」
「どうって……逃げるしかねえだろ」
「逃げ切れるの?組織、本格的にピンポイントであたしたちの居所掴み始めたんだけど」
「読まれねえところに逃げるしかねえ」
ヴィクトールの朗らかな雰囲気と、優しさを感じる口調はすっかり失われていた。今ならファティマを簡単に殺しそうな、近寄りがたい雰囲気だ。
「ヴィクター、怖い」
「俺だって怖いよ」
ファティマはヴィクトールの様子が怖いと言ったのだが、ヴィクトールはファティマが不安を感じていると誤解して、吐き捨てるように言い返した。どうにか、この重苦しい空気だけでも軽くできないだろうか。いつまでもこの空気のまま逃亡生活を続けるのは精神衛生上辛いものがある。
「ヴィクター、練習しよう?いつもの」
「はあ?」
「あたしの男性恐怖症を治してよ」
「!!……それは……!」
その写真はエンリーケの故郷で、子供のころに撮影された写真だ。DV夫と離婚し、女手一つでエンリーケを育てた母と、年の離れた妹が写っている写真だ。妹はDV父が母に産ませた最後の子供で、母は妹を死なせまいとDV夫から必死に逃げ出した。エンリーケにとって命より大切な妹。遠く離れた故郷にあった写真だが、なぜこいつらがそれを持っている?
「お前が故郷に置いてきた母と妹。実は組織で預かっている」
「何!?」
「組織はお前の家族の生殺与奪の権利を握っている。お前は従うしかないだろう?」
エンリーケは狂ったように笑い出した。そんなバカな。エンリーケが組織に入った時にはすでに遠く離れた地域に住んでいた家族だ。今どこで暮らしているか、エンリーケですら把握していないのに、組織に分かるわけがない。
「ハッタリだろ?俺だって家族が今どこに住んでるか知らないんだぜ?俺の荷物に紛れていた写真見せて、ビビらそうとしてるんだろ?」
「撮ったばかりの新しい写真もあるぞ?」
するとファビオは新しい写真もエンリーケに突き付けた。そこには顔かたちは変わったが、確かに面影のある女性が二人写っていた。
「マジなのか……てめえら……」
「マジに決まっているだろう?どうだ、ファティマとヴィクトールを殺すか、俺にこの場で家族もろとも殺されるか、選べ」
「う……うわああああああああああ!!!」
新しい街に逃れてきたヴィクトールとファティマは、借りた宿の一室で何をするでもなく沈黙に包まれていた。
ヴィクトールは何度もエンリーケのスマートフォンに連絡を入れてみた。だが、電源が切られていて通じない。焦燥感と後悔で身も千切れんばかりに苦しんでいた。
落ち込むヴィクトールを見て、ファティマも気が気ではない。エンリーケの脱落は、いよいよ組織の魔手が身近に迫ってきた証拠だ。次は逃げきれないかもしれない。楽しかった逃亡生活の突然の終焉に、ファティマも焦りを感じていた。
「ヴィク、ター……」
「なんだ?」
「これからどうする?」
「どうって……逃げるしかねえだろ」
「逃げ切れるの?組織、本格的にピンポイントであたしたちの居所掴み始めたんだけど」
「読まれねえところに逃げるしかねえ」
ヴィクトールの朗らかな雰囲気と、優しさを感じる口調はすっかり失われていた。今ならファティマを簡単に殺しそうな、近寄りがたい雰囲気だ。
「ヴィクター、怖い」
「俺だって怖いよ」
ファティマはヴィクトールの様子が怖いと言ったのだが、ヴィクトールはファティマが不安を感じていると誤解して、吐き捨てるように言い返した。どうにか、この重苦しい空気だけでも軽くできないだろうか。いつまでもこの空気のまま逃亡生活を続けるのは精神衛生上辛いものがある。
「ヴィクター、練習しよう?いつもの」
「はあ?」
「あたしの男性恐怖症を治してよ」