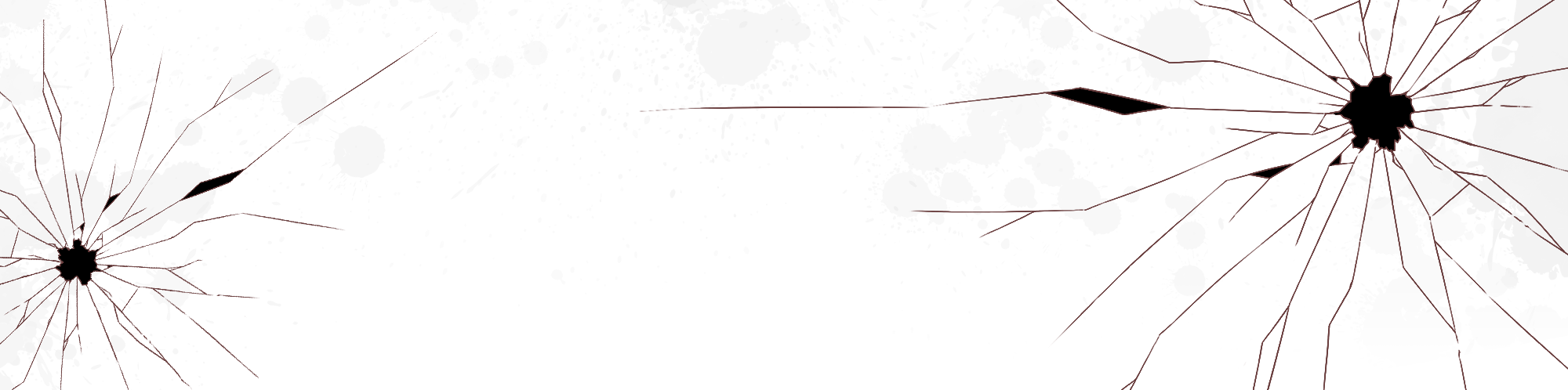第九話 薬物反応
三人は盲滅法 に銃を撃ちながら、姿勢を低くして弾丸をかわし、バーから逃げ出した。だが、バーの外にも敵は待機しており、三人は慌てて車に飛び乗りその場を後にした。車で銃を撃ちながら追跡してくる追手を、ファティマとヴィクトールが窓から銃で応戦し、エンリーケがアクセルベタ踏みで撒く。
追手が追跡できなくなるまで滅茶苦茶な道を走ると、やがて追手の車の姿が見えなくなり、銃声も聞こえなくなるのを確認して、三人は荒野のど真ん中で夜を明かした。
「夜が明けたらモーテルに荷物を取りに行って引き上げよう。今度は奴らが追ってこれなくなる方角に車を走らせよう。エンリーケ、今度は俺が運転代わる。お疲れさん」
エンリーケははあ~っと盛大なため息をついて脱力した。
「死ぬかと思った……。疲れた……」
「エンリーケ、ありがとう」
ファティマも彼をねぎらった。
「なんか入ってたのか、あのカクテル?」
エンリーケがずっと疑問に思っていたことをファティマに質問してみる。ファティマは銃撃戦のせいで記憶があやふやになり、満足に返答できなかったが、覚えている限りをエンリーケに説明する。
「あたし銃撃戦のせいでよく覚えてないんだけど、試験紙の一つが赤く染まったから、即効性のある何らかの毒物が盛られていたのは確かね。ちょっと今手元にないからはっきり言えないんだけど……。飲んでいたら間違いなく死んでいたわ。レイプドラッグみたいな意識を混濁させるものではなくて、即死するようなヤバいやつよ。何だったかな……。ちょっと判定できないんだけど、赤く染まるのには何種類かあって、毒物だったことは覚えてる」
エンリーケはそれを聞いて青ざめた。一瞬口に含んでしまったが、大丈夫なのだろうか?
「俺一滴ぐらい口に入っちまったよ……」
「すぐ吐き出したんでしょ?それなら大丈夫よ」
ヴィクトールはファティマの警戒心に感謝した。
「よく毒が盛られてるかもしれないって分かったな?俺たち今まで何度もあそこでは飲んでいたんだぜ?ファティマ様様だよ」
「今までは気づかなかったのかもしれないわ。あたし、ニュースに顔が出ているらしいのよ。だから何度も街に出たら感づかれるわ。警戒するに越したことはないわけよ。あのモーテルで滞在期間が長引いたから、その間に覚えられたのかもしれないわね」
「おっかねえ……。あんまり長期間同じところにいないほうがいいな」
翌朝、三人はスマートフォンの地図アプリでモーテルの場所を検索し、荷物をピックアップしてチェックアウトすると、再び宛てもない逃亡の旅に出立した。
追手が追跡できなくなるまで滅茶苦茶な道を走ると、やがて追手の車の姿が見えなくなり、銃声も聞こえなくなるのを確認して、三人は荒野のど真ん中で夜を明かした。
「夜が明けたらモーテルに荷物を取りに行って引き上げよう。今度は奴らが追ってこれなくなる方角に車を走らせよう。エンリーケ、今度は俺が運転代わる。お疲れさん」
エンリーケははあ~っと盛大なため息をついて脱力した。
「死ぬかと思った……。疲れた……」
「エンリーケ、ありがとう」
ファティマも彼をねぎらった。
「なんか入ってたのか、あのカクテル?」
エンリーケがずっと疑問に思っていたことをファティマに質問してみる。ファティマは銃撃戦のせいで記憶があやふやになり、満足に返答できなかったが、覚えている限りをエンリーケに説明する。
「あたし銃撃戦のせいでよく覚えてないんだけど、試験紙の一つが赤く染まったから、即効性のある何らかの毒物が盛られていたのは確かね。ちょっと今手元にないからはっきり言えないんだけど……。飲んでいたら間違いなく死んでいたわ。レイプドラッグみたいな意識を混濁させるものではなくて、即死するようなヤバいやつよ。何だったかな……。ちょっと判定できないんだけど、赤く染まるのには何種類かあって、毒物だったことは覚えてる」
エンリーケはそれを聞いて青ざめた。一瞬口に含んでしまったが、大丈夫なのだろうか?
「俺一滴ぐらい口に入っちまったよ……」
「すぐ吐き出したんでしょ?それなら大丈夫よ」
ヴィクトールはファティマの警戒心に感謝した。
「よく毒が盛られてるかもしれないって分かったな?俺たち今まで何度もあそこでは飲んでいたんだぜ?ファティマ様様だよ」
「今までは気づかなかったのかもしれないわ。あたし、ニュースに顔が出ているらしいのよ。だから何度も街に出たら感づかれるわ。警戒するに越したことはないわけよ。あのモーテルで滞在期間が長引いたから、その間に覚えられたのかもしれないわね」
「おっかねえ……。あんまり長期間同じところにいないほうがいいな」
翌朝、三人はスマートフォンの地図アプリでモーテルの場所を検索し、荷物をピックアップしてチェックアウトすると、再び宛てもない逃亡の旅に出立した。